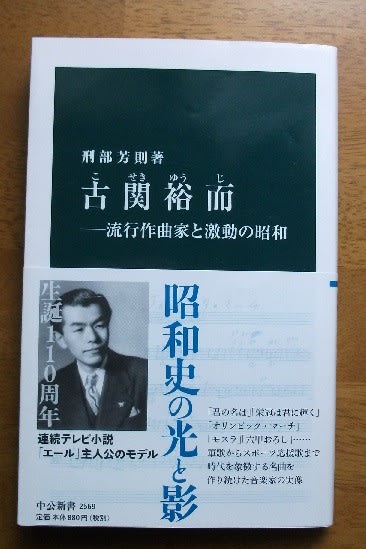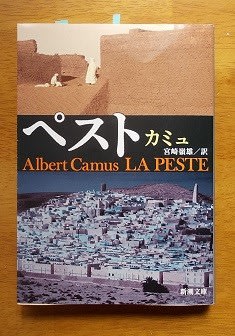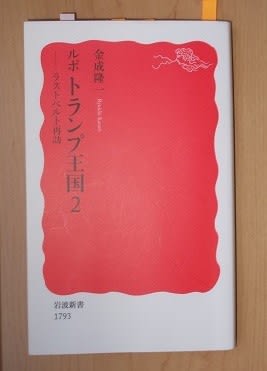著者は、1977年生、日大商学部准教授、専攻は日本近現代史。古関裕而の曲との出会いは、中学3年生(1995年)の時に聞いた『日本の軍歌』の一曲目にあった「露営の歌」。これに衝撃を受け昭和10年代の流行歌を、蓄音機とSPレコードで聞くほどにのめり込む。それがきっかけで、昭和史の研究に進むことになった。今回、NHKの朝ドラの風俗・考証をされている。帯に、「昭和史の光と影」とあるが、時代に求められるまま、作曲を続けた古関の生涯を、詳細な資料に基づいて(最後40頁)著している。
1.福島在住の頃。古関は、音楽学校で教育を受けてはいない。買い与えられた玩具のピアノ、父の蓄音機で聴いた楽曲、音楽教育に熱心だった小学校教師との出会い、それらが、音楽への才能を開かせる。福島商業学校、川俣銀行行員時代。ハーモニカの演奏活動の傍ら、作曲を独学。仙台に通い、金須嘉之進(きすよしのしん)より和音法を学んでいる。楽曲を送り続けていた山田耕作の紹介でコロンビアの専属作曲家になるため上京。昭和恐慌後の不安な世相の中で、同じ専属作曲家の古賀政男が、数々のヒット作を生み出す反面、古関は、うまく出せず、地方小唄、ご当地ソング等でかろうじて会社との契約をつなぎ留められていた。しかし、その間も、西洋音楽は学び続け、帝国音楽学校菅原明朗(すがわらめいろう)に教えを受けている。
2.日中戦争と作曲家としての飛躍満州への旅行の帰路、新聞で懸賞募集で入選の「進軍の歌」の歌詞を偶然読み、車中で作曲。これが、レコード会社の思惑と合致し「露営の歌」(勝ってくるぞと勇ましく~)として大ヒットする。これをきっかけに、陸軍省が制作した愛馬思想普及を目的とした映画『暁に祈る』(ああ、あの顔で、あの声で~)の主題歌等、政府、軍部からの曲の依頼が増え、それに伴い、中国戦線へ慰問団に参加する。
3.アジア・太平洋戦争と戦時歌謡開戦と共に、JOAKは、ニュース歌謡として、大本営の戦果の発表ごとに、作詞・作曲をし、放送に流す番組を制作。JOAKによるシンガポール、ビルマへの慰問団にも参加。18年、映画『決戦の大空へ』の主題歌「若鷲の歌」(若い血潮の予科練の~)の作曲。文壇の火野葦平と共に、インパール作戦の特別報道班に参加。19年ラングーン、サイゴンと回る。終戦時、福島市の疎開先から、JOAKの仕事に戻る際、新橋駅で終戦を知るが、作詞家の西條八十が、戦争犯罪人名簿に載せられたと知り、断罪を恐れ、しばらく福島で過ごす。
4.戦後の長崎の鐘以降の作曲活動。昭和20年11月東京に戻り、翌年、3月からラジオ歌謡の作曲に取り組んでおり、その後、劇作家菊田一夫との二人三脚で、戦後、映画、舞台と数々の曲を作曲していく。ラジオドラマ『鐘の鳴る丘』、『君の名は』。舞台音楽では、井上靖『敦煌』『蒼き狼』、林芙美子『放浪記』。映画音楽『モスラ』。阪神、巨人軍の応援歌。オリンピックマーチ。ラジオ番組の『ひるのいこい』は、現在も続く。 5.努力する天才作曲家古関は、音楽学校へは、進学出来なかったものの、西洋音楽を目指し学び続けたが、この素養が、流行歌の作曲家と相入れないものとなった。しかし、戦争によって、それが戦時歌謡とし受け入れられ、さらに、敗戦後もたらされた芸術文化の自由が、彼の天賦の才能をさらに広げていった。戦争中の作曲活動が、国民の戦意高揚につながった。そのことについては、古関は、あまり発言していない。しかし、「長崎の鐘」にあるように、鎮魂を込めた曲を「鐘」をキーワードに作曲をしている。これに関係し、福島時代、実家の斜め向かいに、福島新町教会があり、その鐘の音を毎日聞いていただろうという古関の友人の言葉を紹介している。文中の次のエピソードも興味深い。音楽を監督した日本初の長編アニメーション「桃太郎海の神兵」を、空襲跡で、手塚治虫が見て感動した。東宝撮影所に、進駐軍部隊が見学した時、フィリッピン決戦の歌をお愛想で流したが、「いざ来い、ニミッツ、マッカーサー、出てくりゃ地獄へ坂落とし」の所で、日本語がわからない将校は、歓迎の曲だと勘違いし大喝采を送った。最後の病床にあってリムスキー・コルサコフの交響曲「シェエラザード」、スメタナのモルダウを聞き続けていたという。青年時代に、教えを受けた金須は、ロシア正教徒で、帝政ロシア時代に、ペテルブルグに留学、コルサコフより教えを受けていた。東京でも、合唱団の有志と一緒に菅原よりコルサコフのテキストで和声法を学んでいる。この直向きさは、正に「努力する天才」だったと理解した。生涯5000曲に渡る作曲をしているが、記憶に残るメロディーが、古関裕而の曲だったのか改めて知ることになった。