12月14日 午後に郵便を確認したら
無能先生が 4日に、お亡くなりになった通知が
最期にお会いしたのが、昨年ですが、会主へ伺い・・
無能先生が 4日に、お亡くなりになった通知が
最期にお会いしたのが、昨年ですが、会主へ伺い・・
最期の説法を聞かせていただきました、腕を怪我されたとかで、・
・大分お体が弱っていた印象を受けてましたが・・
先生の弾き語りテノールの声を聴きたかったです、
心魂は健在でも肉体的な衰えは、いかしたがた無い事ですね
先生の教えは・・二辺往来、阿頼耶識、色々と・
先生の弾き語りテノールの声を聴きたかったです、
心魂は健在でも肉体的な衰えは、いかしたがた無い事ですね
先生の教えは・・二辺往来、阿頼耶識、色々と・
中村天風がベートーヴェンと思ってました、
偶然、同会のご縁も同時期で、時には唱元、時には天風へと行来して・
偶然、同会のご縁も同時期で、時には唱元、時には天風へと行来して・
・真善美から真善美へと・・
潜在的な心の使い方、活き方を学んで、仕事上、経営上で・・難題解決に・・自問自答の毎日でした、そんなときに唱元先生の教えに救われ、
潜在的な心の使い方、活き方を学んで、仕事上、経営上で・・難題解決に・・自問自答の毎日でした、そんなときに唱元先生の教えに救われ、
自己解決、自己管理に、毎日の活き方に役立ちました・・
先生は亡くなっても、今も教えは活き続け、実践しなくてはと想いが
先生は亡くなっても、今も教えは活き続け、実践しなくてはと想いが
強くなりますね
新橋の説法が一番長かったですね、品川、渋谷、青ーとかでも
新橋の説法が一番長かったですね、品川、渋谷、青ーとかでも
聞かせていただきました、
藤原真理さんチェロリサイタルでお会いしたり・・
色々なご教授を先生から戴き 長い間ありがとうございました、
あの世で説法をなさっている事と思います
先生 ありがとうございました 合掌
 献花
献花 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20010年12月19日 最期でした・・
公の会での出席、10名の方々が最期であったと想われますが・・
昨日は遠足気分で・・武蔵小杉から五井・千葉県へ約1時間30分ほどで・・新幹線が小杉駅横を通り過ぎて・・帰りは五井駅で1両車両運行の電車も・・
無能唱元氏に何年振りにお会いしました・・歳を重ねると体は弱くなりますが、心・魂は健在ですね・・先生の話や、会員方々のお話で・・
元氣を戴いて帰宅しました、感謝


09年11月ブログ
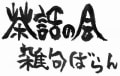
色々なご教授を先生から戴き 長い間ありがとうございました、
あの世で説法をなさっている事と思います
先生 ありがとうございました 合掌
 献花
献花 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20010年12月19日 最期でした・・
公の会での出席、10名の方々が最期であったと想われますが・・
昨日は遠足気分で・・武蔵小杉から五井・千葉県へ約1時間30分ほどで・・新幹線が小杉駅横を通り過ぎて・・帰りは五井駅で1両車両運行の電車も・・
無能唱元氏に何年振りにお会いしました・・歳を重ねると体は弱くなりますが、心・魂は健在ですね・・先生の話や、会員方々のお話で・・
元氣を戴いて帰宅しました、感謝


09年11月ブログ
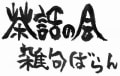
唱元 志しについて
「青年よ大志を抱け」
これは札幌の郊外に今も銅像が立っているクラーク博士の北海道を去るにあたって、日本の若者に残した言葉です。
世の中の殆どの人は「志しの高いことは、人間として立派だ」というように考えております。中国の古典にも「燕や雀には大きな鳥の志しを理解することなどは出来ない」という言葉があります。
しかし私はこの一般的通念には多分に懐疑的なのです。「志し」とはそんなに崇高なものであり、人間にとって必要欠くべからずのものでしょうか?
かって若い日、私もなんの疑いもなくそう信じていた者の一人でした
だが、ある時、まるでパカッと桶の底が抜けたように、すべてのものの姿が見えてきた時、この一般的なるものの考え方が崩れ落ちて、そのはだかの姿が目の前に現れてきたのです
「志し」とは要するに「現在の飢え」ではないでしょうか?
それは、現在に満ち足りていないことであり、それを満ち足りさせる何かにあこがれ求めることではないでしょうか?
本当の飢え、つまりお腹がすくことについて考えてみましょう。我々人間は自然にお腹がすき、放っておくと飢えて死にます。そこで本能として、食べ物を求めるのです。では、この食べ物を求める欲望はは悪でしょうか?または善でしょうか?
もちろん、それは悪でも善でもありません、なざなら、それは自然法則に属するものだかです。同じように志しを求めるのも、精神的な飢えによるものです。それは悪でもなく、といって「たたえられるべき善」でも無論ありません。
これらの飢えの発生は、いわば人間としては「仕方のないものだ」というように私には思えます。
「志し」はまた「未来への期待」であるとも言えます。そしてその期待は現在の飢えを基点として発する意欲でもあります。
食べ物に対する飢えは、その強さは大体万人共通しています、さぜなら胃袋の大きさには、それほどの個人差はないからです。しかし、これが志しに対しての飢えだと、人によっては途方もないほどの個人差があるものです。孔子は「志しがあまりに強大になると狂になり、志し無くなると狷・けん がんこ となる。中庸が大切である」と述べております。
さて次に「期待」について考えてみましょう。
人間は期待する動物であると言ってもいいほど、我々は頻繁にいろいろなものに期待しつづけます。未来にも期待しますし、他人にも期待します。政治にも、社会にも、薬にも、信仰する宗教にも期待します。人生に疑問を抱くある人はその解決を急ぎ求めて・・唱元にも・・期待するではありませんか・・
我々は何かに期待している時は飢えており、そしてその時には安らぎはないのです。そこにあるのは、興奮です、そしてそこには、生き生きとした活発さもあります。しかしそれは静寂ではなく、平和でもないのです。このことの意味をよく理解する必要があります。一言にしてい言えば、それは「飢えとは足りていないこと」だからです。
この精神的飢餓感は、狂おしいまでに、志しの方向へむけて人々を駆り立てるのです。「志し定まれば、氣さかんなり」これは吉田松陰の言葉です。
たしかに志しに対しての決心が定まれば、意気盛んとなり、情熱は火のように燃え上がりましょう。しかし、この時に知っていなければならないのは、生氣エネルギーはチャージされないまま消費し続けているということです。そして、この生氣エネルギーの枯渇は、その人の生命を破壊に導くのです。事実松陰は若くして命を失っております。
氣が盛んと燃えていることは、たしかに生き生きとしていることです、しかし、ここで忘れてならぬことは、燃料補給です、そしてその補給は、心が静寂の内に安らいでいる時においてこそ自動的に供給されるものなのです。
肉体にとって活動と睡眠は必要なように、精神にも興奮と安息が必要なことに氣がついている人は非常に少ないことを、我々は明記しなければなりません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期待なし 希望あり
音楽を聴くなり、散歩なり、心を静寂と活動・・現実と非日常の・・世界へ
何事も中庸であって・・右にブレ 左にブレ・・真中が・・
此れも 波風たたない 心 静寂が
これは札幌の郊外に今も銅像が立っているクラーク博士の北海道を去るにあたって、日本の若者に残した言葉です。
世の中の殆どの人は「志しの高いことは、人間として立派だ」というように考えております。中国の古典にも「燕や雀には大きな鳥の志しを理解することなどは出来ない」という言葉があります。
しかし私はこの一般的通念には多分に懐疑的なのです。「志し」とはそんなに崇高なものであり、人間にとって必要欠くべからずのものでしょうか?
かって若い日、私もなんの疑いもなくそう信じていた者の一人でした
だが、ある時、まるでパカッと桶の底が抜けたように、すべてのものの姿が見えてきた時、この一般的なるものの考え方が崩れ落ちて、そのはだかの姿が目の前に現れてきたのです
「志し」とは要するに「現在の飢え」ではないでしょうか?
それは、現在に満ち足りていないことであり、それを満ち足りさせる何かにあこがれ求めることではないでしょうか?
本当の飢え、つまりお腹がすくことについて考えてみましょう。我々人間は自然にお腹がすき、放っておくと飢えて死にます。そこで本能として、食べ物を求めるのです。では、この食べ物を求める欲望はは悪でしょうか?または善でしょうか?
もちろん、それは悪でも善でもありません、なざなら、それは自然法則に属するものだかです。同じように志しを求めるのも、精神的な飢えによるものです。それは悪でもなく、といって「たたえられるべき善」でも無論ありません。
これらの飢えの発生は、いわば人間としては「仕方のないものだ」というように私には思えます。
「志し」はまた「未来への期待」であるとも言えます。そしてその期待は現在の飢えを基点として発する意欲でもあります。
食べ物に対する飢えは、その強さは大体万人共通しています、さぜなら胃袋の大きさには、それほどの個人差はないからです。しかし、これが志しに対しての飢えだと、人によっては途方もないほどの個人差があるものです。孔子は「志しがあまりに強大になると狂になり、志し無くなると狷・けん がんこ となる。中庸が大切である」と述べております。
さて次に「期待」について考えてみましょう。
人間は期待する動物であると言ってもいいほど、我々は頻繁にいろいろなものに期待しつづけます。未来にも期待しますし、他人にも期待します。政治にも、社会にも、薬にも、信仰する宗教にも期待します。人生に疑問を抱くある人はその解決を急ぎ求めて・・唱元にも・・期待するではありませんか・・
我々は何かに期待している時は飢えており、そしてその時には安らぎはないのです。そこにあるのは、興奮です、そしてそこには、生き生きとした活発さもあります。しかしそれは静寂ではなく、平和でもないのです。このことの意味をよく理解する必要があります。一言にしてい言えば、それは「飢えとは足りていないこと」だからです。
この精神的飢餓感は、狂おしいまでに、志しの方向へむけて人々を駆り立てるのです。「志し定まれば、氣さかんなり」これは吉田松陰の言葉です。
たしかに志しに対しての決心が定まれば、意気盛んとなり、情熱は火のように燃え上がりましょう。しかし、この時に知っていなければならないのは、生氣エネルギーはチャージされないまま消費し続けているということです。そして、この生氣エネルギーの枯渇は、その人の生命を破壊に導くのです。事実松陰は若くして命を失っております。
氣が盛んと燃えていることは、たしかに生き生きとしていることです、しかし、ここで忘れてならぬことは、燃料補給です、そしてその補給は、心が静寂の内に安らいでいる時においてこそ自動的に供給されるものなのです。
肉体にとって活動と睡眠は必要なように、精神にも興奮と安息が必要なことに氣がついている人は非常に少ないことを、我々は明記しなければなりません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
期待なし 希望あり
音楽を聴くなり、散歩なり、心を静寂と活動・・現実と非日常の・・世界へ
何事も中庸であって・・右にブレ 左にブレ・・真中が・・
此れも 波風たたない 心 静寂が
唱元 気分の温度 佐木隆三 「復讐するは我にあり」
気分の温度
陽春のある日の午後、人間の「心」について考えた。「心」が何であるかの答えを得ることは何人にも出来まい。
しかし、しばらくして、ふと氣がついたことがある、「心」が何であるかは解らぬが、それは「気分」という温度で終始上下変化を繰り返していることを。
言い換えれば、それは感情の変化である。人間はこの温度の上下と共に生きている。
人間の心が希望に燃えて何かを目指すとき、気分は高揚し、その温度は上がる。しかし、時と共にそれは沈静化し、温度は下がる。
ところで、人間が広い意味で、人生での成功を得るためには、繰り返し気分が高揚し、その温度が高まっている必要があるのだ。なぜなら、鉄は熱い内に打てという言葉のとおり、希望は燃えている時間を必要としているからである。
では、希望には熱意がなぜ必要なのであろうか?実は、あなたはそれが熱いうちに、ある行動を実行しなけらばならないからだ。
どんなことであれ、人生で、あることを他人よりすぐれて成功させるには、何かの練磨がなければならぬ、それが何であれ、その行動に実行がくりかえされねばならぬ、そして、それを可能にするのは唯一「熱意」だ。
だがその熱は、自然の摂理として次第に冷却してしまうのだ。
この冷却を脱し、氣分の温度を上昇させるものは何か?
簡単に言えば、それは「欲望と夢」である、これ以外に答えは無い。
いつ、いかなる時でも、考える時間が出来たら、あなたの「欲望と夢」を思い起こすことだ。
そうすれば、あなたの氣分の温度はきっと上昇してくる、こうなれば、あなたにとっての成功は目の前だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現状維持メカニズム
金持ちはなぜ金持ちかというと、金持ちだからだ。
貧乏人はなぜ貧乏かというと、貧乏だからだ。
潜在意識は現状を維持しようとする。
人生が思い通りに進まないのは、ほとんどの場合
この潜在意識の現状維持メカニズムが作用しているからである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不完全な自分を許そう・・誰にでも才能は眠っている エンジョー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
善き願い・夢を 潜在意識に・・因果の法則が
////////////////////////////////////////////
先日TV東京で「復讐するは我にあり」ドラマを観ました
信じること 裏切られる この二者択一が哲学的会話に惹かれました
人の心には 善 悪 両面があり・・振り子が何かの切っ掛けで・・
信じ得なくなり 悪の・・振り子へ増幅され
人は復讐などつまらない事を 考えるな 神が人にかわって 復讐するから
復讐する我は 人ではなく 神だと
信じる事は 生きること 神を信じるが 神を信じていた・・
父に裏切られ、神・仏・・神父・宣教師に裏切られ・・人を信じる事を やめてしまった・・生きるしかばね
神・・信じた事はなかった 何もだれも 信じて おらん
殺人を犯した 男が 弁護士を語り・・逃亡先で・・名刺の肩書きで人は信じるものよ
何も疑いを持たない・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『復讐するは我にあり』(ふくしゅうするはわれにあり)は、第74回直木三十五賞を受賞した佐木隆三の小説で、実在した連続殺人犯・西口彰の犯行を題材にした作品である。1979年に日本映画、1984年と2007年にテレビドラマとして映像化された。
映画の制作・配給会社は松竹。今村昌平が監督、馬場当が脚本を担当した。主演は緒形拳。撮影は実際の事件の犯行現場で行われた。第22回ブルーリボン賞ならびに第3回日本アカデミー賞作品賞受賞作品。
なおタイトルの「復讐するは我にあり」という言葉は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」(引用『』は申命記32:35。ヘブル人への手紙10:30もこの箇所を引用)。これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう(参考;詩篇94:1)。」という意味である。
ストーリー
昭和38年。当時の日本の人々はたった一人の男に恐怖していた。榎津巌(えのきづ いわお)。敬虔なクリスチャンでありながら「俺は千一屋だ。千に一つしか本当のことは言わない」と豪語する詐欺師にして、女性や老人を含む5人の人間を殺した連続殺人犯。延べ12万人に及ぶ警察の捜査網をかいくぐり、78日間もの間逃亡したが、昭和39年に熊本で逮捕され、43歳で処刑された。映画ではこの稀代の犯罪者の犯行の軌跡と人間像に迫る。
佐木隆三
裁判官の「お言葉集」出版 厳粛判決に人間味も(朝日新聞) - goo ニュース
陽春のある日の午後、人間の「心」について考えた。「心」が何であるかの答えを得ることは何人にも出来まい。
しかし、しばらくして、ふと氣がついたことがある、「心」が何であるかは解らぬが、それは「気分」という温度で終始上下変化を繰り返していることを。
言い換えれば、それは感情の変化である。人間はこの温度の上下と共に生きている。
人間の心が希望に燃えて何かを目指すとき、気分は高揚し、その温度は上がる。しかし、時と共にそれは沈静化し、温度は下がる。
ところで、人間が広い意味で、人生での成功を得るためには、繰り返し気分が高揚し、その温度が高まっている必要があるのだ。なぜなら、鉄は熱い内に打てという言葉のとおり、希望は燃えている時間を必要としているからである。
では、希望には熱意がなぜ必要なのであろうか?実は、あなたはそれが熱いうちに、ある行動を実行しなけらばならないからだ。
どんなことであれ、人生で、あることを他人よりすぐれて成功させるには、何かの練磨がなければならぬ、それが何であれ、その行動に実行がくりかえされねばならぬ、そして、それを可能にするのは唯一「熱意」だ。
だがその熱は、自然の摂理として次第に冷却してしまうのだ。
この冷却を脱し、氣分の温度を上昇させるものは何か?
簡単に言えば、それは「欲望と夢」である、これ以外に答えは無い。
いつ、いかなる時でも、考える時間が出来たら、あなたの「欲望と夢」を思い起こすことだ。
そうすれば、あなたの氣分の温度はきっと上昇してくる、こうなれば、あなたにとっての成功は目の前だ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現状維持メカニズム
金持ちはなぜ金持ちかというと、金持ちだからだ。
貧乏人はなぜ貧乏かというと、貧乏だからだ。
潜在意識は現状を維持しようとする。
人生が思い通りに進まないのは、ほとんどの場合
この潜在意識の現状維持メカニズムが作用しているからである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不完全な自分を許そう・・誰にでも才能は眠っている エンジョー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
善き願い・夢を 潜在意識に・・因果の法則が
////////////////////////////////////////////
先日TV東京で「復讐するは我にあり」ドラマを観ました
信じること 裏切られる この二者択一が哲学的会話に惹かれました
人の心には 善 悪 両面があり・・振り子が何かの切っ掛けで・・
信じ得なくなり 悪の・・振り子へ増幅され
人は復讐などつまらない事を 考えるな 神が人にかわって 復讐するから
復讐する我は 人ではなく 神だと
信じる事は 生きること 神を信じるが 神を信じていた・・
父に裏切られ、神・仏・・神父・宣教師に裏切られ・・人を信じる事を やめてしまった・・生きるしかばね
神・・信じた事はなかった 何もだれも 信じて おらん
殺人を犯した 男が 弁護士を語り・・逃亡先で・・名刺の肩書きで人は信じるものよ
何も疑いを持たない・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『復讐するは我にあり』(ふくしゅうするはわれにあり)は、第74回直木三十五賞を受賞した佐木隆三の小説で、実在した連続殺人犯・西口彰の犯行を題材にした作品である。1979年に日本映画、1984年と2007年にテレビドラマとして映像化された。
映画の制作・配給会社は松竹。今村昌平が監督、馬場当が脚本を担当した。主演は緒形拳。撮影は実際の事件の犯行現場で行われた。第22回ブルーリボン賞ならびに第3回日本アカデミー賞作品賞受賞作品。
なおタイトルの「復讐するは我にあり」という言葉は、新約聖書(ローマ人への手紙・第12章第19節)に出てくる言葉で、その全文は「愛する者よ、自ら復讐するな、ただ神の怒りに任せまつれ。録(しる)して『主いい給う。復讐するは我にあり、我これを報いん』」(引用『』は申命記32:35。ヘブル人への手紙10:30もこの箇所を引用)。これは「悪に対して悪で報いてはならない。悪を行なった者に対する復讐は神がおこなう(参考;詩篇94:1)。」という意味である。
ストーリー
昭和38年。当時の日本の人々はたった一人の男に恐怖していた。榎津巌(えのきづ いわお)。敬虔なクリスチャンでありながら「俺は千一屋だ。千に一つしか本当のことは言わない」と豪語する詐欺師にして、女性や老人を含む5人の人間を殺した連続殺人犯。延べ12万人に及ぶ警察の捜査網をかいくぐり、78日間もの間逃亡したが、昭和39年に熊本で逮捕され、43歳で処刑された。映画ではこの稀代の犯罪者の犯行の軌跡と人間像に迫る。
佐木隆三
裁判官の「お言葉集」出版 厳粛判決に人間味も(朝日新聞) - goo ニュース




















