
演奏会の疲れも残りつつ、
2月が直ぐそこと知り、
慌てて、お札を頂きにお参りに。
だんなさんとは、もう、何度も行っている。母が亡くなり喪中の時には、郵便でお札を頂いた。
関西の方ならご存知と思う。
清荒神(きよしこうじん)
そう、火の神様。台所の守り神だ。
ここも神仏一体なのか、
お社とお寺の両方になるのか。
今までは、布袋さん(清荒神さんの従者だそう)も毎年、買い換えていた。
今は、最大の7年生で、止まっている。
それでも良いと聞いたので。
それと、火箸をいただくのだが、
我が家は、それは、していない。
古札をお返しする隣に、火箸の山が積んである。
最近では、もう使わないが、台所の象徴みたいなもんだね。
寺社内には、富岡鉄斎の書画を展示する美術館もある。なかなか、見応えがある。
27日、28日と初荒神さんだっただからか、今日は、空いていた。
参道のお店も閉めている所もあった。
節分までに、新しいお札を飾らないといけないと、姑から教えられた。
その昔、その姑とよくお参りしたもんだった。
息子が生まれてからは、三人だったり、姑と母と私と息子の四人でも。
そして、定年になった舅どのとも。
坂道の参道をよく歩いた。
そして、姑が亡くなり、舅どのが亡くなり、母も亡くなり、一時期は、私1人でお参りしていた。
この頃は、だんなさんと行くのが恒例になっている。私たちの様に、
お参りされている方々は、その人ごとに歴史があるんだろうなぁ
と想いながら下りの道を降りた。
何百年と続いてきた参道。
段々に宅地化が進み、お店も減ってきている。淋しい事だ。














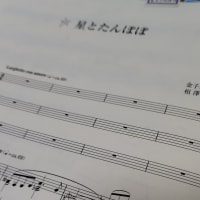





ほほう!初めて聞きました。清荒神。
こちらは火の神様、台所の神様は荒神様といいます。
我が家には台所に荒神様を祀る社はないですが、実家にはありました。
幸いと言って良いのか分かりませんが、我が家の氏神様が火の火伏せに神様なのです。
なので毎年度いただいてくるお札に守っていただいている気がしてます。
お一日の今朝も榊や水
など新しくして2礼2拍手1礼してきました。
仏壇のお線香とお水とお茶、神棚の参拝は毎朝の私の日課です。
節分までに新しくする…それ私も祖母から聞いて育ちました。
父が亡くなった時、祖父母のお墓が実家の菩提寺から叔父や従兄弟の住まいに近い千葉の霊園へ引っ越しました。
一度泊まりかけで母を連れて行った事がありますが、それ以来ご無沙汰でした。
母が亡くなった報告もまだなので明日千葉へ行ってお墓まいりしてきます。
こうやって一つづつ済ませると心が清々しますよね。
ご供養って亡くなった人のためのようでありながら、生かされるいる我々のためのものなのかも知れないですね。
家族の歴史(オーバーですが)って、色んな所にありますね。登場人物は何故か減っていきます。
でも、最近、火事がやたら多いでしょう。
だから、御仏壇のお灯も拝んでいる間だけにしよう、と決めました。二回、灯がついて、ご先祖さま達は、忙しないなぁ、と思っているでしょうね。
お嫁ちゃんには、話はしましたが、、、。
今後の事まで、縛る事は、できないと思っています。彼らは、彼らの人生ですからね。
ただ、気になるのはお墓です。
遠方故に、申し訳ないです。こちらも、話し合っておく方が良いのか、どうか。
まだ、先延ばし中です。
我が家とて、簡易式なお飾りです。
ただ、姑の真似っこをしているだけです。
だんなさんが定年になり、朝のお灯の担当になりましたから、蝋燭立ては、いつも美しいです、笑
でも、火事が多いから、これからは、一度、直ぐに消して、また、私が拝む時にまた、つけて消す、にしました。
忙しない夫婦でしょ、、。