- 言語的に作用している状態と言語の中に意味、内容を他と区別できるように明確に限定する作用をつうじて、システムはこれらの状態のいくつかを次の相互作用の対象とすることができる。次の作用に進むシステムは合意的な区別をもつ高次な領域を生じさせる。この高次な領域は個人にとって影響力のある表現を備えた相互作用領域として現れる。こうしてシステムそのものが自己(専門化)として作用するようになる。このような意味、内容を他と区別できるように明確に限定する作用領域は、ひとたびその組織がシステム内に出来上がってしまえば、その「心」が失われない限り自己の状態との意味や内容の区別をやめるきっかけはないのだから、原理上無際限である。この組織が企画する能力は「心」のシステムが構造の変換の過程をつうじて、様々な状態を次々と無際限に企画するかどうかは、以下の事柄にかかわっている。それは、相互作用する個人の「心」が環境の範囲内で実現するために、専門化という高次の領域で組織のシステムが意味と内容を十分果たしているか、ということである。
- 六処(見る、聴く、味わう、嗅ぐ、触れる、考える)を通して物事を知覚できる生命システムは、六処についての言語的である自分自身の思考的状態と作用することができる。そうすることで生命システムは、自己言語的な思考領域を生み出し、この思考のうちで観察者としての自分自身の観察者となる。これは必然的に際限なく繰り返しうる経過である。この領域を自己観察領域と呼び、自己意識行動は、自己の観察行動の自己観察領域内の行動であると考えたとき、観察者としての観察者は、いつも思考の領域、つまりあらゆるものの関係と影響による専門化された知識領域にとどまりつづける。もちろん絶対的現実の思考は不可能である。そうした思考は、専門者、絶対者との相互作用を必要とするだろうが、専門者、絶対者との関係から生じる表現は、観察者の心的な個人構成によって規定される他はなく、現実に表現され生成、変化、運動がそれによって引き起こされるものと規定されるものではない。したがって思考が生み出すような認知的現実は、避けようがなく知る者にとって環境との密接な関係において成り立つものとなるだろう。
- どんな説明であれ、合意された言語領域で理解をゆだねる以上、ゼロからの出発はなく何かしら合意された表現を含む再生産である。説明される純粋に合理的な思考、つまりリニューアル化は同じ概念(受容、排除の区別などの同一性)に依存していることがわかる。それゆえ、もっとも単純な感覚から最高の絶対知へ至るまで妥当に捉えることのできる普遍的説明(理論)が存在する。この説明は、これらの領域を生み出す背景から、区別と規定されうるものとの過程の可能なまでの関係にかかわるのであって、特性にかかわっているのではない。
・・・・・つづく。

















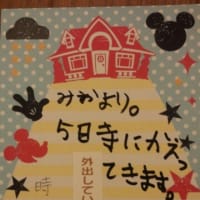


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます