「心」とは、あらゆる領域で存在するための唯一の必要条件である。
すなわち背景から区別されうる自身の過程を規定する、生物が自律性を失うことなく経過していく変形の領域である。その領域は、自身の「心」が自らの経験の空間で実現されてゆくさいの多様なモードから引き抜いた、効率性、適応性、安定性など、構成の仕方によって規定されている。このことから「心」の相互作用領域は必然的に限界づけられたものとなり、他の異なった構成を持つ「心」は、異なった相互作用領域をもっている。
私たちは、傷つき悩むとき、「心」が変形を補正するのを、主要な原因から説明することができる。つまり、規定された個人の構成がこうむっている変形を、現実に作用し、事物の生成・変化・運動がそれによって引き起こされるものだと考えるのである。しかも「心」は構成の仕方により作用領域は限界づけられ、境界づけられているのだから、「心」をシステムとして観察するとき、主要な原因(実体)と相互作用することにより操作することができるように思われる。しかし、システムそのものは主要な原因(実体)を説明することができない。それは、主要な原因(実体)との作用領域をもたないか、主要な原因(実体)がひきおこした変形を補正することができないためである。
「心」のシステムが自律性を失うことなく入っていける作用領域がシステムの認知の領域である。そして「心」のシステムの認知領域は、システムを可能にする説明の領域である。したがって、「心」の特定のモードがシステムの認知領域を、さらにはシステムの行動の多様性を規定している。そのことから「心」の認知領域は、「心」のモードが変化する範囲内でのみ、構造の変換の歴史をつうじて変化していることがわかる。・・・・・つづく。

















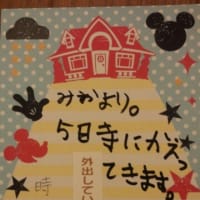


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます