この世界は、一つの出来事が一人の人間に新しい能力を発揮させる関係のネットワークで成り立っている。しかしながら、その新しいものを「不安材料」として扱う古い時代で生きている人々が今だ存在する。ニュートン力学と産業革命の過去の功績を基盤としている者たちだ。今だにしがみつき300年以上前の知恵を頼りにし、数字やグラフ・図などに頼り還元的に表せないものは「妄想」として扱う。ある枠の中で認識できない、操作・管理できないものは排除いてよいという考え方だ。つまり、その中では「不安材料」は在ってはならない。「不安材料」は壊れた部品であり、欠陥を交換し初期のレベルに戻すしかないという「変化」を嫌う機械的思考のアプローチだ。常に初期レベルの世界なので、なにも変わらない。負のエネルギーを費やすだけの、箱の中で操作される機械の部品として消耗されるだけの世界であるため、変革はうまくいかない。それどころか、「見ざる言わざる聞かざる」の文化を生む結果となる。
ローカルな部分を操作する現場。てこの原理のような「支点・力点・作用点」という縦割りの組織体系。そこで生まれる、てこの原理とはほど遠いでたらめな「バランス状態や派閥争い」に懸命になり古い自己にしがみつく。このほとんどの組織体系が約100年前にフレデリック・テイラーが考案した「科学的管理法」に基づいている。もっと昔で言えばニュートン力学に基づいている。「科学的管理法」を簡単に言えば、当初は計画者や設計者は管理効率の改善だけを考え、机上で考えたことをローカルな部分に実行させる・押し付けるという方法だ。その念頭には労働者は愚かなものだということが前提で、それでいて業務に支障をきたさないようにするのが、計画者や設計者の任務だった。机上で、ローカルな部分の「自由と時間を奪う」設計を行い、自由を吸収し「機械」のように働かせ「時間」をも奪う。(それに見合った賃金を与えれば「ありがたがるだろう」という計画が隠されているようだ。)しかし、それにこぞって集まったのが我々だ。つまり、我々も(100年前ほどではないが)それを認めたうえで働いているのだ。利益を第一に考えた場合、ニュートンの力学で言えば【物体の力(エネルギー)は二つの要素、質量と速度の二乗に比例する。】という法則を使うのが賢明だ。(我々は知らずにこの法則を使っている)労働の総力が質量に匹敵し、労働時間が速度に匹敵する。例えば熟練された労力か、体力のある若者か、ということだ。賃金にも差があり、どこで誰を投入するか利益を考えた上で操作をしている。
現場や組織の中で思い当たる節はないだろうか?100年前の「管理法」を基盤として、変化してゆくローカルな部分に不安を感じ安定感のある世界を探している現場や組織はないだろうか?年功序列・成果主義という世界を信じている者はいないだろうか?
何度も言うが、「過去での成功は現在では通用しない!」「安定は『ゼロ』の状態であり変化はない!」「人は力学にはそぐわない!」

















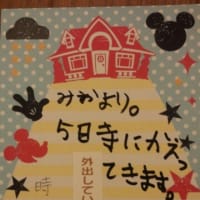


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます