白石草@hamemenさんのツイート。
――「殴る蹴るといった暴力行為は、日本では捕虜に対してだけでなく、自国の兵士に対しても頻繁に行われていたばかりか、通常の社会生活でも当たり前にみられた行為であった。」
日本人は本当に「ウォーギルトプログラム」でGHQに洗脳されたのか https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56971 … #現代ビジネス〔6:46 - 2018年8月17日 〕――

〔資料〕
「日本人は本当に『ウォーギルトプログラム』でGHQに洗脳されたのか」
現代ビジネス/賀茂 道子さん・文(2018.8.16)
☆ 記事URL:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56971
太平洋戦争終結後、日本を占領した連合国とGHQは、「ウォー・ギルト・プログラム」という「洗脳政策」をとり、日本人に罪の意識を植えつけた――そんな俗説がいまも根強く残っている。この見方は、はたして正しいのだろうか?
膨大な資料にもとづき、従来の説に一石を投じる『ウォー・ギルト・プログラム』を上梓した賀茂道子氏が、あの戦争で日本が犯した「罪」の実像を解き明かす。
日本が「無条件降伏」を突きつけられた理由
今年も8月15日がやってきた。今から73年前のこの日、国民の多くが、天皇の玉音放送によって敗戦の事実を知った。それ以来、8月15日は終戦記念日として日本人の心に深く刻み込まれている。
しかし、実は、国際法上の日本の敗戦の日は、降伏文書に署名した9月2日であり、また、ポツダム宣言を受諾したのは8月14日である。こうした事実は意外と知られていない。
日本の終戦にまつわる話でもう一つ誤解されているのが、「無条件降伏」である。当時は「無条件降伏」に関する国際法上の定まったルールがなく、非常にあいまいな概念であった。
それまでは、国家間の戦争を終結する場合、一旦休戦協定を結んで戦闘を中止したうえで、戦争終結の条件を話し合い、その後に講和条約を結ぶという方式が採られていた。これに対し、「無条件降伏」は勝者による一方的な戦争終結であり、近代国家間の戦争において初めて採られた方式であった。
国際法は条約や慣習法(法として認められた一般慣行)などからなる。つまり、それまでの終結方式とは異なる「無条件降伏」という方式には、国際社会で認知された明確な規定がなかったのである。
連合国が日本とドイツに対して「無条件降伏」を要求した背景には、第一次世界大戦でのドイツの戦争終結に対する悔根があった。
第一次世界大戦に敗れたドイツは、休戦協定から講和条約という通常の方式で戦争を終結した。だが、その後ナチスが、「実は我々は敗けていないのに、内部の裏切りによって講和条約を結ぶことになった」といった言説を流布し、それが再度の軍事的台頭へとつながった。
こうしたことから、第二次世界大戦においては、誰の目から見ても日本やドイツの敗戦が明らかであることを示す必要性が生じた。つまり、「無条件降伏」とは、完全敗北を示すための一種のスローガンのようなものと言えるだろう。
「ウォー・ギルト・プログラム」とは何か
日本人の終戦に関する認識が、国際法上のそれとは異なるという話を冒頭でしたのは、こうした認識の違いが、ある一つの占領政策につながったことを紹介するためである。その政策は、「ウォー・ギルト(War Guilt)・プログラム」という。
「ウォー・ギルト・プログラム」は、評論家の江藤淳(1932-1999)によって初めて世に紹介された。
江藤の主張は、「このプログラムにより日本人が洗脳された」というものであった。その後、この主張は検証されないままに独り歩きを続け、「日本人はGHQによって侵略戦争史観を植え付けられ、それが近隣諸国との間で起こっている歴史認識問題に影響を与えている」との言説が、一部保守層によって支持されている。
もちろん、この言説は学術研究をベースとしたものではない。当然これに対し、陰謀論であるとの声も存在するが、こちらも学術研究を基にした反論ではない。
筆者がこのプログラムの研究を開始した背景には、こうした学術研究によらない身勝手な議論が行われていることに対する違和感があった。そのためにまず、いつ、何が、どのように、なぜ行われたのかを一次資料を基に整理し、事実の解明に取り組むことが必要と考えた。
その結果、次のような終戦から占領開始当初にかけての日米の認識の差が、プログラム開始の背景にあったことが明らかとなった。
占領軍の考える「無条件降伏」は、「一切交渉を行わない、軍事的な完全敗北」を指していた。だが、当時の日本政府は、「軍の無条件降伏であり国の無条件降伏ではないのだから、占領体制に関して条件交渉が可能」と考えていた。そのため、マッカーサーを東京に進駐させずに横浜に留めようとするなど、占領軍に様々な要望を出していた。
なかでも占領軍を呆れさせたのは、原爆投下批判の国際世論を形成するために、在外公館を通じてプロパガンダを行おうとしたことであった。米国は日本外務省の暗号を解読していたため、その企ては筒抜けであった。
さらに、それまで連合国内で強い非難をあびていた捕虜虐待やマニラの虐殺といった日本軍による残虐行為が、日本国内で一切報じられておらず、罪の意識がないことにも占領軍は驚いた。
こうした状況に対し、「日本人は、敗けたのに反省していない」と捉えたGHQは、「ウォー・ギルト・プログラム」という形で、「敗戦の真実」と「戦争の有罪性(War Guilt)」を日本国民に認識させるための情報教育政策を開始したのであった。
「侵略戦争」糾弾より重視されたこと
では、「ウォー・ギルト・プログラム」では、具体的にどのようなことが行われたのだろうか。
よく知られているものとしては、新聞連載「太平洋戦争史」とラジオ番組「真相はこうだ」がある。「太平洋戦争史」は、GHQ民間情報教育局のブラッドフォード・スミスが執筆した戦争史であり、12月8日から10日間にわたって、全国紙に連載された。それまでの「自存自衛のための戦い」という大東亜戦争観を打ち消す、米国側の主張に立ったこの戦争史は、後に書籍として出版され、一時期、歴史教科書としても使われた。
そして、そのラジオ版が「真相はこうだ」である。この番組も民間情報教育局が制作したもので、米国のラジオ番組の手法を取り入れたドキュメンタリー調の番組構成であった。
両者の目的は、戦争の真実を日本国民に提示することであったが、米国から見た戦争史である以上、戦争を日本の侵略戦争として糾弾しているのは当然である。
しかしながら、この「太平洋戦争史」および「真相はこうだ」で重要視されていたのは、戦争が日本の侵略戦争であったこと以上に、
(1)日本が軍事的に完全敗北をしていること
(2)軍国主義者の言論弾圧が戦争への道筋を開いたこと
(3)日本軍が残虐行為を行ったこと
この3点であった。
「残虐行為」を自覚していなかった日本
「太平洋戦争史」と「真相はこうだ」で重要視された日本軍の残虐行為とは、捕虜虐待と占領地での住民虐殺などを指し、具体的には、バターン死の行進、南京虐殺、マニラの虐殺などである。これらの行為は、連合国内では強く非難されており、特に捕虜虐待は自国の兵士の身に降りかかる問題として関心が高かった。
ところが、日本では残虐行為について全く報じられていないばかりか、それを戦後に占領軍が発表しても「信じられない」との声が多数を占めた。それだけではなく、先にも述べた、外務省による原爆投下批判の国際世論形成の企てが発覚し、さらに新聞は占領軍の日本での犯罪を大々的に報じていた。
自らが「絶対悪」と考える捕虜虐待をはじめとする残虐行為に対し、全く反省の色がないばかりか、逆に占領軍の犯した罪を追及する――こうした日本の姿勢に対し、連合国はなんらかの手立てを講じなければならないと考えた。そのため、「ウォー・ギルト・プログラム」開始当初、残虐行為の暴露とその罪を理解させることに力がそそがれていたのも当然であろう。
捕虜虐待に関しては、日米間で大きな認識の差があった。そもそも日本兵も十分な食料を与えられておらず、また殴る蹴るといった暴力行為は、日本では捕虜に対してだけでなく、自国の兵士に対しても頻繁に行われていたばかりか、通常の社会生活でも当たり前にみられた行為であった。日本軍では捕虜になることが禁じられていたため、おのずと捕虜に対する待遇も厳しいものとなった。
前回の「戦後日本人の思考回路を作った?対日宣伝工作の真実」で紹介したように、「ウォー・ギルト・プログラム」で追及された残虐行為は、捕虜虐待のような敵兵に対する行為だけではなかった。
勝てないとわかっていても投降を許さなかったこと、傷ついた兵士を見捨てたこと、自決を強要したことなど、自国の兵士に対する非人道的な扱いや、占領地住民に残虐行為を行ったことで国際社会での日本の評価を落としたことなどを、「日本人に対する罪」として糾弾していた。
また、たとえ上官に命令されて行った行為だとしても、罪であることには変わらないとしていた。つまり「ウォー・ギルト・プログラム」で追及された残虐行為の罪とは、戦時国際法違反といった法的な観点だけでなく、「暴力はどのような状況においても罪である」という人道的な観点も伴っていたことになる。
変わりゆくプログラム
「ウォー・ギルト・プログラム」といえば、「太平洋戦争史」および「真相はこうだ」のイメージが強いかもしれないが、この2つは1945年末から1946年初めにかけての、プログラムの開始当初に行われた施策である。
実はプログラムでは、この2つが終了した後、その質・量ともに大きな変化が起こった。
当初の心配をよそに、占領は軌道に乗り日本の政治形態の骨格も完成しつつあった。そのため、当初あった「敗戦の真実」を理解させる必要性は消滅した。
同時に、占領方針が日本側に配慮した宥和路線へと変化したこともあり、しだいに「ウォー・ギルト・プログラム」はGHQの重点政策から外れていった。ただし、東京裁判が開始され、BC級戦犯を裁く横浜裁判も継続中であったことから、両裁判の目的を理解させるために裁判報告のラジオ番組は継続された。
その後、東京裁判の判決を前に、一部の国民の間で東條英機を賛美する傾向が見られたことから、再度プログラムを活性化する提案が出された。だが、結局それは計画倒れに終わった。
ただし、プログラム自体は細々と横浜裁判が終了するまでは行われていたようである。もっともそれは、占領開始直後に見られた、「敗戦の真実」と「戦争の有罪性」を理解させるために積極的に情報発信を行う、初期のプログラムとは異なったものであった。
私たちは「洗脳された」のか?
ところで、読者にとって最も関心があるのは、「ウォー・ギルト・プロラム」は日本人にどのような影響を与えたのか、つまるところは日本人が「洗脳」されたのかどうかではないだろうか。
「ウォー・ギルト・プログラム」が、GHQに都合の良い情報のみを発信したという点において、プロパガンダであったことに疑う余地はない。
だがその影響、とりわけ「洗脳」に関して、筆者がここで資料に基づいた学術的な検証結果を示すことは難しい。そもそも「洗脳」という言葉をどう定義するのかによって答えが変わるうえに、こうした検証には社会学および心理学からのアプローチも必要になるからである。
ただ一つ確かに言えることは、「ウォー・ギルト・プログラム」で重視された捕虜虐待の罪に関していえば、日本人が理解したとは言い難いということである。
占領終了後、戦犯救済運動が盛り上がり、多くのBC級戦犯が赦免された。この運動の背景には、残された戦犯家族の恩給問題もあったが、それ以上に、捕虜虐待に関する罪が理解されていないことがあった。とりわけ、上官から命じられて虐待行為を行ったものに対しては、同情すら向けられていた。
現在では、捕虜虐待の事実は忘れ去られているに等しい。昭和天皇や今上天皇の欧州訪問時に、英蘭の退役軍人が抗議の意思を表した事実や、オバマ大統領の広島訪問時に、米国の退役軍人が日本軍に虐待された捕虜の同行を求めた事実に対し、いったいどれほどの日本人が関心を払ったであろうか。
また日本人は今でも、上から命じられて行った行為に対しては、たとえそれが罪であろうと、寛容である。
占領期に、日本人に「敗戦の真実」と「戦争の有罪性」を認識させるために行われた情報教育政策「ウォー・ギルト・プログラム」は、「軍国主義を排除して、二度と米国の脅威とならない民主主義国家を作る」という米国の国益のために行われたものである。その一方で人道的理念にも支えられていたものであった。
終戦前の対日心理作戦から日本人に向き合い、原爆投下という自らの非人道的行為に苦悩しつつもプログラムを推進したブラッドフォード・スミスやスタッフは、今頃雲の上から現在の日本に対して、何を思っているのだろうか。
――「殴る蹴るといった暴力行為は、日本では捕虜に対してだけでなく、自国の兵士に対しても頻繁に行われていたばかりか、通常の社会生活でも当たり前にみられた行為であった。」
日本人は本当に「ウォーギルトプログラム」でGHQに洗脳されたのか https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56971 … #現代ビジネス〔6:46 - 2018年8月17日 〕――

〔資料〕
「日本人は本当に『ウォーギルトプログラム』でGHQに洗脳されたのか」
現代ビジネス/賀茂 道子さん・文(2018.8.16)
☆ 記事URL:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/56971
太平洋戦争終結後、日本を占領した連合国とGHQは、「ウォー・ギルト・プログラム」という「洗脳政策」をとり、日本人に罪の意識を植えつけた――そんな俗説がいまも根強く残っている。この見方は、はたして正しいのだろうか?
膨大な資料にもとづき、従来の説に一石を投じる『ウォー・ギルト・プログラム』を上梓した賀茂道子氏が、あの戦争で日本が犯した「罪」の実像を解き明かす。
日本が「無条件降伏」を突きつけられた理由
今年も8月15日がやってきた。今から73年前のこの日、国民の多くが、天皇の玉音放送によって敗戦の事実を知った。それ以来、8月15日は終戦記念日として日本人の心に深く刻み込まれている。
しかし、実は、国際法上の日本の敗戦の日は、降伏文書に署名した9月2日であり、また、ポツダム宣言を受諾したのは8月14日である。こうした事実は意外と知られていない。
日本の終戦にまつわる話でもう一つ誤解されているのが、「無条件降伏」である。当時は「無条件降伏」に関する国際法上の定まったルールがなく、非常にあいまいな概念であった。
それまでは、国家間の戦争を終結する場合、一旦休戦協定を結んで戦闘を中止したうえで、戦争終結の条件を話し合い、その後に講和条約を結ぶという方式が採られていた。これに対し、「無条件降伏」は勝者による一方的な戦争終結であり、近代国家間の戦争において初めて採られた方式であった。
国際法は条約や慣習法(法として認められた一般慣行)などからなる。つまり、それまでの終結方式とは異なる「無条件降伏」という方式には、国際社会で認知された明確な規定がなかったのである。
連合国が日本とドイツに対して「無条件降伏」を要求した背景には、第一次世界大戦でのドイツの戦争終結に対する悔根があった。
第一次世界大戦に敗れたドイツは、休戦協定から講和条約という通常の方式で戦争を終結した。だが、その後ナチスが、「実は我々は敗けていないのに、内部の裏切りによって講和条約を結ぶことになった」といった言説を流布し、それが再度の軍事的台頭へとつながった。
こうしたことから、第二次世界大戦においては、誰の目から見ても日本やドイツの敗戦が明らかであることを示す必要性が生じた。つまり、「無条件降伏」とは、完全敗北を示すための一種のスローガンのようなものと言えるだろう。
「ウォー・ギルト・プログラム」とは何か
日本人の終戦に関する認識が、国際法上のそれとは異なるという話を冒頭でしたのは、こうした認識の違いが、ある一つの占領政策につながったことを紹介するためである。その政策は、「ウォー・ギルト(War Guilt)・プログラム」という。
「ウォー・ギルト・プログラム」は、評論家の江藤淳(1932-1999)によって初めて世に紹介された。
江藤の主張は、「このプログラムにより日本人が洗脳された」というものであった。その後、この主張は検証されないままに独り歩きを続け、「日本人はGHQによって侵略戦争史観を植え付けられ、それが近隣諸国との間で起こっている歴史認識問題に影響を与えている」との言説が、一部保守層によって支持されている。
もちろん、この言説は学術研究をベースとしたものではない。当然これに対し、陰謀論であるとの声も存在するが、こちらも学術研究を基にした反論ではない。
筆者がこのプログラムの研究を開始した背景には、こうした学術研究によらない身勝手な議論が行われていることに対する違和感があった。そのためにまず、いつ、何が、どのように、なぜ行われたのかを一次資料を基に整理し、事実の解明に取り組むことが必要と考えた。
その結果、次のような終戦から占領開始当初にかけての日米の認識の差が、プログラム開始の背景にあったことが明らかとなった。
占領軍の考える「無条件降伏」は、「一切交渉を行わない、軍事的な完全敗北」を指していた。だが、当時の日本政府は、「軍の無条件降伏であり国の無条件降伏ではないのだから、占領体制に関して条件交渉が可能」と考えていた。そのため、マッカーサーを東京に進駐させずに横浜に留めようとするなど、占領軍に様々な要望を出していた。
なかでも占領軍を呆れさせたのは、原爆投下批判の国際世論を形成するために、在外公館を通じてプロパガンダを行おうとしたことであった。米国は日本外務省の暗号を解読していたため、その企ては筒抜けであった。
さらに、それまで連合国内で強い非難をあびていた捕虜虐待やマニラの虐殺といった日本軍による残虐行為が、日本国内で一切報じられておらず、罪の意識がないことにも占領軍は驚いた。
こうした状況に対し、「日本人は、敗けたのに反省していない」と捉えたGHQは、「ウォー・ギルト・プログラム」という形で、「敗戦の真実」と「戦争の有罪性(War Guilt)」を日本国民に認識させるための情報教育政策を開始したのであった。
「侵略戦争」糾弾より重視されたこと
では、「ウォー・ギルト・プログラム」では、具体的にどのようなことが行われたのだろうか。
よく知られているものとしては、新聞連載「太平洋戦争史」とラジオ番組「真相はこうだ」がある。「太平洋戦争史」は、GHQ民間情報教育局のブラッドフォード・スミスが執筆した戦争史であり、12月8日から10日間にわたって、全国紙に連載された。それまでの「自存自衛のための戦い」という大東亜戦争観を打ち消す、米国側の主張に立ったこの戦争史は、後に書籍として出版され、一時期、歴史教科書としても使われた。
そして、そのラジオ版が「真相はこうだ」である。この番組も民間情報教育局が制作したもので、米国のラジオ番組の手法を取り入れたドキュメンタリー調の番組構成であった。
両者の目的は、戦争の真実を日本国民に提示することであったが、米国から見た戦争史である以上、戦争を日本の侵略戦争として糾弾しているのは当然である。
しかしながら、この「太平洋戦争史」および「真相はこうだ」で重要視されていたのは、戦争が日本の侵略戦争であったこと以上に、
(1)日本が軍事的に完全敗北をしていること
(2)軍国主義者の言論弾圧が戦争への道筋を開いたこと
(3)日本軍が残虐行為を行ったこと
この3点であった。
「残虐行為」を自覚していなかった日本
「太平洋戦争史」と「真相はこうだ」で重要視された日本軍の残虐行為とは、捕虜虐待と占領地での住民虐殺などを指し、具体的には、バターン死の行進、南京虐殺、マニラの虐殺などである。これらの行為は、連合国内では強く非難されており、特に捕虜虐待は自国の兵士の身に降りかかる問題として関心が高かった。
ところが、日本では残虐行為について全く報じられていないばかりか、それを戦後に占領軍が発表しても「信じられない」との声が多数を占めた。それだけではなく、先にも述べた、外務省による原爆投下批判の国際世論形成の企てが発覚し、さらに新聞は占領軍の日本での犯罪を大々的に報じていた。
自らが「絶対悪」と考える捕虜虐待をはじめとする残虐行為に対し、全く反省の色がないばかりか、逆に占領軍の犯した罪を追及する――こうした日本の姿勢に対し、連合国はなんらかの手立てを講じなければならないと考えた。そのため、「ウォー・ギルト・プログラム」開始当初、残虐行為の暴露とその罪を理解させることに力がそそがれていたのも当然であろう。
捕虜虐待に関しては、日米間で大きな認識の差があった。そもそも日本兵も十分な食料を与えられておらず、また殴る蹴るといった暴力行為は、日本では捕虜に対してだけでなく、自国の兵士に対しても頻繁に行われていたばかりか、通常の社会生活でも当たり前にみられた行為であった。日本軍では捕虜になることが禁じられていたため、おのずと捕虜に対する待遇も厳しいものとなった。
前回の「戦後日本人の思考回路を作った?対日宣伝工作の真実」で紹介したように、「ウォー・ギルト・プログラム」で追及された残虐行為は、捕虜虐待のような敵兵に対する行為だけではなかった。
勝てないとわかっていても投降を許さなかったこと、傷ついた兵士を見捨てたこと、自決を強要したことなど、自国の兵士に対する非人道的な扱いや、占領地住民に残虐行為を行ったことで国際社会での日本の評価を落としたことなどを、「日本人に対する罪」として糾弾していた。
また、たとえ上官に命令されて行った行為だとしても、罪であることには変わらないとしていた。つまり「ウォー・ギルト・プログラム」で追及された残虐行為の罪とは、戦時国際法違反といった法的な観点だけでなく、「暴力はどのような状況においても罪である」という人道的な観点も伴っていたことになる。
変わりゆくプログラム
「ウォー・ギルト・プログラム」といえば、「太平洋戦争史」および「真相はこうだ」のイメージが強いかもしれないが、この2つは1945年末から1946年初めにかけての、プログラムの開始当初に行われた施策である。
実はプログラムでは、この2つが終了した後、その質・量ともに大きな変化が起こった。
当初の心配をよそに、占領は軌道に乗り日本の政治形態の骨格も完成しつつあった。そのため、当初あった「敗戦の真実」を理解させる必要性は消滅した。
同時に、占領方針が日本側に配慮した宥和路線へと変化したこともあり、しだいに「ウォー・ギルト・プログラム」はGHQの重点政策から外れていった。ただし、東京裁判が開始され、BC級戦犯を裁く横浜裁判も継続中であったことから、両裁判の目的を理解させるために裁判報告のラジオ番組は継続された。
その後、東京裁判の判決を前に、一部の国民の間で東條英機を賛美する傾向が見られたことから、再度プログラムを活性化する提案が出された。だが、結局それは計画倒れに終わった。
ただし、プログラム自体は細々と横浜裁判が終了するまでは行われていたようである。もっともそれは、占領開始直後に見られた、「敗戦の真実」と「戦争の有罪性」を理解させるために積極的に情報発信を行う、初期のプログラムとは異なったものであった。
私たちは「洗脳された」のか?
ところで、読者にとって最も関心があるのは、「ウォー・ギルト・プロラム」は日本人にどのような影響を与えたのか、つまるところは日本人が「洗脳」されたのかどうかではないだろうか。
「ウォー・ギルト・プログラム」が、GHQに都合の良い情報のみを発信したという点において、プロパガンダであったことに疑う余地はない。
だがその影響、とりわけ「洗脳」に関して、筆者がここで資料に基づいた学術的な検証結果を示すことは難しい。そもそも「洗脳」という言葉をどう定義するのかによって答えが変わるうえに、こうした検証には社会学および心理学からのアプローチも必要になるからである。
ただ一つ確かに言えることは、「ウォー・ギルト・プログラム」で重視された捕虜虐待の罪に関していえば、日本人が理解したとは言い難いということである。
占領終了後、戦犯救済運動が盛り上がり、多くのBC級戦犯が赦免された。この運動の背景には、残された戦犯家族の恩給問題もあったが、それ以上に、捕虜虐待に関する罪が理解されていないことがあった。とりわけ、上官から命じられて虐待行為を行ったものに対しては、同情すら向けられていた。
現在では、捕虜虐待の事実は忘れ去られているに等しい。昭和天皇や今上天皇の欧州訪問時に、英蘭の退役軍人が抗議の意思を表した事実や、オバマ大統領の広島訪問時に、米国の退役軍人が日本軍に虐待された捕虜の同行を求めた事実に対し、いったいどれほどの日本人が関心を払ったであろうか。
また日本人は今でも、上から命じられて行った行為に対しては、たとえそれが罪であろうと、寛容である。
占領期に、日本人に「敗戦の真実」と「戦争の有罪性」を認識させるために行われた情報教育政策「ウォー・ギルト・プログラム」は、「軍国主義を排除して、二度と米国の脅威とならない民主主義国家を作る」という米国の国益のために行われたものである。その一方で人道的理念にも支えられていたものであった。
終戦前の対日心理作戦から日本人に向き合い、原爆投下という自らの非人道的行為に苦悩しつつもプログラムを推進したブラッドフォード・スミスやスタッフは、今頃雲の上から現在の日本に対して、何を思っているのだろうか。










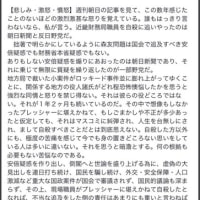




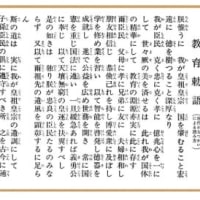




非人道的行為を行ってたのは日本だけではないし、太平洋戦争に持ち込んだのはハルノートがきっかけである。
周りのアジアが植民地にされていることに対し、小国ながらよく戦い、またそれがきっかけでアジアの独立も増えていったのは事実。
あの餓死寸前でも何も知らなくても沢山の大切な人、物をなくしても耐えてきた人々、原爆を落とされても戦争だったんだから仕方ない、勝者がルールを作るから仕方ないと耐えてきた人々。敗戦後もここまで作り上げた人々を悪く言うことはできない。今、自分に降りかかるなら到底無理な心中だと思う。
アメリカを悪く言うんではなく、虐殺行為もしたり、されたり、日本だけが特別ではない
時代だっただけだ。