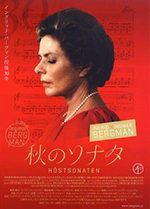
Story
ノルウェーの美しい田園地方の牧師館で、夫と静かに暮らすエーヴァ(リブ・ウルマン)は、7年も会っていない母のシャロッテ(イングリット・バーグマン)を自宅に招くために、手紙を書いた。
老いても美しく華やかなシャルロッテは、今も世界を飛び回るピアニストだ。高級車を運転して牧師館に到着したシャロッテと、笑顔で抱き合うエーヴァ。だが、登場人物たちは、お互いを観察し、その心情を探り合う。彼らは皆、心の中に満たされない思いを抱えているのだ。
シャロッテは、この家に、もう一人の娘ヘレーナが同居していると聞いて動揺した。脳性麻痺で寝たきりのヘレーナは長く療養所に預けられていたが、母親のシャロッテは見舞いに行かず、退院にも気づいていなかったのだ。
夕食後、エーヴァは母のピアノ演奏に圧倒され、母を尊敬していた子供の頃の心情が蘇った。幼いエーヴァは母親を恋しく慕ったが、演奏旅行と奔放な恋で留守勝ちだったシャロッテは、自宅では練習に没頭し、家族を省みない女性だった。
その夜、シャロッテと二人きりで語り合うエーヴァ。酒を飲んだエーヴァは、酔いに任せて娘時代の鬱積をぶちまけた。暇な時だけ過剰に干渉する母に苦しみつつ、嫌われまいとびくびくして暮らしたと、初めて本音で話し、母を責めるエーヴァ。自分も苦しんだと反論するシャロッテ。二階から必死に母を呼ぶヘレーナの声には気づかずに、シャロッテは翌日、牧師館を後にした。
数日後、エーヴァは母のシャロッテに、「まだ手遅れではない」と手紙を書くのだった。(Wikipediaより引用。人名部分をパンフ表記に変更。)
1978年/スウェーデン/イングマール・ベルイマン監督作品
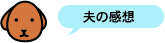
評価 ★★★★☆
てっきり、バーグマンとリブ・ウルマンがピアノを弾きながら静かに語り合う映画だと思っていたのですが、まさかこんなに激しい内容だったとは・・・。
7年ぶりの再会で最初は喜び合う2人。しかし、バーグマン演じる母親のシャロッテが難病のもう一人の娘に接するあたりから2人の間にきしみが生じ始める。エーヴァ(ウルマン)が過去のわだかまりを爆発させ、シャロッテを糾弾します。2人の表情を追うカメラが一歩も引かずすごい緊迫感をはらんで展開します。エーヴァがシャロッテをなじるシーンは下手なホラーより怖い。難病の妹は母親の愛情を必死にほしがるエーヴァの分身ではないかと思えて来ます。
エーヴァが、事故で亡くした息子の部屋で心情を吐露する場面。ここで、”境界”の概念について語るのですが、彼女は”境界”を取り払っている、だから無数の現実が重なり合って存在しているのが理解できる。だから息子も生きていると感じることができると。私はこの場面が妙に引っかかっているのですが、もしかしたら境界という概念がこの映画を理解するキーワードではと。エーヴァが境界を無くした女だとすれば、シャロッテは境界線をつくってその中で生きる人ですね。2人が衝突するのはそこに原因があるのかもしれません。
シャロッテが去った後エーヴァが和解の手紙を書くのですが、その内容が私にはどうしても空虚に思えたのでした。実際、亭主のヴィクトルが読んだ後、無造作に封筒に押し込みましたからね。やれやれまた2人の喧嘩に付き合わされるのか、という感じ。(映画の冒頭でも、シャロッテを家に呼ぶとなったときにパイプをポイと放り投げて、やっかいな人が来るな、という気持ちを醸し出したりしてました。)結局人間とはそう簡単に変われないものですから2人が本当の意味で和解することはなく、また同じことが繰り返されるのではと思いました。ヴィクトルは直感的にそのことを感じたのではないでしょうか。
離れると恋い焦がれ、会うと反発する。まさに愛憎相半ばするアンビバレントな母娘関係を強烈に描いた秀作です。

評価 ★★★★☆
ほとんど、バーグマンとリヴ・ウルマンの会話だけで進行する物語なのですが、2人の演技の迫力に終始目が釘付け状態でした。
リブ・ウルマンは、バーグマン演じる母親を糾弾する側で、その演技はとても真に迫ってくるものがあります。一方の糾弾される側のバーグマンはその表情の演技がすごく巧みで、敢えて演技に優劣をつけるとすれば、バーグマンが一歩抜きん出ていたかなと感じました。
表情と言えば、2人でショパンの前奏曲を引く場面。ウルマンが弾くのをみるバーグマンの表情、今度はバーグマンが弾く時のウルマンの表情。2人の表情にこれまでの互いへの想いが凝縮されているようでとても印象に残っています。
それから、現在進行中の場面はクロースアップが多いのですが、回想場面になるとカメラが引いて全体像を映し出す感じになり、そこで起こっていることを観客に想像させる、という手法がとても効果的だと思いました。
ウルマンの少女時代に、バーグマンが十分な愛情を注がず抑圧してしまったのが、そもそもの悲劇の始まりだと思います。この母親は、難病の娘に接する態度もそうなのですが、とにかくひどい現実には眼を向けないというか、全て自分の理想とする姿に統一しないと収まらない人なのですね。この映画は極端な例なのですが、私も育児をしている関係上、バーグマン演じる母親は反面教師として良い参考になったような気がします。
映画『秋のソナタ』公式サイト
(「秋のソナタ」2013年 10月 塩尻市 東座 にて鑑賞。)
ノルウェーの美しい田園地方の牧師館で、夫と静かに暮らすエーヴァ(リブ・ウルマン)は、7年も会っていない母のシャロッテ(イングリット・バーグマン)を自宅に招くために、手紙を書いた。
老いても美しく華やかなシャルロッテは、今も世界を飛び回るピアニストだ。高級車を運転して牧師館に到着したシャロッテと、笑顔で抱き合うエーヴァ。だが、登場人物たちは、お互いを観察し、その心情を探り合う。彼らは皆、心の中に満たされない思いを抱えているのだ。
シャロッテは、この家に、もう一人の娘ヘレーナが同居していると聞いて動揺した。脳性麻痺で寝たきりのヘレーナは長く療養所に預けられていたが、母親のシャロッテは見舞いに行かず、退院にも気づいていなかったのだ。
夕食後、エーヴァは母のピアノ演奏に圧倒され、母を尊敬していた子供の頃の心情が蘇った。幼いエーヴァは母親を恋しく慕ったが、演奏旅行と奔放な恋で留守勝ちだったシャロッテは、自宅では練習に没頭し、家族を省みない女性だった。
その夜、シャロッテと二人きりで語り合うエーヴァ。酒を飲んだエーヴァは、酔いに任せて娘時代の鬱積をぶちまけた。暇な時だけ過剰に干渉する母に苦しみつつ、嫌われまいとびくびくして暮らしたと、初めて本音で話し、母を責めるエーヴァ。自分も苦しんだと反論するシャロッテ。二階から必死に母を呼ぶヘレーナの声には気づかずに、シャロッテは翌日、牧師館を後にした。
数日後、エーヴァは母のシャロッテに、「まだ手遅れではない」と手紙を書くのだった。(Wikipediaより引用。人名部分をパンフ表記に変更。)
1978年/スウェーデン/イングマール・ベルイマン監督作品
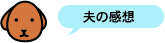
評価 ★★★★☆
てっきり、バーグマンとリブ・ウルマンがピアノを弾きながら静かに語り合う映画だと思っていたのですが、まさかこんなに激しい内容だったとは・・・。
7年ぶりの再会で最初は喜び合う2人。しかし、バーグマン演じる母親のシャロッテが難病のもう一人の娘に接するあたりから2人の間にきしみが生じ始める。エーヴァ(ウルマン)が過去のわだかまりを爆発させ、シャロッテを糾弾します。2人の表情を追うカメラが一歩も引かずすごい緊迫感をはらんで展開します。エーヴァがシャロッテをなじるシーンは下手なホラーより怖い。難病の妹は母親の愛情を必死にほしがるエーヴァの分身ではないかと思えて来ます。
エーヴァが、事故で亡くした息子の部屋で心情を吐露する場面。ここで、”境界”の概念について語るのですが、彼女は”境界”を取り払っている、だから無数の現実が重なり合って存在しているのが理解できる。だから息子も生きていると感じることができると。私はこの場面が妙に引っかかっているのですが、もしかしたら境界という概念がこの映画を理解するキーワードではと。エーヴァが境界を無くした女だとすれば、シャロッテは境界線をつくってその中で生きる人ですね。2人が衝突するのはそこに原因があるのかもしれません。
シャロッテが去った後エーヴァが和解の手紙を書くのですが、その内容が私にはどうしても空虚に思えたのでした。実際、亭主のヴィクトルが読んだ後、無造作に封筒に押し込みましたからね。やれやれまた2人の喧嘩に付き合わされるのか、という感じ。(映画の冒頭でも、シャロッテを家に呼ぶとなったときにパイプをポイと放り投げて、やっかいな人が来るな、という気持ちを醸し出したりしてました。)結局人間とはそう簡単に変われないものですから2人が本当の意味で和解することはなく、また同じことが繰り返されるのではと思いました。ヴィクトルは直感的にそのことを感じたのではないでしょうか。
離れると恋い焦がれ、会うと反発する。まさに愛憎相半ばするアンビバレントな母娘関係を強烈に描いた秀作です。

評価 ★★★★☆
ほとんど、バーグマンとリヴ・ウルマンの会話だけで進行する物語なのですが、2人の演技の迫力に終始目が釘付け状態でした。
リブ・ウルマンは、バーグマン演じる母親を糾弾する側で、その演技はとても真に迫ってくるものがあります。一方の糾弾される側のバーグマンはその表情の演技がすごく巧みで、敢えて演技に優劣をつけるとすれば、バーグマンが一歩抜きん出ていたかなと感じました。
表情と言えば、2人でショパンの前奏曲を引く場面。ウルマンが弾くのをみるバーグマンの表情、今度はバーグマンが弾く時のウルマンの表情。2人の表情にこれまでの互いへの想いが凝縮されているようでとても印象に残っています。
それから、現在進行中の場面はクロースアップが多いのですが、回想場面になるとカメラが引いて全体像を映し出す感じになり、そこで起こっていることを観客に想像させる、という手法がとても効果的だと思いました。
ウルマンの少女時代に、バーグマンが十分な愛情を注がず抑圧してしまったのが、そもそもの悲劇の始まりだと思います。この母親は、難病の娘に接する態度もそうなのですが、とにかくひどい現実には眼を向けないというか、全て自分の理想とする姿に統一しないと収まらない人なのですね。この映画は極端な例なのですが、私も育児をしている関係上、バーグマン演じる母親は反面教師として良い参考になったような気がします。
映画『秋のソナタ』公式サイト
(「秋のソナタ」2013年 10月 塩尻市 東座 にて鑑賞。)













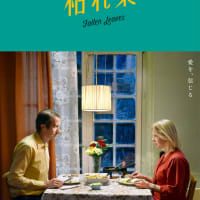




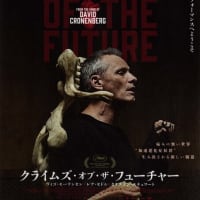







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます