
ローマ、それは永遠の都。
ローマとは、現在ではイタリア半島にある国家イタリアの首都。あるいは、カトリック教会の中枢であるヴァチカン市国のことである。・・・そう、考える人が多いと思います。
しかし、多少なりとも歴史の教養がある人なら、「ローマ」と聞けば、「神聖ローマ帝国」あるいは「古代ローマ帝国」のことかと思い至るのではないでしょうか。
今回は、後者の「古代ローマ帝国」についてです。まぁ、「古代」なんて歴史の特殊語なんてとっぱらって、「ローマ帝国」としたほうがよいのですが。
『 ローマ人の物語 』
著:塩野七生 刊行:新潮社 1992年から毎年刊行
この本は、ローマ帝国について、その成り立ちから偉大なまでに栄えた時期、そしてその衰亡までを、できるだけ克明に、かつ分かり易く著述したものです。
著者の塩野女史は、もともとイタリア在住の作家。イタリアのルネサンス時代やローマ法王庁、ヴィザンティン帝国などをテーマにした、歴史小説なんだか学術論文なんだか判別の難しい著作を発表している人です。
ローマ人に惚れ込んで、それをきっかけに、その国と人々について書くことを決心したとも言われていて、本書もなかなか熱が込められた文章が綴られています。
この手の本は、ともすれば大学教授の書くような、論述展開がややこしく、小難しい言い回しも多く、結論も曖昧模糊としているようなモノが多い。
ですが、この『ローマ人の物語』は、塩野女史自身が「“わかりたいこと”を書くのです」と言っているように、「何故、ローマ帝国は偉大なまでに発展し、なおかつ滅んでしまったのか」が解るように、あるいは思い当たるように述べられていくので、大変読みやすい。また、ローマ史の人物・・・例えば、ハンニバル、キケロ、ユリウス・カエサル、アウグストゥス・・・といった『人間』に焦点を当てているため、常に頁を繰るその先に強い関心を保ち続けることが出来ます。つまり、学術書と違って、読んでいて「飽きない」ということです。
思い返せば、私も卒論を書いていた時期、この手の事をいつも感じていました。
結論を導くためとはいえ、ごちゃごちゃした事を述べていかねばならない。政策、政令、法令、制度のみを述べる。なんとつまらなかったことか。
人間を扱わない以上、その文章は活き活きとはならず、必然的につまらないものにならざるを得ないのかもしれません。
ローマ史は、長い。建国がB.C.700年頃といわれ、A.D.395年に東西に分裂。西ローマ帝国はA.D.476年に、東ローマ帝国はA.D.1453年にそれぞれ滅亡します。西ローマ帝国だけを見ても、その興亡は1000年のスパンで。東ローマ帝国も含めたら、2000年のスパンです。
そのため、『ローマ人の物語』は、1992年から毎年一冊が刊行されていくスタイルを取っています。一冊がほぼ450ページ以上で、なんと全15冊予定。まさしく大著です。
現在、13冊まで刊行され、残り2冊。
私自身は、第8冊目の『危機と克服』から読み始め、次に第4冊目の『ユリウス・カエサル ルビコン以前』を読む、という飛ばし読みを試みています。
(ええ、別に構いません。私は一応、西洋史概説の講義で、ローマ史はひととおり終えましたので。なんとか歴史の流れは解りますから・・・)
かつて、歴史を学ぶのは、「教養」であると言われた時代がありました。
現代では、役に立たないと酷評される歴史ですが。それでも、どこの国でもいい、幾許かでも歴史を知るということは、少なくとも未来の予測には役に立つ。
まして、「人間」の行動、行為を知ることには、むずむずする面白さがあると思います。
ローマ人たちの歴史を、人間の営みを、活き活きと語る『ローマ人の物語』シリーズ。なかなかに魅惑的です。
ローマとは、現在ではイタリア半島にある国家イタリアの首都。あるいは、カトリック教会の中枢であるヴァチカン市国のことである。・・・そう、考える人が多いと思います。
しかし、多少なりとも歴史の教養がある人なら、「ローマ」と聞けば、「神聖ローマ帝国」あるいは「古代ローマ帝国」のことかと思い至るのではないでしょうか。
今回は、後者の「古代ローマ帝国」についてです。まぁ、「古代」なんて歴史の特殊語なんてとっぱらって、「ローマ帝国」としたほうがよいのですが。
『 ローマ人の物語 』
著:塩野七生 刊行:新潮社 1992年から毎年刊行
この本は、ローマ帝国について、その成り立ちから偉大なまでに栄えた時期、そしてその衰亡までを、できるだけ克明に、かつ分かり易く著述したものです。
著者の塩野女史は、もともとイタリア在住の作家。イタリアのルネサンス時代やローマ法王庁、ヴィザンティン帝国などをテーマにした、歴史小説なんだか学術論文なんだか判別の難しい著作を発表している人です。
ローマ人に惚れ込んで、それをきっかけに、その国と人々について書くことを決心したとも言われていて、本書もなかなか熱が込められた文章が綴られています。
この手の本は、ともすれば大学教授の書くような、論述展開がややこしく、小難しい言い回しも多く、結論も曖昧模糊としているようなモノが多い。
ですが、この『ローマ人の物語』は、塩野女史自身が「“わかりたいこと”を書くのです」と言っているように、「何故、ローマ帝国は偉大なまでに発展し、なおかつ滅んでしまったのか」が解るように、あるいは思い当たるように述べられていくので、大変読みやすい。また、ローマ史の人物・・・例えば、ハンニバル、キケロ、ユリウス・カエサル、アウグストゥス・・・といった『人間』に焦点を当てているため、常に頁を繰るその先に強い関心を保ち続けることが出来ます。つまり、学術書と違って、読んでいて「飽きない」ということです。
思い返せば、私も卒論を書いていた時期、この手の事をいつも感じていました。
結論を導くためとはいえ、ごちゃごちゃした事を述べていかねばならない。政策、政令、法令、制度のみを述べる。なんとつまらなかったことか。
人間を扱わない以上、その文章は活き活きとはならず、必然的につまらないものにならざるを得ないのかもしれません。
ローマ史は、長い。建国がB.C.700年頃といわれ、A.D.395年に東西に分裂。西ローマ帝国はA.D.476年に、東ローマ帝国はA.D.1453年にそれぞれ滅亡します。西ローマ帝国だけを見ても、その興亡は1000年のスパンで。東ローマ帝国も含めたら、2000年のスパンです。
そのため、『ローマ人の物語』は、1992年から毎年一冊が刊行されていくスタイルを取っています。一冊がほぼ450ページ以上で、なんと全15冊予定。まさしく大著です。
現在、13冊まで刊行され、残り2冊。
私自身は、第8冊目の『危機と克服』から読み始め、次に第4冊目の『ユリウス・カエサル ルビコン以前』を読む、という飛ばし読みを試みています。
(ええ、別に構いません。私は一応、西洋史概説の講義で、ローマ史はひととおり終えましたので。なんとか歴史の流れは解りますから・・・)
かつて、歴史を学ぶのは、「教養」であると言われた時代がありました。
現代では、役に立たないと酷評される歴史ですが。それでも、どこの国でもいい、幾許かでも歴史を知るということは、少なくとも未来の予測には役に立つ。
まして、「人間」の行動、行為を知ることには、むずむずする面白さがあると思います。
ローマ人たちの歴史を、人間の営みを、活き活きと語る『ローマ人の物語』シリーズ。なかなかに魅惑的です。










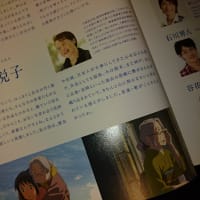
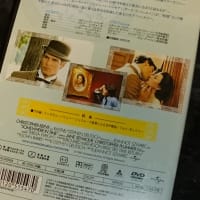

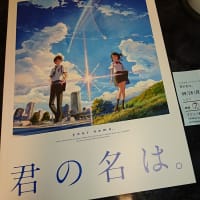






 Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。
Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。




