
新聞というものが、凋落してしまい 久しいですが、皆さま、たまには活字をお読みでしょうか。
私は、新聞の定期購読はしておらず、コンビニにて購入しています。 大体、1ヶ月に 10日分程度でしょうか。
最近は、日経新聞しか読んでいません。
なぜかと云うと、朝日新聞は変態的に左派ですし、毎日・産経も狂気的。 読売新聞は、偏りすぎない右ではあるけれども、「球界の独裁者」のタイトルホルダーが会長をなさっているからか、なんともいえない記事の珍妙味。
さらに、日本の新聞の旧弊というべきか、記事の内容の薄さと、署名記事の少なさから、定期購読するほどではないかな~…と。
まだ、VoCE か anan を購読した方がマシかな?
ネットにて、ニュースもただ流し状態ですし、まぁ…紙媒体を、わざわざ買うほどでもないし。 上記のような新聞は、買うほどのおもしろさもないかな~…と。
「買うほどには、おもしろい」―― そう思わさせられるものが、世界の政治や社会問題、文化などについて報道し、各種コンテンツも豊富な 週刊誌『 Newsweek (ニューズウィーク) 日本版 』 です。
デジタル版と、紙媒体のものとありますが、もっぱら紙媒体のものを、書店などにて購入します。
「ベッドサイド・ライブラリー」として、就寝前にも読み物をベッドに持ち込んだりしますので、とかく紙を好むのです。 読み終われば、スキャンしてお気に入りの部分だけデータ化してスクラップブックにして、不要なら、リサイクルに回しますし。 デジタルとアナログとでバランスをば。
***
震災と原発とは、もちろんまったく別モノのテーマなどではありません。複雑に関係しています。
ただ、原発事故のそれは、事故が「地震によって引き起こされた」ものであるにもかかわらず、「設計ミスや人的ミスによって引き起こされた」ものであるかのように、日本のメディア報道はなされている傾向が強い―― もとい、強すぎます。
事故や事件といった、「起こったことを、そのまま伝えること」を目的とし、記者会見や現場取材したものをそのまま記事にした、「ストレート記事」。
また、事故や事件が、なぜ起きたのかなどについて、「解説・分析を加えて書かれたもの」には、記者の署名が入る事から、「署名記事」。
―― 大まかですが、大別二つのタイプがあります。 日本の新聞、それに少なからぬ雑誌は「無署名記事」が多い。
署名の有る無しは、いわゆる、報道の真摯さ・信念に通じていると思いますので、私は署名記事の多いものを好みます。
たとえ、朝日新聞でも、「教育問題」についての記事は、読ませる力のあるものが多いので、たまには買います。
まぁ―― ふだんは買わないんですが。
ニューズウィークは、全編 ほぼ署名記事。 まぁ、それだけなら、ただのリベラル雑誌なんですが。
ニューズウィークの姿勢に、感心させられるのは、「文句たれ」ではないこと。
***
最新号2011/03/30号では、 『想定されていた 「フクシマ」 の暴走』 とタイトルを付けて、6ページの特集が組まれています。
福島第一原発のリスクは、実際 以前から警告はされていた。
東電による 津波対策にては、想定以上を「想定せず」。 県議団との遣り取り。
原子炉格納容器からの、「排気決断の遅延疑惑」。 政府の顔色うかがい――。
東電と政府の連携のまずさ。 「統合対策本部」設置は、15日。 実に、地震発生から4日後。
…などなど、通り一遍の、事実とその分析を客観的に、分かりやすく―― 下手な日本の週刊誌より、手短に分かりやすく報道。
また、対応が、遅きに失したことは、しっかり批判する。
ですが、最後のまとめの段階で、問いかけるのです。
地震発生前の日本国民の原発への関心はどうであったかと。
原子炉の過去の事故を例に挙げたあと、大意 以下のように続ける。
いかなる事故が起きても、時がたてば国民の恐怖心は消え、興味・関心を失う。
メディアもまた、監視の目をゆるめたのだ。
日本は資源が乏しい以上、エネルギーを安定供給できる唯一の方法は、「原発」しかなかった。
日本の電力の3割は原発が供給する。
その一斉停止は、不可能ではないか。 電力不足による、経済活動や生活の不便さは、皮肉にも今回のことで、身に沁みたろう。
事故の経緯は、詳細に検証され、再発防止に活かさねばならない。
しかし、いかに事故を起こさぬように努力しても、リスクをゼロにはできない。想定外の事態は、いつでも起こり得る。
ゼロに近づける努力は 出来るが、そのためにも、「綺麗事ではない情報の公開」が必要。
どれだけの確率で、どのような事故が起きるのか。
放射性物質の放出がやむを得ないとして、どれくらいの量が検出される可能性があるのか。
崩壊した家屋を見た我々には、冷静に受け止める準備は出来ているはずだ。
原発と正面から向き合ってこそ、原発のリスクと利便性を てんびんに掛けることが出来るだろう。
***
エネルギー資源問題は、実に1970年代オイルショック当時から言われていたし、原発の利便性とリスクもまた、言われ続けた。
日本は、それを慎重に秤にかけ、決を出したのではなかったか。
破局を迎えないように、努力し続けた電力会社と原発は、たしかにあるのです。
関心を失い、電力会社に、慎重な点検・対策を練るよう・行うように監視し続けなかったのは、確かに我々国民であり、原発付近の住民であったのです。
誰かを血祭りにあげるのは、たしかにスッキリしますし、ガス抜きによいでしょう。 目の前の不安から、逃げも出来る。
ただ、それだけでなく、未来を視ることも必要。
ジャーナリストは、事実を伝える時も、自信と冷静さを失わず、それによって国民にパニックにならず、平常心を取り戻すよう働きかけるように 努めるべきではないでしょうか。
合衆国は、テロ9・11の時、ジャーナリストが率先してパニックを起こし、結局 全員が過ちを犯しました。
その経験が、今回の様な国外での大災害を報道する、ニューズウィークの その記事の姿勢にも表れていると感じます。
「知識と経験とが、恐怖に対する最良の武器」―― そう言われます。
ただの「文句たれ」 だけでは、百害あって、一利があるか、ないか―― うん、ないんじゃないでしょうか。
願わくば、アエラのような 『放射能が来る!!』 という、およそ良識を疑う表紙を付ける雑誌を読む読者ばかりでないことを願ってやみません。
***
―― もちろん、2か月向こうぐらいには、東電のボンクラ幹部はフルボッコですが。
まさか、水がたまっているであろう場所に、長靴なしに作業員を送り込むほど アフォとは思いませんでした。
安全確認や 非常時の対応を、何も考えて無かったんですかねぇ…。










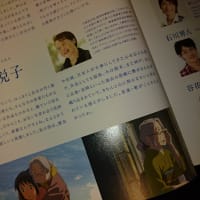
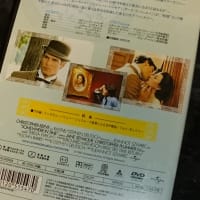

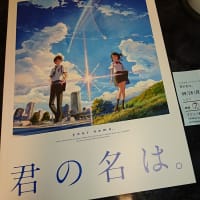






 Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。
Name; Melville
モットーは「Bygones!」
JAPAN辺境四国在住。




