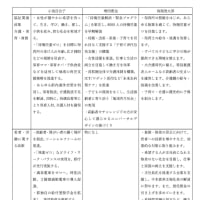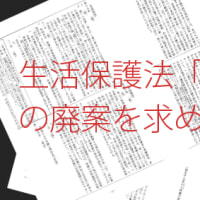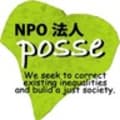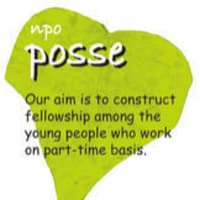日本経団連と連合が首脳懇談会…春闘、事実上スタート (読売新聞)
春闘が始まった。日本は今、史上最長の好景気を持続し、企業はバブル時代を上回る利益を確保している。
では、なぜ経団連は賃上げを拒むのだろうか。
●景気回復=賃金が下がったから!?
今回の景気回復を牽引したのは若者である。ある経済学者の研究によると、企業は小泉改革の5年間に利益を12兆円増やしたが、労働者全体の賃金は同じく12兆円減っているという。つまり、働く人へ分配する額が減った分だけ景気が良くなっているにすぎないのだ。
その中でも特に分配が減らされたのが、若者の労働者なのだ。
フリーターはイメージとは異なって、低賃金で正社員並みの労働を行っているし、若者の正社員の賃金や福祉は切り下げられているのだ。
経団連が賃上げを拒むのも当然である。彼らは企業努力を行うことよりも、徹底的な賃金引き下げ戦略を世界に先駆けて行い、それで景気回復を実現させているのだから。
●M&A中心の企業活動に
なぜこんなことになったのか?
こうした若者の使い捨て戦略が可能となったのにはそれなりの理由がある。グローバル化と規制緩和は、企業で長期間に渡り人材を育成したり、戦略を 立てることを無意味化しつつあるのだ。企業の評価システムがアメリカの圧力でかわり、短期的な利益がそのまま企業の評価と直結するようになった。短期的な 利益を出すには、リストラ(フリーターの増加)が一番てっとりばやい。
リストラによって一時的に利益を増える→増えた利益は株主の配当にまわす→株価が上がる→株式を転売して利益がでる。
こうしたM&A中心の企業活動が公然と行えるように、小泉改革が行われたのだ。
●春闘の役割って!?
ちなみに春闘というのは、日本独特な行事だ。これは、日本の労働組合の特殊性から来ている。普通の欧米の労働組合は、企業ごとではなくて、産業ご とに作られている。そこでは日常的に業界団体と業種別組合の代表が討議し、労働条件を決めている。ところが、日本の場合は企業別なので、そうしたことがで きない。交渉力も皆無に等しい。
それを補うために、年に一回全体で議論しよう、という制度なのだ。
次に、労働組合が強いことは必ずしも経営側にとってマイナスではない。「労働政治」と言われる現象だが、経営側は強力な労働組合をうまく利用してきたのだ。つまり、強力な組合のトップと話をつける。そしてその組合に労働者を支配させる、というある種の癒着構造がある。
日本の春闘は、だから労働者のためということもあろうが、経団連にとっても利用しがいのある制度だと言えるだろう。
このまま経団連にまるめこまれて、若者の状況改善は今年も実現できない、などということにならないようにしてほしいものだ。
最新の画像もっと見る
最近の「ニュース解説・まとめ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事