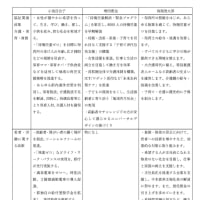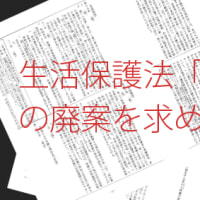「労働審判制度」をご存じだろうか。この制度は、昨年4月から始まった新しい労働紛争処理システムだ。労使間で解雇や労働条件の内容についてトラブルが起こったとき、労働者は裁判に訴え、契約内容について争うことができる。しかし、既存の裁判システムは非常に時間や労力がかかり、多大なコストを強いる。そこでこの労働審判制度が登場するに至ったのだ。
労働審判制度は、3回の審理で決着がつく。数ヶ月で終わるという早さだ。これまでの裁判が何年間にも及んできたことを考えれば、極めて効率的な制度と言えよう。こうしたスピード解決を実現するために、審理は労働側委員と使用者側委員そして裁判官という三者の審判員が審理を行う。彼らは労働事件に精通しており、素早く論点を見つけ出す。労働審判での結審は法的な拘束力は持たないが、この審理を通じて双方の主張を整理し、仮に裁判を行ったとしても妥当な「落としどころ」がどこにあるかを示すことができる。(従って労働審判制度では、スピード解決に向かない複雑な法的論点を持つ事件については扱わないことになっている)。そのため双方がおおよその解決内容を納得し、法的な拘束力が無くとも審理を受け入れることが見込まれるという。
この制度が昨年4月に始まり、同年12月までにあつかった案件は603件。そのうち解決した事例が427件(7割)となっている。これは非常に高い解決率だ。しかも、同制度を開始した後も労働裁判の案件は増えているというから、これまで「コスト」を気にして法的な措置を取ることができなかった層が活用していると見ることができるだろう。
このように、労働審判制度はその目的に照らして大きな効果をあげている。労働側にとっても、非常に使い勝手のよい制度と言える。労働弁護士と話をしていても、やはり使いやすく、解決に持ち込みやすいとの評価が多い。使用者側の審判員であっても不正を行う企業については「こういう経営のあり方はおかしい」とはっきり指摘することが多く、審理内容も悪くないというのだ。
だが、問題はないのだろうか? ここからは、華々しく見える「成果」の影に潜む問題点について検討していきたい。
・「法の解釈」をめぐって争わない
労働審判制度がはらむ問題性は、大きくいって二つあると考えられる。一つは法律の解釈を争わないということだ。通常、裁判を行えば結果として裁判所の命令が出され判例となる。つまり、一つの裁判の結果が次の事件の前例となる。働く側にとって、法的に有利な結果を勝ち取ることがそのまま普遍的な獲得物となるのだ。しかし労働審判制度はそうならない。あくまでも個別の事例を「解決」するための制度にすぎないからだ。ある有名な労働弁護士の話は興味深かった。彼が言うには、この制度を活用するようになって以来、労働事件は即解決する仕事になってしまい、落としどころが見えやすく張り合いが無くなったという。一つの裁判の結果が判例となり、法律の解釈の内容を普遍的に争うという緊張感の喪失が、現場の指揮レベルにも影響しているという。こうした傾向は今の法制度全般にもついても言える。法による正義や、新しい解釈を争うのではなく、法が専ら「手続き」の次元に引き下げられつつあるのだ。これまですでに形成された解釈や、行政通達(=行政による解釈)が大きな力を持ち、実際の裁判は正義や公正を争わない。始める段階からすでに結果が見えてしまっている。
格差社会が深刻さを増し、人々の不満が増大する中、国家は福祉を増大させるのではなくスピード解決で即決の裁判を「使いやすく」提供することで対応しているのだろう。こうした中で法は形骸化し、社会のあり方をめぐって闘争する闘技場としての性格をなくし、ただ現状を追認し正当化する装置と化すのである。
・労組=集団性の意義を掘り崩す

次に、労働審判制度は労働組合の意義を掘り崩す危険性をもっている。日本の労働組合法は非常に優れた内容をもっている。それは、個人加盟でも労働組合を結成できるからだ。最近では地域別や産業別で非常に有意義な活動をしているユニオンが多数活躍している。(「ユニオン」とは労働組合を横文字にしたもので、同じ意味です。ただ慣行上、個人加盟できる労働組合を「ユニオン」と呼ぶ場合が多いようだ)。
彼らは一人一人の個別の事件を、職場を超えた集団的な力で解決を図る。一人の問題を集団の力で解決することによって、さらにその力を増していく。そうした営みは労働側の力を増大させ、産業レベルで労使の関係性に影響を与えることができ、さらには国家レベルの政策決定や産業構造のあり方へも切り込むことが可能である。
労働審判制度が拡充していく中で逆にこうした集団による解決が衰退しないか、ということが第二の懸念だ。
そもそも労働審判制度などのADR(=裁判外紛争解決)は労働組合の集団性の低下に対応するために生み出されてきた。たとえば、これまで労働組合と使用者の間の紛争を調整するために存在してきた地方の労働委員会も、今では法律が改正され、個別個人の相談に応じるようになっている。このように、労働現場の紛争を個別に解決するという趨勢は、一貫して生じてきており、その延長線上に労働審判制度の発足がある。
だが、こうした紛争の個別化(=アトム化)の進行は重大な問題を孕んでいる。本来労使の紛争は、労働側が集団になることによって行われるべきものだとされてきた。その理由は端的に二つあり、すなわち①個別の労働者は使用者に対して、社会的に弱い立場にあり、さらに②労働市場において労働者は、お互いに競争状態(低い賃金で働くほうが雇われる)にあるため、それが使用者に対する交渉力を弱めるからだ。使用者にとって労働者はいくらでも代わりがいるのである。つまり、労働者は使用者に対して社会的に弱い立場にあり、しかも労働市場の原理が労働者間の競争を生み出すため、個別の労働者は使用者との交渉力をさらに弱くしてしまうということだ。
こうした状況を「フィクションとしての市民社会」ということがある。本来「市民社会」とは、対等な立場で契約を結び、自由に経済活動を諸個人が行える社会のことを指している。今の日本社会の建前も、こうした平等な市民社会である。しかし、労働者と使用者の関係ではそうならず、圧倒的に使用者が有利な環境の下に契約が結ばれるのが普通だ。だから市民社会は常に「フィクション」だということになる。こうした力の不均衡を是正し、市民社会の建前を実現するために制定されたのが労働組合法なのだ。
そのため労働組合は非常に大きな力を持っている。労働基準法などと比べても、労組法は比較にならないほどの法的拘束力を持っている。それは、労使の問題は本来労働組合を作り、集団的に解決することによって、「力の不均衡」という市民社会のフィクションを乗り越え、対等な関係で社会関係を結ぶことを、法律が予定しているからだ。このことは、言い換えれば労働組合に加入しなければ、本来の「対等な決定」という市民社会の原則は守られないということに他ならない。
以上をまとめると、労働者は集団性を持つことによって、①個別の交渉力を高めることができ、②労働者間の競争を抑制して、産業全体の労働条件の水準を引き上げることが可能となり、③国家に働きかけ、法制定による規制を実現する回路を持つことができるようになる。
本題に戻ろう。労働審判制度は、それ自体としては個別の紛争の処理に役立っているといえるだろう。だが、こうした個別紛争処理システムは、高い集団性が確立している社会の下でしか本来の役割を果たすことはできない。なぜなら、「②労働者間の競争を抑制して、産業全体の労働条件の水準を引き上げることが可能とならず」、集団で労働条件を交渉する枠組みがない中では、「妥当な解決の社会的水準」それ自体が引き下げられていくからだ。個別の紛争は産業構造や、社会全体の労働条件水準を引き上げることができない。個人のままでは社会的な力関係は変化させないし、労働者間の競争を緩和して社会全体の労働条件の向上も望むこともできないのだ。それどころか労働審判制度は、本来労働組合に加入し、紛争を解決していく過程で集団性を獲得し、労働市場全般の規制力の強化を促していくべき人々から、集団性獲得の機会を簒奪してしまう効果を持つ危険性があるとさえいえるのではなかろうか。こうした状況では「③国家に働きかけ、法制定による規制を実現する回路を持つことができるようになる」への道をも閉ざしてしまうだろう。
もし個別紛争として解決を行わず、個人加盟ユニオンに加盟していたならば、同じ解決であっても、社会的な意義はまったく異なったものになる。集団性の確立は個別の問題を解決するだけではなく、社会的規範水準の向上への道筋をも作り出すものなのだ。
・進行するアトム化
ここで、なぜ今労働審判制なのか、ということについてもう少し述べておきたい。現在日本では、非正規雇用化が著しく進行している。派遣労働や契約社員、パート・アルバイトがとても増えてきており、すでに全雇用者の4割程度がそうした働き方をしている。こうした非正規雇用化の進行は、二つの現象をもたらす。まず、非正規雇用のほとんどは働く期間が定められている「有期雇用」なので、多くの会社を横断し流動的に働くことになる。そのため会社単位で構成されることがほとんどの日本の労働組合はそうした人々をほとんど組織化できない(むしろ、積極的に排除さえしてきた)。第二に、非正規化は「働き方の多様化」をもたらす。みんなが同じ時間、同じ場所で働くわけではなくなるし、労働条件もまちまちになって、定まった基準も存在しない。こうした状況では一つの目標を掲げて集団になることは極めて難しくなるのだ。
しかし、すでに述べたように労使間の紛争は集団的に解決することが前提とされており、事実、そのようにしか有効に解決できない。裁判で争うにも、多大なコストがかかってしまう。しかし一方で集団性は無くなってきている。そこで、行政が仲介に入って解決する枠組みや、個人でも司法を有効に活用できるように対策が講じられてきているのだ。しかしこれらの施策は、ますます問題を個別化していくだろう。
こうした中で、労働者の集団性は低下の一途をたどっている。これまでの職場単位で構成されてきたほとんどの日本の労働組合は、非正規雇用として職場を流動化する人々を集団性の中に組織化することができないでいるのだ。しかし、一部の人々が実現しているように、職場を流動化する批正雇用労働者でも労働組合を作ることができる。日本の労働組合法はそうした意味では非常に進歩的な内容を持っている。こうした制度を活用し、社会全体の水準を向上させようと取り組み始めたユニオンも多い。こうした動きが広がっていけば、あえて個別紛争解決システムを活用しなくとも、個別紛争解決の道筋は集団性の中でつくることができるのだ。そうして確立した集団性は、「②労働者間の競争を抑制して、産業全体の労働条件の水準を引き上げることが可能と」し、「③国家に働きかけ、法制定による規制を実現する回路を持つことができるように」する可能性を開くのだ。
・アトム化に抗して
このように、第一の懸念は労働審判制度が法の形骸化を促進し、現在の秩序を正当化するという今日の法の傾向を促進しないか、というものである。そして第二の懸念は、非正規雇用化の中で労働者の集団的規制力が減退している日本において、労働審判制度がそうした傾向を加速させていくものになるのではないか、ということだ。
では、労働審判制度はなくしたほうがいいのだろうか?
最後に、この点について私の意見を述べておきたい。

ここまで述べてきたように、労働審判制度は個別紛争解決システムとしては高い効果を発揮している。だが、そもそも「個別紛争解決」というところに大きな問題を抱えている。それは集団性の獲得による労使の対等化という根本原理に反し、また法の形骸化を推進するものだからである。であれば、集団性獲得の獲得や法の実質化と労働審判制度が共存することができれば問題は解決し、むしろ労働審判制度は疑いなく優れた制度となる。
そこで思うことは、流動化や多様化の進行していく中で、「集団性」の内容も必然的に変化せざるを得ないのではないか、ということだ。これまでの集団性は一つの会社を拠点とし、同質な(正社員・男性)人々を凝集するものであった。だが、これから求められる集団性は、多様で流動的な人々が凝集するのではなく、移動しながら、多様性を保持しつつつながっていく(ネットワーク的な)ものでなければならないだろう。
私たちPOSSEは「LAW! DO! ~法律を守らせよう、法律を活用しよう~」というキャンペーンを行っている。そこで労働相談を受けているのだが、POSSE自体はNPOであるので、いわゆる労働組合ではない。だが前述の事情から、私たちの世代にとって労働組合はとてもなじみがなく、いきなり相談に行くには敷居が高い。だから、私たちのところに相談に訪れる人がたくさんいるのだ。こうした人たちは、行政の労働相談や弁護士に相談する層に近いのではないだろうか。また、職場を流動している人々にとっては、むしろさまざまな場所な内容のユニオン(地方を含む)をネットワークでつなぐNPOへの参画は魅力的だろう。つまり、POSSEでは労働組合からこぼれた層から労働相談を受けているということになる。POSSEでは、ただ個別の労働相談に応じ解決することを目指すのではなく、そこから集団性を獲得して行く道筋を示すことを目標にしているのである。
私はこれから、NPOによるこうした層に対する受け皿づくりはますます必要になってくると思う。そうした人々が単に個別の問題として自分の紛争を解決するのではなく、NPOなどの、広い意味でも集団性に入ってくることができれば実際上の労働運動の層は厚みを増し、社会的規制力を向上させていく道筋に加わることができる。事実、POSSEでは労働組合法に基づく交渉を行うべき場面では、ユニオンへの加入を推奨している。何かの形で労働運動、いいかえるならば社会的連合の中に入っていることがとても大事なのだ。こうした「新しい集団性」は、働く人の交渉力を新しい形で保障し、いずれは大きなレベルでの制度設計への参画も可能にするだろう。すなわち、②労働者間の競争規制や、③国家の法制定への介入を実現していく回路を、より幅広い人々のネットワークへの参加を得ることによって、実現していく可能性が得られるのだ。
さらに一方で、新しい集団性の形成されることは、法の形骸化にも対抗することができる。法も社会集団の対抗の中で「解釈」が争われてきたからだ。新しい集団性が、法をめぐって争うとき、そこは単なる手続きの場ではなく、解釈をめぐる闘技場と化すだろう。「法の活用」はその内容を社会的文脈の中で位置づけられることによって、新たな意味をもつ。「LAW!DO!」をPOSSEが行うことには、こうした意義があるのだ。
労働審判制度が法の形骸化を促進するとしても、集団性の獲得による社会的規範水準の向上という文脈の中にさえあれば(つまりNPOやユニオンの支援の下で行われるのであれば)、例え解決の過程が「手続き的」であったとしても常に社会的対抗の内容を争うものにならざるをえないのである。
このように、そもそもの個別紛争化=アトム化を促してきた従来の集団性の解体に対し、ネットワークによる新しい集団性を確立し、その中で労働審判制度を活用することによって、この制度の意義は反転するだろう。さらに、集団性の中で行われる「法の活用」は現状の正当化を行わせるのではなく、法の解釈をめぐる闘技場へと変化させるに違いない。
労働審判制度は、「LAW! DO! ~法律を守らせよう、法律を活用しよう~」やユニオンの支援があるという文脈の中でこそ意義を持ちうる。これが私の結論だ。(今野)