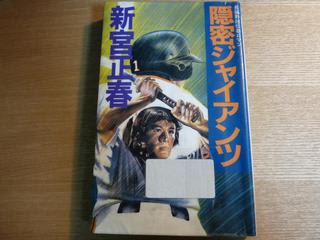
まずは、巨人・清武代表の声明全文、そして記者との一問一答をお読みください(どちらも別ウインドウで開きます)。
■ プロ野球・巨人の清武代表、渡邉恒雄会長の「人事独裁」を内部告発 (「声明」全文あり)(ニコニコニュース・2011年11月11日)
■ 【巨人】清武代表緊急会見一問一答(ニッカン・2011年11月11日)
それにしても驚きました。コンプライアンス(法令順守)上の重大な件、しかもプロ野球界のルールにかかわることで、場所もあろうに文科省で会見を行うという予告だけでも驚きましたが、内容も完全に予想の外側でした。
「コンプライアンス」という言葉からすれば、思いつくのは反社会的団体との関係発覚。しかし会見場所は文科省。となれば、やはりアマ関係者への裏金か……などと考えていたら、結果はまるで違う話だったのです。
ここで、「コンプライアンス」という言葉について確認しておきましょう。
【コンプライアンス】 事業活動において法律を遵守すること、広くは倫理や道徳などの社会的規範を守って行動すること。一般には、法令遵守と訳される。
企業不祥事が企業に与えるダメージは、事態収束のために要する直接コストのみならず、信用失墜、ブランド・イメージ低下、社会的制裁など極めて大きい。企業不祥事が発生しないようにコンプライアンスを重視することは、経営の最重要課題の1つとなっている。(グロービスのMBA経営辞書・2011年11月11日閲覧)
つまり、コンプライアンスを単純に理解するなら、法令や規範を遵守することとなりそうです。ただ、ここで気になるのは、渡邊会長による人事介入が、はたしてコンプライアンスに関わることなのかです。
確かに、最高権力者たるべきオーナーを無視して人事をゴリ押ししようとしたならば、かつ、清武代表が言うように、オーナーの地位すら左右しようとしたのならば、一般通念からはズレているとは思います。
とはいえ、これが法令に違反するとは言えないでしょう。社会的規範には合わないような気もしますが、さりとていわゆる「不祥事」とみなすことには違和感があります。
それだけに、コンプライアンス上の重大な問題という事前の話からすると、会見の内容にはいささか肩透かし感、いや、むしろ猫だまし感を覚えました。
ですが、だからといって清武代表の会見に意味がないということは決してありません。むしろ大アリです。
ネット上で見かけた意見でなるほどと思ったのですが、清武代表が非難する問題とは、コンプライアンスというよりも、巨人という球団のガバナンスの問題です。
清武代表が批判したのは、権限がない者が人事を「鶴の一声で覆した」ことです。そして、自分より職位が上のはずのオーナーを、さも当然のように挿げ替えようとする発言です。
とすれば、これは巨人、もっといえば読売グループにおいて、本来あるべき企業統治のシステムに反して威力を行使する個人が存在することへの批判となります。つまり、読売新聞グループの企業統治への批判なのです。
そして、そのような問題を読売グループは自ら解決することができなかった。できていれば、身内のゴタゴタを世間に晒すことなどないはずです。このことこそが最大の問題ではないかと、私などは思います。
ともあれ、清武代表は球団やグループ内部での解決を諦め、公開の場で渡邊会長を批判する道を選びました。正直に言って、私は第一報を見た時に胸のすくような思いを感じました。
もちろん、清武代表も無条件の義人ではないかも知れません。彼なりの計算があって会見を開いたのだとは思います。
とすると、どのような計算があったのか?この点については憶測に憶測を重ねるよりほかありませんが、だとしても考えていくと、感心させられる点は少なくありません。
清武代表は自らが属する企業グループの「ドン」にケンカを売るわけですから、グループ内や部下、同僚に味方を求めることは極めて困難です。
だとすれば、味方は外に求めるしかありません。その際に頼るべき相手として、一方では公的な権力を持つ機関、もう一方では一般世論を外すことはできません。
その点で、文科省の記者クラブで、かつニコニコ生放送という新興ジャンルのメディアを絡めた会見を開いたのは大正解ですし、その慧眼に感服してしまいました。
文科省といえば、東日本大震災の発生にもかかわらず、当初予定通りの開幕を目論んだセ・リーグを正面から批判したのが記憶に新しいところです。そして、当時開幕時期を押し通そうとしたのがまさに渡邊会長なのです。
とすると、渡邊会長に反旗を翻す際の後ろ盾として、文科省に期待するのは当然と言えるでしょう。今後は予断を許しませんが、記者クラブでの会見を認めたわけですから、現時点では非好意的とは言えますまい。
そして一般世論の支持を得る上で、既存メディアにのみ頼るのは危険ですし、ネット上のメディアなど、新興メディアを絡めることは絶対に欠かせません。
その理由の1つは言うまでもなく、既存メディアの最大手が味方になってくれないことです。もう1つは、ネット上を中心とするプロ野球ファンなら、「ナベツネ批判」に同調することが期待されることです。
とすれば、世論の支持を拡大するには、ネットを中心に、かつ野球好きを起点としていくのが最も確実だと思われます。さらに、生放送というインパクトの強い、かつ編集されずに済む手段を使ったのも正解です。
ですが、はたして清武代表が何の迷いもなくインターネット放送を利用したかというと、少なからず疑問を感じます。
清武代表は読売新聞の記者として歩んできた人物です。だとすれば、新聞というメディアへの愛着は、われわれが感じるよりはるかに強く持っているはずです。
そのような人物が、新聞を含め既存のメディアを脅かす(少なくとも、脅かしかねない)メディアを利用することに、何のためらいもなかったとはとても思えません。むしろ、葛藤を感じる方が自然ではないでしょうか。
そしてそれゆえに、読売グループにとって清武球団代表の行動は苦々しく思えるかも知れません。残念なことですが、利敵行為ととらえる人がいても仕方ないな、とすら思います。
ですが、だからこそ、清武球団代表の捨て身の批判を読売新聞グループにぜひとも真摯に受け止めてほしいと、私は切に願います。
そうせずに、自らにとって都合のいいことのみを紙面で書き連ねるならば、読売新聞グループは自浄作用を発揮する空前絶後の機会を、自らの手で潰すことになってしまいます。
そしてそれは、日本のメディア、そしてメディアを利用するわれわれ自身にとって、決して好ましいことではないのです。
ともあれ、これで巨人を含めた読売新聞グループのガバナンスに1つの穴が開きました。一人の人間の恣意に左右される体制に中から一石が投じられ、その石が外に出てきたのです。
はたして、この穴はすぐにふさがるのか?あるいは拡がっていって、ガバナンス自体を崩してしまうのか?
個人的には、後者を期待してしまいます。その理由の1つは、今のガバナンスはもはや持続可能とはとても思えないからです。
そしてもう1つは、今のガバナンスが崩れ去った後に、全く異なる新たなガバナンスを築く努力こそが、巨人のみならずプロ野球界全体に好ましい影響を生むのではないかという期待を持たずにはいられないからなのです。
■ プロ野球・巨人の清武代表、渡邉恒雄会長の「人事独裁」を内部告発 (「声明」全文あり)(ニコニコニュース・2011年11月11日)
■ 【巨人】清武代表緊急会見一問一答(ニッカン・2011年11月11日)
それにしても驚きました。コンプライアンス(法令順守)上の重大な件、しかもプロ野球界のルールにかかわることで、場所もあろうに文科省で会見を行うという予告だけでも驚きましたが、内容も完全に予想の外側でした。
「コンプライアンス」という言葉からすれば、思いつくのは反社会的団体との関係発覚。しかし会見場所は文科省。となれば、やはりアマ関係者への裏金か……などと考えていたら、結果はまるで違う話だったのです。
ここで、「コンプライアンス」という言葉について確認しておきましょう。
【コンプライアンス】 事業活動において法律を遵守すること、広くは倫理や道徳などの社会的規範を守って行動すること。一般には、法令遵守と訳される。
企業不祥事が企業に与えるダメージは、事態収束のために要する直接コストのみならず、信用失墜、ブランド・イメージ低下、社会的制裁など極めて大きい。企業不祥事が発生しないようにコンプライアンスを重視することは、経営の最重要課題の1つとなっている。(グロービスのMBA経営辞書・2011年11月11日閲覧)
つまり、コンプライアンスを単純に理解するなら、法令や規範を遵守することとなりそうです。ただ、ここで気になるのは、渡邊会長による人事介入が、はたしてコンプライアンスに関わることなのかです。
確かに、最高権力者たるべきオーナーを無視して人事をゴリ押ししようとしたならば、かつ、清武代表が言うように、オーナーの地位すら左右しようとしたのならば、一般通念からはズレているとは思います。
とはいえ、これが法令に違反するとは言えないでしょう。社会的規範には合わないような気もしますが、さりとていわゆる「不祥事」とみなすことには違和感があります。
それだけに、コンプライアンス上の重大な問題という事前の話からすると、会見の内容にはいささか肩透かし感、いや、むしろ猫だまし感を覚えました。
ですが、だからといって清武代表の会見に意味がないということは決してありません。むしろ大アリです。
ネット上で見かけた意見でなるほどと思ったのですが、清武代表が非難する問題とは、コンプライアンスというよりも、巨人という球団のガバナンスの問題です。
清武代表が批判したのは、権限がない者が人事を「鶴の一声で覆した」ことです。そして、自分より職位が上のはずのオーナーを、さも当然のように挿げ替えようとする発言です。
とすれば、これは巨人、もっといえば読売グループにおいて、本来あるべき企業統治のシステムに反して威力を行使する個人が存在することへの批判となります。つまり、読売新聞グループの企業統治への批判なのです。
そして、そのような問題を読売グループは自ら解決することができなかった。できていれば、身内のゴタゴタを世間に晒すことなどないはずです。このことこそが最大の問題ではないかと、私などは思います。
ともあれ、清武代表は球団やグループ内部での解決を諦め、公開の場で渡邊会長を批判する道を選びました。正直に言って、私は第一報を見た時に胸のすくような思いを感じました。
もちろん、清武代表も無条件の義人ではないかも知れません。彼なりの計算があって会見を開いたのだとは思います。
とすると、どのような計算があったのか?この点については憶測に憶測を重ねるよりほかありませんが、だとしても考えていくと、感心させられる点は少なくありません。
清武代表は自らが属する企業グループの「ドン」にケンカを売るわけですから、グループ内や部下、同僚に味方を求めることは極めて困難です。
だとすれば、味方は外に求めるしかありません。その際に頼るべき相手として、一方では公的な権力を持つ機関、もう一方では一般世論を外すことはできません。
その点で、文科省の記者クラブで、かつニコニコ生放送という新興ジャンルのメディアを絡めた会見を開いたのは大正解ですし、その慧眼に感服してしまいました。
文科省といえば、東日本大震災の発生にもかかわらず、当初予定通りの開幕を目論んだセ・リーグを正面から批判したのが記憶に新しいところです。そして、当時開幕時期を押し通そうとしたのがまさに渡邊会長なのです。
とすると、渡邊会長に反旗を翻す際の後ろ盾として、文科省に期待するのは当然と言えるでしょう。今後は予断を許しませんが、記者クラブでの会見を認めたわけですから、現時点では非好意的とは言えますまい。
そして一般世論の支持を得る上で、既存メディアにのみ頼るのは危険ですし、ネット上のメディアなど、新興メディアを絡めることは絶対に欠かせません。
その理由の1つは言うまでもなく、既存メディアの最大手が味方になってくれないことです。もう1つは、ネット上を中心とするプロ野球ファンなら、「ナベツネ批判」に同調することが期待されることです。
とすれば、世論の支持を拡大するには、ネットを中心に、かつ野球好きを起点としていくのが最も確実だと思われます。さらに、生放送というインパクトの強い、かつ編集されずに済む手段を使ったのも正解です。
ですが、はたして清武代表が何の迷いもなくインターネット放送を利用したかというと、少なからず疑問を感じます。
清武代表は読売新聞の記者として歩んできた人物です。だとすれば、新聞というメディアへの愛着は、われわれが感じるよりはるかに強く持っているはずです。
そのような人物が、新聞を含め既存のメディアを脅かす(少なくとも、脅かしかねない)メディアを利用することに、何のためらいもなかったとはとても思えません。むしろ、葛藤を感じる方が自然ではないでしょうか。
そしてそれゆえに、読売グループにとって清武球団代表の行動は苦々しく思えるかも知れません。残念なことですが、利敵行為ととらえる人がいても仕方ないな、とすら思います。
ですが、だからこそ、清武球団代表の捨て身の批判を読売新聞グループにぜひとも真摯に受け止めてほしいと、私は切に願います。
そうせずに、自らにとって都合のいいことのみを紙面で書き連ねるならば、読売新聞グループは自浄作用を発揮する空前絶後の機会を、自らの手で潰すことになってしまいます。
そしてそれは、日本のメディア、そしてメディアを利用するわれわれ自身にとって、決して好ましいことではないのです。
ともあれ、これで巨人を含めた読売新聞グループのガバナンスに1つの穴が開きました。一人の人間の恣意に左右される体制に中から一石が投じられ、その石が外に出てきたのです。
はたして、この穴はすぐにふさがるのか?あるいは拡がっていって、ガバナンス自体を崩してしまうのか?
個人的には、後者を期待してしまいます。その理由の1つは、今のガバナンスはもはや持続可能とはとても思えないからです。
そしてもう1つは、今のガバナンスが崩れ去った後に、全く異なる新たなガバナンスを築く努力こそが、巨人のみならずプロ野球界全体に好ましい影響を生むのではないかという期待を持たずにはいられないからなのです。




















清武専務はGM兼任とのことですんで、ご自身の職分を侵害され、球団GM制が空洞化するのを恐れた……ということでしょうか。
ただ、まだ昨日の段階では清武氏の主張を聞いただけですので、渡辺氏や読売球団の主張も見聞きしてみたいと思います。
かつGM制度を敷いた以上、現場の人事権はないはずです。
とすれば、自分の知らない現場の人事は認めないという資格は、制度上はありませんし、
そのようなゴリ押しが罷り通ることには、違和感を感じますね。
この件では渡邊氏の反論と清武氏の再反論が出てきたので、
それらについていずれまた書こうかなと思ってます。
私見ですが、これは一プロ野球団だけの問題ではなく、
世論形成に影響を及ぼす巨大メディアの在り方にも関わってるわけで、
その面でこそ決して無視してはならない問題だと考えています。