公明・山口代表が習近平氏と会談
国益を損なう人々は外交をやめよ
リバティニュースクリップ 1/27 転載
http://www.the-liberty.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━
◆公明・山口代表が習近平氏と会談 国益を損なう人々は外交をやめよ
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5537
公明党の山口那津男代表が25日、中国共産党の習近平総書記と
会談した。だが山口代表は、懸案の尖閣問題や歴史問題について
主張すべきことを主張しないばかりか、安倍首相の親書を渡す際に
深々と頭を下げる姿が海外メディアで報じられるなど、
日本側に負い目があるかのような印象を与えてしまった。
26日付の大手紙には、会談時の山口代表の具体的な発言内容は、
挨拶以外ほとんど紹介されていない。同日付公明新聞が詳しく報じている。
同紙によると、尖閣問題について習氏は「立場、意見が違うが、
対話と協議でコントロールしつつ問題解決すべきだ」と主張。
これに対し、山口代表は「立場の違いがあるのは事実だが、
外交上の問題は対話を通じ冷静に対応していけば必ず解決できる」
と話した。
だが、一方的に尖閣を奪いに来ているのは中国である。
「冷静に対応していけば必ず解決できる」という言葉からは、
日本と中国が尖閣に対して領有を主張する権利を、対等に
持っているかのような誤解を与える。
また、日中の歴史問題について、習氏が「直視していくことが
未来につながり、これまでの教訓を生かして慎重に対応してほしい」
とけん制したのに対し、山口代表は
「日中共有の認識を踏まえて対応し、後世に伝えていくことが大事だ」
と応えた。
この言葉もおかしい表現だ。
「日中共有の認識」とは何なのか。
「南京大虐殺で30万人が犠牲になった」という中国共産党の
でっちあげを共有するということか。
政治や外交は「言葉の勝負」である。
その意味において、今回、山口代表は敗北したと言える。
そもそも、習氏との会談が決まったのは始まる1時間半前であり、
習氏が日本側を手玉に取っていることを内外にアピールする
材料にされた。
これでは、日本の連立与党の一方の党首が、中国に「朝貢」
したようにしか見えない。
その証拠に、26日付英フィナンシャル・タイムズ紙の1面トップには、
山口代表が深々と頭を下げて習氏に親書を渡す写真が大きく掲載された。
また中国国内では、同じ場面の写真がネット上に出回り、
溜飲が下がったと喜ぶ書き込みが相次いだという。
山口代表は訪中に先立ち、中国の主張に沿った「尖閣棚上げ論」を
口にして批判を浴びた。それ以前には鳩山由紀夫元首相が「係争地」などと
発言し、南京大虐殺記念館で頭を下げた。
さらに、来週28日からは、村山富市元首相や加藤紘一・元自民党幹事長ら
親中派が訪中する。
これ以上、国益を損なう可能性の高い人々が外交の場に
出ることはやめていただきたい。(格)
【関連記事】
2013年1月22日付本欄
尖閣問題で中国の「国益」を代弁 訪中前に公明党代表
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5493
公開霊言抜粋レポート
「核で脅してアメリカを追い出し、日本を手に入れる」
習近平守護霊が明かす戦慄の野望
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=4877
◆アベノミクスは通貨戦争? 海外からの批判は近視眼的
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5536
大規模な財政出動や金融緩和といった安倍晋三首相の経済政策
「アベノミクス」に対して、「意図的に円安に誘導している」
という批判の声が海外から出ている。
ドイツの中央銀行である連邦銀行のワイトマン総裁は21日、
安倍政権の圧力が日銀の独立性を損なう恐れがあると危機感を示し、
「為替相場の政治問題化」につながりかねないと述べた。
メルケル独首相も24日、「日本を見ていて、不安が
まったくないわけじゃない」と発言し、
アベノミクスに対する不信感をにじませた。
イギリスなども、各国が競って為替を切り下げることで輸出を
増やそうとする「通貨戦争」に発展する恐れを示唆している。
日本が通貨安になれば、その分自国の輸出競争力が落ちかねない
という不安が、批判の背景に読み取れる。しかし結果的に通貨安を
招くとしても、各国が必要に応じて自国経済を刺激するための政策を
取るのは当たり前のことであり、批判されるいわれはない。
IMF(国際通貨基金)のブランシャール首席エコノミストも23日の会見で、
「通貨戦争の話は騒ぎすぎだ。各国は経済が健全な状態になるように、
正しい政策を取るべきだ」と述べている。
日本経済の低迷を招いてきたデフレの深刻さを考えれば、
財政・金融の両面から国内需要を喚起しようとするアベノミクスは
常道と言える。
確かに金融緩和は円安を招く動きだが、そもそもの問題は、
金融危機後に大幅な緩和に踏み切る各国を尻目に、日銀がデフレに
手をこまねいて過度の円高をつくってきたことだ。
安倍政権の政策は不当に安い円相場をつくるためのものではなく、
デフレを退治して、本来あるべき金融政策を取り戻そうという動きである。
アベノミクスの効果が波及し始めれば、世界経済にとっても
プラスが大きい。国内需要が喚起されれば、日本が海外から物を
買ってあげることができ、各国の経済が潤うからだ。
甘利明・経済再生担当相は英フィナンシャル・タイムズ紙
(24日付・アジア版)のインタビューで「日本は単に他国の消費で
満足するわけにはいかない。世界のリーダーになれるように、
自分たちの経済の基礎力を高めないといけない」と話している。
バブルが潰えた後の日本は、少しでも景気回復の芽が見えると
金融引き締めなどでそれを踏みつぶす誤った政策を繰り返し、
長期不況をつくった。同じ轍を踏まないよう、実際に好景気が実現するまで
粘り強く政策の効果を待つのが肝要だ。(呉)
【関連記事】
2013年1月23日付本欄
物価目標2% 政府・日銀共同声明 本格的な金融緩和は4月以降か
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5498
2013年1月3日付本欄
【2013年展望・経済編】
増税不安と金融緩和期待が交錯する中で、新経済秩序を創れるか
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5416
◆止まらない「活断層」による原発狩り
議論を打ち切り早期再稼働を目指せ
http://www.the-liberty.com/article.php?item_id=5535
原子力規制委員会の「活断層」認定による"原発狩り"が止まらない...
。










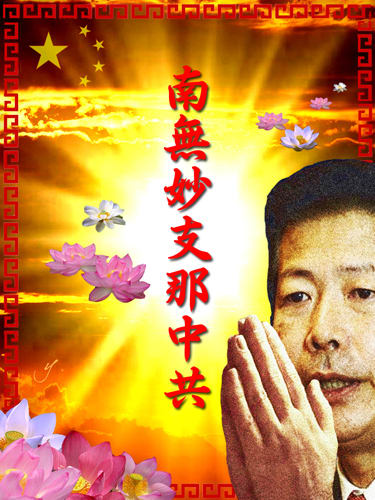
.gif)






