2009年5月30日 (土)
楠木氏の出自について(真言僧儀海の足跡より抜粋)
「…楠正成の出自については、さまざまな説が出され、商業活動に従事した隊商集団の頭目という面が強調されている。一方、楠という名字の地が摂津・河内・和泉一帯にないことから、土着の勢力という通念に疑問が出され始めている。『吾妻鏡』には、楠氏が玉井・忍・岡部・滝瀬ら武蔵猪俣党の武士団と並んで将軍随兵となっており、もとは利根川流域に基盤をもつ武蔵の党的武士であった可能性が高い。武蔵の党的武士は、早くから北条得宗家(本家)の被官となって、播磨や摂津・河内・和泉など北条氏の守護国に移住していた。河内の観心寺や天河など正成の活動拠点は、いづれも得宗領であったところであり、正成は本来得宗被官として河内に移住してきたものとおもわれる(海津一朗著『楠正成と悪党』)。新人物往来社刊『全譯吾妻鏡』二、建久元年十一月七日条、次の随兵四十二番、に楠四郎とある。海津一朗氏の説を地域的に考えれば新田氏と楠氏の接点はかなり近いと言えないだろうか。越後の新田氏の一族が義貞の旗揚げの日に間に合うのには当時の交通事情からすると、事前に義貞が楠正成と綿密に連絡をとりあっていなければと思われる。千早城攻めから義貞が撤退した時点では、すでに幕府に反旗を翻す計画が正成との間で決まっていたと思われる。…」
楠木氏の出自について(真言僧儀海の足跡より抜粋)
「…楠正成の出自については、さまざまな説が出され、商業活動に従事した隊商集団の頭目という面が強調されている。一方、楠という名字の地が摂津・河内・和泉一帯にないことから、土着の勢力という通念に疑問が出され始めている。『吾妻鏡』には、楠氏が玉井・忍・岡部・滝瀬ら武蔵猪俣党の武士団と並んで将軍随兵となっており、もとは利根川流域に基盤をもつ武蔵の党的武士であった可能性が高い。武蔵の党的武士は、早くから北条得宗家(本家)の被官となって、播磨や摂津・河内・和泉など北条氏の守護国に移住していた。河内の観心寺や天河など正成の活動拠点は、いづれも得宗領であったところであり、正成は本来得宗被官として河内に移住してきたものとおもわれる(海津一朗著『楠正成と悪党』)。新人物往来社刊『全譯吾妻鏡』二、建久元年十一月七日条、次の随兵四十二番、に楠四郎とある。海津一朗氏の説を地域的に考えれば新田氏と楠氏の接点はかなり近いと言えないだろうか。越後の新田氏の一族が義貞の旗揚げの日に間に合うのには当時の交通事情からすると、事前に義貞が楠正成と綿密に連絡をとりあっていなければと思われる。千早城攻めから義貞が撤退した時点では、すでに幕府に反旗を翻す計画が正成との間で決まっていたと思われる。…」











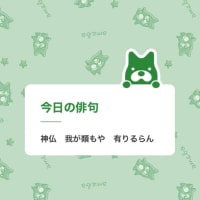








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます