都知事選の階級的本質と細川護熙候補支持の意義(下)
――マルクスは奴隷制廃止の実現へリンカーンを支持した
(前からつづく)
(C)全原発廃炉か、原発維持かの非和解的な対立
細川候補の「脱原発」、「原発ゼロ」の主張の意味、その階級的性格は、非常に明らかとなったのではないだろうか。そしてその「原発ゼロ」の旗を掲げて、小泉元首相の支援を受けた細川氏が都知事選に参入してきたのである。細川選挙戦は、文字通り細川=小泉選挙戦なのであり、それ以外ではありえない。それを踏まえるとき、今次都知事選の階級的な本質もまた浮き彫りになってくる。
●原発問題をめぐる三つの対立軸
前述したように、今次都知事選の階級的・社会的・歴史的な基底にあるものは、〈全原発廃炉か、原発維持か〉の非和解的な対立である。そこには、三つの対立軸が重なり合っている。
第一の対立軸は、3・11の衝撃を満身で受け止めて、福島を先頭にして立ちあがった脱原発運動と、日本帝国主義およびその原発維持路線の対立である。
この脱原発運動には、相当広範に、原発建設は日本の独自の核武装のためであり、原発問題は戦争問題であるという認識がある。そして、安倍政権の強引なまでの原発推進路線と、沖縄での辺野古新基地建設の執拗な追求、第9条改訂や天皇の国家元首化という憲法改正策動、特定秘密保護法の制定、国家安全保障会議の設立、靖国神社公式参拝、日本軍「慰安婦」問題のあからさまな開き直りと隠ぺいなどの攻撃が同根であるという認識がある。つまり、日本帝国主義による戦争と暗黒、搾取と差別の総体とそれに反対するたたかいとの対決は、原発維持か全原発廃炉かという対決を最大の軸として成立しているといえる。たたかう側からいえば、沖縄問題と並んで、原発問題でもっとも切迫した、そしてもっとも有利な対峙関係を形成しているのである。
第二の対立軸は、前章でみたように、日本帝国主義の支配階級の中での脱原発=ポスト原発路線か原発維持路線かの対立である。ここでの脱原発派はいまだ形成されているとはいえず、都知事選での細川勝利をとおして初めて形成されるしかない。
第三の対立軸は、日本や世界の脱原発運動と、アメリカ帝国主義の核政策――核戦争戦略およびそれと表裏をなす核不拡散政策、そして原発産業の原子力利権の保護政策――との対立である。原発問題は、アメリカ帝国主義の世界支配における不可欠の武器であり、アメリカ・ブルジョアジーの利害をかけた国際的スケールでの資本の運動の大きな推進軸なのである。菅政権―野田政権が「2030年代に原発ゼロ」へ舵を切ろうとしたことにたいして、オバマ大統領が直接に待ったをかけ、これをストップさせた。それは、諸資料からも明らかになっているところである。第三次アーミテージ報告でも、「原発再稼働」を強力に要求し、「原子力は日本の包括的安全保障の絶対に必要な要素である」としている(12年8月)。
都知事選は、原発をめぐるこうした重畳的な対立構造を基底にして、細川=小泉ラインによって形成されんとする支配階級内の脱原発派が、既存の原発維持派にたいして、ブルジョア日本の生き残りのために方向転換を迫る場となったのである。
そもそも、細川=小泉ら脱原発派は、今のままでは支配階級内のヘゲモニーをとる見通しがなかった。だが、猪瀬直樹都知事の5000万円スキャンダルによって到来した都知事選を絶好の機会ととらえた。そこから、支配階級内の抗争に勝つために、1300万人の都民を巻き込み、大衆動員の力で都知事選を制することによって、ポスト原発の路線を具体化する突破口にしようとしているのである。こうして、細川=小泉ラインにとって、都知事選は、その成否を決する文字通りの政治決戦としての性格をもつところとなっている。
彼らは、選挙戦に入ってからは、いくらかのちゅうちょの後に、第一の対立軸をつくり出している首都圏・全国の脱原発運動に掉さす選択をした。細川選対の事務局長に座っていた馬渡龍治元衆院議員(元鳩山邦夫議員秘書)の突如の解任は、その転機があったことを示している。
●細川=小泉ラインはなぜ都知事選にうって出たのか
では、なぜ、細川=小泉の支配階級内脱原発派は、都知事選出馬という劇場型政治の手法にあえて踏み切ったのか。
それは、そうする以外に、日本帝国主義の原発堅持構造のあまりにも硬い岩盤を穿つことはできないと判断したからである。
その岩盤の硬さは何によるものか。
一つは、敗戦帝国主義日本の核武装の野望である。
原発政策は核戦争政策以外の何ものでもない。原発がいかにコストのかかるものであり、巨大で過酷な事故を引き起こすものであれ、日本帝国主義が原発政策を手放さないのは、原子炉で製造されるプルトニウムを確保し、それを原料にして、いつでも核兵器製造に移行できるようにしておくためである。1950年代から「核の平和利用」などと偽って原発建設にすすんできたのも、敗戦の軛を打ち破って、再び戦争のできる帝国主義軍事大国へと飛躍するためであった。だから、歴代の自民党政権は、けっして原発政策を捨てたりはしなかったのである。
では、小泉氏は核武装の道をあきらめたのかというと、けっしてそう単純ではない。日本はすでに長崎型原発4000発に相当する約45トンのプルトニウムを持っており、それをどう確保し続けることができるか、さまざまな選択肢をさぐっているのは明らかであろう。
だが、小泉氏が都知事選を制するには、またたとえ都知事選を制したとしても、支配階級内の極少数派である脱原発派が多数派に転化するには、核武装の道の可能性を残していることを説得できなければならないであろう。そのことは、小泉氏にとって大きな壁である。まして、次に述べるように、アメリカが、3・11後の日本の原発事情をみて、昨年13年から高濃度の兵器級プルトニウムなど300キロのプルトニウムの返還を迫っている状況の中では、小泉氏は「核武装の道を捨てるのか」という非難に答えるのが難しい。
二つは、アメリカ帝国主義とその原発政策の存在である。
アメリカの側からするならば、アメリカの核軍事戦略およびエネルギー戦略に日本を組み込むものとして、戦後日本の原発路線を位置づけている。そのことで、アメリカの核政策の世界展開も、原子力利権の拡大も、可能となっているのである。そうした日米関係を規定するものが、すなわち日米原子力協定にほかならない。同協定は、非核保有国である日本に例外的に核燃料サイクル、つまり事実上の核兵器製造サイクルを認めるという特権を確認している(1968年に旧協定締結、1987年に新協定締結、翌年7月発効。18年に満期を迎える)。
事故を起こした福島第一原発をとっても、1号炉と2号炉およびそれらの核心技術はGE製であり、3号炉の東芝、4号炉の日立もGEの技術指導を受けたものである。
そのGEと日立が提携して、07年にGE日立ニュークリア・エナジーを設立している。またWHは、イギリス核燃料会社を経て、06年に東芝に売却されている。これについては、アメリカは、過酷事故が起こった場合に責任追及され、巨額の損害賠償を受けるのを回避するために、原子炉の開発・建設から撤退し、それを日本に転嫁しているといわれている。
実際、アメリカは、1979年のスリーマイル島原発事故以来、原発の新規建設を棚上げしてきたが、オバマ政権が12年2月に原子炉2基の新設を決めた。この原子炉は東芝傘下のWH製なのである。ただし、その後、米原子力規制委員会が、使用済み核燃料処理の規準が定まるまでは、原発の新設および既存原発の運転期間延長を認めないという決定を出している。このように、3・11の衝撃を受けて、オバマ政権の原子力大国路線の復活も、実は混迷している。
そうだからこそ、アメリカは、日米原子力協定を盾にして、日本の原発ゼロ化を絶対に容認しない。あくまでも、アメリカの世界大的な核軍事戦略とエネルギー戦略のコントロール下に日本を置き続けなければならない。
したがって、細川=小泉ラインの「原発ゼロ」を掲げた都知事選への登場は、アメリカへのあまりにもあからさまな挑戦という意味をもつ。国政レベルではなく、東京都のレベルではあっても、そこでの政治的・経済的な日米摩擦の大きさははかりしれない。
(D)都知事選の勝利が新たな展望を切り開く
このように、脱原発への道を阻む岩盤は硬い。細川=小泉ラインは、だからこそ、支配階級内での激しい抗争に勝つために、都知事選を劇場型政治の絶好の場として徹底的に使う手法に訴えたのである。
だが、それだけが都知事選の階級的本質ではない。前述の第一の対立軸を担う脱原発運動の主要な担い手たちが、千載一遇のチャンスととらえ、あえて敢然と細川支持の決断をしたこと、細川=小泉ラインと連携して、脱原発運動の決定的な前進をつくり出すべく総決起していることが、都知事選をして反原発・脱原発の下からの大衆運動の歴史的な再激化の場に転化させているのである。
原発問題をめぐる支配階級内の分岐もまた、3・11以来、この3年間の福島の被災者・内部被曝者を先頭とする非妥協的な脱原発の広範で粘り強い運動が生み出したものではないか。これが細川出馬をもたらした根底的な動力であることは、明々白々たる真実である。
私たち脱原発運動の側は、残念ながら独自の共同候補をもつことができなかった。その経緯は、ここでは省くが、前回の12年12月都知事選に立候補した宇都宮健児氏は、それを支える日本共産党ともども、今回の共同候補づくりの努力において大衆運動のルールを破ってしまった。それは、けっして小さな咎ではない。
独自の共同候補をもてなかった私たちは、支配階級内の鋭い分岐に介入して、その圧倒的な少数派を支援する以外になかったし、むしろここで勝利をかちとることで、脱原発への道を阻む難関の一つを決定的に破砕するチャンスを得たということではないだろうか。何度もいうが、千載一遇のチャンスとは、まさにこのことである。このたたかいに、今次都知事選の真に階級的な本質が内在している。
福島を先頭とする私たちの脱原発運動の力で細川都知事を実現するならば、一つには、細川都知事のこれからの脱原発のための政策、被災者・内部被曝者への支援と補償、国への要求、東電への追及に心棒を入れることができ、それが本物になっていく可能性が増すのである。
二つには、そうするならば、自民党内の脱原発派を析出させ、その政治行動化を促し、安倍自民党を必ずやがたがたに揺さぶるものとなろう。
三つには、そうするならば、「積極的平和主義」を掲げる安倍政権の侵略戦争と暗黒、搾取と差別の政治、それがあまりにも一方的で強権的なやり方で暴走している恐るべき現実にストップをかける転機となるであろう。じつは、細川候補支持に踏み切った多くの人々を駆り立てたものこそ、今日の安倍政治への不安感、危機感、無力感であり、追いつめられた絶望的な断崖絶壁から乾坤一擲の逆襲に出ようという決意なのである。
それを視野に入れて、私たちは、細川=小泉ラインにたいして、批判すべきをびしびし批判し、正されるべきをきっちりと正し、細川候補の当選=勝利のために奮闘すべきなのではないだろうか。
重ねていうが、〈全原発廃炉〉、〈脱原発〉は、じつに人類史的な宿願である。
これは、多くの重大な課題のうちの一つではない。あらゆる現実を規定するような大きさをもったテーマであり、これをさて措いては、他の諸問題の解決も一歩も進まないものなのである。
(E)「星条旗に『奴隷制廃止』と書きつけよ」
●マルクスたち第一インターはリンカーンの政府と軍を支持した
ところで、ここで、約150年前のアメリカ南北戦争に同時代人として際会したマルクス、エンゲルスを始めとするイギリスなどヨーロッパの革命家たちと多くの労働者人民がとった態度を想起することも、あながち無意味なことではないであろう。
マルクスたちは、周知のように、1861年4月に南北戦争が勃発するや、ただちにリンカーンとその政府および軍、つまりアメリカ合衆国、実体的には北部諸州ブルジョアジーを敢然と支持した。マルクスの論文の中には「支持」という言葉はないが、支持という言葉を使うまでもなく、ヨーロッパのたたかう人々の間では、奴隷制廃止の世界史的な大義において、それはきわめて必然的で、自明のことであった。
4年間にわたった激烈な南北戦争の間中、マルクスとエンゲルスは、戦争の推移や戦況および南北の新旧ブルジョアジーたちの動向をつぶさに分析した。そして、北部ブルジョアジーの政治的代表者であり、もともと奴隷制廃止論者ではなく、優柔不断なリンカーンを厳しく叱咤激励し、時には、南軍粉砕の戦術をも提案した。
なぜなら、アメリカ南北戦争の勝敗のいかんがヨーロッパの革命運動、労働運動の命運に直結しているという認識に立っていたからであり、奴隷解放が自分たち労働者階級自身の正面課題であると受け止めていたからである。
実際、イギリスの労働者は、自国政府の南北戦争への干渉、南軍援護に激しく反対し、繰り返し政治集会とデモをうった。当時のヨーロッパの労働者や亡命革命家たちは、ヨーゼフ・ヴァイデマイアー、アウグスト・ヴィリヒ、フリッツ・ヤーコビらを筆頭に、北軍の義勇軍に身を投じた。戦争の後期に実施された1864年11月の大統領選挙でリンカーンが当選するや、マルクスが筆をとって、同年9月に結成されたばかりの国際労働者協会、すなわち第一インターナショナルとしての祝辞を送った。リンカーンからは特別にていねいな返書があった。第一インターは、リンカーンが暗殺されると哀悼の意を表し、後継のジョンソン大統領にも激励のメッセージを送った。
●南北戦争の遂行過程とその諸結果は今日的な教訓に満ちている
マルクスたちによるリンカーンら北部諸州支持の核心点は次のようなものであった。
第一に、南北戦争をめぐる全事態を奴隷制の維持と拡大を許すか否かの戦争であるととらえたことである。
マルクスは、「南部連合の戦争は、ことばの真の意味において、奴隷制の拡大と永遠化のための侵略戦争である」と規定した。南部の中では「大奴隷制共和国の建設」などという恐るべき叫びもあがったように、北部が北部の防衛にとどまることができない戦争だとみたのである。もともと奴隷制廃止論者ではなかったリンカーンには「戦争には戦争をもってこたえるかの選択しか残されていなかった」(マルクス「北アメリカの内戦」)。
第二に、奴隷所有者の州である南部諸州連合の合衆国からの分離・独立(まさに奴隷制独立王国)を打ち砕くためには、「諸事件そのものが、決定的な標語――奴隷解放――の宣布をせまっている」として、リンカーン政府に革命的な戦争遂行方式に移行せよ、星条旗に「奴隷制廃止」という戦いのスローガンを書きつけよ、と懸命に促したことである。
黒人をただちに解放して戦闘部隊に編成し、あわせて労働者を軍事的に組織し、南部との戦いに送りこむことを提起したのであった(マルクス「アメリカの事態の批判」)。
マルクスは、リンカーンにむかって「いくじなし」、「いまだに南部に信をおいている」、「子どもにも軽蔑されるリンカーンとその政府」、「自分自身を奴隷制賛成の妥協派の道具におとしめるな」などと強く批判し続けた。そうすることで、前述したごとくにリンカーンが戦争を革命戦争方式に転換させ、前半の劣勢を立て直して、1864年4月を転機に戦争の主導権を握るにいたったことに大いに寄与したのである。
第三に、アメリカの労働者階級は奴隷制が維持されているかぎり、また黒人の奴隷労働の犠牲の上に立っているかぎり、自由ではありえないという立場があったことである。同時に、南部の黒人奴隷の犠牲による綿花を受ける位置にあったイギリスの労働者階級は、自国政府の南北戦争への干渉に繰り返し反対し、それこそ自己犠牲的に北部および黒人と連帯するたたかいに立ち上がった。マルクスたちは、そのたたかいを牽引したが、イギリス労働者階級の決起を「不朽の歴史的名誉をかちえた」とたたえたことである。
第四に、南北戦争の当事者はアメリカの新旧ブルジョアジーであったが、その相互の対立と分裂に掉さす形で、北部支持の行動を起こしたことである。
北部側には、大工業ブルジョアジーおよび勃興しつつあった金融資本家、新興ブルジョアジーがおり、南部側には、奴隷所有プランターやそれと結びついた北部の奴隷制維持に賛成の大ブルジョアジーがいた。労働者階級と本来的に敵対するブルジョアジーの一方を支持したのは、奴隷制廃止の決定的な意義をつかんでいたからなのである。
マルクスは、南北戦争での勝利が北部アメリカの労働者にとっての社会的・歴史的な「進歩」であることを謳うとともに、「奴隷制反対戦争が労働者階級の権力を伸長する新しい時代をきりひらくであろうと確信しています」と宣言したのであった(「リンカーン再選への祝辞」)。
しかし、内戦の終結の結果、戦争のための国債の重荷がアメリカ労働者階級に犠牲的に一方的に転嫁されたのである。金融資本家が跋扈し、戦争の甘い汁を吸った戦争成金が肥え太る一方で、「アメリカの労働者の地位の悪化」がもたらされたのであった。この現実を前にして、マルクスは、リンカーンの政府を支持したことの意義を揺らぐことなく断固として確認したのであった。「労働者階級の苦難にもかかわらず、内戦は、奴隷を解放し、その結果として諸君自身の階級の運動に精神的刺激をあたえたがゆえに、これらのことを償ってあまりあるものであった」と訴えたのだった(マルクス起草第一インター評議会「アメリカ合衆国全国労働同盟への呼びかけ」)。
以上のように、マルクスたちがアメリカ南北戦争にあたってリンカーンの政府と軍を支持してたたかったことには奥深い意味があり、その意義は不滅である。
それは、〈奴隷制廃止〉というまさに人類史的な大義を第一義的に重んじた、同時代人としての優れた政治的決断であったといえる。マルクスやエンゲルスはもとより、当時のヨーロッパの労働者階級の政治的・思想的な深さと高さに、改めて感服するところである。何よりも、そこに貫かれた思想――労働者階級の解放は、ただ人間の全人間的解放としてのみ実現され、また同時に、ありとあらゆる人間の解放は労働者階級の解放を条件としてのみ実現されるという思想――の豊かさを、学ぶことができよう。
(F)細川候補を支持し、すべての脱原発票を細川に集中しよう
さて、私たちは、全原発廃炉を全世界的に実現する重大な課題の前にいる。日本帝国主義の体内にあるすべてのおぞましさを体現するかのように、恐るべき反動と腐敗のかぎりを尽くす安倍政権と対峙するところに、私たちはいる。率直にいって、私たちは、今日の独特の階級的力関係の中で、非常な危機、つまり主体的な危機に立たされている。それは端的にいえば、じつに広範で多様性をもった、しかも非妥協的な原則を貫ける運動の力がありながら、その党派的な表現をもちえていないという主体的な危機にほかならない。
この主体的な危機を直視するとき、残り少なくなった都知事選の日々をどうたたかうか、問題は鮮明ではないだろうか。
歴史の発展段階も異なり、基礎にある社会的諸条件や階級的諸関係も違うが、南北戦争をめぐるマルクスたち第一インターのたたかいの教訓に思いをめぐらせるならば、今日、日本支配階級内部に形成されつつある脱原発派と連携してたたかうという、かつてなかったようなあり方に、きっぱりと確信をもつことができるのではないだろうか。
重ねていうが、〈全原発廃炉〉、〈脱原発〉は、じつに人類史的な宿願である。
これは、多くの重大な課題のうちの一つではない。あらゆる現実を規定するような大きさをもったテーマであり、これをさて措いては、他の諸問題の解決も一歩も進まないものなのである。
3・11以来、3年間にわたって持続し拡大しつつある脱原発運動に強い確信をもとう。かつ沖縄・名護市長選挙での稲嶺進氏再選の勝利、さらに南相馬市長選挙での桜井勝延氏再選の勝利、この沖縄と福島における感動的な勝利を引き継ごう。今、ここで首都東京における脱原発都知事の誕生を何としてもなしとげようではありませんか。
2014年1月30日
隅 喬史(すみ・たかし)
――マルクスは奴隷制廃止の実現へリンカーンを支持した
(前からつづく)
(C)全原発廃炉か、原発維持かの非和解的な対立
細川候補の「脱原発」、「原発ゼロ」の主張の意味、その階級的性格は、非常に明らかとなったのではないだろうか。そしてその「原発ゼロ」の旗を掲げて、小泉元首相の支援を受けた細川氏が都知事選に参入してきたのである。細川選挙戦は、文字通り細川=小泉選挙戦なのであり、それ以外ではありえない。それを踏まえるとき、今次都知事選の階級的な本質もまた浮き彫りになってくる。
●原発問題をめぐる三つの対立軸
前述したように、今次都知事選の階級的・社会的・歴史的な基底にあるものは、〈全原発廃炉か、原発維持か〉の非和解的な対立である。そこには、三つの対立軸が重なり合っている。
第一の対立軸は、3・11の衝撃を満身で受け止めて、福島を先頭にして立ちあがった脱原発運動と、日本帝国主義およびその原発維持路線の対立である。
この脱原発運動には、相当広範に、原発建設は日本の独自の核武装のためであり、原発問題は戦争問題であるという認識がある。そして、安倍政権の強引なまでの原発推進路線と、沖縄での辺野古新基地建設の執拗な追求、第9条改訂や天皇の国家元首化という憲法改正策動、特定秘密保護法の制定、国家安全保障会議の設立、靖国神社公式参拝、日本軍「慰安婦」問題のあからさまな開き直りと隠ぺいなどの攻撃が同根であるという認識がある。つまり、日本帝国主義による戦争と暗黒、搾取と差別の総体とそれに反対するたたかいとの対決は、原発維持か全原発廃炉かという対決を最大の軸として成立しているといえる。たたかう側からいえば、沖縄問題と並んで、原発問題でもっとも切迫した、そしてもっとも有利な対峙関係を形成しているのである。
第二の対立軸は、前章でみたように、日本帝国主義の支配階級の中での脱原発=ポスト原発路線か原発維持路線かの対立である。ここでの脱原発派はいまだ形成されているとはいえず、都知事選での細川勝利をとおして初めて形成されるしかない。
第三の対立軸は、日本や世界の脱原発運動と、アメリカ帝国主義の核政策――核戦争戦略およびそれと表裏をなす核不拡散政策、そして原発産業の原子力利権の保護政策――との対立である。原発問題は、アメリカ帝国主義の世界支配における不可欠の武器であり、アメリカ・ブルジョアジーの利害をかけた国際的スケールでの資本の運動の大きな推進軸なのである。菅政権―野田政権が「2030年代に原発ゼロ」へ舵を切ろうとしたことにたいして、オバマ大統領が直接に待ったをかけ、これをストップさせた。それは、諸資料からも明らかになっているところである。第三次アーミテージ報告でも、「原発再稼働」を強力に要求し、「原子力は日本の包括的安全保障の絶対に必要な要素である」としている(12年8月)。
都知事選は、原発をめぐるこうした重畳的な対立構造を基底にして、細川=小泉ラインによって形成されんとする支配階級内の脱原発派が、既存の原発維持派にたいして、ブルジョア日本の生き残りのために方向転換を迫る場となったのである。
そもそも、細川=小泉ら脱原発派は、今のままでは支配階級内のヘゲモニーをとる見通しがなかった。だが、猪瀬直樹都知事の5000万円スキャンダルによって到来した都知事選を絶好の機会ととらえた。そこから、支配階級内の抗争に勝つために、1300万人の都民を巻き込み、大衆動員の力で都知事選を制することによって、ポスト原発の路線を具体化する突破口にしようとしているのである。こうして、細川=小泉ラインにとって、都知事選は、その成否を決する文字通りの政治決戦としての性格をもつところとなっている。
彼らは、選挙戦に入ってからは、いくらかのちゅうちょの後に、第一の対立軸をつくり出している首都圏・全国の脱原発運動に掉さす選択をした。細川選対の事務局長に座っていた馬渡龍治元衆院議員(元鳩山邦夫議員秘書)の突如の解任は、その転機があったことを示している。
●細川=小泉ラインはなぜ都知事選にうって出たのか
では、なぜ、細川=小泉の支配階級内脱原発派は、都知事選出馬という劇場型政治の手法にあえて踏み切ったのか。
それは、そうする以外に、日本帝国主義の原発堅持構造のあまりにも硬い岩盤を穿つことはできないと判断したからである。
その岩盤の硬さは何によるものか。
一つは、敗戦帝国主義日本の核武装の野望である。
原発政策は核戦争政策以外の何ものでもない。原発がいかにコストのかかるものであり、巨大で過酷な事故を引き起こすものであれ、日本帝国主義が原発政策を手放さないのは、原子炉で製造されるプルトニウムを確保し、それを原料にして、いつでも核兵器製造に移行できるようにしておくためである。1950年代から「核の平和利用」などと偽って原発建設にすすんできたのも、敗戦の軛を打ち破って、再び戦争のできる帝国主義軍事大国へと飛躍するためであった。だから、歴代の自民党政権は、けっして原発政策を捨てたりはしなかったのである。
では、小泉氏は核武装の道をあきらめたのかというと、けっしてそう単純ではない。日本はすでに長崎型原発4000発に相当する約45トンのプルトニウムを持っており、それをどう確保し続けることができるか、さまざまな選択肢をさぐっているのは明らかであろう。
だが、小泉氏が都知事選を制するには、またたとえ都知事選を制したとしても、支配階級内の極少数派である脱原発派が多数派に転化するには、核武装の道の可能性を残していることを説得できなければならないであろう。そのことは、小泉氏にとって大きな壁である。まして、次に述べるように、アメリカが、3・11後の日本の原発事情をみて、昨年13年から高濃度の兵器級プルトニウムなど300キロのプルトニウムの返還を迫っている状況の中では、小泉氏は「核武装の道を捨てるのか」という非難に答えるのが難しい。
二つは、アメリカ帝国主義とその原発政策の存在である。
アメリカの側からするならば、アメリカの核軍事戦略およびエネルギー戦略に日本を組み込むものとして、戦後日本の原発路線を位置づけている。そのことで、アメリカの核政策の世界展開も、原子力利権の拡大も、可能となっているのである。そうした日米関係を規定するものが、すなわち日米原子力協定にほかならない。同協定は、非核保有国である日本に例外的に核燃料サイクル、つまり事実上の核兵器製造サイクルを認めるという特権を確認している(1968年に旧協定締結、1987年に新協定締結、翌年7月発効。18年に満期を迎える)。
事故を起こした福島第一原発をとっても、1号炉と2号炉およびそれらの核心技術はGE製であり、3号炉の東芝、4号炉の日立もGEの技術指導を受けたものである。
そのGEと日立が提携して、07年にGE日立ニュークリア・エナジーを設立している。またWHは、イギリス核燃料会社を経て、06年に東芝に売却されている。これについては、アメリカは、過酷事故が起こった場合に責任追及され、巨額の損害賠償を受けるのを回避するために、原子炉の開発・建設から撤退し、それを日本に転嫁しているといわれている。
実際、アメリカは、1979年のスリーマイル島原発事故以来、原発の新規建設を棚上げしてきたが、オバマ政権が12年2月に原子炉2基の新設を決めた。この原子炉は東芝傘下のWH製なのである。ただし、その後、米原子力規制委員会が、使用済み核燃料処理の規準が定まるまでは、原発の新設および既存原発の運転期間延長を認めないという決定を出している。このように、3・11の衝撃を受けて、オバマ政権の原子力大国路線の復活も、実は混迷している。
そうだからこそ、アメリカは、日米原子力協定を盾にして、日本の原発ゼロ化を絶対に容認しない。あくまでも、アメリカの世界大的な核軍事戦略とエネルギー戦略のコントロール下に日本を置き続けなければならない。
したがって、細川=小泉ラインの「原発ゼロ」を掲げた都知事選への登場は、アメリカへのあまりにもあからさまな挑戦という意味をもつ。国政レベルではなく、東京都のレベルではあっても、そこでの政治的・経済的な日米摩擦の大きさははかりしれない。
(D)都知事選の勝利が新たな展望を切り開く
このように、脱原発への道を阻む岩盤は硬い。細川=小泉ラインは、だからこそ、支配階級内での激しい抗争に勝つために、都知事選を劇場型政治の絶好の場として徹底的に使う手法に訴えたのである。
だが、それだけが都知事選の階級的本質ではない。前述の第一の対立軸を担う脱原発運動の主要な担い手たちが、千載一遇のチャンスととらえ、あえて敢然と細川支持の決断をしたこと、細川=小泉ラインと連携して、脱原発運動の決定的な前進をつくり出すべく総決起していることが、都知事選をして反原発・脱原発の下からの大衆運動の歴史的な再激化の場に転化させているのである。
原発問題をめぐる支配階級内の分岐もまた、3・11以来、この3年間の福島の被災者・内部被曝者を先頭とする非妥協的な脱原発の広範で粘り強い運動が生み出したものではないか。これが細川出馬をもたらした根底的な動力であることは、明々白々たる真実である。
私たち脱原発運動の側は、残念ながら独自の共同候補をもつことができなかった。その経緯は、ここでは省くが、前回の12年12月都知事選に立候補した宇都宮健児氏は、それを支える日本共産党ともども、今回の共同候補づくりの努力において大衆運動のルールを破ってしまった。それは、けっして小さな咎ではない。
独自の共同候補をもてなかった私たちは、支配階級内の鋭い分岐に介入して、その圧倒的な少数派を支援する以外になかったし、むしろここで勝利をかちとることで、脱原発への道を阻む難関の一つを決定的に破砕するチャンスを得たということではないだろうか。何度もいうが、千載一遇のチャンスとは、まさにこのことである。このたたかいに、今次都知事選の真に階級的な本質が内在している。
福島を先頭とする私たちの脱原発運動の力で細川都知事を実現するならば、一つには、細川都知事のこれからの脱原発のための政策、被災者・内部被曝者への支援と補償、国への要求、東電への追及に心棒を入れることができ、それが本物になっていく可能性が増すのである。
二つには、そうするならば、自民党内の脱原発派を析出させ、その政治行動化を促し、安倍自民党を必ずやがたがたに揺さぶるものとなろう。
三つには、そうするならば、「積極的平和主義」を掲げる安倍政権の侵略戦争と暗黒、搾取と差別の政治、それがあまりにも一方的で強権的なやり方で暴走している恐るべき現実にストップをかける転機となるであろう。じつは、細川候補支持に踏み切った多くの人々を駆り立てたものこそ、今日の安倍政治への不安感、危機感、無力感であり、追いつめられた絶望的な断崖絶壁から乾坤一擲の逆襲に出ようという決意なのである。
それを視野に入れて、私たちは、細川=小泉ラインにたいして、批判すべきをびしびし批判し、正されるべきをきっちりと正し、細川候補の当選=勝利のために奮闘すべきなのではないだろうか。
重ねていうが、〈全原発廃炉〉、〈脱原発〉は、じつに人類史的な宿願である。
これは、多くの重大な課題のうちの一つではない。あらゆる現実を規定するような大きさをもったテーマであり、これをさて措いては、他の諸問題の解決も一歩も進まないものなのである。
(E)「星条旗に『奴隷制廃止』と書きつけよ」
●マルクスたち第一インターはリンカーンの政府と軍を支持した
ところで、ここで、約150年前のアメリカ南北戦争に同時代人として際会したマルクス、エンゲルスを始めとするイギリスなどヨーロッパの革命家たちと多くの労働者人民がとった態度を想起することも、あながち無意味なことではないであろう。
マルクスたちは、周知のように、1861年4月に南北戦争が勃発するや、ただちにリンカーンとその政府および軍、つまりアメリカ合衆国、実体的には北部諸州ブルジョアジーを敢然と支持した。マルクスの論文の中には「支持」という言葉はないが、支持という言葉を使うまでもなく、ヨーロッパのたたかう人々の間では、奴隷制廃止の世界史的な大義において、それはきわめて必然的で、自明のことであった。
4年間にわたった激烈な南北戦争の間中、マルクスとエンゲルスは、戦争の推移や戦況および南北の新旧ブルジョアジーたちの動向をつぶさに分析した。そして、北部ブルジョアジーの政治的代表者であり、もともと奴隷制廃止論者ではなく、優柔不断なリンカーンを厳しく叱咤激励し、時には、南軍粉砕の戦術をも提案した。
なぜなら、アメリカ南北戦争の勝敗のいかんがヨーロッパの革命運動、労働運動の命運に直結しているという認識に立っていたからであり、奴隷解放が自分たち労働者階級自身の正面課題であると受け止めていたからである。
実際、イギリスの労働者は、自国政府の南北戦争への干渉、南軍援護に激しく反対し、繰り返し政治集会とデモをうった。当時のヨーロッパの労働者や亡命革命家たちは、ヨーゼフ・ヴァイデマイアー、アウグスト・ヴィリヒ、フリッツ・ヤーコビらを筆頭に、北軍の義勇軍に身を投じた。戦争の後期に実施された1864年11月の大統領選挙でリンカーンが当選するや、マルクスが筆をとって、同年9月に結成されたばかりの国際労働者協会、すなわち第一インターナショナルとしての祝辞を送った。リンカーンからは特別にていねいな返書があった。第一インターは、リンカーンが暗殺されると哀悼の意を表し、後継のジョンソン大統領にも激励のメッセージを送った。
●南北戦争の遂行過程とその諸結果は今日的な教訓に満ちている
マルクスたちによるリンカーンら北部諸州支持の核心点は次のようなものであった。
第一に、南北戦争をめぐる全事態を奴隷制の維持と拡大を許すか否かの戦争であるととらえたことである。
マルクスは、「南部連合の戦争は、ことばの真の意味において、奴隷制の拡大と永遠化のための侵略戦争である」と規定した。南部の中では「大奴隷制共和国の建設」などという恐るべき叫びもあがったように、北部が北部の防衛にとどまることができない戦争だとみたのである。もともと奴隷制廃止論者ではなかったリンカーンには「戦争には戦争をもってこたえるかの選択しか残されていなかった」(マルクス「北アメリカの内戦」)。
第二に、奴隷所有者の州である南部諸州連合の合衆国からの分離・独立(まさに奴隷制独立王国)を打ち砕くためには、「諸事件そのものが、決定的な標語――奴隷解放――の宣布をせまっている」として、リンカーン政府に革命的な戦争遂行方式に移行せよ、星条旗に「奴隷制廃止」という戦いのスローガンを書きつけよ、と懸命に促したことである。
黒人をただちに解放して戦闘部隊に編成し、あわせて労働者を軍事的に組織し、南部との戦いに送りこむことを提起したのであった(マルクス「アメリカの事態の批判」)。
マルクスは、リンカーンにむかって「いくじなし」、「いまだに南部に信をおいている」、「子どもにも軽蔑されるリンカーンとその政府」、「自分自身を奴隷制賛成の妥協派の道具におとしめるな」などと強く批判し続けた。そうすることで、前述したごとくにリンカーンが戦争を革命戦争方式に転換させ、前半の劣勢を立て直して、1864年4月を転機に戦争の主導権を握るにいたったことに大いに寄与したのである。
第三に、アメリカの労働者階級は奴隷制が維持されているかぎり、また黒人の奴隷労働の犠牲の上に立っているかぎり、自由ではありえないという立場があったことである。同時に、南部の黒人奴隷の犠牲による綿花を受ける位置にあったイギリスの労働者階級は、自国政府の南北戦争への干渉に繰り返し反対し、それこそ自己犠牲的に北部および黒人と連帯するたたかいに立ち上がった。マルクスたちは、そのたたかいを牽引したが、イギリス労働者階級の決起を「不朽の歴史的名誉をかちえた」とたたえたことである。
第四に、南北戦争の当事者はアメリカの新旧ブルジョアジーであったが、その相互の対立と分裂に掉さす形で、北部支持の行動を起こしたことである。
北部側には、大工業ブルジョアジーおよび勃興しつつあった金融資本家、新興ブルジョアジーがおり、南部側には、奴隷所有プランターやそれと結びついた北部の奴隷制維持に賛成の大ブルジョアジーがいた。労働者階級と本来的に敵対するブルジョアジーの一方を支持したのは、奴隷制廃止の決定的な意義をつかんでいたからなのである。
マルクスは、南北戦争での勝利が北部アメリカの労働者にとっての社会的・歴史的な「進歩」であることを謳うとともに、「奴隷制反対戦争が労働者階級の権力を伸長する新しい時代をきりひらくであろうと確信しています」と宣言したのであった(「リンカーン再選への祝辞」)。
しかし、内戦の終結の結果、戦争のための国債の重荷がアメリカ労働者階級に犠牲的に一方的に転嫁されたのである。金融資本家が跋扈し、戦争の甘い汁を吸った戦争成金が肥え太る一方で、「アメリカの労働者の地位の悪化」がもたらされたのであった。この現実を前にして、マルクスは、リンカーンの政府を支持したことの意義を揺らぐことなく断固として確認したのであった。「労働者階級の苦難にもかかわらず、内戦は、奴隷を解放し、その結果として諸君自身の階級の運動に精神的刺激をあたえたがゆえに、これらのことを償ってあまりあるものであった」と訴えたのだった(マルクス起草第一インター評議会「アメリカ合衆国全国労働同盟への呼びかけ」)。
以上のように、マルクスたちがアメリカ南北戦争にあたってリンカーンの政府と軍を支持してたたかったことには奥深い意味があり、その意義は不滅である。
それは、〈奴隷制廃止〉というまさに人類史的な大義を第一義的に重んじた、同時代人としての優れた政治的決断であったといえる。マルクスやエンゲルスはもとより、当時のヨーロッパの労働者階級の政治的・思想的な深さと高さに、改めて感服するところである。何よりも、そこに貫かれた思想――労働者階級の解放は、ただ人間の全人間的解放としてのみ実現され、また同時に、ありとあらゆる人間の解放は労働者階級の解放を条件としてのみ実現されるという思想――の豊かさを、学ぶことができよう。
(F)細川候補を支持し、すべての脱原発票を細川に集中しよう
さて、私たちは、全原発廃炉を全世界的に実現する重大な課題の前にいる。日本帝国主義の体内にあるすべてのおぞましさを体現するかのように、恐るべき反動と腐敗のかぎりを尽くす安倍政権と対峙するところに、私たちはいる。率直にいって、私たちは、今日の独特の階級的力関係の中で、非常な危機、つまり主体的な危機に立たされている。それは端的にいえば、じつに広範で多様性をもった、しかも非妥協的な原則を貫ける運動の力がありながら、その党派的な表現をもちえていないという主体的な危機にほかならない。
この主体的な危機を直視するとき、残り少なくなった都知事選の日々をどうたたかうか、問題は鮮明ではないだろうか。
歴史の発展段階も異なり、基礎にある社会的諸条件や階級的諸関係も違うが、南北戦争をめぐるマルクスたち第一インターのたたかいの教訓に思いをめぐらせるならば、今日、日本支配階級内部に形成されつつある脱原発派と連携してたたかうという、かつてなかったようなあり方に、きっぱりと確信をもつことができるのではないだろうか。
重ねていうが、〈全原発廃炉〉、〈脱原発〉は、じつに人類史的な宿願である。
これは、多くの重大な課題のうちの一つではない。あらゆる現実を規定するような大きさをもったテーマであり、これをさて措いては、他の諸問題の解決も一歩も進まないものなのである。
3・11以来、3年間にわたって持続し拡大しつつある脱原発運動に強い確信をもとう。かつ沖縄・名護市長選挙での稲嶺進氏再選の勝利、さらに南相馬市長選挙での桜井勝延氏再選の勝利、この沖縄と福島における感動的な勝利を引き継ごう。今、ここで首都東京における脱原発都知事の誕生を何としてもなしとげようではありませんか。
2014年1月30日
隅 喬史(すみ・たかし)












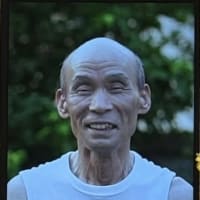













とりわけ、マルクスと第一インターの態度について明確に示されたことは、今日的に大変に重要です。
なぜかというと、とくに全共闘世代=70年安保世代にとっては、イデオロギー的躊躇と混乱があるからです。
私の周りでも、「細川とんでもない、ましてや小泉なんて・・・」という人がほとんどです。
そこでの整理がつかず、戸惑いと混乱の中で、結局は自分の態度が示せない・・・・。というのが現状だろうと思います。
私は、自民党が崩壊し、民主党政権が誕生したとき、これはワイマール政権ではないかと思いました。だとすれば、その後に登場してくるのはナチスのようなものだと。・・・・そして、やはり出てきたのは歴史の歯車を逆に回そうとする安倍政権でした。そして、それは、私たちがかつて語っていた「1930年代へのラセン的回帰」というものです。
階級闘争の黎明期に、マルクスやエンゲルスが階級的諸課題に対してどのような態度をとったのか、あるいは第一次大戦を前にして、レーニンはどのような態度をとったのか、第二次大戦を前にして、トロッキーがどのような態度をとったのか・・・そのことがもう一度明確にされなければならないと思っています。
細川立候補の歴史的意味を考察していることが正しい。
この、細川・小泉連携の深さ、支配階級にとっての深刻さ
を掴みとることが大事である。
第1インターナショナルと南北戦争を、今の都知事選に重ね合わせる、と言うことは私自身不明にして考えていませんでした。NCももはやこのような見地から都知事選を展開できないことと思います。理論レベルの低下と運動論の欠如のなせる業と思います。私自身腑に落ちました。