レーニンからのとらえ返し批判が必要になる
三村洋明「反障害―反差別論」strong>
2015年10月25日
たわしの読書メモ・・ブログ299から転載
・水谷保孝/岸宏一『革共同政治局の敗北1975~2014 あるいは中核派の崩壊』白順社2015
※勝手ながらタイトル、見出しは管理者がつけたことをお断りします。
●組織的活動の総括の共有化のための提起
政治党派の組織活動をしたものには、活動の中で知りえたことは墓場までもっていくという鉄則があります。このことはこの本の中にも出てきます。そのことを承知の上で、あえてそのことを踏み外しています。そのことは、この本のサブタイトルの「中核派の崩壊」という認識と、水谷さんの「あとがき」の編集者への謝辞の前に書かれている最後のことば「革共同は筆者らの愚かな破産と敗北を含めて、もう死んだのだ。弔旗もいらない。葬送の歌もいらない。ただインターナショナルな共産主義的解放を求める一人ひとりの人間がいればいい。」という認識から来ているようです。もうひとつ、「50年間も革命運動をやっていて革命を成就させえない党は解党すべきである。」という本多さんのことばが著者たちの頭に残っていて、そこで、あえて、ほとんど事実関係を知らされていない中核派のひとたちに、そしてすべての運動を担うひとたちに、組織的活動の総括の共有化というところで提起されているようです。
二人とも、中核派の「最高指導部」の政治局にいたひとです。水谷さんは七・七総括、諸戦線担当として、岸さんは三里塚現闘として大衆運動を担い、党派の戦線切り捨てと、党派の政治利用主義を内的にとらえ返してきたひとたちです。
このような組織内の党内闘争的なことは、少なからず起きていたことだと思っています。古くは『ロシア共産党党内闘争史』、そして連合赤軍の総括リンチの総括と、まだわたしはほとんど押さえられていませんが、この本はひとつの総括として大切な資料になっていくと思います。ただ、オープンにする判断自体がわたしにはよく分からないままです。そのことは中核派に残っているひとたちとの議論として進めてもらうしかありません。
●「障害者宣言」をもって組織と訣別
わたしの立場を書いて置きます。わたしは大衆運動局面で中核派と一定の共闘関係がありつつも、この本の中でも書かれているように、むしろ対立的な関係としてあってしまった社青同解放派の同盟への入り口あたりをうろついていた立場です。解放派も分裂していったのですが、わたしは分裂寸前の組織の中で、差別問題をめぐって党内闘争が起きている過程で、どちらもおかしいと思いつつ離脱した立場です。差別の問題で内糾闘争が行われていて(なぜ、「内」なのかという、糾弾闘争のオープン化の原則を踏み外していたのですが)、軍事的展開をしつつ反差別を基底にして共産主義党の建設と謳うグループと、労働運動を軸にして階級闘争的に党建設を進めていこうという対立だったのですが、前者も所詮政治利用主義でしかありませんでした。当時わたしは、そのあたりのことをハッキリつかんでいなかったのですが、わたしが「障害者宣言」をし、自己を確立しようとしていたときに、内糾支持派のわたしへ直属の指導にいたひとの差別的な対応の中で党派を離脱しました。結局「障害者宣言」をなしえない中で、離脱してしまったのですが、その総括を5年かかって、「障害者宣言」を出す中で一応書き上げ、離脱した組織に突きつけ、結局それが党派との決別宣言になりました。わたしの離脱後、党派は分裂をくり返し、党内闘争から殺も含んだ党派闘争に移行したのですが、もとより、わたしの属した党派も軍事展開の中で議論がオープンな形で進行していませんでした。しかも、わたしは入り口あたりにいた立場で、地区会議や直属の指導者との議論しかした経験がなく、組織の総括をする立場ではないのですが、わたしを放逐した(わたしの総括としては「逃亡」(逃亡せざるをえなかった?)として総括することですが)、わたしを指導していたひとが、殺を含む党派闘争の一方の「てっぺん」に座ったところで、わたしがあのときにきちんと批判できれば少しは党内情況が変わっただろうかとの思いは持って居ます(総括にIfなどありえず、当時のわたしの障害観-世界観、思想性できちんと対峙しようもなかったのですが)。その後、わたしは「障害者宣言」の延長線上で、『反障害原論』【三村洋明著『反障害原論――障害問題のパラダイム転換のために――』 2010年1月刊、世界書院】を書き出版しました。それは、反差別コミュニズム論としてつなげて書き上げていこうと思っています。それがわたしの総括の継続だとも思っていて、一生をかけて成し遂げようと思っています。
●対革マル「先制論」を対権力に展開したことの間違い
話を戻します。著者たちも主張していることですが、党内闘争や党派闘争にゲバルトは持ち込むべきではないという基本認識が必要だと思います。尤も相手があることで、日本の場合、大衆運動の推進ではなく、党派のイデオロギー的フラクション形成の中で、他党派をゲバルトでつぶすことによって、党形成をしようとした革マル派の存在があり、その中で強いられた党派闘争であったのですが、そもそもそれ以前の日本共産党以来の、安易なゲバルトの行使の批判からとらえかえしていかねばなりません。そのことをこの本の中でも書かれています。もとより、全共闘が暴力を否定しないところで運動を進めていったのは、この社会が差別社会であり、差別は暴力であるという認識で、平和幻想批判をしていくことがあったからです。そして、秩序ということの中で進められることがまさに差別的関係の押しつけという、そこに暴力があるからです。そして、そのことを押しとどめる実力闘争が必要になるからなのです。しかし、その実力闘争はゲバルトの行使そのものではありません。尤も、これは相手がゲバルトの行使で押しつぶしてくることへの防衛的対峙が必要になります。それは白色テロやクーデター的反革命との攻防を考えることなしには革命はなしえないということにも通じて行きます。革マルとの対峙の中で、まさに中核派の「先制論」がでてきたのですが、なされるままにつぶされていくということはあり得ない中で、わたしはこれ自体は必要になっていたと思います。ですが、このことを権力闘争の中におけるゲバルトとしてのゲリラ戦・パルチザン戦ということに展開させたのは、わたしは情況分析の間違いだと思っています。わたしが属した解放派も「ゲリラ的・パルチザン的」戦いを展開したのですが、わたしは「的」ってなんだと疑問に思っていました。まさにクラウゼビッツの『戦争論』から出て来る「軍事の弄び」ではないかと。
さて、著者の二人は、中核内左派として、中核派の先制的内戦戦略を肯定的にとらえ返しているし、その中身の権力へのゲリラ戦・パルチザン戦も継続するべきだったとか、読める文になっています。これは、赤軍派の前段階武装蜂起論なり、プロパガンダとしての戦争論への批判にも繋がります。これは情況認識の問題です。わたしは「沖縄返還」あたりで、大衆的実力闘争の中での組織化の路線はまだあったとしても、「68革命」の敗北はみえていたのではないかと思います。著者たちが書いているように、軍事展開は大衆運動や大衆意識から遊離したところで行われてはならないことで、むしろ阻害的なことになっていきます。だから「軍事のもてあそび」なのです。党派闘争として、やりきるというところで「先制」というようにおいたのは間違ってはいないとしても(著者たちは「本多さんは党派闘争自体をどこかで納めることを模索していた」というような内容のことも書いています。その判断なり、模索は実際あったかもしれないし、必要だったのだともわたしも考えています)、それを権力闘争にまで展開したのは、間違っていのだと思います。
●なぜ反スタ・スターリニストになったのか
さて、党内闘争の話に戻りますが、わたしは革共同の「反帝・反スタ」の「反スタ」の中身が理解できないでいます。スターリニズムは一国社会主義建設と入っていったところで、党の支配、組織における上下関係から逃れ得なかったというところで、壮絶な党内闘争・粛正をやり、国という範疇から逃れ得ず、ロシアの「帝国的支配」のようなことも起きていったというとらえかえしになるのでしょうか?
そのあたり、カリスマ的人格による運動の推進ということもその内容に含めるのなら、著者たちが書いている「本多独裁」から「清水カリスマ性」の批判が反スタとして必要ではないかと思うのです。革共同は両派とも反スタ・スターリニストに結局成ってしまったのではと思います。著者たちも書いていますが、運動のための組織であり、組織のための運動ではない、逆転させてはならないというところをきちんと押さえねばなりません。このことを組織の物神化批判としておさえねばなりません。どうもわからないのは、著者たちから、過去の回顧としてでしょうが、「中核派魂」というようなことばが出て来ることです。たとえば、「日本人魂」というようなことを書くと、ナショナリズムだと批判することです。こういう表現をすることは組織の物神化に陥っているのではないでしょうか?
わたしはそもそもレーニンからのとらえ返し批判が必要になるのではないかと思います。解放派もレーニン主義に傾斜していく中で、最も全共闘的大衆運動を体現していたと思える組織から、スターリニスト的党に展開していったのではないかと、入り口から党派を見ていた立場でしかないのですが、とらえ返しています。
レーニン主義、ボリシェビキズムの党が主導する革命という前衛党論は、現代革命論としてまちがいなのではないかと思うのです。むしろ、とりわけ反差別運動の戦線では繰り返し、政治利用主義批判が行われてきていて、むしろ「前衛たる大衆」に学ぶ「後衛としての革命党(フラクション)」というようなことでしかなかったし(そういう枠組み自体が超えるべきことなのかもしれませんが)、そこから、大衆運動を下支えする「党派」というところで、下支えする中で、個別戦線が個別利害的なところしかとらえられなくなる傾向をどう突破して結びつけ、総体的大衆運動的に展開していくための情報・理論をいかに提起し、大衆運動の中で強力に押し包める個やグルーブとして参加していくのかという運動展開になるのではと考えたりしています。
水谷さんも最後に一人一党的なところを展開されているので、そのあたりの批判の視角もあるのかとも思いますが。
●「血債の思想」に欠落するもの
もうひとつ中核派の「血債の思想」が「血債主義」批判として葬り去られたことの批判を書かれています。これは反差別ということの党派的な葬りです。しかし、そもそも他党派から「血債の思想」は批判されていました。それは反差別運動としての方針として間違っているという批判です。反差別運動には、自らの被差別における闘いから、他の差別において、差別する側にあるというところで、その差別性を自己批判しつつ、反差別の連帯の闘いとして取り組むということです。「血債の思想」には、「自らの被差別との闘いから」ということが欠落しているようにとらえられるのです。
わたしはマルクス派のひとで、差別の問題をきちんと押さえたひとに出会っていません。わたしも自己批判をくり返してきた立場で、入り口にたとうとしていることでしかありませんが。新左翼諸党派で、反差別諸戦線を常に政治利用主義に落とし込めてきた歴史があるのではと思っています。わたしがいた党派の中で「共産主義の基底としての反差別」ということをいう突き出しもありましたが、それも政治利用主義でしかありませんでした。結局共産主義運動の中に反差別と言うことを押さえ切れていないのです。これはわたしのいろいろ抱えている課題の最後の課題として置いていることです。そういうところで、この本を読みながらわたしは中核派の流れの中では、著者の2人が最も語れるひとではないかと思っているのです。ただ、この本の文は、情報提供にとどまっていて、総括的なところでは「未熟だった」ということしか出ていず、総括の文にはなりえていません(総括とは生涯をかけてやりきりことで終わりがないとも言えるのですが)。わたしの考えでは、総括とは今後の展望につなげる文になるのですが、そのようなところがほとんど出ていません。そのあたりの論の展開に入られ、これまでの活動の蓄積の中から、運動に情報・理論を提供し推進主体となっていって欲しいと思えるふたりなのです。
三村洋明「反障害―反差別論」strong>
2015年10月25日
たわしの読書メモ・・ブログ299から転載
・水谷保孝/岸宏一『革共同政治局の敗北1975~2014 あるいは中核派の崩壊』白順社2015
※勝手ながらタイトル、見出しは管理者がつけたことをお断りします。
●組織的活動の総括の共有化のための提起
政治党派の組織活動をしたものには、活動の中で知りえたことは墓場までもっていくという鉄則があります。このことはこの本の中にも出てきます。そのことを承知の上で、あえてそのことを踏み外しています。そのことは、この本のサブタイトルの「中核派の崩壊」という認識と、水谷さんの「あとがき」の編集者への謝辞の前に書かれている最後のことば「革共同は筆者らの愚かな破産と敗北を含めて、もう死んだのだ。弔旗もいらない。葬送の歌もいらない。ただインターナショナルな共産主義的解放を求める一人ひとりの人間がいればいい。」という認識から来ているようです。もうひとつ、「50年間も革命運動をやっていて革命を成就させえない党は解党すべきである。」という本多さんのことばが著者たちの頭に残っていて、そこで、あえて、ほとんど事実関係を知らされていない中核派のひとたちに、そしてすべての運動を担うひとたちに、組織的活動の総括の共有化というところで提起されているようです。
二人とも、中核派の「最高指導部」の政治局にいたひとです。水谷さんは七・七総括、諸戦線担当として、岸さんは三里塚現闘として大衆運動を担い、党派の戦線切り捨てと、党派の政治利用主義を内的にとらえ返してきたひとたちです。
このような組織内の党内闘争的なことは、少なからず起きていたことだと思っています。古くは『ロシア共産党党内闘争史』、そして連合赤軍の総括リンチの総括と、まだわたしはほとんど押さえられていませんが、この本はひとつの総括として大切な資料になっていくと思います。ただ、オープンにする判断自体がわたしにはよく分からないままです。そのことは中核派に残っているひとたちとの議論として進めてもらうしかありません。
●「障害者宣言」をもって組織と訣別
わたしの立場を書いて置きます。わたしは大衆運動局面で中核派と一定の共闘関係がありつつも、この本の中でも書かれているように、むしろ対立的な関係としてあってしまった社青同解放派の同盟への入り口あたりをうろついていた立場です。解放派も分裂していったのですが、わたしは分裂寸前の組織の中で、差別問題をめぐって党内闘争が起きている過程で、どちらもおかしいと思いつつ離脱した立場です。差別の問題で内糾闘争が行われていて(なぜ、「内」なのかという、糾弾闘争のオープン化の原則を踏み外していたのですが)、軍事的展開をしつつ反差別を基底にして共産主義党の建設と謳うグループと、労働運動を軸にして階級闘争的に党建設を進めていこうという対立だったのですが、前者も所詮政治利用主義でしかありませんでした。当時わたしは、そのあたりのことをハッキリつかんでいなかったのですが、わたしが「障害者宣言」をし、自己を確立しようとしていたときに、内糾支持派のわたしへ直属の指導にいたひとの差別的な対応の中で党派を離脱しました。結局「障害者宣言」をなしえない中で、離脱してしまったのですが、その総括を5年かかって、「障害者宣言」を出す中で一応書き上げ、離脱した組織に突きつけ、結局それが党派との決別宣言になりました。わたしの離脱後、党派は分裂をくり返し、党内闘争から殺も含んだ党派闘争に移行したのですが、もとより、わたしの属した党派も軍事展開の中で議論がオープンな形で進行していませんでした。しかも、わたしは入り口あたりにいた立場で、地区会議や直属の指導者との議論しかした経験がなく、組織の総括をする立場ではないのですが、わたしを放逐した(わたしの総括としては「逃亡」(逃亡せざるをえなかった?)として総括することですが)、わたしを指導していたひとが、殺を含む党派闘争の一方の「てっぺん」に座ったところで、わたしがあのときにきちんと批判できれば少しは党内情況が変わっただろうかとの思いは持って居ます(総括にIfなどありえず、当時のわたしの障害観-世界観、思想性できちんと対峙しようもなかったのですが)。その後、わたしは「障害者宣言」の延長線上で、『反障害原論』【三村洋明著『反障害原論――障害問題のパラダイム転換のために――』 2010年1月刊、世界書院】を書き出版しました。それは、反差別コミュニズム論としてつなげて書き上げていこうと思っています。それがわたしの総括の継続だとも思っていて、一生をかけて成し遂げようと思っています。
●対革マル「先制論」を対権力に展開したことの間違い
話を戻します。著者たちも主張していることですが、党内闘争や党派闘争にゲバルトは持ち込むべきではないという基本認識が必要だと思います。尤も相手があることで、日本の場合、大衆運動の推進ではなく、党派のイデオロギー的フラクション形成の中で、他党派をゲバルトでつぶすことによって、党形成をしようとした革マル派の存在があり、その中で強いられた党派闘争であったのですが、そもそもそれ以前の日本共産党以来の、安易なゲバルトの行使の批判からとらえかえしていかねばなりません。そのことをこの本の中でも書かれています。もとより、全共闘が暴力を否定しないところで運動を進めていったのは、この社会が差別社会であり、差別は暴力であるという認識で、平和幻想批判をしていくことがあったからです。そして、秩序ということの中で進められることがまさに差別的関係の押しつけという、そこに暴力があるからです。そして、そのことを押しとどめる実力闘争が必要になるからなのです。しかし、その実力闘争はゲバルトの行使そのものではありません。尤も、これは相手がゲバルトの行使で押しつぶしてくることへの防衛的対峙が必要になります。それは白色テロやクーデター的反革命との攻防を考えることなしには革命はなしえないということにも通じて行きます。革マルとの対峙の中で、まさに中核派の「先制論」がでてきたのですが、なされるままにつぶされていくということはあり得ない中で、わたしはこれ自体は必要になっていたと思います。ですが、このことを権力闘争の中におけるゲバルトとしてのゲリラ戦・パルチザン戦ということに展開させたのは、わたしは情況分析の間違いだと思っています。わたしが属した解放派も「ゲリラ的・パルチザン的」戦いを展開したのですが、わたしは「的」ってなんだと疑問に思っていました。まさにクラウゼビッツの『戦争論』から出て来る「軍事の弄び」ではないかと。
さて、著者の二人は、中核内左派として、中核派の先制的内戦戦略を肯定的にとらえ返しているし、その中身の権力へのゲリラ戦・パルチザン戦も継続するべきだったとか、読める文になっています。これは、赤軍派の前段階武装蜂起論なり、プロパガンダとしての戦争論への批判にも繋がります。これは情況認識の問題です。わたしは「沖縄返還」あたりで、大衆的実力闘争の中での組織化の路線はまだあったとしても、「68革命」の敗北はみえていたのではないかと思います。著者たちが書いているように、軍事展開は大衆運動や大衆意識から遊離したところで行われてはならないことで、むしろ阻害的なことになっていきます。だから「軍事のもてあそび」なのです。党派闘争として、やりきるというところで「先制」というようにおいたのは間違ってはいないとしても(著者たちは「本多さんは党派闘争自体をどこかで納めることを模索していた」というような内容のことも書いています。その判断なり、模索は実際あったかもしれないし、必要だったのだともわたしも考えています)、それを権力闘争にまで展開したのは、間違っていのだと思います。
●なぜ反スタ・スターリニストになったのか
さて、党内闘争の話に戻りますが、わたしは革共同の「反帝・反スタ」の「反スタ」の中身が理解できないでいます。スターリニズムは一国社会主義建設と入っていったところで、党の支配、組織における上下関係から逃れ得なかったというところで、壮絶な党内闘争・粛正をやり、国という範疇から逃れ得ず、ロシアの「帝国的支配」のようなことも起きていったというとらえかえしになるのでしょうか?
そのあたり、カリスマ的人格による運動の推進ということもその内容に含めるのなら、著者たちが書いている「本多独裁」から「清水カリスマ性」の批判が反スタとして必要ではないかと思うのです。革共同は両派とも反スタ・スターリニストに結局成ってしまったのではと思います。著者たちも書いていますが、運動のための組織であり、組織のための運動ではない、逆転させてはならないというところをきちんと押さえねばなりません。このことを組織の物神化批判としておさえねばなりません。どうもわからないのは、著者たちから、過去の回顧としてでしょうが、「中核派魂」というようなことばが出て来ることです。たとえば、「日本人魂」というようなことを書くと、ナショナリズムだと批判することです。こういう表現をすることは組織の物神化に陥っているのではないでしょうか?
わたしはそもそもレーニンからのとらえ返し批判が必要になるのではないかと思います。解放派もレーニン主義に傾斜していく中で、最も全共闘的大衆運動を体現していたと思える組織から、スターリニスト的党に展開していったのではないかと、入り口から党派を見ていた立場でしかないのですが、とらえ返しています。
レーニン主義、ボリシェビキズムの党が主導する革命という前衛党論は、現代革命論としてまちがいなのではないかと思うのです。むしろ、とりわけ反差別運動の戦線では繰り返し、政治利用主義批判が行われてきていて、むしろ「前衛たる大衆」に学ぶ「後衛としての革命党(フラクション)」というようなことでしかなかったし(そういう枠組み自体が超えるべきことなのかもしれませんが)、そこから、大衆運動を下支えする「党派」というところで、下支えする中で、個別戦線が個別利害的なところしかとらえられなくなる傾向をどう突破して結びつけ、総体的大衆運動的に展開していくための情報・理論をいかに提起し、大衆運動の中で強力に押し包める個やグルーブとして参加していくのかという運動展開になるのではと考えたりしています。
水谷さんも最後に一人一党的なところを展開されているので、そのあたりの批判の視角もあるのかとも思いますが。
●「血債の思想」に欠落するもの
もうひとつ中核派の「血債の思想」が「血債主義」批判として葬り去られたことの批判を書かれています。これは反差別ということの党派的な葬りです。しかし、そもそも他党派から「血債の思想」は批判されていました。それは反差別運動としての方針として間違っているという批判です。反差別運動には、自らの被差別における闘いから、他の差別において、差別する側にあるというところで、その差別性を自己批判しつつ、反差別の連帯の闘いとして取り組むということです。「血債の思想」には、「自らの被差別との闘いから」ということが欠落しているようにとらえられるのです。
わたしはマルクス派のひとで、差別の問題をきちんと押さえたひとに出会っていません。わたしも自己批判をくり返してきた立場で、入り口にたとうとしていることでしかありませんが。新左翼諸党派で、反差別諸戦線を常に政治利用主義に落とし込めてきた歴史があるのではと思っています。わたしがいた党派の中で「共産主義の基底としての反差別」ということをいう突き出しもありましたが、それも政治利用主義でしかありませんでした。結局共産主義運動の中に反差別と言うことを押さえ切れていないのです。これはわたしのいろいろ抱えている課題の最後の課題として置いていることです。そういうところで、この本を読みながらわたしは中核派の流れの中では、著者の2人が最も語れるひとではないかと思っているのです。ただ、この本の文は、情報提供にとどまっていて、総括的なところでは「未熟だった」ということしか出ていず、総括の文にはなりえていません(総括とは生涯をかけてやりきりことで終わりがないとも言えるのですが)。わたしの考えでは、総括とは今後の展望につなげる文になるのですが、そのようなところがほとんど出ていません。そのあたりの論の展開に入られ、これまでの活動の蓄積の中から、運動に情報・理論を提供し推進主体となっていって欲しいと思えるふたりなのです。



















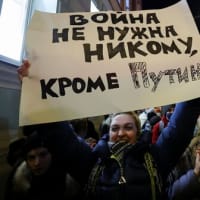
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます