すでに始まっている集団的自衛権の行使容認を阻止しよう!
1、問題は日米安保体制再編と沖縄基地強化にある
安倍政権による集団的自衛権の行使容認は、日本帝国主義がまたもや侵略戦争への歴史を繰り返すことだ。それは、国連加盟国が集団的自衛権の行使を安全保障理事会に報告した14件の事例、アメリカ帝国主義のアフガニスタン侵略戦争へのNATO加盟国の派兵(01年10月)、ハンガリー革命へのソ連の武力侵攻(1956年10月)、ベトナム戦争への韓国軍の派兵(1964年、1965年8月)、など集団的自衛権の行使が侵略戦争を引き起こした事例を持ち出すまでもなく明らかである。
個別的自衛権であろうと集団的自衛権であろうと、その行使は「自衛の名を借りる」と「わが国と密接な関係にある外国が攻撃され日本に重大な影響がある時」との理由の違いはあっても、日本帝国主義が本格的に戦争のできる国に踏み込むものである。安倍の集団的自衛権の行使に対して、「個別的自衛権や警察権で対応できる」という議論では同じ穴のむじなでしかない。二度と侵略戦争は繰り返さないと誓った憲法9条は、安倍政権の憲法解釈の変更によって、安倍のお友達の何の法的な権限もない私的な諮問機関の報告を契機として投げ捨てられようとしている。安倍の憲法解釈の変更は憲法論や机上の議論ではない。現実の日米安保条約の強化、その具体的な攻撃としての沖縄の米軍基地・体制の強化、在日米軍基地の強化や自衛隊の強化、国家総動員体制への国家のかたちの変更など具体的な攻撃として一気に襲いかかってくる。
安倍の解釈変更による集団的自衛権の容認は、決して日本帝国主義の磐石の体制下での攻撃ではない。すさまじい日帝の矛盾と危機の下での攻撃である。
一つは、日米関係である。
アメリカ帝国主義オバマ政権は安倍の政治に「うさん臭さ」を感じ取っている。米帝は日帝の軍事大国への道は米帝のコントロールの下でのそれ、米帝の戦争を補完する限りにおいて容認している。対中国・韓国との歴史認識問題をめぐる軋轢にしても、米帝の主導権の下での対中国批判は認めても、戦後世界体制を根底から転覆するような歴史観は絶対に認めない。安倍の靖国神社参拝に、米帝はその後者の危険を感じ取っている。親日的といわれ、米帝の対日政策を助言しているアーミテージも、安倍の靖国神社参拝には、「安倍は選挙公約を果たしたらもうこの問題は終わりだ(靖国神社参拝など口にするな。米帝のために、円安を特別に容認してやっているように、経済成長に精を出せ)」という趣旨の発言を繰り返している。
しかし日帝は、集団的自衛権の行使容認において「同盟国が攻撃された場合」ではなく「わが国と密接な関係にある外国が攻撃された場合」としているように、日米安保体制を双務的な対等の同盟へ変えるという思惑を隠していない。
米帝は財政赤字問題の軍事費へのしわ寄せを日帝を始めとする同盟国への転嫁で乗り切ろうとしており、また釣魚台(日本名「尖閣諸島」)への日米安保条約の適用も米帝の主導権のもとでのみ発動する。この米帝の主導権での日帝の動員と日帝独自の利害とは、無視できない矛盾を生み出す。
安倍は集団的自衛権の行使容認を日米安保体制の強化のためだと強調する。日米首脳会談の報道などを通じて、安倍の集団的自衛権行使容認を米帝が支持しているとの宣伝が盛んになされている。安倍は対中国・対北朝鮮を例に挙げながらアジアでの日本を取り巻く安全保障環境の変化を挙げ、あたかも離島などへの侵略があるかのごとく騒ぎ立て、戦争体制の構築を叫んでいる。靖国神社参拝が米帝基軸の戦後体制への挑戦として登場している、と中国が指摘したことは当たっている。米帝オバマは集団的自衛権の行使容認は日米安保体制の強化であると確認する時には、必ず「同盟の枠内で」という枠をはめる。安倍政権が「同盟国が攻撃された時」ではなく「密接な関係にある外国が攻撃された時」とする意図に、靖国神社参拝への危惧を重ねあわせ、米帝の主導権の下での、日米安保の枠内というタガをはめている。そこには、日米安保体制の矛盾の爆発という問題がある。それは沖縄基地の強化と重なる。
二つには、集団的自衛権の行使容認は沖縄の在日米軍基地・自衛隊基地の強化として具体的に攻撃が強化されるということである。
日米防衛協力の指針(ガイドライン)の14年中の改定と一体のものとして進められる。集団的自衛権の行使容認は、「やまと」の側が沖縄基地強化の攻撃としてかけられてくることを真正面から受け止め、沖縄の人々と固く連帯し、集団的自衛権行使容認を「やまと」の側の沖縄闘争として闘うことである。
三つ目には、集団的自衛権の行使容認はアベノミクスに顕著に現れているアジアなどの新興国への官民一体となったインフラ投資と一体の攻撃である。
安倍政権は自動車産業のアジア市場の制覇を手本にしながら、商社・重工業・建築・原発などの産業をインフラ産業と位置づけ、ODA、円借款、政府系金融機関の融資などをテコに、官民一体となって進出を強めている。ミャンマーのティラワ工業団地などをはじめインドチャイナ半島の東西・南北の回廊などへの開発の関与を、日帝は強めている。日帝企業の進出は超過利潤の収奪であり、それに対して、日帝の工場での現地労働者の賃上げや労働条件の改善を求める労働争議はカンボジアやベトナムやインドなどでも頻発している。そうした安倍政権の地球的規模の外交や積極的平和主義は、集団的自衛権の行使容認によって帝国主義の魂を吹き込まれるのである。
四つ目には、集団的自衛権の行使容認は、憲法9条を投げ捨て再び侵略戦争への道を繰り返すことである。
自衛権の解釈論議や憲法の机上の論議ではなく、具体的に集団的自衛権の行使容認が沖縄米軍基地を強化し、在日米軍基地を強化し、自衛隊の増強や国家総動員体制の強化として進められるのである。この現実を生き生きと暴露し、集団的自衛権の行使容認が憲法9条を亡きものにする攻撃であることとの対決を鮮明にすることだ。集団的自衛権の行使容認は、帝国主義の社会体制が戦争に行き着く矛盾を抱えた体制として不可避の攻撃であり、この帝国主義の矛盾の爆発である戦争への準備・その勃発を、戦争をなくす闘いと戦争のない新たな社会の建設への世界史的事業として取り組もう。
2、安保法制懇の報告書案を批判する
来週の5月13日には「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の報告書が提出され、その報告を土台に「政府見解」が出され、今夏に閣議決定、早ければ今秋の臨時国会には自衛隊法など関連法の改悪案が提出されると言われている。憲法9条が時の政府の解釈変更によって集団的自衛権を行使できる憲法条項に解釈されていき、もって侵略戦争ができる根拠に変えられていく。ここで憲法9条を再確認しておく。
《憲法第9条》
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文が「わが国と密接な関係にある外国が攻撃され、日本に重大な影響がある」と時の首相が判断すれば、集団的自衛権を行使する根拠になるというのだ。現在の階級情勢は、決して安易な見通しを許す情勢ではない。東アジアをめぐって一触即発の情勢に入っているのである。
その中で、「革命党」を名乗る自称前衛勢力は見る影もない。しかし、労働者人民に矛盾と犠牲を強要する帝国主義の政治に怒り、何とかしたいと考えている人々は大勢いる。この勢力と結びつき、集団的自衛権の解釈変更による戦争のできる国づくりを阻止しよう。
安倍は、憲法9条を改悪することなく解釈の変更で強行する道を選んだ。その理由は、①98条改革から行けば時間がかかること、②もしも国民投票で否決されればやり直しは難しい、③真正面からの改憲論議を避けたい、④年末の日米防衛協力の指針の改定に間に合わせるため、ということが考えられる。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書案(4月3日付の日経新聞)では、(1)「集団的自衛権は憲法が認める必要最小限度の自衛権に含まれ、北朝鮮や中国の安保環境の変化で、憲法改正をしなくても集団的自衛権を行使できる」。(2)発動の6条件として、①対象は日本と密接な関係にある国(対象国を明記せず米国以外との国々との協力の余地を残す)、②放置すれば日本の安全に重要な影響が出る場合、③当該国からの明確な要請、④第3国の領域を通過する場合には許可が必要、⑤首相が総合的に判断、⑥原則、国会の事前承認を得る。事後承認は緊急時のみ~~などと報道されている。
「集団的自衛権は必要最小限度の自衛権に含まれる」という主張は、3月31日の自民党が集団的自衛権の行使容認を党内論議でまとめるために安倍が設置した安全保障法制整備本部(本部長・石破茂自民党幹事長)で突然、自民党副総裁の高村正彦が提案した。高村は、「自国の存立に必要な自衛措置は認められる」とした1959年の砂川事件最高裁判決を引用し、憲法が許容する「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権の一部が含まれるとする「限定的に容認」という考えを示した。
首相・安倍晋三はこの「限定容認論」を支持(8日、BSフジ番組)し、「(砂川判決は)集団的自衛権を否定していないのははっきりしている」と断定している。
公明党の5月9日の安全保障に関する研究会で衆院法制局の担当者は、「砂川判決でいう自衛権は個別的自衛権と解釈するのが一般的」と発言したことを引用するまでもなく、砂川判決が集団的自衛権行使も個別的自衛権に含まれるとする論法には無理がある。
しかし、国家の自衛権を承認してそれを根拠に集団的自衛権行使を否定するやり方、集団的自衛権ではなく個別自衛権を行使すれば事足りるからという論議は、自衛権行使の延長に侵略戦争が繰り返えされた歴史を振り返れば、危険である。それは、安保法制懇が「わが国を取り巻く安全保障環境の変化」を口実として明確に北朝鮮および中国を仮想敵国視しているように、対北朝鮮、対中国の扇情的な排外主義によって可能とされた論理なのである。
安保法制懇の座長代理の北岡伸一はインタビューに答えてこう発言している。「安全保障の要諦は相手の裏をかくことだ。全てを類型化すれば安保はできない」「集団的自衛権行使を可能にして日米同盟を強化する」「(1954年の必要最小限の自衛権行使を認めた最高裁判決について)この変化に比べればささやかな変更だ。憲法を守るだけで国は守れない」と。
ここにははっきりと帝国主義戦争の論理、強盗戦争の論理、秘密軍事外交の論理が動いているのである。
さらに安保法制懇の報告書では「国際紛争」に関する憲法解釈の変更を提言し、憲法9条で禁止している「国際紛争」は日本が当事者の場合に限るとの新解釈を打ち出し、PKOでの武器使用の制限緩和を求めるというのだ。現行解釈は「全ての国際紛争」が該当するとして、離れた場所で攻撃を受けた国の隊員の救援(駆けつけ警護)や国連の多国籍軍の給油や輸送を禁止しているが、これが可能になるのだ。
3、安倍政権の狙いはすでに現実に具体化されつつある
安倍政権は安保法制懇の報告書を受けて集団的自衛権の行使容認の「政府方針」を決定し、閣議決定する方針だ。
その「政府方針」素案(2014.5.2)では、①国家が存立を全うするために必要な自衛権は認められる。②自衛権行使は必要最小限度にとどまる。③自国が攻撃を受けていなくても、密接な関係にある国が攻撃された場合など自衛権が行使できる状況がある。④他国への攻撃に対して自衛権を行使するのは、日本の安全に重大な影響がある場合などに限る。⑤攻撃を受けた国からの要請や国会の同意なども行使の条件とする。⑥日本を取り巻く安全保障環境の悪化を踏まえれば、抑止力を高める必要がある~~とした上で、文案では公明党や創価学会の反発を和らげるために「集団的自衛権」という表現を使うのを避けたと報道されているが、③で集団的自衛権の行使容認を明白に規定している。
集団的自衛権の行使容認はすでに始まっている。沖縄基地強化や在日米軍・自衛隊の強化である。
米軍はヘーゲル・小野寺会談(4月6日)でアジア・太平洋への米軍配備の拡大を確認し、具体的にはイージス艦を2隻追加し7隻体制に、日米合わせると13隻の巨大編成になる。また昨年12月には、最新鋭P8対潜哨戒機を沖縄米軍基地に配備し、無人偵察機「グローバルホーク」の配備も決定した。2月には米海軍佐世保基地に新鋭の輸送揚陸艦「グリーンベイ」(排水量は現在配備されている揚陸輸送艦の1.5倍の2万5000トン、最新鋭の機器を使った指揮命令システムを装備し、オスプレイを格納している。事が起こればこの輸送揚陸艦が佐世保を出港し、沖縄で海兵隊を乗り組ませ、戦場に輸送する)を配備し、さらに今年の5月には能力の高い掃海艇「パイオニア」「チーフ」を配備する。
自衛隊は、中期防衛力整備計画で新設を明記したが、水陸両用作戦を展開する3000人規模の「水陸機動団」を長崎県・相浦駐屯地に新設。陸自西部方面隊普通科連隊を中核とし、米海兵隊との共同訓練で育成していく。現在、水陸両用作戦部隊は西部方面隊に700人配置されている。さらに15年度から民間の高速フェリー2隻を自衛隊輸送に活用し、PFI(民間資金を使った社会資本整備)の枠組みで金融機関などから出資を募る。13年12月の防衛計画大綱で「民間輸送力との連携」としたことの具体策であり、海自は「おおすみ」など輸送艦3隻体制だが、巡航速度が40キロ/時で緊急時の機動力がないため、速度70キロ/時で大型トレーラー30台、乗用車100台収容の「ナッチャンWorld」(津軽海峡フェリー)、「はくおう」(新日本海フェリー)を金融機関や海運会社出資で設立する特別目的会社SPCが購入し、防衛省との運行契約に基づいて輸送を担う。乗組員には、外国軍に侵攻された地域などに部隊を運ぶ場合は民間の乗組員は立ち入りできないから「予備自衛官」を活用する。14年度に2隻を購入、15年度に防衛省がSPCと20年の利用計画を結ぶ。
陸自を機動的に運用するために。18年度までに全国五つの方面隊などを統括する「陸上総隊」を設ける。海自や空自と同様に指揮系統を一元化し、全国規模で部隊を運用する際などに調整しやすくする。陸自には五つの方面区と防衛相直轄の中央即応集団などもある。
集団的自衛権行使は作戦レベルではすでに始まっている。
13年3月に岩崎茂統合幕僚長とロックリア太平洋軍司令官が協議し、夏に決定した釣魚台(「尖閣」)有事の際の日米共同作戦計画がすでに存在している。その内容は ①グアムのアンダーセン空軍基地からB52を急派、②普天間基地に駐留する海兵隊を佐世保基地の輸送揚陸艦を用いながら上陸させるというものである。釣魚台で事が起こった場合は、米軍はB52を出撃させる計画なのだ。B52で釣魚台諸島を爆撃するわけではあるまい。B52は軍事基地や大都市への爆撃であり、核爆弾も装備している。米軍は釣魚台とその周辺で事が起これば中国本土への爆撃をすると宣言しているのだ。
現に、この計画が作成されて以降の中国による防空識別圏の設定に対して、米軍が最初にとった行動はグアムからB52を2機、防空識別圏の中を飛行させるというものであった。戦闘機の護衛をつけないという条件をつけてである。佐世保基地への最新鋭揚陸輸送艦の配備も、この作戦計画に沿ったものである。
前出の北岡発言に端的であるが、すでに帝国主義侵略戦争の力学に沿った論理や行動が平然ととられ始めている現実を重視しなければならない。
集団的自衛権行使容認と闘うためには、自衛権も含めて一切の戦争をまずは否定しなければならない。まずはこの立場で一切の戦争を否定することである。広く議論を起こすには、この信頼関係にたって初めて、なぜ帝国主義の現代社会は戦争を不可避とするのか、戦争は帝国主義の政治の継続であり、この帝国主義の政治、帝国主義社会を根底からひっくり返す以外に戦争はなくならないという議論が始まる。自衛権、ひいてはナショナリズムに縛られず、国家の自衛権を真っ向から否定し、一切の戦争に反対することが重要である。
同時に、対中国、対北朝鮮、さらには対韓国の上からと下からの排外主義、レイシズムが帝国主義戦争突入の最大の動力とされることを見すえ、一切の自衛の名による戦争が実は侵略戦争以外の何ものでもないことを明らかにして闘うことである。
全力で闘おう。
2014年5月11日
博多のアイアンバタフライ
1、問題は日米安保体制再編と沖縄基地強化にある
安倍政権による集団的自衛権の行使容認は、日本帝国主義がまたもや侵略戦争への歴史を繰り返すことだ。それは、国連加盟国が集団的自衛権の行使を安全保障理事会に報告した14件の事例、アメリカ帝国主義のアフガニスタン侵略戦争へのNATO加盟国の派兵(01年10月)、ハンガリー革命へのソ連の武力侵攻(1956年10月)、ベトナム戦争への韓国軍の派兵(1964年、1965年8月)、など集団的自衛権の行使が侵略戦争を引き起こした事例を持ち出すまでもなく明らかである。
個別的自衛権であろうと集団的自衛権であろうと、その行使は「自衛の名を借りる」と「わが国と密接な関係にある外国が攻撃され日本に重大な影響がある時」との理由の違いはあっても、日本帝国主義が本格的に戦争のできる国に踏み込むものである。安倍の集団的自衛権の行使に対して、「個別的自衛権や警察権で対応できる」という議論では同じ穴のむじなでしかない。二度と侵略戦争は繰り返さないと誓った憲法9条は、安倍政権の憲法解釈の変更によって、安倍のお友達の何の法的な権限もない私的な諮問機関の報告を契機として投げ捨てられようとしている。安倍の憲法解釈の変更は憲法論や机上の議論ではない。現実の日米安保条約の強化、その具体的な攻撃としての沖縄の米軍基地・体制の強化、在日米軍基地の強化や自衛隊の強化、国家総動員体制への国家のかたちの変更など具体的な攻撃として一気に襲いかかってくる。
安倍の解釈変更による集団的自衛権の容認は、決して日本帝国主義の磐石の体制下での攻撃ではない。すさまじい日帝の矛盾と危機の下での攻撃である。
一つは、日米関係である。
アメリカ帝国主義オバマ政権は安倍の政治に「うさん臭さ」を感じ取っている。米帝は日帝の軍事大国への道は米帝のコントロールの下でのそれ、米帝の戦争を補完する限りにおいて容認している。対中国・韓国との歴史認識問題をめぐる軋轢にしても、米帝の主導権の下での対中国批判は認めても、戦後世界体制を根底から転覆するような歴史観は絶対に認めない。安倍の靖国神社参拝に、米帝はその後者の危険を感じ取っている。親日的といわれ、米帝の対日政策を助言しているアーミテージも、安倍の靖国神社参拝には、「安倍は選挙公約を果たしたらもうこの問題は終わりだ(靖国神社参拝など口にするな。米帝のために、円安を特別に容認してやっているように、経済成長に精を出せ)」という趣旨の発言を繰り返している。
しかし日帝は、集団的自衛権の行使容認において「同盟国が攻撃された場合」ではなく「わが国と密接な関係にある外国が攻撃された場合」としているように、日米安保体制を双務的な対等の同盟へ変えるという思惑を隠していない。
米帝は財政赤字問題の軍事費へのしわ寄せを日帝を始めとする同盟国への転嫁で乗り切ろうとしており、また釣魚台(日本名「尖閣諸島」)への日米安保条約の適用も米帝の主導権のもとでのみ発動する。この米帝の主導権での日帝の動員と日帝独自の利害とは、無視できない矛盾を生み出す。
安倍は集団的自衛権の行使容認を日米安保体制の強化のためだと強調する。日米首脳会談の報道などを通じて、安倍の集団的自衛権行使容認を米帝が支持しているとの宣伝が盛んになされている。安倍は対中国・対北朝鮮を例に挙げながらアジアでの日本を取り巻く安全保障環境の変化を挙げ、あたかも離島などへの侵略があるかのごとく騒ぎ立て、戦争体制の構築を叫んでいる。靖国神社参拝が米帝基軸の戦後体制への挑戦として登場している、と中国が指摘したことは当たっている。米帝オバマは集団的自衛権の行使容認は日米安保体制の強化であると確認する時には、必ず「同盟の枠内で」という枠をはめる。安倍政権が「同盟国が攻撃された時」ではなく「密接な関係にある外国が攻撃された時」とする意図に、靖国神社参拝への危惧を重ねあわせ、米帝の主導権の下での、日米安保の枠内というタガをはめている。そこには、日米安保体制の矛盾の爆発という問題がある。それは沖縄基地の強化と重なる。
二つには、集団的自衛権の行使容認は沖縄の在日米軍基地・自衛隊基地の強化として具体的に攻撃が強化されるということである。
日米防衛協力の指針(ガイドライン)の14年中の改定と一体のものとして進められる。集団的自衛権の行使容認は、「やまと」の側が沖縄基地強化の攻撃としてかけられてくることを真正面から受け止め、沖縄の人々と固く連帯し、集団的自衛権行使容認を「やまと」の側の沖縄闘争として闘うことである。
三つ目には、集団的自衛権の行使容認はアベノミクスに顕著に現れているアジアなどの新興国への官民一体となったインフラ投資と一体の攻撃である。
安倍政権は自動車産業のアジア市場の制覇を手本にしながら、商社・重工業・建築・原発などの産業をインフラ産業と位置づけ、ODA、円借款、政府系金融機関の融資などをテコに、官民一体となって進出を強めている。ミャンマーのティラワ工業団地などをはじめインドチャイナ半島の東西・南北の回廊などへの開発の関与を、日帝は強めている。日帝企業の進出は超過利潤の収奪であり、それに対して、日帝の工場での現地労働者の賃上げや労働条件の改善を求める労働争議はカンボジアやベトナムやインドなどでも頻発している。そうした安倍政権の地球的規模の外交や積極的平和主義は、集団的自衛権の行使容認によって帝国主義の魂を吹き込まれるのである。
四つ目には、集団的自衛権の行使容認は、憲法9条を投げ捨て再び侵略戦争への道を繰り返すことである。
自衛権の解釈論議や憲法の机上の論議ではなく、具体的に集団的自衛権の行使容認が沖縄米軍基地を強化し、在日米軍基地を強化し、自衛隊の増強や国家総動員体制の強化として進められるのである。この現実を生き生きと暴露し、集団的自衛権の行使容認が憲法9条を亡きものにする攻撃であることとの対決を鮮明にすることだ。集団的自衛権の行使容認は、帝国主義の社会体制が戦争に行き着く矛盾を抱えた体制として不可避の攻撃であり、この帝国主義の矛盾の爆発である戦争への準備・その勃発を、戦争をなくす闘いと戦争のない新たな社会の建設への世界史的事業として取り組もう。
2、安保法制懇の報告書案を批判する
来週の5月13日には「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の報告書が提出され、その報告を土台に「政府見解」が出され、今夏に閣議決定、早ければ今秋の臨時国会には自衛隊法など関連法の改悪案が提出されると言われている。憲法9条が時の政府の解釈変更によって集団的自衛権を行使できる憲法条項に解釈されていき、もって侵略戦争ができる根拠に変えられていく。ここで憲法9条を再確認しておく。
《憲法第9条》
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この条文が「わが国と密接な関係にある外国が攻撃され、日本に重大な影響がある」と時の首相が判断すれば、集団的自衛権を行使する根拠になるというのだ。現在の階級情勢は、決して安易な見通しを許す情勢ではない。東アジアをめぐって一触即発の情勢に入っているのである。
その中で、「革命党」を名乗る自称前衛勢力は見る影もない。しかし、労働者人民に矛盾と犠牲を強要する帝国主義の政治に怒り、何とかしたいと考えている人々は大勢いる。この勢力と結びつき、集団的自衛権の解釈変更による戦争のできる国づくりを阻止しよう。
安倍は、憲法9条を改悪することなく解釈の変更で強行する道を選んだ。その理由は、①98条改革から行けば時間がかかること、②もしも国民投票で否決されればやり直しは難しい、③真正面からの改憲論議を避けたい、④年末の日米防衛協力の指針の改定に間に合わせるため、ということが考えられる。
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書案(4月3日付の日経新聞)では、(1)「集団的自衛権は憲法が認める必要最小限度の自衛権に含まれ、北朝鮮や中国の安保環境の変化で、憲法改正をしなくても集団的自衛権を行使できる」。(2)発動の6条件として、①対象は日本と密接な関係にある国(対象国を明記せず米国以外との国々との協力の余地を残す)、②放置すれば日本の安全に重要な影響が出る場合、③当該国からの明確な要請、④第3国の領域を通過する場合には許可が必要、⑤首相が総合的に判断、⑥原則、国会の事前承認を得る。事後承認は緊急時のみ~~などと報道されている。
「集団的自衛権は必要最小限度の自衛権に含まれる」という主張は、3月31日の自民党が集団的自衛権の行使容認を党内論議でまとめるために安倍が設置した安全保障法制整備本部(本部長・石破茂自民党幹事長)で突然、自民党副総裁の高村正彦が提案した。高村は、「自国の存立に必要な自衛措置は認められる」とした1959年の砂川事件最高裁判決を引用し、憲法が許容する「必要最小限度の自衛権」に集団的自衛権の一部が含まれるとする「限定的に容認」という考えを示した。
首相・安倍晋三はこの「限定容認論」を支持(8日、BSフジ番組)し、「(砂川判決は)集団的自衛権を否定していないのははっきりしている」と断定している。
公明党の5月9日の安全保障に関する研究会で衆院法制局の担当者は、「砂川判決でいう自衛権は個別的自衛権と解釈するのが一般的」と発言したことを引用するまでもなく、砂川判決が集団的自衛権行使も個別的自衛権に含まれるとする論法には無理がある。
しかし、国家の自衛権を承認してそれを根拠に集団的自衛権行使を否定するやり方、集団的自衛権ではなく個別自衛権を行使すれば事足りるからという論議は、自衛権行使の延長に侵略戦争が繰り返えされた歴史を振り返れば、危険である。それは、安保法制懇が「わが国を取り巻く安全保障環境の変化」を口実として明確に北朝鮮および中国を仮想敵国視しているように、対北朝鮮、対中国の扇情的な排外主義によって可能とされた論理なのである。
安保法制懇の座長代理の北岡伸一はインタビューに答えてこう発言している。「安全保障の要諦は相手の裏をかくことだ。全てを類型化すれば安保はできない」「集団的自衛権行使を可能にして日米同盟を強化する」「(1954年の必要最小限の自衛権行使を認めた最高裁判決について)この変化に比べればささやかな変更だ。憲法を守るだけで国は守れない」と。
ここにははっきりと帝国主義戦争の論理、強盗戦争の論理、秘密軍事外交の論理が動いているのである。
さらに安保法制懇の報告書では「国際紛争」に関する憲法解釈の変更を提言し、憲法9条で禁止している「国際紛争」は日本が当事者の場合に限るとの新解釈を打ち出し、PKOでの武器使用の制限緩和を求めるというのだ。現行解釈は「全ての国際紛争」が該当するとして、離れた場所で攻撃を受けた国の隊員の救援(駆けつけ警護)や国連の多国籍軍の給油や輸送を禁止しているが、これが可能になるのだ。
3、安倍政権の狙いはすでに現実に具体化されつつある
安倍政権は安保法制懇の報告書を受けて集団的自衛権の行使容認の「政府方針」を決定し、閣議決定する方針だ。
その「政府方針」素案(2014.5.2)では、①国家が存立を全うするために必要な自衛権は認められる。②自衛権行使は必要最小限度にとどまる。③自国が攻撃を受けていなくても、密接な関係にある国が攻撃された場合など自衛権が行使できる状況がある。④他国への攻撃に対して自衛権を行使するのは、日本の安全に重大な影響がある場合などに限る。⑤攻撃を受けた国からの要請や国会の同意なども行使の条件とする。⑥日本を取り巻く安全保障環境の悪化を踏まえれば、抑止力を高める必要がある~~とした上で、文案では公明党や創価学会の反発を和らげるために「集団的自衛権」という表現を使うのを避けたと報道されているが、③で集団的自衛権の行使容認を明白に規定している。
集団的自衛権の行使容認はすでに始まっている。沖縄基地強化や在日米軍・自衛隊の強化である。
米軍はヘーゲル・小野寺会談(4月6日)でアジア・太平洋への米軍配備の拡大を確認し、具体的にはイージス艦を2隻追加し7隻体制に、日米合わせると13隻の巨大編成になる。また昨年12月には、最新鋭P8対潜哨戒機を沖縄米軍基地に配備し、無人偵察機「グローバルホーク」の配備も決定した。2月には米海軍佐世保基地に新鋭の輸送揚陸艦「グリーンベイ」(排水量は現在配備されている揚陸輸送艦の1.5倍の2万5000トン、最新鋭の機器を使った指揮命令システムを装備し、オスプレイを格納している。事が起こればこの輸送揚陸艦が佐世保を出港し、沖縄で海兵隊を乗り組ませ、戦場に輸送する)を配備し、さらに今年の5月には能力の高い掃海艇「パイオニア」「チーフ」を配備する。
自衛隊は、中期防衛力整備計画で新設を明記したが、水陸両用作戦を展開する3000人規模の「水陸機動団」を長崎県・相浦駐屯地に新設。陸自西部方面隊普通科連隊を中核とし、米海兵隊との共同訓練で育成していく。現在、水陸両用作戦部隊は西部方面隊に700人配置されている。さらに15年度から民間の高速フェリー2隻を自衛隊輸送に活用し、PFI(民間資金を使った社会資本整備)の枠組みで金融機関などから出資を募る。13年12月の防衛計画大綱で「民間輸送力との連携」としたことの具体策であり、海自は「おおすみ」など輸送艦3隻体制だが、巡航速度が40キロ/時で緊急時の機動力がないため、速度70キロ/時で大型トレーラー30台、乗用車100台収容の「ナッチャンWorld」(津軽海峡フェリー)、「はくおう」(新日本海フェリー)を金融機関や海運会社出資で設立する特別目的会社SPCが購入し、防衛省との運行契約に基づいて輸送を担う。乗組員には、外国軍に侵攻された地域などに部隊を運ぶ場合は民間の乗組員は立ち入りできないから「予備自衛官」を活用する。14年度に2隻を購入、15年度に防衛省がSPCと20年の利用計画を結ぶ。
陸自を機動的に運用するために。18年度までに全国五つの方面隊などを統括する「陸上総隊」を設ける。海自や空自と同様に指揮系統を一元化し、全国規模で部隊を運用する際などに調整しやすくする。陸自には五つの方面区と防衛相直轄の中央即応集団などもある。
集団的自衛権行使は作戦レベルではすでに始まっている。
13年3月に岩崎茂統合幕僚長とロックリア太平洋軍司令官が協議し、夏に決定した釣魚台(「尖閣」)有事の際の日米共同作戦計画がすでに存在している。その内容は ①グアムのアンダーセン空軍基地からB52を急派、②普天間基地に駐留する海兵隊を佐世保基地の輸送揚陸艦を用いながら上陸させるというものである。釣魚台で事が起こった場合は、米軍はB52を出撃させる計画なのだ。B52で釣魚台諸島を爆撃するわけではあるまい。B52は軍事基地や大都市への爆撃であり、核爆弾も装備している。米軍は釣魚台とその周辺で事が起これば中国本土への爆撃をすると宣言しているのだ。
現に、この計画が作成されて以降の中国による防空識別圏の設定に対して、米軍が最初にとった行動はグアムからB52を2機、防空識別圏の中を飛行させるというものであった。戦闘機の護衛をつけないという条件をつけてである。佐世保基地への最新鋭揚陸輸送艦の配備も、この作戦計画に沿ったものである。
前出の北岡発言に端的であるが、すでに帝国主義侵略戦争の力学に沿った論理や行動が平然ととられ始めている現実を重視しなければならない。
集団的自衛権行使容認と闘うためには、自衛権も含めて一切の戦争をまずは否定しなければならない。まずはこの立場で一切の戦争を否定することである。広く議論を起こすには、この信頼関係にたって初めて、なぜ帝国主義の現代社会は戦争を不可避とするのか、戦争は帝国主義の政治の継続であり、この帝国主義の政治、帝国主義社会を根底からひっくり返す以外に戦争はなくならないという議論が始まる。自衛権、ひいてはナショナリズムに縛られず、国家の自衛権を真っ向から否定し、一切の戦争に反対することが重要である。
同時に、対中国、対北朝鮮、さらには対韓国の上からと下からの排外主義、レイシズムが帝国主義戦争突入の最大の動力とされることを見すえ、一切の自衛の名による戦争が実は侵略戦争以外の何ものでもないことを明らかにして闘うことである。
全力で闘おう。
2014年5月11日
博多のアイアンバタフライ















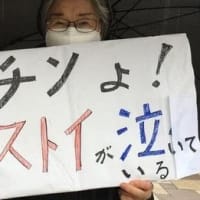




との提起ですが、「一切の戦争に反対する」のではあまりにも抽象的、且つ一般論ではないでしょうか。革命党が不在であるという否定的現実を踏まえて、闘うアジア人民と連帯して自国帝国主義打倒、の立場を鮮明にすることだと思います。同じく「革命的祖国敗北主義」の立場でもって、排外主義との戦闘的な闘いを戦取することも明確にすることで、革命的共産主義者の立場を合わせて鮮明にすることだと思います。
無論、そこには国家権力との関係で「革命的・階級的暴力の思想の復権」」を革命党再建の基軸に据える必要があるのではないでしょうか。
いつまでも、戦後世界体制の幻想と虚妄の戦後民主主義イデオロギーに留まっていると、全く現実を見失ってしまいます。日本とアメリカの関係も基本的には、戦前と同じ敵対的関係に急速に回帰していますし、それは、オバマの「アジア回帰」に対して、安倍の諸政策として、誰の目にも見える形で表れてきています。
今後、膨張を続けるほかない日本・ドイツとこれを阻止せんとするアメリカとの対立と激突は、世界中で戦争的緊張を高めていきますし、資本であれ政治家であれ、この力を押しとどめることはできません。ただ社会主義革命のみがそれを可能とするでしょう。
従って、我々の仕事としては、労働者人民に容易に理解できる高度の現状分析を提供する事。さらに最低でも社会主義に至る道筋を提示し、これをイデオロギーとして世界的な潮流のひとつに成長させること。理論的な一貫性があればこれらのことは可能でしょう。政党の役割とは、本来そのようなもので有ろうと思います。