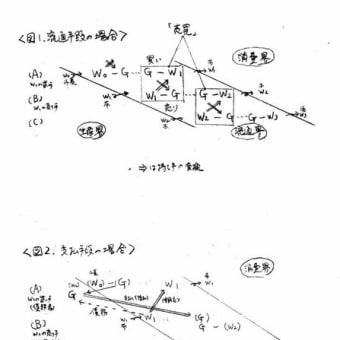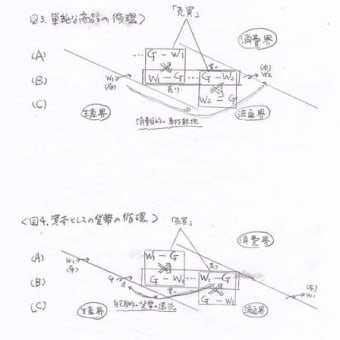「読む会」だより(24年8月分)文責IZ
前回の読む会でお知らせしましたように、8月の「読む会」は休止とさせていただきます。
「たより」も今回は復習1だけとし、7月での議論などは9月の「たより」で報告します。
(9月の読む会は通常通りの15日(日)開催予定です。)
今回の「復習1商品と交換価値(価値)」は、「たより3月用」の<資本論第1章での価値の説明について>と、4月用の「3月の議論など」で触れた点をまとめ直したものです。もう少し文章になっているつもりでしたが、口頭説明が多くほぼ書き直しになりました。
(復習項目は、2時間ほどの読む会の中で30分ほど時間をとって、『資本論』を“読む”ために不可欠であろうことをできるだけ分かりやすい形で取り上げることを考えています。)
──復習1商品と交換価値(価値)──
商品は、それがモノとして色々な有用性をもつという性質つまり使用価値であるという性質と、それが他の商品と一定の比率で交換されうるという(価格などで表わされているように)性質つまり交換価値をもつという、二つの属性(性質)を同時に持っています。前者が商品の物質的な属性によるもの(言い換えれば、モノと人間との関係)であるのに対して、後者は商品の社会的な属性(言い換えれば、人間と人間との関係がモノの属性として現れたもの)であるために、その理解にはさまざまな困難が生じます。
マルクスは『資本論』の冒頭のほうで次のように述べています。
・「ある一つの商品、たとえば1クォーターの小麦は、x量の靴墨とか、y量の絹とか、z量の金とか、要するにいろいろに違った割合の他の諸商品と交換される。だから、小麦は、さまざまな交換価値<様々な商品の様々な量で表わされる交換比率>をもっているのであって、ただ一つの交換価値をもっているのではない。しかし、x量の靴墨もy量の絹もz量の金その他も、みな1クォーターの小麦の交換価値なのだから、x量の靴墨やy量の絹やz量の金などは、たがいに置き換えられ得る、またはたがいに等しい大きさの、諸交換価値でなければならない。@
そこで、第一に、同じ商品の妥当な諸交換価値は一つの同じものを表わしている、ということになる。しかし、第二に、およそ交換価値は、ただ、それとは区別される或る実質の表現様式、『現象形態』でしかありえない、ということになる。」(第1章第1節、全集版P50)
第一の点からいえば、様々な使用価値の違いを“捨象して”──つまりそれらの違いを生み出している種々の有用労働の違いを考慮外におけば──、諸商品に共通で、しかも量的に比較できるものが何かといえば、それは、それらに“対象化されている”(実現されている)無差別なあるいは抽象的な人間労働だというのです。
一見、分かりにくいことのようですが、次のように考えれば当然のことでしょう。全面的な商品交換によって生活を成り立たせている社会(商品社会)にあっては、人々はもっぱら自分自身のためにではなく他人のためにあらゆるものを生産し、他方で自らは他人の生産したものを利用することで生活を成り立たせています。だからこそ、こうした社会関係のもとでは人々の労働はそれがどんな種類のものであるかにかかわらず(その具体的有用的な姿の如何を問わず)、それが社会の必要を満たすものである限りでは、社会的な(つまり諸個人相互にとっての)同等性・同質性を獲得するのであり、これが商品の価値の内容・実体を形成するのです。発展した分業をもつ社会にあっては、商品の「価値の実体」が同質な「抽象的人間労働」(社会的労働の同等性)であることは、単なる想像上のものではなくて、そこでの諸個人の労働がもつ“実在的な”社会的性質なのですから、このこと自体は言葉ほどには難解ではないのです。
マルクスはロビンソンを例にとって、抽象的人間労働について次のように分かりやすく説明しています(個人的な生産と社会的な生産とではいくつかの違いはありますが)。
・「生来質素な彼ではあるが、彼とても色々な欲望を満足させなければならないのであり、したがって道具を作り、家具をこしらえ、ラマを馴らし、漁猟をするなど、いろいろな種類の有用労働をしなければならない。……彼の生産的諸機能はいろいろに違ってはいるが、彼は、それらの諸機能が同じロビンソンのいろいろな活動形態でしかなく、したがって人間労働のいろいろな仕方でしかないということを知っている。必要そのものに迫られて、彼は自分の時間を精確に自分のいろいろな機能のあいだに配分するようになる。彼の全活動の内でどれがより大きい範囲を占めどれがより小さい範囲を占めるかは、目指す有用効果の達成のために克服しなければならない困難の大小によって定まる。経験は彼にそれを教える。……」(同第3節、P102)
商品は、私的に行なわれる様々な有用労働の結果としてそれぞれ質の異なる使用価値をもつばかりではなくて、社会的な分業・協業のもとでのそれらの人間労働としての同等・同質な性格(価値性質、価値実体)を、その使用価値とは区別される他の商品との交換割合(つまり交換価値)として表示しているのです。この同質な内容は、量的には必要労働量として規定されます。
はじめの引用で述べられているように商品の交換関係を考察するならば、「第一に、同じ商品の妥当な諸交換価値は一つの同じものを表わしている」ということ、そして、にもかかわらずそれぞれの商品はそれぞれに違うものなのですから、「第二に、およそ交換価値は、ただ、それとは区別される或る実質<岩波文庫訳では〔内在物〕つまり抽象的人間労働>の表現様式、『現象形態』でしかありえない」ということは、さほど難解な事柄ではないでしょう。
つまり商品は、それぞれに異質な「使用価値」をもつと同時に、他の商品と同質で量的にだけ区別される「交換価値」(交換割合)をもちます。そして交換価値としては、商品はそれらの使用価値とは全く異なる「抽象的人間労働」という社会的同質性(「価値の実体」)を表現しており、またその大きさ(「価値量」)がその生産に必要な労働時間として規定されることになります。これらのことは、商品のもつ価値性格が、生産“物”そのものの性質ではなくて生産物を“商品”(つまり異質な使用価値であるとともに同質な価値をもつもの)とする人間相互の労働の関係=社会関係に“内在する”ものであると分かるならば、言葉ほどには難解ではありません。難解なのは、商品の価値(抽象的人間労働)の『現象形態』である交換価値は、直接に労働時間として表現されるのではなくて、それと交換される他の商品の使用価値の大きさとして(つまり他の商品の身体を借りて)表現されるほかない、という商品相互による価値表現の仕方にあるのです(この点については、復習2などで触れます)。
商品社会の基礎となっているのは、自然発生的で無政府的に行われる人々の生産活動つまり私的労働であって、それ自身は直接には社会的に結合された労働ではありません。しかし同時に、ここでの労働は、その生産物が商品として交換されるということによって媒介的に結合されることによって、有用労働としても抽象的労働としても社会的なものであるということを、あるいはそれが私的な労働であるとともに社会的な労働であることを“実証”していかねばならないという矛盾に満ちた労働です。言い換えれば、それは直接に社会的に結合した労働として止揚され、解決されなければならないのです。
そしてこのように生産が社会的意識的に組織されるのではなくて、生産を私的な労働生産物の“交換”を基礎として行なう商品社会においては、諸労働を社会的に結合するという役割は人々自身ではなくてその生産物である商品が担うことになるために、人間労働の社会的に同等な性質が物(生産物)の社会的に同等な性質(価値性質)として現われるという“転倒”が起こります。このために、商品の価値とは何であり、またそれがどのような役割を果たしているのかということの理解は困難になるのです。
(第4節でマルクスはこう述べています。「ここ<宗教的世界>では、人間の頭の産物<神や精霊など>が、それ自身の生命を与えられてそれら自身のあいだでも人間とのあいだでも関係を結ぶ独立した姿に見える。同様に、商品世界では人間の手の生産物がそう見える。これを私は呪物崇拝と呼ぶ……」全集版、P98)
「たより3月用」では、これらのことを同じ個所にある別の引用を引いて下記のように説明しました。それなりの意味があると思うので再録しておきます。
「商品が交換価値をもつという“現象”の背後にある人々の社会関係は、商品を生産する労働はすべて社会的な労働であり、抽象的・一般的人間労働としてはすべての労働が同質であるという内容・質をもちます。この社会関係こそが生産物に価値性格をもたらし(すなわち生産物を商品とし)、それが商品の交換価値として現れるのです。しかしだからこそ、この社会関係の理解抜きには価値を本当に把握することはできませんし、しかもこの引用の後で詳しく述べられるように、この商品交換で成り立つ社会にあっては人と生産物との関係がまるで鏡のなかの世界のように反転して見えるのです。労働の社会的性格(抽象的労働としての同質性、平等性)こそが生産物に価値をもたらし、生産物を商品とする内容であり“社会的実体”であることは、言葉ほどには難しいことではないのですが、人々の労働自身ではなくてその生産物が価値をもつという外観がこのことを見えにくくしているのです。具体的労働が生産物の使用価値を生み出すということは自然的な事柄であって誰にでも分かりやすいのですが、その同じ労働がなぜ商品交換のなかでは生産物の価値をもたらすのかということは特殊歴史的な事柄であって、商品交換の社会のなかに閉じこもっていては理解することはできません。社会的な労働が人々によって意識的に組織され、諸個人の労働の同等性が担保される社会であれば生産物が価値をもつ必要がない、ということは第4節で述べられていることから明らかでしょう。」
また、「たより4月用」では、この説明について次のような補足をしました。
「第一点は、引用した第1章での説明<全集版、P51の部分>は社会現象に対する認識ということでは科学的な方法だが、はじめて読む人には価値の全体的なイメージが湧きづらいだろうと考えてこのようにまとめてみました。全体が見えてくれば方法にも興味を持ってもらえるでしょうが、その間はあまり方法にこだわるとむしろ読む興味自体を失ってしまうのではないかという反省があるためです。
第二点は、マルクスをかじった人なら価値とは労働時間のことだと思い浮かべるでしょうが、引用部分のすぐ後で「価値を形成する実体の量」として指摘されている労働時間について触れることを忘れていました。価値とは労働がもつ社会的な性格であり、全ての労働が同質とみなされるという社会関係が商品に価値をもたらすとたより<3月用>で触れました。しかし、この価値性格は実際には労働時間として存在することになります。(『経済学批判』では「労働時間は……量的であるとともに、その内在的尺度をもつ労働の生きた定在である」(岩波文庫版、P25)とあります)。なぜかと言えば、社会的な生産においては、労働が種々の生産部門に質的に分割されるとともに、それぞれの部門に総労働時間が量的に適切に分配されなければ生産が継続しえないという必然性を持つからです。この必然性のために、商品のもつ価値性格は、労働時間という“社会的な実体”を持つことになるとチューターは考えています。(商品社会ではこの必然性は価値法則という姿をとります、言い換えれば商品は社会的必要労働時間として価値法則を実現していくものになります。)」
この補足の第一点については、方法を無視するというわけではないということで了承願います。また、第二点の前半部分で触れている、「価値を形成する実体<抽象的人間労働>の量」としての、あるいは「労働の生きた定在」としての「労働時間」という問題については、7月の読む会でも質問が出ましたので、次回9月の「たより」でもう少し補足したいと思います。
第二点の後半部分で「この必然性のために、商品のもつ価値性格は、労働時間という“社会的な実体”を持つことになる」と触れた点は、不適切でした。その後で触れているように、社会の再生産のためには総労働が種々の部門に適切な量で配分されなければならないという必然性は、商品社会にあっては価値法則(価値規定や等価交換等々)として貫かれるとチューターは考えます。しかし商品に価値性格をもたらすものが、そうした総労働の分配の必然性であるといった説明は正しくありませんでした。
今回説明しましたように、商品に、というよりも商品を生み出す労働に、それらは社会を成り立たせる総体としての人間労働の一部分である(つまり抽象的人間労働である)という価値性格を与えるのは、自然発生的な分業によって相互的に生活を成り立たせる人々の社会関係なのでした。