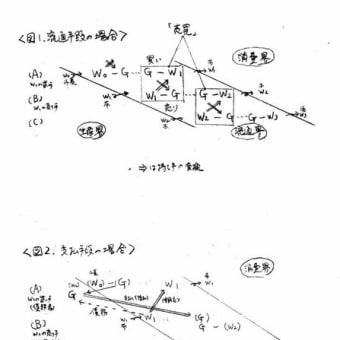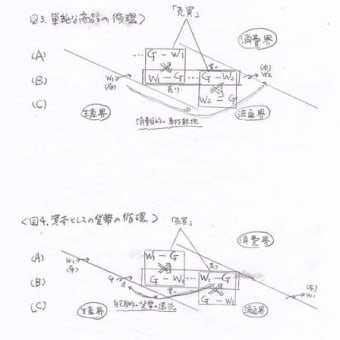「読む会」だより(21年4月用)文責IZ
(前2回の議論など)
前2回の「読む会」は、MMT理論の批判的理解の糸口になればと、貨幣とりわけその計算貨幣の機能について触れてみましたが、あまりうまくいきませんでした。
チューターの問題意識は、プロメテウス59号での林・第一論文、P20上段の、
「貨幣があってはじめて、そのさまざまな貨幣の機能を語り、規定し、明らかにでき、貨幣の一機能、つまり『計算貨幣』の機能も概念規定されうるのだが、彼らは何と反対に、貨幣の『計算貨幣』としての機能から、貨幣そのものを、その必然性を説くのである、あるいは貨幣には『計算貨幣』の役割しかないと思い込んでいる……」
の部分(とりわけアンダーラインの部分)の理解を深めたいというところにありました。
「貨幣があってはじめて、そのさまざまな貨幣の機能を語り、規定し、明らかにでき、貨幣の一機能、つまり『計算貨幣』の機能も概念規定されうるのだが、彼らは何と反対に、貨幣の『計算貨幣』としての機能から、貨幣そのものを、その必然性を説くのである、あるいは貨幣には『計算貨幣』の役割しかないと思い込んでいる……」
の部分(とりわけアンダーラインの部分)の理解を深めたいというところにありました。
いまのチューターの理解としては、商品のもつ矛盾──実在物としては特定の使用価値でありながら、同時に社会物としては普遍的な価値でなければならない──によって商品が二重化し、商品にとって外的な価値の尺度となる(言い換えれば、諸商品の価値表現の材料になる)ための貨幣が“まず”生み出される。そして、“はじめて”計算貨幣などの機能が貨幣にもたらされる、ということのように思います──といっても、論理的にでしょうが。(林さん自身はここでは、貨幣とは何かという、より単純でより純粋な概念がまずなければいけないと言っているだけかもしれませんが、もう聞くことはできません。)
貨幣が価値尺度(つまり商品の価値表現の材料)となり、諸商品が「価格」をもつ──人間の諸欲望(使用価値)とは切り離された、同質な価値の表現として──ことによってはじめて、実際に“物”である商品が、人間の意識や意図からは“自立”した社会関係を相互にもち、人間の諸関係を“物”(商品や貨幣や資本など)の諸属性として投影することが可能になるのだと思います。
2月21日に開かれた「読む会」では、まずMMT理論に関して「資本論とどのような関係にあるのか」という質問と、「かつて戦後のハイパーインフレを経験したものにとっては、MMTの話は信じられない」という感想が出ました。MMT理論は、近代経済学とりわけケインズ理論から出発していると考えられるので、資本論の貨幣理論とは関係していません。むしろ、マルクスはスチュアートの批判などを通じて観念的価値尺度論の誤りを指摘しているように思います。
たよりの内容に関しては、「貨幣は、計算貨幣から鋳貨=金になると購買力をもつといったことか」という質問が出ました。チューターは、そうではなくて、貨幣の購買力というのは貨幣が商品の価値の形態として認められているからこそだ。だから商品は貨幣へと形態を変えることができれば他商品へと自由に転換しうる。購買といい販売といい、その内容は商品価値の価値形態と現物形態との転換だとマルクスは強調している、と説明しました。さらに、貨幣が生み出されることによって、商品が価格すなわち観念的な貨幣に共通に還元されるからこそ、諸商品は比較しうるものになり、そのことによって貨幣は計算貨幣という機能をもつということを、MMTの理論は忘れているだろう、と述べました。
また、たよりでの説明について「なになになのは、こうこうだからだ」と書くのではなくて、「こうこうだから、なになにだ」というふうにひっくり返して書いてくれると分かりやすい、という意見がありました。参考にさせてもらいます。
3月21日に開かれた「読む会」では、たよりの末尾にある「定在」という言葉の意味を説明しないまま、久留間の引用をしたために「それは価格を固定化するといった意味か?」という質問が出ました。誤解を招いて申し訳ありませんでした。
コトバンクの日本大百科事典によれば「定在」は、ヘーゲル哲学の基本概念として以下のような説明になっています。マルクスの言葉をヘーゲルのものと同一視はできませんが、「認識論」の言葉としてはこの説明でよいように思います。ただし最後に挙げてある2例は、いわゆる“逆立ち”した──つまり外界の“認識”という目的から外れ、意識のなかをさまよう“空想”へと帰着した──ヘーゲル「哲学」の典型でしょう。
『定有・定在・定存在
いずれも原語はDaseinで「規定された存在、質をもつ存在」の意。ヘーゲル以外の哲学者の用語としては「現存在」と訳されるが、それは「現に目の前に現れている」というところに強調点があるからである。ヘーゲルでは「一定の具体的な実在物」のこと。たとえば「食塩」「酸素」「農民」「所有物」など。定有は質を身につけている。すなわち、他のものとの差異、性質上の限界、制限を自分の性質としてもっている。定有は、限界を身の周辺につけているだけではなくて、限界を自分の核心に体している。しかし限界という規定はその定有の否定である。ゆえに定有とは、自己の否定を自己のうちに含む存在である。また、定有は本性の現れ、示現、権化、托身、受肉である。たとえば、私の所有物は私の所有権の定有である。国家は自由の定有である。』
慣れないと難しい言葉だらけでしょうが、マルクスは、価値形態の部分を除いては『資本論』には難しいところはない、中学生にも分かるだろう、とどこかで述べています。ある程度意味がつかめればよいということで進んでいきたいと思います。
なお経済体制としての社会主義が、いわゆる“ソ連型”の統制経済や計画経済とは全く別なものであることは、それらが貨幣によって、あるいは貨幣を利用して行なわれたことが経済的には何よりの証拠と言えます──労働者への搾取・抑圧という階級的側面も無論ですが。というのは、貨幣とは、人々が社会的に意識的に労働と生産を組織できないために、したがってまた人々の労働の分割と配分とが、私的な生産“物”である商品の交換を通じて行なわるほかないがゆえに、その媒介物として生まれざるをえなかったものなのですから。人々の生産力の発達とともに生まれるべくして生まれた貨幣は、その社会的条件がなくなるとともに消え去っていく”歴史的なもの”なのです。貨幣を利用した、「統制」や「計画」といったものはブルジョア的なもの、すなわち国家資本主義なのであって、社会主義とは無縁だと言わねばなりません。
遅れましたが、今回から昨年10月に引き続き第5章に入ります。
(説明)第5章「労働過程と価値増殖過程」 第1節「労働過程」
1)使用価値の生産は、それを生み出した人間の社会関係・社会形態とは無関係である。使用価値の生産のための合目的的活動であるという労働の普遍的な性格は、それが資本家的な生産であるということによって変わるものではない。労働過程の単純な諸契機は、合目的的な活動または労働そのものとその対象とその手段である。
(下線の部分を20年11月のたよりから訂正、追加しました。また後半の「資本家的な生産においては、使用価値と同時に価値をもつ“商品”の生産のために労働力が用いられる。このために、労働対象と労働手段という客観的な条件のなかで行われる労働過程が、同時に価値増殖過程として遂行される。ここに資本家的生産の特徴がある」の部分は、次回の「価値増殖過程」のところで説明します。)
この労働過程の部分は、ほとんど説明が要らないほど分かりやすいうえに、マルクスのマルクスらしさがあふれている──唯物史観の適用として──部分と思われます。ほとんど引用になってしまいますが、要点は以下のようなものです。(アンダーライン他は、これまで通り)
・「労働力の使用は労働そのものである。労働力の買い手は、労働力の売り手に労働をさせることによって、労働力を消費する。このことによって労働力の売り手は、現実に、活動している労働力、労働者になるのであって、それ以前はただ潜勢的にそうだっただけである。彼の労働を商品に表わすためには、彼はそれをなによりもまず使用価値に、なにかの種類の欲望を満足させるのに役立つ物に表わさなければならない。だから、資本家が労働者に作らせるものは、ある特殊な使用価値、ある一定の品物である。@
使用価値または財貨の生産は、それが資本家のために資本家の監督のもとで行われることによっては、その一般的な性質を変えるものではない。それゆえ、労働過程はまず第一にどんな特定の社会的形態にもかかわりなく考察されなければならないのである。」(全集版、P233)
労働過程は、特定の社会的形態にかかわりのないものとして、つまり労働がそのなかで行われる社会関係を捨象しても残る、使用価値の生産という側面に抽象化(純粋化)して、まず考察しなければならない、そして、そのようにしてはじめて労働過程が価値増殖過程と結びついている資本主義社会の歴史的特殊性が把握できるのだ、と、こうマルクスは述べているのだと思われます。次いで
・「労働は、まず第一に人間と自然との間の一過程である。この過程で人間は自分と自然との物質代謝を自分自身の行為によって媒介し、規制し、制御するのである。人間は、自然素材にたいして彼自身一つの自然力として相対する。彼は、自然素材を、彼自身の生活のために使用されうる形態で獲得するために、彼の肉体にそなわる自然力、腕や足、頭や手を動かす。人間は、この運動によって自分の外の自然に働きかけてそれを変化させ、そうすることによって同時に自分自身の自然〔天性〕を変化させる。彼は、彼自身の自然のうちに眠っている潜勢力を発展させ、その諸力の営みを彼自身の統御に従わせる。@
ここでは、労働の最初の動物的な本能的な形態は問題にしない。労働者が彼自身の労働力の売り手として商品市場に現われるという状態にたいしては、人間労働がまだその最初の本能的な形態から抜け出ていなかった状態は、太古的背景のなかに押しやられているのである。われわれは、ただ人間だけにそなわるものとしての形態にある労働を想定する。@
蜘蛛は、織匠の作業にも似た作業をするし、蜜蜂はその蝋房の構造によって多くの人間の建築師を赤面させる。しかし、もともと、最悪の建築師でさえ最良の蜜蜂にまさっているというのは、建築師は蜜房を蝋で築く前にすでに頭の中で築いているからである。労働過程の終わりには、その始めにすでに労働者の心像のなかには存在していた、つまり観念的にはすでに存在していた結果が出てくるのである。労働者は、自然的なものの形態変化を引き起こすだけではない。彼は、自然的なもののうちに、同時に彼の目的を実現するのである。その目的は、彼が知っているものであり、法則として彼の行動の仕方を規定するものであって、彼は自分の意思をこれに従わせなければならないのである。……」(同、P234)
ここではチューターが下手に説明すべきではないほどに、人間の労働の特性が見事に語られています。すなわち、人間の労働の特性は、「自然的なものの形態変化を引き起こすだけではな」くて、「自然的なもののうちに、同時に」頭のなかで観念的にはすでに存在していた、「彼の目的を実現する」というところにある、と言うのです。そしてさらに、この目的は、「法則として彼の行動の仕方を規定」し、「自分の意思をこれに従わせなければならない」、つまりその活動を客観的な合法則性に適合させる場合にのみ目的を遂げ得る、とこう言うのです。次いで
・「労働過程の単純な諸契機は、合目的的な活動または労働そのものとその対象とその手段である。……原料……」(同、P235)
「契機」という言葉については、とりあえず「変化・発展を起こす要素・原因」というように理解願います。
使用価値の生産という側面に純粋化すれば、労働過程の要素・要因は、人間の主体的活動としての労働そのものと、その対象である客体と、両者を媒介するその手段という、三つの要因に分けられるというまことに単純な真理です。次いで
・「……労働者が直接に支配する対象は──完成生活手段、例えば果実などのつかみ取りでは、彼自身の肉体的器官だけが労働手段として役立つのであるが、このような場合は別として──労働対象ではなく、労働手段である。こうして、自然的なものがそれ自身彼の活動の器官となる。その器官を彼は、聖書の言葉にもかかわらず、彼自身の肉体器官につけ加えて、彼の自然の姿を引き延ばすのである。……@
およそ労働過程がいくらかでも発展していれば、すでにそれは加工された労働手段を必要とする。最古の人間の洞窟のなかにも石製の道具や石製の武器が見いだされる。加工された石や木や骨や貝殻の他に、人類史の発端では、馴らされた、つまりそれ自身すでに労働によって変えられた、飼育された動物が、労働手段として主要な役割を演じている。労働手段の使用や創造は、萌芽としてはすでにある種の動物も行うことだとはいえ、それは人間特有の労働過程を特徴づけるものであり、それだからこそフランクリンも人間を“道具を作る動物”だと定義しているのである。死滅した動物種族の体制の認識にとって遺骨の構造がもっているのと同じ重要さを、死滅した経済的諸構成体の判定にとっては労働手段の遺物がもっているのである。何が作られるかではなく、どのようにして、どんな労働手段で作られるかが、いろいろな経済的時代を区別するのである。労働手段は、人間の労働力の発達の測度器であるだけではなく、労働がそのなかで行われる社会的諸関係の表示器でもある。……」(同、P235)
人間の労働が直接に働きかけるのは、労働対象ではなくて、もっぱら労働手段であるということ、これもまことに否定しえない歴史的な真実です。次いでマルクス自身、労働過程についてこうまとめています。
・「要するに、労働過程では人間の活動が労働手段を使って一つの前もって企図された労働対象の変化を引き起こすのである。この過程は生産物では消えている。@
その生産物はある使用価値であり、形態変化によって人間の欲望に適合するようにされた自然素材である。労働はその対象と結びつけられた。労働は対象化されており、対象は労働を加えられている。労働者の側に不静止<活動=有用労働>の形態で現れたものが、いまでは静止した性質として、存在の形態で、生産物の側に現われる。労働者は紡いだのであり、生産物は紡がれたものである。
この全過程をその結果である生産物の立場から見れば、二つのもの、労働手段と労働対象とは生産手段として現われ、労働そのものは生産的労働(※)として現われる。
(※)このような生産的労働の規定は、単純な労働過程の立場から出てくるものであって、資本主義的生産過程についてはけっして十分なものではない。」(同、P237)
このマルクス自身のまとめのなかで特に重要な事柄は、労働という人間の活動は、それが対象化された結果である生産物(使用価値)の姿においては、消え去っている、ということでしょう。同様に、対象化された労働の歴史的形態である商品の価値もまた、その使用価値においては消え去っているのであり、だからこそただ相対的にのみ、すなわち他の商品との等価関係において、その社会的実体として現われることができるだけなのです。
ところで、この「労働過程」について、岡崎次郎──向坂訳の岩波版『資本論』の翻訳を実質的に担ったことや大月版『資本論書簡』の翻訳などで知られる──は、『資本論辞典』(青木)のなかで次のような説明を加えています。
「人間が各種の欲望を充足するために行なわなければならない各種の使用価値の生産は、つねにある時間的長さをもつ一つの過程として、すなわち《生産過程》として現われる。生産過程は、それが商品の生産として、資本家のために、資本家の管理のもとに行なわれることによって、その一般的性質を変えるものではない。生産過程は、まず第一に、すべての社会形態に共通な《労働過程》として考察される。…<以後の部分は『資本論』の叙述のほぼ繰り返し>…」
「人間が各種の欲望を充足するために行なわなければならない各種の使用価値の生産は、つねにある時間的長さをもつ一つの過程として、すなわち《生産過程》として現われる。生産過程は、それが商品の生産として、資本家のために、資本家の管理のもとに行なわれることによって、その一般的性質を変えるものではない。生産過程は、まず第一に、すべての社会形態に共通な《労働過程》として考察される。…<以後の部分は『資本論』の叙述のほぼ繰り返し>…」
一見、『資本論』の叙述をまとめただけかに見えますが、マルクスの言葉と照らし合わせると相当奇妙なものです。
まず岡崎は、なぜか「生産過程は、まず第一に、すべての社会形態に共通な《労働過程》として考察される」と、マルクスの語っていることとは全然別のことを、すなわち《生産過程》をまず《労働過程》として考察することがここでの重要な課題であるかに述べています。
しかしマルクスがここで“第一に”重要なことだと言っているのは、どのような社会形態のもとでも人間が生活するために不可避な条件であり活動であるところの──岡崎の言葉を借りれば、各種の欲望を充足するために行なわなければならない──、「使用価値または財貨の生産は、それが資本家のために資本家の監督のもとで行われることによっては、その一般的な性質を変えるものではない。それゆえ、労働過程はまず第一にどんな特定の社会的形態にもかかわりなく考察されなければならない」ということです。つまり、使用価値を生産する労働すなわち具体的有用労働の必然性は、特定の社会的形態(そこで労働が行なわれる一定の社会関係)にかかわりない、それゆえ、労働過程はまず社会的形態を捨象した純粋な抽象的な形でその要件(主体的なまた客体的な)について考察すべきだということにすぎません。だからこそ引き続いてそれらの抽象的な(つまり社会的形態にはかかわりのない、あるいは岡崎の言うように「すべての社会形態に共通な」)諸要件が説明されていくことになります。
労働過程を特定の社会形態を捨象して考察するということは、岡崎の言うような生産過程はまず労働過程として考察すべきということとは全く別ですし、ここで生産過程が労働過程として説明されているわけでないことは一読して明らかでしょう。そうではなくて、特定の社会形態を捨象してみるならば、誰にでも分かるように、「労働過程の単純な諸契機は、合目的的な活動または労働そのものとその対象とその手段である」と触れられているのです。
たしかに最後の引用にあるように、「この全過程をその結果である生産物の立場から見れば、二つのもの、労働手段と労働対象とは生産手段として現われ、労働そのものは生産的労働として現われる。」とマルクスは言っています。これを見れば《労働過程》を、結果としての生産物の立場から見たものが、あるいは人間の活動的で主体的な労働の過程を、それが対象化される客体的な労働要件の側面からみたものが《生産過程》だと言っているように思われます。しかしだからといっても岡崎の言うように、生産過程をまず第一に労働過程として考察することが、つまり両者の区別を問題とすることがここでの課題とされているわけではありません。ここでの課題は、労働過程の単純な諸契機とその結びつきを明らかにすることであり、そのなかでこそ生産過程を形作る客体的な諸契機が明らかになるというべきでしょう。
第二に、岡崎の説明でのもう一つの問題は、岡崎が労働“過程”について「各種の使用価値の生産は、つねにある時間的長さをもつ一つの過程として、すなわち《生産過程》として現われる」と語って、“過程”を時間の契機に還元している点でしょう。
マルクスは、引用したように労働“過程”についてこう語っています。「労働はその対象と結びつけられた。労働は対象化されており、対象は労働を加えられている。労働者の側に不静止の形態で現れたものが、いまでは静止した性質として、存在の形態で、生産物の側に現われる。労働者は紡いだのであり、生産物は紡がれたものである」
労働“過程”は──生産“過程”でも同じでしょうが──、岡崎の言うように時間だけを契機としているのではなくて、引用に挙げているような主体的なあるいは客体的な契機から成り立っており、そうした内的要因が「結びつき」、関係をもつことによって“過程”は成立するのであって──だから、なにがどのように結びついているのかという、その関係の分析が重要なのであって──、“時間”は過程にとってのいわば外的な契機でしかないと言うべきでしょう。(ただし“循環”の考察の場合には、当然に“時間”が、つまり循環の始点と終点の区別や、個々の過程と全体との区別等が問題とされざるをえないのですが。)
なお岡崎は、同書の「生産過程」の説明のところでも、「すべて、生産は、ある時間的経過のうちに、その現実の諸条件(労働力、労働対象、労働手段)の一定の変化をもたらすところの、一つの過程であり、かようなものとして、生産は生産過程である」と言っています。ここでも“過程”にとっては、同義反復的でしかない時間的契機を強調するのは的外れであって、非歴史的で漫画チックなマックス・ウェーバー風の抽象への傾斜とすら思われます。
2)の部分は申し訳ありませんが、タイトルを含め次回にまわします。