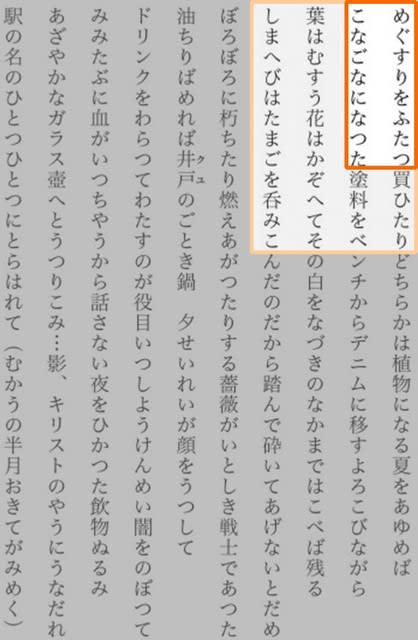三上さんの作品世界に漂う、不確かで象徴的な存在性、言葉と言葉の繋がりの不思議な質感をどんなふうに捉えたらいいのだろう。一読、意味の取りにくい作品もあるが、トリッキーな訳でもないように思える。ただ、輪郭を奪われたかのような動揺を覚えた。一首一首を、何が有力で、何が無力なのかを測りつつ読んだ。
人間はひとりにひとつ持たされた三百円のおやつであった
人間なのだとされている「三百円のおやつ」を持っている「ひとり」も人間なのだろうか。森羅万象や時空世界のような、大いなるイメージも立ち上がってくる。どちらにしても逆説めいた一首だ。
ひとりひとりに生誕日あるかなしさを鎮めるようにゆれる炎は
バースデーケーキに立てられた蝋燭の炎なのだろう。「生誕日」という硬質な言葉選びが、炎のゆらめきの重々しさを映像化させてくれる。
生きているひとはいいねとおもいつつ帰っていったツナマヨネーズ
「ツナマヨネーズ」が誰かの手で冷蔵庫に仕舞われたのだろう。だとすれば、一句目から四句目までが「ツナマヨネーズ」の擬人化に使われているのだが、間延びした感じはない。「おもいつつ」のひらがな表記の力無さが効果的だ。
赤ちゃんは生まれてこない 月面の低重力のスケートリンク
地球上の重力でなければ、受精は完了しないらしい。結句の「スケートリンク」はそんな不安定さの象徴だろうか。月色の冷たさも伝わる。
ナナフシは鳥に食べられ遠くまで卵を運んでもらうだろうか?
調べてみたら、ナナフシの卵はまるで木の実のようだった。ナナフシ自体も小枝に擬態していて、ほんとうに植物そのもののような昆虫だ。この作品では生より死が、捕食者より捕食される者が有力だ。
ペグシルの芯のようなる断片が転がっているかばんの底に
「ペグシル」は鉛筆の先だけをプラスチックの柄にはめ込んだような小さな筆記具だ。作品中の「断片」が何かはわからないが、そういえばそういうことあるある、と納得させられる。倒置法で静かに置かれた結句が、読み手をあざやかに実感へ導いている。
犬がいますのシールがやたら貼りついた玄関だけがある芥子畑
一読、不思議な作品だが、子どもの頃の感覚に戻って鑑賞するとよく解る。「玄関」は畑の囲いにある、ただの入り口なのだろう。「犬」はほんとうにいるのだろうか。たくさん貼られた「シール」の中の一枚なのかもしれない。そう考えると、幼い頃の記憶の錯誤のようなシュール感が楽しめる。
人類は滅びたあとに目が覚めてスクランブルエッグを焼くだろう
「滅びた」ものとは何なのか。例えば、人類の誕生より以前に絶滅した、恐竜や猿人などを基点にして鑑賞しても面白い。滅びたのが人類だとすれば、「スクランブルエッグ」が廃墟と化した都市の惨状を連想させる。「目が覚めて」に生をイメージするのか、死をイメージするのかが醍醐味だ。
さよならの森林浴に行きました 兵隊さんはみんなの誇り
戦争で手をつなぎたいだけなのに手はつなげない 蝋燭がきれい
表題の在り処のようにも思えた二首。表題の通り、戦う意志は感じられない。戦争ではなく、仕事や人間関係など、日々の生活にある不調和を投影しているように感じられた。「森林浴」、「蝋燭」、清らかなモノが有力だ。
妹はいないのだった 妹が冷たい水を渡してくれる
不在という存在。いる人よりもいなくなってしまった人が、人の心を充たすことがある。「わたしには世界の果ての私がコーヒーカップをテーブルに置く」香川ヒサさんの一首を思い出したりもした。
水切りの平たい石がこの国の頭に絶えず降ってくる夏
夏を蒸留したような一首だと思った。二句目までの具象が新鮮だ。「この国の頭」の意図がうまく読み取れないのが悔しい。
人類の楽しい走馬灯であるアドベントカレンダーめくるかな
「人類の楽しい走馬灯」という表現に心が惹かれた。十二月の独特の雰囲気や空気感を、一抹の悲しさを添えて伝えてくれる。人は亡くなる時、走馬灯のように人生を思い出すという。それがこの作品のままに、クリスマスを待つような楽しさであってほしい。
光りは屈折する 透明な夢のなかを――田村隆一『緑の思想』
いつの日か子供のころに抜け殻の犬をあつめる遊びをしよう
初句と結句は未来に向けられているのだが、「子供のころ」とは過去だ。このちぐはぐ感を詞書が開いてくれる。夢への道のりを探っているかのような作者がいる。
フードコートのいたるところでそれぞれの警告音がひびく海の日
セルフサービスの飲食スペースで、注文の料理が用意できたことを知らせるブザーの音のことなのだろう。「いたるところで」「それぞれの」と畳み掛けているところに、休日の人混みの中での、作者の居た堪らなさを感じた。
人間はひとりにひとつ持たされた三百円のおやつであった
人間なのだとされている「三百円のおやつ」を持っている「ひとり」も人間なのだろうか。森羅万象や時空世界のような、大いなるイメージも立ち上がってくる。どちらにしても逆説めいた一首だ。
ひとりひとりに生誕日あるかなしさを鎮めるようにゆれる炎は
バースデーケーキに立てられた蝋燭の炎なのだろう。「生誕日」という硬質な言葉選びが、炎のゆらめきの重々しさを映像化させてくれる。
生きているひとはいいねとおもいつつ帰っていったツナマヨネーズ
「ツナマヨネーズ」が誰かの手で冷蔵庫に仕舞われたのだろう。だとすれば、一句目から四句目までが「ツナマヨネーズ」の擬人化に使われているのだが、間延びした感じはない。「おもいつつ」のひらがな表記の力無さが効果的だ。
赤ちゃんは生まれてこない 月面の低重力のスケートリンク
地球上の重力でなければ、受精は完了しないらしい。結句の「スケートリンク」はそんな不安定さの象徴だろうか。月色の冷たさも伝わる。
ナナフシは鳥に食べられ遠くまで卵を運んでもらうだろうか?
調べてみたら、ナナフシの卵はまるで木の実のようだった。ナナフシ自体も小枝に擬態していて、ほんとうに植物そのもののような昆虫だ。この作品では生より死が、捕食者より捕食される者が有力だ。
ペグシルの芯のようなる断片が転がっているかばんの底に
「ペグシル」は鉛筆の先だけをプラスチックの柄にはめ込んだような小さな筆記具だ。作品中の「断片」が何かはわからないが、そういえばそういうことあるある、と納得させられる。倒置法で静かに置かれた結句が、読み手をあざやかに実感へ導いている。
犬がいますのシールがやたら貼りついた玄関だけがある芥子畑
一読、不思議な作品だが、子どもの頃の感覚に戻って鑑賞するとよく解る。「玄関」は畑の囲いにある、ただの入り口なのだろう。「犬」はほんとうにいるのだろうか。たくさん貼られた「シール」の中の一枚なのかもしれない。そう考えると、幼い頃の記憶の錯誤のようなシュール感が楽しめる。
人類は滅びたあとに目が覚めてスクランブルエッグを焼くだろう
「滅びた」ものとは何なのか。例えば、人類の誕生より以前に絶滅した、恐竜や猿人などを基点にして鑑賞しても面白い。滅びたのが人類だとすれば、「スクランブルエッグ」が廃墟と化した都市の惨状を連想させる。「目が覚めて」に生をイメージするのか、死をイメージするのかが醍醐味だ。
さよならの森林浴に行きました 兵隊さんはみんなの誇り
戦争で手をつなぎたいだけなのに手はつなげない 蝋燭がきれい
表題の在り処のようにも思えた二首。表題の通り、戦う意志は感じられない。戦争ではなく、仕事や人間関係など、日々の生活にある不調和を投影しているように感じられた。「森林浴」、「蝋燭」、清らかなモノが有力だ。
妹はいないのだった 妹が冷たい水を渡してくれる
不在という存在。いる人よりもいなくなってしまった人が、人の心を充たすことがある。「わたしには世界の果ての私がコーヒーカップをテーブルに置く」香川ヒサさんの一首を思い出したりもした。
水切りの平たい石がこの国の頭に絶えず降ってくる夏
夏を蒸留したような一首だと思った。二句目までの具象が新鮮だ。「この国の頭」の意図がうまく読み取れないのが悔しい。
人類の楽しい走馬灯であるアドベントカレンダーめくるかな
「人類の楽しい走馬灯」という表現に心が惹かれた。十二月の独特の雰囲気や空気感を、一抹の悲しさを添えて伝えてくれる。人は亡くなる時、走馬灯のように人生を思い出すという。それがこの作品のままに、クリスマスを待つような楽しさであってほしい。
光りは屈折する 透明な夢のなかを――田村隆一『緑の思想』
いつの日か子供のころに抜け殻の犬をあつめる遊びをしよう
初句と結句は未来に向けられているのだが、「子供のころ」とは過去だ。このちぐはぐ感を詞書が開いてくれる。夢への道のりを探っているかのような作者がいる。
フードコートのいたるところでそれぞれの警告音がひびく海の日
セルフサービスの飲食スペースで、注文の料理が用意できたことを知らせるブザーの音のことなのだろう。「いたるところで」「それぞれの」と畳み掛けているところに、休日の人混みの中での、作者の居た堪らなさを感じた。