
北海道の南部、函館市街地を中心に回遊するこれから人気が出ること間違いナシのみなみ北海道おすすめ観光スポットをシリーズでご紹介する「驚き!ときめき!感動∞無限のみなみ北海道おすすめスポット」。
今回はそのPARTⅣ「トラピスト修道院・木古内・知内・福島・松前」のおすすめ観光スポットをご紹介します。

「函館」から津軽海峡沿いを西に向かったエリアにあるのが北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町。
このゾーンは本州との結びつき、幕末の激動と北海道開拓の歴史と伝統を深く感じるスポットですね。
まずは函館市街地から「函館・江差自動車道」を使って函館湾沿いに走ること約40分。

函館山がこんな風に左手に見えます。
まるで島ですね。
そして、海岸線の国道228号線に出て、しばらくして右の山へ入っていったところにあるのが「トラピスト修道院」です。



この修道院は1896年(明治29年)、カトリック教会の中でも厳格な戒律と労働と学習を重んじるフランスのシトー会の中の「トラピスト会」という会派から修道士が来日して、ここに修道院を設立したそうです。

そして、ここからさらに山へ入っていった先にあるのが「ルルドの洞窟」です。
けっこうきついこう配の坂を上ります。

「ルルドの洞窟」とはフランス南部にあるルルドという村の奇跡、聖母マリア様が現れ、難病を治す泉が湧いたとして今では巡礼地となっている洞窟のことで、泉は湧いていませんが、ここに再現されています。

その洞窟の右にあるほこらに立つマリア様の像はやさしさに溢れていますね。

展望台から望む津軽海峡にはこのように函館市街地と函館山をご覧いただけます。

そして、「ルルドの洞窟」から修道院まで戻ってきたら、売店で敷地内の牧場と食品加工場で作られたバターを使用したソフトクリームでちょっと休憩されてみてはいかがでしょう。
上品な甘さとコクで美味しいですね、スプーン代わりに名物の「トラピストクッキー」が付いています。
あらためてのご説明になりますが、昭和の頃より「函館」のお土産として定番の「トラピストクッキー」と「トラピストバター飴」、そして、本州のスーパーでも販売されている缶に入った「トラピストバター」はここで作られており、所在地は北斗市ですので、厳密に言えば「北斗市」の名物土産。
また、よく勘違いされて函館空港の近くにあるのが「トラピスト修道院」だと思われている方も少なくありませんが、間違いです。
函館空港の近くにあるのは「トラピスチヌ修道院」。
似たような名前だから勘違いされやすいのですが、それもそのはずで同じ「トラピスト会」の修道院だから。
何が違うのかというとこちらの北斗市にある「トラピスト修道院」は男性のみの修道院で、函館市の「トラピスチヌ修道院」は女性のみの修道院なんです。
さて、そういう幕末にいち早く開港した函館ならではの西洋文化の歴史と伝統に触れたあとには海岸線を西に向かい隣町の木古内町に入り、道内における北海道新幹線の終点一つ手前の駅であり、「いさりび鉄道」の駅でもある「木古内駅」の駅前にある道の駅「みそぎの郷 きこない」さんに立ち寄り。


ここでは地元地域の特産品やお土産品の販売の他、山形県とゆかりがあることから鶴岡市の有名なイタリアンレストラン「アル・ケッチャーノ」の奥田シェフ監修のレストランも併設されており、お食事も楽しめます。

ここ木古内町は漁業と林業が盛んな町ですが、それを開拓したのは、よく藤沢周平さんの小説、映画にも出てきますが山形県にあった「庄内藩」から幕末に移住してきた藩士家族。
それゆえ地区名には「鶴岡」など山形県に由来する地名があります。

木古内駅の近くにあるこちらの郷土資料館「いかりん館」さんでは、その開拓の歴史資料や、国鉄時代の鉄道関連資料の他、縄文遺跡から出土した土器などが展示されています。


こちらに収蔵展示されてる縄文土器って割とPOPなデザインが多いんですよね。
また木古内では、毎年1月に豊漁・豊作を願う地元の神社のお祭りでご神体をふんどし一丁の若い男性が抱いて海に入り清める「寒中みそぎ祭り」も沢山の観光客を呼んでいます。
そして、また海岸線を走り隣町に入るとそこは知内町。

ここは知る人ぞ知る演歌の大御所「北島三郎」さんの故郷。
地元の特産品を販売しているこちらの道の駅「しりうち」さんでは御大「北島三郎」さんの曲が流れています。
そして、ここは北海道新幹線の線路脇ということもあり、もう撮り鉄の方々には有名な撮影ポイントになっていますが、新幹線の展望塔が建っています。

エレベーター付きです。

これは「新函館北斗駅」方面のアングル。
緑豊かな自然の中を快走するH5系、E5系が撮れますよ。

そして、近年では知内町の「カキ」「ニラ」が特産品として有名になってきていますが、「ワカメ」も美味しいんですよ。

繊維がしっかりしていて多少煮ても溶けにくく旨味も強く、美味しいです。
さあ、知内町をあとに海岸線からちょっと峠道をまわってまた海岸線に出るとそこは福島町。

ここは大相撲ゆかりの地。
二人の大横綱を輩出し、その記念館が建てられています。

こちらがそのひとり、第41代横綱・千代の山雅信さん。

そして、その千代の山関が引退後、九重を襲名し、独立した九重部屋から横綱になったのが、現在はNHKの大相撲中継の解説でもお馴染みの北の富士勝昭さんで、その次に横綱になったのが〝ウルフ〟の愛称で親しまれたこちらの第58代横綱・千代の富士貢さんです。
お二人とも若くして病魔に侵され、この世を去りましたが、こちらの「横綱千代の山・千代の富士記念館」(冬期休館)ではお二人にゆかりの品々を見ることが出来ます。


そして、こちらの記念館の中にはけいこ場が再現されているんですが、ただ見学用に再現されたわけではないんです。

先代の九重親方(千代の富士関)の時代から、毎年、九重部屋が合宿で訪れて、そのけいこ場として実際に使用しているんです。
そして、こちらの稽古場の土俵には一般の見学者も裸足になれば入ることが出来て記念撮影することも出来るんです。
なかなかそういう経験は出来ないですよね。
ただし、大相撲の古くからのしきたりにより、女性の方にはご遠慮いただいているそうです。
現在、大相撲では千代の富士関が育てた関取が何人も活躍していますが、みなこの土俵でけいこをして力をつけていったんですね。
そして、この記念館の横の小高い山を上って行ったところにあるのが地元の氏神様である「福島大神宮」。

その参道の階段の横にある坂道を上っていくとそこには土俵があるんです。

ここでは「わんぱく相撲」や「おんな相撲」など年に数回、大会が開かれています。

そして、参道を上っていくとこちらがお社です。
お参りのあと帰り道の視界に広がるのはこの津軽海峡を望む入り江の景色。

この海岸線の先は船でしか見られない海面が神秘的なブルーになる「青の洞窟」がある「岩部海岸」。
来年(2019年初夏)にはクルーズ船の就航が予定されています。詳しくはこちら

他にも福島町には青函トンネルに関する資料が展示されている「青函トンネル記念館」があります。
そして、福島町からさらに西へ進むと、そこはもう津軽海峡と日本海とのミックスゾーンの城下町・松前町です。
ここは江戸時代に蝦夷(北海道)を統治していた松前藩の本拠地で松前城があり、当時は城下町として栄え、本州との往来をしていた貿易船「北前船」の貿易港でもありました。

松前というと松前城がある「松前公園」の桜が見事で、5月に行われる桜まつりには大勢の花見客が訪れます。
そして、その松前公園のそばに作られているのが「松前藩屋敷」(冬期休園)というテーマゾーン。
ここは時代劇の撮影が出来るくらいの再現性です。


まるでタイムスリップしたかのようです。
そして、道の駅「北前船 松前」がある海岸線からは美しい日本海が見られます。

そこには沖に停泊する北前船との荷物の往来をしていたはしけ船の波止場が今でも残っています。

北海道からは昆布など豊かな海産物、本州からは織物などが荷車に積まれてこの石畳をお往復していたでしょうか。
歴史ロマンを感じずにはいられません。
さて、ここから先は日本海に面したみなみ北海道西海岸を北上していくことになりますが、それは次回、PARTⅤにてご紹介してまいりたいと思います。
みなみ北海道巡りは当社タクシーが詳しくご案内させていただきます。
シリーズ「驚き!ときめき!感動∞無限のみなみ北海道おすすめスポット」
PARTⅠ「戸井・恵山・椴法華地区」はこちら
PARTⅡ「南茅部地区・鹿部町」はこちら
PARTⅢ「七飯町・大沼国定公園」はこちら
PARTⅤ「上ノ国・江差・厚沢部・乙部」はこちら
【道南ハイヤー(smile Taxi)】
〈タクシーのご用命は〉TEL:0138-46-1100
〈観光貸切のご予約は〉TEL:0138-47-0005
オフィシャルサイト:http://www.smile-taxi.com/










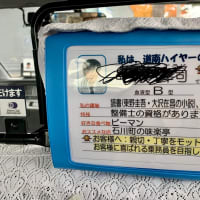









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます