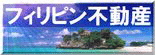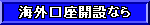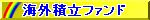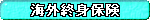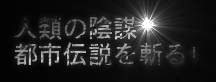ゴールデンウィークの真っ只中、豚インフルエンザのニュースに隠れるように、聞き捨てならないニュースが発表された。
ついに公的年金制度が破綻することを国が認めてしまった!! 
これまで、「年金は絶対になくならない」とか「未納者が増えても破綻しない」とか、年金システムを老後資金の安全パイと論じてきた多くの論文を見てきたが、この事実を聞いても「絶対もらえる」と言えるのだろうか。
新聞各社は揃って記事を発表しているが、内容は全て同じ。下記に一部の記事を載せてみる。
********************************
厚生年金積立金、31年度に枯渇
過去10年の経済指標で試算
5月1日23時20分配信 時事通信
厚生労働省は1日、物価上昇率などの経済指標が過去10年の平均値で推移した場合、2031年度に厚生年金の積立金が枯渇するとの試算をまとめた。民主党の要求を受け作成した。
同省が2月に公表した公的年金の財政検証では、物価上昇率1.0%、賃金上昇率2.5%、運用利回り4.1%などを前提に最も可能性が高いとする「基本ケース」を試算。 現役世代の平均手取り収入に対する厚生年金の給付水準(所得代替率)は、将来にわたり政府保証の50%台を維持できるとした。
しかし、民主党は「試算の前提が甘い」と批判し、過去10年と20年の物価上昇率、賃金上昇率、運用利回りの平均値を用い再計算するよう求めていた。
厚労省によると、過去10年の平均値である
物価上昇率マイナス0.2%
賃金上昇率マイナス0.7%
運用利回り1.5%を前提とした場合
09年度末に約144兆円ある厚生年金の積立金は31年度に枯渇し、実質的に年金制度は破綻(はたん)するとしている。
過去20年を見た場合は、50年度に国民年金の積立金が底を突く見通しだ。
*******************************  個人年金の作り方はこちら
個人年金の作り方はこちら
この試算は、物価上昇率がマイナス、運用利回りが年利1.5%プラスしていった場合の計算である。
人口が減少する日本経済にとって、労働者賃金が毎年上がり続けることは、間違っても望めない。
ならば、物価が上昇し、運用利回りも低下または減少した場合はどうなるのか。
物価は、日本だけを見ていても今後の予想はつけ難いと思う。現に、高級食材マグロは中国に買い占められ品薄状態ではないか。
衰退する日本経済を尻目に、内需拡大に大きくテコ入れする中国経済は、消費大国、経済大国の道を驀進中である。中国以外のアジアも同様、世界不況とは言え、人口増加と共にバリバリ経済成長を続けているのである。
日本はこれまで大幅な貿易黒字を計上していたが、それもこの不況でマイナスに。そして気付くのである。
日本の自給率の低さが物価に大きく跳ね返ることを。
日本人が欲しがる物は、成長著しいアジア諸国も欲しいのだ。当然、全力で買い占めてくる。その競争力に日本が勝ち残れないとどうなるか。
今まで想像したことのない物不足の日本になるのではないか。
または、物はあっても高額だから、金持ちは問題ないが貧乏人は奪い合いが起こってしまうのではないか。いよいよ日本のスラム化が本格的に始まりそうだ。 個人年金の作り方はこちら
個人年金の作り方はこちら
そして、運用の利回りがプラス試算であることも疑問がある。
ファイナンシャルリテラシーの最低な日本なのである。2007年に発覚したサブプライム問題から3年目。あまりニュースに出ないが、この間、年金原資がどれ程目減りしているのか想像するとマジで恐ろしい。
今後も、アメリカの赤字国債を買わされ続けるのであろうが、本気で利益を出せるポートフォリオマネージャーは日本にはいないのか。
国民の年金原資の管理すらできない日本である。真面目な国民性だったはずなのに、役所は仕事をすればするほど金のかかるミスをする。
国民の年金記録を確認するため送られた「ねんきん定期便」。既に3万人を超えるミスが発覚している。全く持って税金の無駄遣いだ。呆れて物が言えない・・・。
ああ~、本当に日本の経済事情を考えるとイライラすることが多い。殺人事件や政治家の揚足取りのニュースは程々に、もっと経済を考えるニュースを流さないと世界に置いて行かれるんじゃないかな。
とにかく、今の年金制度は崩壊することがやっと国民に知らされた。これからどうすればいいのか。
国や地方に文句を言っても救ってくれない。頼りは自分自身だ。死ぬまで働くか、自分で年金を作るしかないのである。
私にとっては、今頃こんなタイミングで年金破綻のニュースを流すのかと思うが、「年金安心」と考えていた人にとっては、かなりショックかな。
個人年金の効果的な作り方をご案内してますので参考にして欲しい。 個人年金の作り方はこちら
個人年金の作り方はこちら
要するに、日本人がリスクとリターンを許容して資産を守り殖やすしか道はないのです。郵便局に預ければいいなんて時代は、何世代も昔の話・・・。変化しないと生き残れない時代になっているのである。

最新の画像[もっと見る]