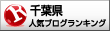後から炉を切ったらしく畳の寸法はバラバラ、困った事に御点前の畳が一番小さい寸法で目乗りにもなっていない状態でした。
中物や炉畳も目乗りではなく床の間は一分以上持ち上がり、寄せもバラバラ、炉の電気コードは畳の下に入れてあり、敷き合わせで躓く位の段差、何だこの茶室は・・・と思ったほどでした。
関東間のこの建物、御点前畳が七分小~八分小で反対側の客畳の通しが五分大~七分大
、中物が2枚とも二分大巾、炉を切っていなくてもなんでこの割付???と思う寸法。
炉の蓋も二分以上寸法が小さく、敷いてある畳が一寸八分厚に対し、二寸の厚みがありました(呆)
寸法を直しながら目乗りに変えていきます。



畳の下ではなく、加工して板の下にコードを通しましたので段差はありません。

もちろん御点前畳も炉畳も中物も、この部屋全体を縁巾も工夫しながら総目乗りとしました。

色々手間が鰍ゥりましたが、自分なりに気に入った仕事が出来ました。

夕方、静まり返った休日の商家町並み