指導実習について
1 基本の重要性、対象に応じた指導内容と指導技術
入門したての子どもは、たいてい「強くなりたい」という意志を持って道場に入ってくる。多くが黒帯をとることが目的である。そのような子どたちに、基本の必要性を感じさせることは大切である。なぜなら、空手の上達を考えた場合、一番重要でおろそかにしてはいけないのが基本だからである。しかし、子どもが一番つまらないと感じるのも基本である。だから、基本を教えながら、「なぜ、それが大切であるかを言葉で教える。」ことも大切である。基本をやりながら、基本の大切さや空手道に対する構えをも指導するのである。正しい動作や動きを身につけたものは上達も早いものである。
初級者への指導
(1) まず礼法から教える。(立礼、座礼)
(2) 立ち方を教える。(結び、サンチン、平行、前屈、後屈、四股、猫足、閉そく等)
(3) 立ち方の移動と変化を行う。(同じ立ち方での移動、立ち方の変化)
(4) 受け、突き、蹴りを順に指導する。
(5) (一通りできるようになったところで)基本形の運足のみ行う。
(6) 受け突きを入れた動作の順番を区切っておぼえさせる。
(7) 通しで行う。なお、この時には、以下のようなことを加味して行う。
・技の意味を理解させる。
順序をおぼえたら、どんな技に対してその動作を行っているのか、つまり形の中で使われている技の意味を理解しなければならない。形技能は、基本的に1人で行うものであるが、相手をおいて、実際の技の攻防をさせながら指導すると技の意味の理解がしやすい。
・やり方に変化をつける。
形を習熟させるためには、繰り返して練習することが求められる。しかし、単に繰り返すだけでは苦しく、鍛練的要素が強くなりすぎる。また、精神的にもやらされている状態になってしまう。
① 部分を取り出して行う。
② 立ちの方位を変え、形の演武をする。
③ 普段行っている形を、逆方向から演武する。→左右のバランスを鍛える。
④ 形の演武を目をつむったまま平行立ちで行う。→集中力を養う。
2 空手道の安全対策
生涯体育の観点からも、けがすることなく競技を続けるように指導をする。練習前後のストレッチは確実に行う。練習内容によっては、過度な疲労や障害にまでつながることもあるので、指導者の立場でそれらをきちんと予見できるようにする。とりわけ、対人練習において、打撲や骨折が起こりやすい。きちんと技をコントロールできる技術と精神力を身につけた上で競技させることが重要である。また、打撃の部位によっては、命に関わるので稽古の中でそれをきちんと指導しておく必要がある。また、近年AEDが設置してある場所も増えてはいるが、私の道場にはまだおいていないので、早く設置するように働きかけたい。
本年度、水泳指導のために消防署主催の救急救命処置方講座を受講した。そこで、心肺蘇生法やAEDの使用法を実践で学んだ。これを、空手道においても生かせるようにしたい。また、必要な知識として、応急処置時に必要なRICEも大切である。RICE処置を損傷直後に適切に行うことで、治癒を早めることができる。
Rest(安静)-スポーツ活動の停止
受傷直後から体内で痛めた部位の修復作業が始まる。しかし、患部を安静させずに運動を続けることでその作業の開始が遅れる。その遅れが結果的に完治を遅らせリハビリテーションに費やす時間を長引かせることになるので、受傷後は安静にすることが大切である。
Ice(アイシング)-患部の冷却
冷やすことで痛みを減少させることができ、また血管を収縮されることによって腫れや炎症をコントロールすることができる。
Compression(圧迫)-患部の圧迫
適度な圧迫を患部に与えることで腫れや炎症をコントロールすることができる。
Elevation(挙上)-患部の挙上
心臓より高い位置に挙上をすることで重力を利用し腫れや炎症をコントロールすることができる。













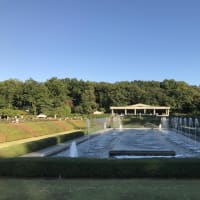




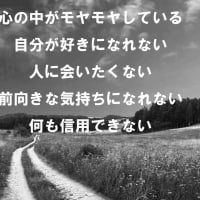



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます