おはようございます。
必ず行政書士と司法書士事務所を開設する千葉県茂原市茂原市在住の山本 徹です。
さて、昨晩、大阪府在住の父方の叔母(86歳)の夫の1周忌(昨年2月没)があり、このコロナの環境下、家族だけで執り行うとのことでしたので、供物を送らせて頂きました。そのお礼の連絡がありました。
約1時間ほど、叔母自身や二人の娘(私の従妹)含め、聞き役を務めていました。その話題の1つに「主人が亡くなって、お金が入用なのに、長い間頼りにしていた最寄りの銀行の故人の名義の銀行口座がいきなりロックされ、お金が引き出せなくなり、困ったことやその銀行の担当者を頼りにしていたのに腹が立った。」等のコメントがありました。
実は、そのような際、遺産分割前に預貯金の一部をおろすことができるようになりました。それが、昨年4月から施工となった民法909条の2です。(2か月、早ければ、叔母も、助かったのですが・・・)
909条の2は「 各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権 額の3分の1に第 900条及び第 901条の規定により算定した当該共同相続人の相続 分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費,平均的な葬式の費用の額その他の事情 を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)につい ては,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行 使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを 取得したものとみなす。 」と規定されています。
要約すれば、相続開始時の預貯金債権額×1/3の払戻しを求める共同相続人の法定相続分権利行使できる預貯金債権の割合および額は、個々の預貯金債権ごとに判断します。その割合による制限のほか,1つの金融機関に払戻しを請求できる金額についても法務省令で定める上限額による制限があるので、注意してください。(現在の省令では、上限額150万円だと思いますが、正確な金額は、銀行にご確認願います。)
PS:私の父が3年半前に亡くなった際、相続人である母(金沢在住)、弟(大阪府在住)と私の3人で、四十九日のタイミングで、父名義の自宅の土地家屋と銀行の預貯金を母名義にするために金沢法務局や銀行に手続きを自分たちでやったことを思い出していました。


















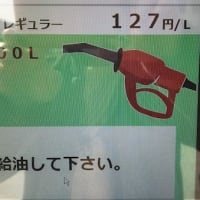

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます