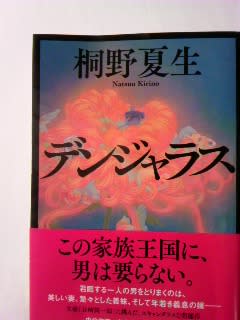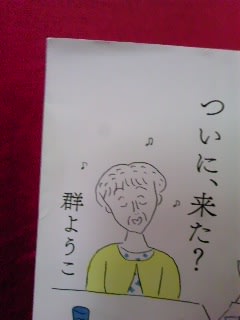11月13日(金)
「デンジャラス」桐野夏生(中央公論新社 )を読了。
文化勲章をもらった谷崎潤一郎が4人の女に囲まれてご満悦な場面から始まります。
語り手は、谷崎の義妹(3番目の妻の妹)で、この人選がまずすごくいい!
この義妹目線で一族の人間模様のあれやこれやが語られ、
その奥に君臨する谷崎の姿はちらちらとしか見えてこない気がします。
ところが読後、作品全体を見渡すと、
谷崎潤一郎という男の、いや、「作家」という生き物のおぞましさでびっしり埋まってたんだこの話!という戦慄!!
そこから1ミリも逃げたり目をそらしたりせず格闘し描き切る桐野夏生が凄まじいです。
「デンジャラス」桐野夏生(中央公論新社 )を読了。
文化勲章をもらった谷崎潤一郎が4人の女に囲まれてご満悦な場面から始まります。
語り手は、谷崎の義妹(3番目の妻の妹)で、この人選がまずすごくいい!
この義妹目線で一族の人間模様のあれやこれやが語られ、
その奥に君臨する谷崎の姿はちらちらとしか見えてこない気がします。
ところが読後、作品全体を見渡すと、
谷崎潤一郎という男の、いや、「作家」という生き物のおぞましさでびっしり埋まってたんだこの話!という戦慄!!
そこから1ミリも逃げたり目をそらしたりせず格闘し描き切る桐野夏生が凄まじいです。
9月25日(金)
「丸の内魔法少女ミラクリーナ」村田沙耶香(角川書店 2020年)を読了。
表題作は、小学生のときの「私は魔法少女ミラクリーナである」という設定を守り続けて生きる36歳の話で、ほか3作が収められた短編集です。
村田沙耶香は、きっと「性」とか「感情」とか、そういう、人間の核の部分にあるドゥルッとしたもの(生卵の白身みたいな)が気になって仕方ないんですね。
それを外に引きずり出して格闘してみたり、中に溜めたまま撫でたり擦ったり、そんな作品集だと思いました。
最後の「変容」という作品は、
親の介護で2年間社会と接点が持てなかった女性が久しぶりにアルバイトを始めたら、
世間では「怒り」を持たない人間がトレンドになっていた、という話です。
怒りは6秒で治まるとかいう「アンガーマネジメント」なんて言葉がありますが、そっちに話がいくと思いきや、例えば「今年の流行色」みたいに「性格の流行」を誰かが決めている、という展開だったのが意外でした。
ここに出てくる「エクスタシー五十川」という50代女性が本当におもしろかった。
コントとして上演したらいいかもしれないです。
五十川さんは松尾嘉代みたいな人がいい!
草食動物の群れの中でも燦然と輝く肉食恐竜みたいな。
「丸の内魔法少女ミラクリーナ」村田沙耶香(角川書店 2020年)を読了。
表題作は、小学生のときの「私は魔法少女ミラクリーナである」という設定を守り続けて生きる36歳の話で、ほか3作が収められた短編集です。
村田沙耶香は、きっと「性」とか「感情」とか、そういう、人間の核の部分にあるドゥルッとしたもの(生卵の白身みたいな)が気になって仕方ないんですね。
それを外に引きずり出して格闘してみたり、中に溜めたまま撫でたり擦ったり、そんな作品集だと思いました。
最後の「変容」という作品は、
親の介護で2年間社会と接点が持てなかった女性が久しぶりにアルバイトを始めたら、
世間では「怒り」を持たない人間がトレンドになっていた、という話です。
怒りは6秒で治まるとかいう「アンガーマネジメント」なんて言葉がありますが、そっちに話がいくと思いきや、例えば「今年の流行色」みたいに「性格の流行」を誰かが決めている、という展開だったのが意外でした。
ここに出てくる「エクスタシー五十川」という50代女性が本当におもしろかった。
コントとして上演したらいいかもしれないです。
五十川さんは松尾嘉代みたいな人がいい!
草食動物の群れの中でも燦然と輝く肉食恐竜みたいな。
9月11日(金)
「告白」町田康(中公文庫 2008年)を読了。
自分の中の思考が的確な言葉に結びつかず、発する言葉はいつも内面とズレているので他人には決して届かない。
みんなが自然にできていることが何故か自分には全くできず、理解もできない。
だから理解されることもない。
そんな苦痛を抱えて生きた主人公・城戸熊太郎の一代記。
モチーフとなった河内音頭「河内十人斬り」をYouTubeで聞いてみたんですが、
この城戸熊太郎を「思考が言葉として外に出せない人物」「一度も本当のことを言えたことがない人物」と設定したところに町田康のすごさがあるなあと思いました。
熊太郎の脳みそは頭蓋骨という牢に閉じ込められて出口を失っています。
そこに潜り込み、息つく間もなく言葉を与え続ける作家の作業。
想像しただけで頭がぐわんぐわんしてきます。
土石流みたいな言葉の重量とスピードに何度も押し流されそうになり、
あ、ちょっと待って!となってページを戻してじっくり読み直す、みたいなことを繰返しながら読み終わりました。
そのくらいの疾走感。しかも高濃度。
町田康は、これを書きながらよくも正気でいられたなあ、とため息が出ます。
すごい胆力というか体力というか執念というか……。むー、壮絶だ……。
「告白」町田康(中公文庫 2008年)を読了。
自分の中の思考が的確な言葉に結びつかず、発する言葉はいつも内面とズレているので他人には決して届かない。
みんなが自然にできていることが何故か自分には全くできず、理解もできない。
だから理解されることもない。
そんな苦痛を抱えて生きた主人公・城戸熊太郎の一代記。
モチーフとなった河内音頭「河内十人斬り」をYouTubeで聞いてみたんですが、
この城戸熊太郎を「思考が言葉として外に出せない人物」「一度も本当のことを言えたことがない人物」と設定したところに町田康のすごさがあるなあと思いました。
熊太郎の脳みそは頭蓋骨という牢に閉じ込められて出口を失っています。
そこに潜り込み、息つく間もなく言葉を与え続ける作家の作業。
想像しただけで頭がぐわんぐわんしてきます。
土石流みたいな言葉の重量とスピードに何度も押し流されそうになり、
あ、ちょっと待って!となってページを戻してじっくり読み直す、みたいなことを繰返しながら読み終わりました。
そのくらいの疾走感。しかも高濃度。
町田康は、これを書きながらよくも正気でいられたなあ、とため息が出ます。
すごい胆力というか体力というか執念というか……。むー、壮絶だ……。
8月29日(土)
「沖で待つ」絲山秋子(文春文庫 2009年)を読了。
短編集で「勤労感謝の日」「沖で待つ」「みなみのしまのぶんたろう」の3つが収録されています。
真ん中の「沖」は芥川賞作品でたしかにおもしろい。
主人公の女性がいいかんじに薄汚れているのもい。
小谷野敦が褒めるのも納得。文句なし。
なのにふと、候補になりながら惜しくも逃した何人かの作家を思い出してしまいました。
もちろん絲山秋子は筆力も洞察力もあって受賞は当然だと思うけど、
例えば若合春侑や大森兄弟みたいな作家が負けてるとはどうしても思えない。
そして、そういう作家はけっこういますよね。
運とかタイミングとか言われちゃうと、そうかもなあ……とも思うんですが、
もし、受賞してたら今でも彼らの新作がばんばん(じゃなくてもいいけど)出てたのかなあと想像してしまうんです。
文学賞というもの自体にはそんなに価値を感じないけど、
やっぱり受賞すれば作家の寿命は延びますよね。
だから、今村夏子が受賞したときは、「おお!これでこれからも今村作品が読めるぞ、うひひ」と喜んだものです。
そういう意味で、賞をとるって大きいことですね、作家にとってはもちろん、われわれ読者にとっても。
「沖で待つ」絲山秋子(文春文庫 2009年)を読了。
短編集で「勤労感謝の日」「沖で待つ」「みなみのしまのぶんたろう」の3つが収録されています。
真ん中の「沖」は芥川賞作品でたしかにおもしろい。
主人公の女性がいいかんじに薄汚れているのもい。
小谷野敦が褒めるのも納得。文句なし。
なのにふと、候補になりながら惜しくも逃した何人かの作家を思い出してしまいました。
もちろん絲山秋子は筆力も洞察力もあって受賞は当然だと思うけど、
例えば若合春侑や大森兄弟みたいな作家が負けてるとはどうしても思えない。
そして、そういう作家はけっこういますよね。
運とかタイミングとか言われちゃうと、そうかもなあ……とも思うんですが、
もし、受賞してたら今でも彼らの新作がばんばん(じゃなくてもいいけど)出てたのかなあと想像してしまうんです。
文学賞というもの自体にはそんなに価値を感じないけど、
やっぱり受賞すれば作家の寿命は延びますよね。
だから、今村夏子が受賞したときは、「おお!これでこれからも今村作品が読めるぞ、うひひ」と喜んだものです。
そういう意味で、賞をとるって大きいことですね、作家にとってはもちろん、われわれ読者にとっても。
8月7日(金)
津村記久子の短編集「サキの忘れ物」(新潮社 2020年)を読了。
今までにもいくつか短編集が出ていますが、
一番バラエティ豊かというか、色とりどり。
でも、バラバラかというとそうではない。
なんというか、偉そうに言っちゃうと、
津村記久子、脂がのり始めたかんじがします。
惚れ直します。
これまであまり感じなかった(たぶん表に出てなかった)「自信」がみなぎって、
フリーハンドを得たような、なんでも書ける!って宣言したような、そんな雰囲気です。
これは、成長とか幅を広げたとか以上に「深化」であるところがさすがです。
とくに、冒頭の表題作と最後の作品には、本当に微かな、小さな声をしっかり拾う津村記久子作品の醍醐味が濃くあって、
何度も「読み終わりたくないよー」と思いました。
デビュー作から一貫して、小さな人間を誠実にコツコツ描いていて、でもそこには必ず「暴力」があるんですよね。
彼らは様々な種類の暴力にさらされ、踏みにじられる。
今までは、その当事者目線で真っ向から描くものが多かったけど、
この最新作には、そうした人を見守る作家の「慈悲の目」みたいなものを感じます。
それから、表紙がまたいいんです。
ひとつひとつの話を読むたびに、そこに描かれた絵の意味がわかるという素敵な仕掛けです。
津村記久子の短編集「サキの忘れ物」(新潮社 2020年)を読了。
今までにもいくつか短編集が出ていますが、
一番バラエティ豊かというか、色とりどり。
でも、バラバラかというとそうではない。
なんというか、偉そうに言っちゃうと、
津村記久子、脂がのり始めたかんじがします。
惚れ直します。
これまであまり感じなかった(たぶん表に出てなかった)「自信」がみなぎって、
フリーハンドを得たような、なんでも書ける!って宣言したような、そんな雰囲気です。
これは、成長とか幅を広げたとか以上に「深化」であるところがさすがです。
とくに、冒頭の表題作と最後の作品には、本当に微かな、小さな声をしっかり拾う津村記久子作品の醍醐味が濃くあって、
何度も「読み終わりたくないよー」と思いました。
デビュー作から一貫して、小さな人間を誠実にコツコツ描いていて、でもそこには必ず「暴力」があるんですよね。
彼らは様々な種類の暴力にさらされ、踏みにじられる。
今までは、その当事者目線で真っ向から描くものが多かったけど、
この最新作には、そうした人を見守る作家の「慈悲の目」みたいなものを感じます。
それから、表紙がまたいいんです。
ひとつひとつの話を読むたびに、そこに描かれた絵の意味がわかるという素敵な仕掛けです。
8月1日(土)
「感応連鎖」朝倉かすみ(講談社 2010年)を読了。
母親に「セシルちゃん」と呼ばれる重量級の女子中学生・節子の話から、
彼女の担任の先生の奥さん、
同級生の絵里香、
同級生の由季子、と螺旋状に展開して、
最後、「そこに着地するか!」という驚きと喜び。
ものすごく緻密なモザイク画のような完成度です。
中でも、筒井康隆「家族八景」のリアル版みたいな人物(たぶん彼女が主人公)が出てきて、
その怒りと悲哀が印象的です。
ひとつひとつは丁寧に描かれていて説得力があり、
さらに遠くから全体像を見渡すと大きな仕掛けがある作品。
大満足でした。
「感応連鎖」朝倉かすみ(講談社 2010年)を読了。
母親に「セシルちゃん」と呼ばれる重量級の女子中学生・節子の話から、
彼女の担任の先生の奥さん、
同級生の絵里香、
同級生の由季子、と螺旋状に展開して、
最後、「そこに着地するか!」という驚きと喜び。
ものすごく緻密なモザイク画のような完成度です。
中でも、筒井康隆「家族八景」のリアル版みたいな人物(たぶん彼女が主人公)が出てきて、
その怒りと悲哀が印象的です。
ひとつひとつは丁寧に描かれていて説得力があり、
さらに遠くから全体像を見渡すと大きな仕掛けがある作品。
大満足でした。
7月26日(日)
「タイガー理髪店心中」小暮夕紀子(朝日新聞出版 2020年)を読了。
表題作ともうひとつ(「残暑のゆくえ」)が収められていて、
前者はおじいさん、後者はおばあさん(といっても70代半ばだけど)目線の話。
どちらも、とぼけた味わいがあって、近所にいたらたまには立ち話の相手をしてもおもしろそうな年寄りなのに、
(あ、おじいさんはそうでもないか、町の歴史を教わりに来た子供に地球誕生の演説から始める人だから)
その皮膚をぺろっとはがした中に潜む恐怖との落差がすごいです。
笑ったり怯えたりしながら読んだので、へろへろになりました。
ちょっと吉田知子のような雰囲気もあるし、「タイガー」の方は「夢十夜」の「こんな晩だったな」っていうあれを思い出しました。
今年はまだ5ヶ月残ってるけど、今年いちばん面白かった本になる気がします。
「タイガー理髪店心中」小暮夕紀子(朝日新聞出版 2020年)を読了。
表題作ともうひとつ(「残暑のゆくえ」)が収められていて、
前者はおじいさん、後者はおばあさん(といっても70代半ばだけど)目線の話。
どちらも、とぼけた味わいがあって、近所にいたらたまには立ち話の相手をしてもおもしろそうな年寄りなのに、
(あ、おじいさんはそうでもないか、町の歴史を教わりに来た子供に地球誕生の演説から始める人だから)
その皮膚をぺろっとはがした中に潜む恐怖との落差がすごいです。
笑ったり怯えたりしながら読んだので、へろへろになりました。
ちょっと吉田知子のような雰囲気もあるし、「タイガー」の方は「夢十夜」の「こんな晩だったな」っていうあれを思い出しました。
今年はまだ5ヶ月残ってるけど、今年いちばん面白かった本になる気がします。
7月26日(日)
「ついに、来た?」群ようこ(幻冬舎文庫 2020年)を読了。
認知症がテーマの短編小説集。
人物間のやりとりや物言いが、橋田壽賀子ドラマを何倍もおもしろくしたかんじ。
特に問題も解決せず、認知症や介護の深刻な(あるいは絶望的な)場面は巧みに避けられていて、
はあ、やれやれ、みたいな調子で描かれてるところが、かえって気楽に読めていいかもしれません。
群ようこ作品って、エッセイも小説も、あんまり負担がかからないからついつい読んでしまいます。
読書の合間の休憩におすすめです。
「ついに、来た?」群ようこ(幻冬舎文庫 2020年)を読了。
認知症がテーマの短編小説集。
人物間のやりとりや物言いが、橋田壽賀子ドラマを何倍もおもしろくしたかんじ。
特に問題も解決せず、認知症や介護の深刻な(あるいは絶望的な)場面は巧みに避けられていて、
はあ、やれやれ、みたいな調子で描かれてるところが、かえって気楽に読めていいかもしれません。
群ようこ作品って、エッセイも小説も、あんまり負担がかからないからついつい読んでしまいます。
読書の合間の休憩におすすめです。
7月17日(金)
「平場の月」朝倉かすみ(光文社 2018年)を読了。
50代男女の恋愛もの、といえばたしかにそうだけど、それ以上のあれやこれやが胸に迫る作品でした。
これ、終始男性(青砥)側からの視点で描かれていますが、
女性(須藤)側から見たら全然違う話になりますよね、
そして、もしそうだったらちょっとつまらない作品になったんではないかと思うんです。
だから冒頭で須藤がすでに亡くなっていることを明らかにしているとか、この青砥目線で話が展開するしかけとか、とにかくうまい作家です。
実は業の深い、この須藤という女の厄介さを上手にくるんで読者に食わせることに成功しているから。
あと、須藤の妹とか“ウミちゃん”という同級生が出てきますが、ああ、こういう人いるいる!と叫びたくなるリアルな人物造形がすごいです。
ワンカットだけ登場したウミちゃんの娘がとてもいい。
今の50歳くらいって、自分がキラキラ若いときには社会もまだキラキラしていて、いい“思い出”みたいなものを持ちながら、中年になってもその感覚を手放せずにいる一方で、
でも自身の“老い”や“病”からは目を逸らせなくなる時期でもあり、
親の介護やら死やらの向こうに自分の死がちらつき始める、ってかんじなんですかね。
悪い言い方をすれば幼稚、未成熟なまま老いていくのはなんと残酷なことであるか、となんだか不憫に感じたのでした。
自分がまさにそんなお年頃なんですけどね。
「平場の月」朝倉かすみ(光文社 2018年)を読了。
50代男女の恋愛もの、といえばたしかにそうだけど、それ以上のあれやこれやが胸に迫る作品でした。
これ、終始男性(青砥)側からの視点で描かれていますが、
女性(須藤)側から見たら全然違う話になりますよね、
そして、もしそうだったらちょっとつまらない作品になったんではないかと思うんです。
だから冒頭で須藤がすでに亡くなっていることを明らかにしているとか、この青砥目線で話が展開するしかけとか、とにかくうまい作家です。
実は業の深い、この須藤という女の厄介さを上手にくるんで読者に食わせることに成功しているから。
あと、須藤の妹とか“ウミちゃん”という同級生が出てきますが、ああ、こういう人いるいる!と叫びたくなるリアルな人物造形がすごいです。
ワンカットだけ登場したウミちゃんの娘がとてもいい。
今の50歳くらいって、自分がキラキラ若いときには社会もまだキラキラしていて、いい“思い出”みたいなものを持ちながら、中年になってもその感覚を手放せずにいる一方で、
でも自身の“老い”や“病”からは目を逸らせなくなる時期でもあり、
親の介護やら死やらの向こうに自分の死がちらつき始める、ってかんじなんですかね。
悪い言い方をすれば幼稚、未成熟なまま老いていくのはなんと残酷なことであるか、となんだか不憫に感じたのでした。
自分がまさにそんなお年頃なんですけどね。
7月11日(土)
「BUTTER」柚木麻子(新潮文庫 2020年)を読了。
あちこちで絶賛されてるのも納得です。
ざっくりいえば、木嶋佳苗の事件が発覚したとき、多くの女性がよくも悪くも引き付けられた、無視できなかったのはなぜか、という話です。
同時期に、同じように数人の男性を殺害したとされた上田美由紀もなかなかだと思うんですが、世の中の女性は圧倒的に木嶋佳苗が気になって仕方なかった。
その理由を象徴するのが“バター”です。
男女雇用機会均等法という建前が当たり前のように存在する中で大人になった彼女らが、
実は“女は決して男を凌駕してはいけない”という不文律が世間にあることを思い知らされ、もがき苦しむ中で、
“なんておばかさん。こっち側に来ればいろんなものを手に入れられるのに。”と艶然と微笑むのが木嶋(作中では梶井)だったのかも。
週刊誌の女性記者である主人公や〇〇(登場人物)が、拘置所の梶井と面会する場面は映画「羊たちの沈黙」みたいでゾクゾクするし、
ふんだんに登場する食べ物に関する描写のうまいことといったらありません。
たらこスパゲッティが食べたくなります。
「BUTTER」柚木麻子(新潮文庫 2020年)を読了。
あちこちで絶賛されてるのも納得です。
ざっくりいえば、木嶋佳苗の事件が発覚したとき、多くの女性がよくも悪くも引き付けられた、無視できなかったのはなぜか、という話です。
同時期に、同じように数人の男性を殺害したとされた上田美由紀もなかなかだと思うんですが、世の中の女性は圧倒的に木嶋佳苗が気になって仕方なかった。
その理由を象徴するのが“バター”です。
男女雇用機会均等法という建前が当たり前のように存在する中で大人になった彼女らが、
実は“女は決して男を凌駕してはいけない”という不文律が世間にあることを思い知らされ、もがき苦しむ中で、
“なんておばかさん。こっち側に来ればいろんなものを手に入れられるのに。”と艶然と微笑むのが木嶋(作中では梶井)だったのかも。
週刊誌の女性記者である主人公や〇〇(登場人物)が、拘置所の梶井と面会する場面は映画「羊たちの沈黙」みたいでゾクゾクするし、
ふんだんに登場する食べ物に関する描写のうまいことといったらありません。
たらこスパゲッティが食べたくなります。
6月24日(水)
斎藤美奈子の「文芸誤報」で取り上げられていた朝倉かすみのデビュー短編集「肝、焼ける」を読了。
実は以前に「田村はまだか」の最初の方で挫折していた(図書館の期限がきちゃったからだったかも)のと、
同年代の女性の書き手のものにあまり馴染みがない(2、3人を除いて)せいで、縁がなかったんですが、
斎藤美奈子がそこまでいうなら!と思いまして。
そしたらこれがガツンとくる作品群だったですよ。
途中で、これは自分のことか、と思って、数日間読めなくなったりして。
例えばビジネスホテルで、ちょっと飲み物を飲んで着替えて外に出る、くらいの場面でも、これでもかというほど五感が働いて、ぴんぴん立ってくるような表現が休みなしで流れ込んできます。
細かい描写の力と語彙の豊かさとそのチョイスの的確さ、そこに読みやすさは外さないという技術の高さ。
この人の文章なら、なんにも事件が起きなくても読めそうです。
ナイーブさや人間を見る目の繊細さなどは津村記久子と共通している気がするけど、
世代の差なのか性格の違いなのか何なのか、こちらにはしぶとさがありますよね。
そんなわけで今、「田村」に再挑戦するか、他のにするか迷い中。
斎藤美奈子の「文芸誤報」で取り上げられていた朝倉かすみのデビュー短編集「肝、焼ける」を読了。
実は以前に「田村はまだか」の最初の方で挫折していた(図書館の期限がきちゃったからだったかも)のと、
同年代の女性の書き手のものにあまり馴染みがない(2、3人を除いて)せいで、縁がなかったんですが、
斎藤美奈子がそこまでいうなら!と思いまして。
そしたらこれがガツンとくる作品群だったですよ。
途中で、これは自分のことか、と思って、数日間読めなくなったりして。
例えばビジネスホテルで、ちょっと飲み物を飲んで着替えて外に出る、くらいの場面でも、これでもかというほど五感が働いて、ぴんぴん立ってくるような表現が休みなしで流れ込んできます。
細かい描写の力と語彙の豊かさとそのチョイスの的確さ、そこに読みやすさは外さないという技術の高さ。
この人の文章なら、なんにも事件が起きなくても読めそうです。
ナイーブさや人間を見る目の繊細さなどは津村記久子と共通している気がするけど、
世代の差なのか性格の違いなのか何なのか、こちらにはしぶとさがありますよね。
そんなわけで今、「田村」に再挑戦するか、他のにするか迷い中。
6月13日(土)
「こころ」「走れメロス」「銀河鉄道の夜」「藪の中」の新解釈を披露する「文豪たちの怪しい宴」鯨統一郎(創元推理文庫)を読了。
例えば「こころ」の“先生”と“K”は他殺で、
その犯人として「はぁ?」と言われそうな人物が挙げられるんですが、
感心するのは、その論拠の提示の仕方と順番!
“「メロス」夢オチ”説はちょっともやっとしたけど、
そのくらい矛盾だらけの作品だ(だからこそ名作)っていう証拠かもしれないです。
ここで描かれているのは銀河ではなくて○○○だと主張する「銀河鉄道」はむしろ王道な読みのような気がするし、
はっきり犯人を名指しした「藪の中」に至ってはもうこれが正解なんじゃないかと。
すぐ納得しちゃうからな~。
「そっかー」と思わされる快感、みたいな。
鯨統一郎って、「邪馬台国はどこですか」からずーっと腕が落ちないっていうか、いつ行ってもうまい店みたいでいいですよね。
そのわりにたまにしか行かない店ですが。
目次が井上陽水くくりになっているので、どこかで陽水が絡んでくるのかと気にしながら読み進めましたがわからずじまいでした。
「こころ」「走れメロス」「銀河鉄道の夜」「藪の中」の新解釈を披露する「文豪たちの怪しい宴」鯨統一郎(創元推理文庫)を読了。
例えば「こころ」の“先生”と“K”は他殺で、
その犯人として「はぁ?」と言われそうな人物が挙げられるんですが、
感心するのは、その論拠の提示の仕方と順番!
“「メロス」夢オチ”説はちょっともやっとしたけど、
そのくらい矛盾だらけの作品だ(だからこそ名作)っていう証拠かもしれないです。
ここで描かれているのは銀河ではなくて○○○だと主張する「銀河鉄道」はむしろ王道な読みのような気がするし、
はっきり犯人を名指しした「藪の中」に至ってはもうこれが正解なんじゃないかと。
すぐ納得しちゃうからな~。
「そっかー」と思わされる快感、みたいな。
鯨統一郎って、「邪馬台国はどこですか」からずーっと腕が落ちないっていうか、いつ行ってもうまい店みたいでいいですよね。
そのわりにたまにしか行かない店ですが。
目次が井上陽水くくりになっているので、どこかで陽水が絡んでくるのかと気にしながら読み進めましたがわからずじまいでした。