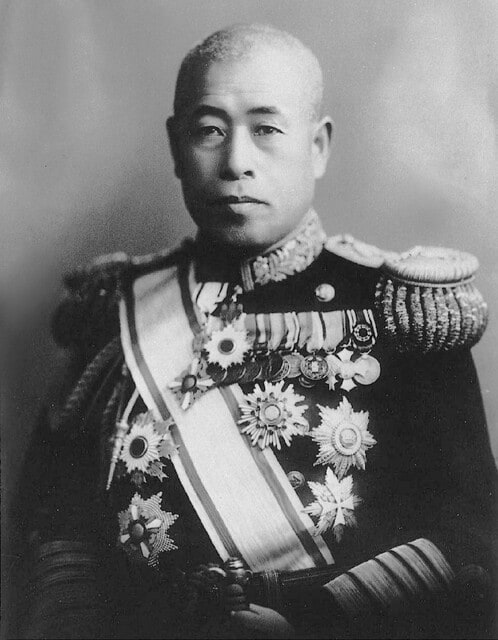「勉強をしろ!」という語気の強い発言は、特に受験勉強の関係でよく見る。
そうでなくても、例えば宿題を理由に口うるさく言う人もいる。
時期を選ばず、「早ければ早いほどいい」「お前以外はみんな努力している」「お前はそんなもんじゃないだろ」とまくしたてる。
見ていて、あまり気分のいいものではない。
それは脅しだ。
圧を用いて行動を強いているに過ぎない。
動機付けの観点からすれば、これらの発言は勉強させるには不十分であるといえる。
勉強をさせたいのであれば、まず動機が必要だ。
つまり、勉強をする理由が必要だ。
それが具体的であればあるほど、効力は増す。複数持っていても罰は当たらない。
「大学に受かるため」であれば、大学でやりたいことやできること、どんなキャンパスライフを送りたいかを言葉にする。知識を得るでも、サークル活動でも、ちやほやされたいでも、何でもいい、具体性が欲しい。
「就活で優位でありたいから」であれば、どの職に就きたいかを言葉にする。その職がどういったことをするのか、実態をおさえておくとよりいいだろう。
「やりたいことをやるため」であれば、やりたいことがどういったものかを言葉にする。今すぐにできるのであれば、やってみて、実感をおさえるのは有効である。
具体的な言葉にする理由は、自分が次に何をすればいいかがわかるから。
闇雲に勉強をするのはつらい。
自分がいま進歩しているのかどうかがわからないのが、一番つらい。
何のために苦労しているのかがわからないのだから、投げ出したくなる。
だから、苦労するに足る理由が必要だ。
理由があれば、目標も進捗もわかる。
目標を達成するために、効率よく勉強することもできる。
だから、動機づけは学業成績に深くかかわるのだ(Froiland & Worrell 2016)。
それと、
その理由は絶対的なものじゃない。
人間は変化していく生き物。都度、やりたいこともできることも変わっていく。
だから、1つの理由にすがるのはあまり好ましくない。
1つの理由に縋らざるを得ない状況は好ましくない、ともいえる。
ちなみに、
「とりあえず大学に入っておく」「世間体的に入っておかないとまずいから」でも構わないが、それらはひどく脆い。
それは脅しに従っているに過ぎず、具体性のかけらもない。
すぐに、何のために苦労しているのかがわからなくなる。
それでも圧をかけてくるようであれば、それは圧をかけてくる相手をめいっぱい恨んでいい。
もうひとつ。
勉強をさせるために効果的な方法がある。
それは周囲からの支援だ。
勉強している人への励ましや理解は有効だ。
「勉強がつらい」という声を否定しない。「勉強が楽しい」と無理に言わせることもしない。その努力に対し下手に茶々を入れることなく、時々励ましの言葉を入れるのが好ましい。差し入れは大歓迎。
支援を惜しまないというのであれば、支援する人自身も勉強するのはどうだろう。
お互いの勉強する姿を見て、焚きつけられる。お互いに励ましあう。お互いのつらさを共有する。究極は、同じ課題を一緒にこなす、そして達成感を味わう。勉強する人のような立ち振る舞いだが、理論上、これが効く。
下手な励ましより、一緒に勉強する友人が何よりの励ましになるのは、こういうことでもある。
もういっそのこと、動機について、勉強する理由について一緒に吟味するのはどうだろう?
なぜ大学に行きたいのか? どうしてこの職に就きたいのか? やりたいことは何で、できることはなにか? これを一緒に、まじめに考える。
「まじめ」というのは、なにもその人の支えになるとかではない。その人が言葉にしたことを決してあしらうことなく聞き入る、ということである。
動機づけは個人で完結するものではない。周囲の影響を多大に受ける。
「勉強をしろ!」と圧的に、どこか無関心を含んだ焚きつけでは不十分。
勉強をする理由を具体的な言葉にするのが先決であり、
それを軽くあしらわず、受け入れてくれる周囲が必要となる。
でもね、たぶんこれをしてくれる人はそういないと思う。
めんどくさいのだ。支援することで得られる利益が明確じゃないからだ。
焚きつけてやった感を味わいたいだけ、というのも大きいのだろう。
参考文献
西村 多久磨, 櫻井 茂男, 中学生における自律的学習動機づけと学業適応との関連, 心理学研究, 2013, 84 巻, 4 号, p. 365-375, 公開日 2013/12/25, Online ISSN 1884-1082, Print ISSN 0021-5236, https://doi.org/10.4992/jjpsy.84.365, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/84/4/84_365/_article/-char/ja,
西村 多久磨, 河村 茂雄, 櫻井 茂男, 自律的な学習動機づけとメタ認知的方略が学業成績を予測するプロセス, 教育心理学研究, 2011, 59 巻, 1 号, p. 77-87, 公開日 2011/09/07, Online ISSN 2186-3075, Print ISSN 0021-5015, https://doi.org/10.5926/jjep.59.77, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/59/1/59_1_77/_article/-char/ja,
Froiland, J.M. and Worrell, F.C. (2016), INTRINSIC MOTIVATION, LEARNING GOALS, ENGAGEMENT, AND ACHIEVEMENT IN A DIVERSE HIGH SCHOOL. Psychol. Schs., 53: 321-336.