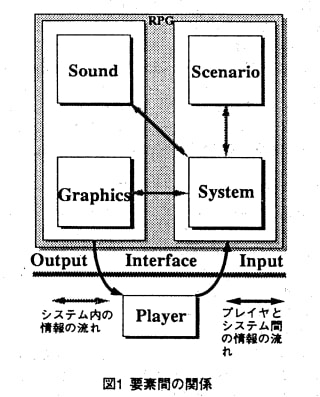問題。
理論上、課金による売り上げが一番伸びるゲームは次のうちどれでしょう。
補足として、すべてのゲームが一定以上のクオリティを保証しているものとする。


1:課金しないとまともに収集できないゲーム(例:ASPHALT9)


2:課金しなくても十分に遊べるけど、課金したほうがもっと楽しめるゲーム(例:原神)


3:売上という概念をゴミ箱に捨て性癖を煮詰めたゲーム(例:ブルーアーカイブ)
正解は…3:売り上げという概念をゴミ箱に捨てただ性癖を煮詰めたゲームでした。
どうでしょう。この問題正解できましたか? できなかったとしてもあなたの回答を監視している公的機関は存在しないはずなので、事前解答を撤回して正解を答えられたことにしても問題ありません。よかったね。
はい、理屈と根拠を説明します。
プレイヤーの課金動機として最も有力なのは購入に関する合理的な根拠と状況によるもの。プレイヤーはそのゲームが個人的に好きだったり、プレイヤーがそのゲームのクオリティを認めていたり、値段設定が適切なものだったりするときに、プレイヤーは課金したくなるそう。
また、独立した要因としてゲームに対する支援が挙げられる。そのゲームが凄くよくできていて、大好きで大好きで仕方なくて、使っちゃいけないお金を使ってでもこのゲームを続けたい、続いてほしいという熱意が課金意欲を掻き立てているという。
なので、特定の描写に異常なまでの拘りを見せているようなゲームや、課金しなくても充分にプレイできるし課金額も負担にならないちょうどいい塩梅なゲームは、結果的にとても儲かるのです。具体例については「ブルアカ セルラン1位」とでも検索してみて。
今回引用した研究を参照にするならば、1:課金しないとまともに収集できないゲームはあまり集金できそうにない。
2:課金しなくても十分に遊べるけど、課金したほうがもっと楽しめるゲームも確かにお金は集まるだろう。課金動機の1つに反復作業の回避や待ち時間の省略などの、不快感解消のためのものもある。が、上記の購入に関する合理的な根拠と状況によるものには劣るという。
もっとも、今回の統制条件として挙げた「一定以上のクオリティを保証している」ことが一番の課金理由だったりするが。
基本的に、Free-to-playなゲームの課金総額の過半数は上位数パーセントのプレイヤーにより積み上げられ、8~9割のプレイヤーは課金しないか微額の課金を行っている。
ここで、ガチャチケット等の課金アイテムをとてもたくさん配ったとしよう。
上位数パーセントのプレイヤーはたとえたくさんのアイテムをもらったところで、課金行為は簡単にはやめないし、増減もほぼないだろう。
8~9割のプレイヤーはシンプルにアイテムがたくさんもらえるためとてもうれしくなる。
また、そうしたお配りは新規プレイヤーの参入機会にもなる。初期費用が保障されているからだ。
この主張は研究ではなく、実際のゲームにて起きた事象を参考にしている。
理論上、性癖をめっちゃ煮詰めたゲームが一番課金される。
そして、課金しないと解消されない不快感を増やすよりも、課金したくなるような設計を組んだほうが、結果的に儲かるのだ。
参考文献
Juho Hamari, Kati Alha, Simo Järvelä, J. Matias Kivikangas, Jonna Koivisto, Janne Paavilainen. Why do players buy in-game content? An empirical study on concrete purchase motivations. Computers in Human Behavior, Volume 68, 2017, Pages 538-546, ISSN 0747-5632, https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.045.