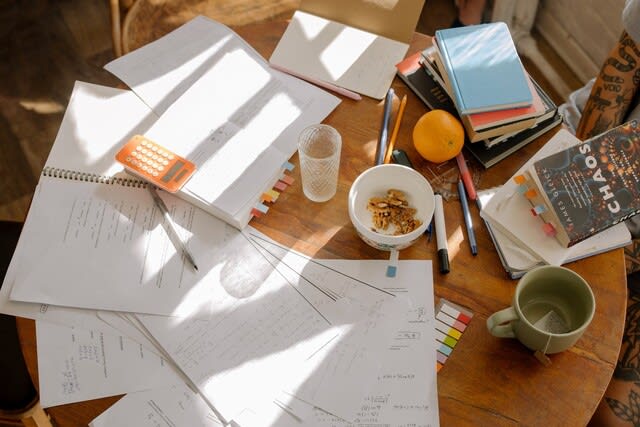2014年に発表された論文によると、Facebookの使用は承認欲求を媒介することでうつ病に影響を与えることが分かった。
「SNSをやりすぎるとうつ病になる」「SNSをやりすぎると対人関係がうまくいかなくなる」という言葉は少々説明不足だし、あまりにも大雑把すぎる。
確かに、そう訴える彼らが認知しているような、SNSを使用することで気分を悪くするなどの悪影響を被る人もいる。
だが同時に、こういった研究ではSNSを使用することで逆にうつ病が改善したり、気分が高揚したりする人も観測されるのだ。
両者の差分は何か。
そこから得られる、SNSを使用すると悪影響を被る人の条件とはなにか。
それを見極めずに単一的な思考でSNSが悪い、SNSをすることで何々が、と訴えるのは……言葉を選ばずにいうと悪手でしかない。
原因となるのは承認欲求だ。
ここでいう承認欲求は「他人に自分を認めてほしい欲」という認識でOK。
承認欲求は集団で生きる限り、というか人間である限り発生するものであり、身を置く集団に無下に扱われる(例えばいじめ、虐待など)程度ではそう簡単に潰えたりしない。
だが身を置く集団が対象を無下に扱っていれば、もしくは対象が正当に評価されるような集団に居なければ、いつまでたっても欲求は解消されない。
解消されない欲求はどこで満たす? どこで解消する?
解消されない欲求へのいら立ちはどこへぶつければいい?
そう、誰もが扱えるSNSがそういった悩みを打ち当てる場所となる。
そこからの経路はかなり複雑だが、基本的に承認欲求を起点とする摩擦や依存へとつながり、結果的に悪影響へとつながっていくのだ。
満たされない欲求は、次第に暴走していく。
ゲームをやりたい子供からゲームを取り上げても、子供はなにをしてでもゲームをしようとするだろう。ゲームができない苛立ちから、子供はあらぬ行為に出ることだろう。
それとほぼ同じことが、SNSで、インターネット上の対人関係で発生するのだ。
「SNSをやりすぎると対人関係がうまくいかなくなる」のではない。
「周囲との対人関係がうまくいかなかったからSNSをやりすぎる」のであり、「SNSでの対人関係がうまくいかないからうつ病になる」のだ。
SNSを使用すると悪影響を被る人間の特徴の1つは、承認欲求が満たされていないこと。
SNSが単体で悪者扱いされる問題では、決してない。
参考文献
Edson C.TandocJr,PatrickFerrucci,MargaretDuffy (2014) Facebook use, envy, and depression among college students: Is facebooking depressing?