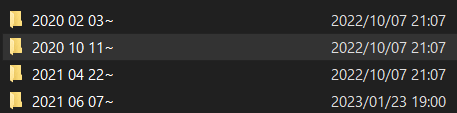自発的な行動、特に目的的行動の文脈の内発的動機付けや知的好奇心など、自分自身で目標を立てそれに従い行動することはかなり難しいとされる。
「かなり難しいとされる」と曖昧な表現をしたのは、自発的な行動の成功率や維持率を直接計ることがほぼ不可能なため、直接的な証拠を提示できないことに由来する。
代わりに研究者らは「どうすれば自発的な行動を妨げられるのか」に焦点を当て研究を行った。そしてその研究成果から組み立てられた環境の現実における再現性の高さや普遍性から、「かなり難しいとされる」と表現するに至った。
…つまり、私たちの身の回りにおいてそれを阻害する要素が多いから、自発的な行動は起こしにくいし続けにくいかもね、ってことが言いたいのだ。
内発的動機付けについて掘り下げた認知評価理論というお話がある。これを引用する限り、内発的動機付けは身の回りの環境によって、身の回りの環境を本人がどう解釈したかによって変化するという。
①環境が統制的かどうか。周りがあれこれ指示したり、禁止や圧力をかけたりして、自分の思うように行動できないと内発的動機付けは低下する。
②環境が本人の意思を尊重したり、励ましたりするか。「なんでそれやってるの? 意味あるのそれ?」みたいな本人の意思全否定や、「90点取れるなら100点も行けたでしょ?」とかのまったく励まさない姿勢は、内発的以前に意欲をごっそり削っていく。
③環境が本人の能力を否定しているかどうか。先ほどの「90点取れるなら」に近い文脈。「無理無理絶対できるわけないよ」みたいな。こちらは本人が陥ったときに追い打ちをかけるようなイメージか。
また、認知評価理論では内発的動機付けを低下させる要因をいくつかピックアップしている。
一番有名なのは報酬関係か、アンダーマイニング効果とかなんとかいわれているやつ。
報酬が内発的動機付けを下げるのはあくまでも報酬の獲得を目的として認知している場合であり、報酬そのものは内発的動機付けを下げるわけではない。「私はお金を得るために頑張っている!」っていうような状態は内発的動機付けとは言えないな。
「私はお金を得るために頑張っている!」状態に移行させないようにすれば、例えばなんの予兆もなくご褒美をポンと渡すとかであれば問題なかったりする。
周囲による評価も内発的動機付けを下げることがある。
正確には、これも評価の獲得を目的として認知するような場合、それを下げてしまう。
最初はお絵描き楽しくて、それだけでいつまでも楽しくやっていたのに、気が付いたらいいねとかコメントとかを気にするようになって、自分の描きたいものを見失ってしまった…みたいなエピソードをたまに聞くと思うが、それはまさしくこれが原因。
また、評価の獲得を目的にしたとき、そもそも動機づけの維持が難しいというのもある。
学校の成績で例えれば、自分がいくら頭が良くても、周りがもっと頭が良ければ相対的に評価されなくなって、やる気をなくす…という現象が頻発するのだ。
第三者による監視も似たような理由で低下させる。私たちは過剰に人の目を気にするのだ。
時間制限もまた、内発的動機付けを下げる。
取り組む時間の制限、つまり期限は否応なしにその期間までの完成を目標に掲げられる。
目的的行動が手段的行動にすげかわるという意味で、内発的動機付けが低下するのだ。
競争に関する話題はちょっとややこしい。
少なくとも、勝敗という相対的評価への依存という観点からすれば、内発的動機付けは低下するものと考えられる。
勝ったら気分高揚するし、負けたら気分ダダ下がり。そして勝つか負けるかは自分の能力と相手の能力で決定される。
一般の動機付けとしても、安定するかは怪しい。一部の動機付け論者は競争を「百害あって一利なし」って切り捨ててる。
内発的動機付けは、行動そのものが目的だったり、探究活動であったり、目標をすべて自分で決めていたりと、行動に関するほぼすべての意思決定が自身で完結しているか自身の範疇にあるものだ。
そして、その動機付けの表出が自発的な行動である。
この自発的な行動は、周りの不理解や、評価の機会、報酬などの茶々入れで簡単に阻害される。行動の目的がほかにできたり、探究どころではなくなったり、目標が他人に決められたりして。
簡単に阻害でき、阻害できる方法が多く、日常にはびこっているため、私は自発的な行動を起こしたり維持したりするのがかなり難しいとした。
裏返せば、この阻害要因をしらみつぶしにすれば、自発的な行動は起こりやすく維持しやすくなる。
参考文献
岡田 涼, 内発的動機づけ研究の理論的統合と教師―生徒間の交互作用的視点, 名古屋大学大学院教育発達科学研究科紀要, 心理発達科学, 2434-1258, 名古屋大学大学院教育発達科学研究科, 2007-12-28, 54, 49-60, https://cir.nii.ac.jp/crid/1390009224509489024,10.18999/nupsych.54.49
鹿毛 雅治, 内発的動機づけ研究の展望, 教育心理学研究, 1994, 42 巻, 3 号, p. 345-359, 公開日 2013/02/19, Online ISSN 2186-3075, Print ISSN 0021-5015, https://doi.org/10.5926/jjep1953.42.3_345, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/42/3/42_345/_article/-char/ja,
新動機づけ研究の最前線. 上淵寿, 大芦治編著. 京都 : 北大路書房. 2019.8. ISBN 9784762830723 ; (BB28720481) ; https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB28720481