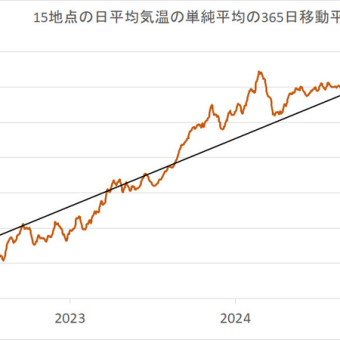その後だったと記憶しているが、父は鉄道模型を購入してくれた。父が選んだのは、3線式のOゲージの鉄道模型だった。後に知ったことだが、鉄道模型の形式はいろいろあって、直流2線式、交流3線式が当時の代表的なもののようだった。その後流行るのは、直流2線式のHOゲージで、その後9mmが主流となった。
直流2線式は、右側のレールに+左側のレールに-で前進、その逆で後退となる。交流式は、進行方向を決めるスイッチが機関車に付いていて、そのスイッチは、電源トランスにあるスイッチで逆転できたと記憶している。しかし、その動作には不安定なところがあり、予期せぬところで逆転が生じたりした。
最初はループレールとチョコレート色の機関車にブルートレイン様の客車と車掌車のセットだったと記憶している。そのうち、父はポイントを2台買い増して、レールの配置にバラエティを加えられるようになった。
3線交流式のメリットは、なんといっても信号機が簡単に作動することで、機関車の集電シューと接触する端子をレールに3か所セットしておくと、機関車のいちによって信号機が赤、黄、緑と変化していった。父は、それを販売店で見て知っていたから、3線交流式を選んだのだろう。すぐにこの信号機を買ってきた。
線路やポイントの収納ケースの裏には、色々な線路の配置図(レイアウト)の絵が描かれていた。すぐに、そのようなレイアウトを構成したくなったが、父もそこまでどんどん買い足すことはしなかった。
Oゲージは場所をとるが、8畳間にあるものをすべて片づけてレールを張り巡らして遊ぶところまでは行った。これが、父が買ってくれたおもちゃの最後のものであった。私が中学に入ってからは、もはやおもちゃは買ってくれなかった。
私は、中学に入って、小遣いをもらえるようになり、それをためてHOゲージの模型をやるようになった。最初は機関車の組み立てキットを購入し、その後、部品を購入して組み立てることも行った。ただ、仕上がりは、塗装のところから先でうまくいかなかった。線路も最初は木製道床のものを購入し、後にフレキシブルレールを購入してレイアウトを組んでみたりしたが、次第に割けるお金も時間もなくなり、やめてしまった。
==================================
おとといの台風15号の通過時には、一時猛烈な風が吹いた。屋上の風は特に強く、立ち入るのは、危険な状態であった。その屋上に置いてあった鉢植えの百日紅は、その強風に耐えた。今日見たら、花がほころんでいた。

三つあった蕾の一つはなくなってしまっていたが、二つはピンク色の花が咲きかけている。

強い風で、葉は再び萎れ気味になってきているが、あの猛烈な風でも花が残ったのは奇跡的に思える。
ちなみに、地上の百日紅の花も大半は散ってしまった。高い位置にあった花ほど風の被害は大きかった。背丈の低いマリーゴールドなど、被害が少なかった花はあるが、キバナコスモスなどは全滅した。道路際の株の処理に半日かかった。