日本の法律では「土地の所有権」は認められていますが、実際に土地を「所有」すると「土地所有税」ではなく「固定資産税」を取られます。これは、「土地は資産である」と国家が認定していると解釈でき、その土地の総面積は「日本国の国土面積」になります。外国大使館の敷地も当然ながら日本の国土で有る事は、日本の法務局に不動産登記している事からも明らかです。(土地取得から10年間は地方税として特別土地保有税が課税)
「日本国土は日本国(国民)の資産」なので、会計上その反対側に裏付けとなる「資本」と「負債」が必要になります。企業の所有地ならば貸借対照表等でその概要を見ることが出来ますが、個人や国家の場合は良く分かりません。しかし、個人の相続された所有地にも「固定資産税」は掛けられているので、「資本」と「負債」が必要になります。
「資産」=「負債」+「資本」
個人の所有地に「土地所有税」が掛かるのなら「生活に必要な土地を所有するにも税がかかる」と理解できますが、「資産税」だとその意味から、個人も「利益を追求する資本主義を構成する成分」になり、その「資産」の根拠である「負債」と「資本」が必要になります。
資本とは、事業活動などの元手のことです。相続を受ける時に「土地や現金」に対して相続税を取られ、相続が完了した後は「固定資産税」が掛かりますが、「現金資産税」は掛かりません。勿論、「負債税」や「資本税」も掛かりません。
「負債」とは、将来的に、他の経済主体に対して、金銭などの経済的資源を引き渡す義務のこととされています。貧乏人でも自分の所有地の「固定資産税」を払うという事は、「土地」は「借金の金利払い」と同じ現象と言え実質的には「負債」と言えなくも有りません。実際に、「固定資産税」を払えなくなったら「差し押え(没収)」されます。差し押えされても取り敢えずは「使用権」は残っています。
また、資本主義国家での「資産」である以上、運用しなければ「減価」が進み、価値が無くなる恐れがあります。実際に、数百年土地を「所有し続ける」と、土地の購入価格以上の「固定資産税」取られることになります。例え、自分が土地を所有していなくても、他の誰かが「固定資産税」を負担した土地に住むことになり、間接的に自分も負担している事になります。
土地を売れば時価で換金できますが、当人にとってみれば、支払った「固定資産税」の総額だけ「減価した」と言えます。地価の上昇が有れば、この「減価分」を補う事が出来、通常は経済成長によってこれが担保されます。
これらの「所有権」のある土地の面積の合算を「日本の国土面積」と言いますが、日本全体では、所有者不明の土地が一割以上有るそうです。これは「所有権の不明な土地」でも日本の領土になる事を示しています。
日本の領土の根拠を、外務省は「現在の日本の領土は、第二次世界大戦後の1952年発効のサンフランシスコ平和条約により法的に確定された。」としていますが、サ条約二条には「日本が、権利・権原・請求権を放棄する、領域の範囲」が書かれているだけで、残存領域が日本固有の領域である事の法的根拠は、日本の現行法にはありません。
法的根拠も無く、所有者すら分からない土地でも、なぜ日本の国土であるかは「古事記」「日本書紀」まで遡らなければ証明できません。「記紀」と歴史の科学的根拠を考えると、「日本の国土」は「天皇の領有地」と解釈できます。
「天皇の土地」を個人や会社が「所有」出来る根拠は、聖武天皇の勅による「墾田永年私財法」などの正式な法律に拠ります。この法でも、「もし許可を受けて3年経っても開墾しない場合は、他の者へ開墾を許可してもよいこととする。」となっていて、「土地の所有」ではなく「土地の使用」の権利を与えられているだけと解釈できます。
「記紀」は日本政府の正式な歴史書で、これを否定する「現行法」は存在しない事から、明らかに「日本の国土」とその領有権を担保しています。これは、「記紀」や「天皇由来の法律」を無効にすると、日本の国土が失われる事を意味します。
古代の歴史から考えると日本国の国土は「国の固定資産」ではなく「天皇の所有物」であり、国民は「天皇の土地を借用」していて、その使用料を天皇に支払う「土地使用税」が妥当に思えます。
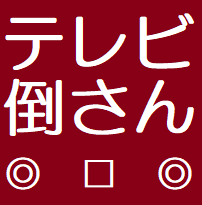










次のブログのヒントを有難う御座います。