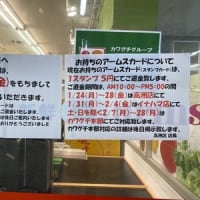今日は、午前中に教育委員会へ行き、図書館と公民館図書室の状況について、職員の方から聞き取りを行ないました。千葉市の図書館の蔵書数は200万冊で県内では、トップレベルの蔵書数です。課題もあるようなので、実際に、図書館や公民館図書室をまわってみようと思います。
今日は、午前中に教育委員会へ行き、図書館と公民館図書室の状況について、職員の方から聞き取りを行ないました。千葉市の図書館の蔵書数は200万冊で県内では、トップレベルの蔵書数です。課題もあるようなので、実際に、図書館や公民館図書室をまわってみようと思います。午後は、党県委員会で公共住宅(UR・県営・市営住宅)の問題で、これもまた聞き取りですが、行きと帰りは徒歩でしたので、途中にある登渡神社を訪れました。今まで中に入ったことはありませんでした。
千葉市教育委員会が設置した説明版によれば、「登渡神社の前身は、白蛇山真光院定胤寺。1644年に千葉家の子孫・登戸権介定胤が祖先の霊を供養するため、千葉妙見寺(現在の千葉神社)の末寺として建立したと伝え、別殿に妙見社を祀り…(中略)…妙見社を登渡神社と改めました。」とされています。
本殿には、鼠や龍、虎などの十二支、鳳凰などの彫刻があります。また、「彫刻は信州諏訪の名工・立川和四郎富昌または三代富重、次男の富種が関与されていたと考えられています。」とされ、立川流の作品で、登渡神社の作品が最も東方に残されているものです。