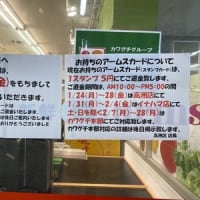一般質問の報告の4つ目は、防災・減災についてです。多岐にわたるため、中でも重要なトイレ対策について報告します。
第1回定例会でも、災害発生後のトイレ対策についての重要性について指摘されていました。5月22日にはNPО法人「日本トイレ研究所」における「能登半島地震・避難所等のトイレ調査報告会」が実施されました。調査報告会を受けての千葉市での課題等は明らかになったのかただしました。
危機管理監は「この報告会では、被災地において携帯トイレや簡易トイレが多く使われていることや、避難者の中で清掃当番を決めて衛生環境を保っている避難所があること、和式の簡易トイレが使いづらかったこと、また、東日本大震災の被災地の中には災害用トイレの訓練を毎年行っている自治体があることなどが紹介されました。これらの調査報告を受け、本市においても携帯トイレを使った訓練を行うことや、トイレの衛生環境保持について避難所運営委員会への研修会等で理解を深めることの重要性について、改めて認識したところ」と答えました。
災害用トイレには、マンホールトイレや簡易トイレ、携帯トイレ、汚物密封ポータブルトイレ、トイレトレーラー・トイレカーなどがあります。長所や短所を考慮し、千葉市では重層的、総合的にトイレ対策をする必要があるのではと求めました。
危機管理監は「本市では、マンホールトイレや携帯トイレ、簡易トイレなど、複数の手段で災害用トイレを確保しております。今後も、能登半島地震での事例等を研究するとともに、各種トイレの特性を考慮して、本市にとって有効な災害用トイレ対策を進めていく」と答えました。
大規模地震などでトイレ対策が教訓、課題としてありますが、重要な対策と位置づけて取り組むことが必要です。