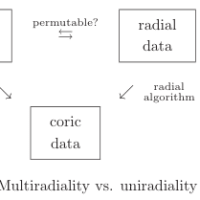節へのリンク
「汝の敵を愛せ」?
キリスト教徒の無慈悲
イエスの思想≠キリスト教/聖書の思想
命題:「愛すべき「敵」」は「隣人」と見なせる範囲に限定される
キリスト教/聖書の思想=「「隣人」以外には不寛容であるべき」
経済史的視点:「ローマのキリスト教(=カトリック)の変質」と不寛容
付録:キリスト教徒が「他集団への無慈悲や不寛容さで際立つ」ローマ時代の例
- 初期キリスト教の闇
- ローマ皇帝ユリアヌスへの評価
更新履歴
「汝の敵を愛せ」は、新約聖書に出てくるイエスの言葉としてトップクラスの有名度。
言葉の解釈としても素直に慈悲や寛容を説いたとして問題なさそう(「右の頬を打たれれば」の
方は、下記によれば、意味合いが違うそうだ)。
「奴隷のままでいて、全てを受け入れ、現世では我慢するように」などと言っていたわけでは
なく、"平和的な闘い方"を教えていたのだ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Tocana_201501_post_5600/
しかし、歴史上のキリスト教徒は、社会あるいは世界の中で「他集団への無慈悲や不寛容さで
際立つ集団」を形成している事例が目立つ。一般の信徒が崇高な教えを守るのが難しいという
レベルのことなら分かるが、(かなり高位の)聖職者を含めて、不寛容ないし無慈悲の極み
としか言いようがない言動を継続的に行う例が多々ある。
十字軍、異端審問、プロテスタント対カソリック、そして何より大航海時代以降の途方もない
事例の数々については言うまでもないだろうが、比較的初期のローマ時代の時点で相当ひどい
(付録参照)わけで、いくら
「汝の敵を愛せよ」はイエスが伝道中にたまたま口走った言葉であって、聖書(特に旧約聖書)
を支える思想とは言えません。 アカデミックな立場では誰でも認めることですが、イエスの
思想と聖書の思想、キリスト教の思想は、実際のところかなりの食い違いがあります。」
( Yahoo 知恵袋: [質問]汝の敵を愛せよ )
とは言っても、どう折り合いを付けるのか不思議な気がするので、説明を考えてみた。
命題:「愛すべき「敵」」は「隣人」と見なせる範囲に限定される。つまり、「隣人」と
見なせないなら、「人」であっても愛する必要はない。例えば異教徒や宗派が異なる人は
「隣人」と見なさない。
時々目にする「異教徒は人間と見なさない」という説明より無理がなく「隣人を愛せよ」とも
整合性があるので、上の命題が大半のキリスト教徒にとって暗黙の前提になっていると考えて
おくのがよさそう。少なくとも、イエスは「全ての人を愛せ」とは言っていない。
少なくとも、異教徒に対しては、むしろ不寛容あるいは無慈悲であることが、もともとの
聖書の思想ないしキリスト教の思想。下記が典型的。
「すなわちあなたの神、主が彼らをあなたに渡して、これを撃たせられる時は、あなたは彼らを
全く滅ぼさなければならない。彼らとなんの契約をもしてはならない。彼らに何のあわれみをも
示してはならない。」(申命記第7章2)申命記(口語訳) - Wikisource
キリスト教の指導者達の間に他の宗派や他の宗教への寛容という考え方が出てくるのが比較的
最近なので、一般的信徒の間では、もともとの他の集団への不寛容/無慈悲の思想が根強いと
思われる。特に、いわゆる「原理主義」的な宗派ほど、その傾向が強いのは、当然かも。
「キリスト教的な不寛容」には「債権者と債務者の利害衝突」という、経済的+社会的背景から
派生した側面もあるようだ。
マイケル・ハドソンという歴史的視点を重視する経済学者が、「古代西アジアでの有利子負債」
関連の社会制度を系統的に調査した結果、多くの古代社会では「債務奴隷の増加」や「債権者
階級による実質的な寡頭制成立」防止用の社会的安全弁として、「債務免除/清算/帳消し」が
制度化されていた事、および古典ギリシャ-ローマ時代は、この伝統的制度が失われた事により
特徴付けられる事を、さまざまな文献学的証拠に基いて結論付けた。
イエスの主張=最初期キリスト教の教義には、伝統的な債務免除制の復活=債務者への寛容が
含まれていたが、既に債権者寡頭制となっていたローマで国教として「体制化」するに際して、
都合の悪い「債務者への寛容」の教義は放棄/隠蔽され、祈りの言葉も改変されてしまった。
「債務者への寛容」は「社会的弱者への寛容」とも言える。∴それを否定した宗教が不寛容へと
傾くのは、当然であろう。さらに、この体制化されたキリスト教会にとっての「不都合な真実」
である初期キリスト教の教義を知るユダヤ教徒や「(教会に属さないが)聖書を読める人物」は
「不都合な存在」となり、迫害の対象となったわけだ。
ここでの「経済的+社会的背景」の説明は、主に下記の記事に基づいている。
https://mekong.hatenablog.com/entry/2023/05/05/215827
上記記事の主題=マイケル・ハドソン著「古代の崩壊」関連情報を拾う際は下記が有用。
https://mekong.hatenablog.com/search?q=古代の崩壊
マイケル・ハドソン本人について→本ブログの「マイケル・ハドソン」カテゴリの記事全般
付録:キリスト教徒が「他集団への無慈悲や不寛容さで際立つ」ローマ時代の例(by Wikipedia)
- 381年、テオドシウスは非キリスト教の神に捧げる犠牲を禁じ、「誰も、聖域に行くことなく、
寺院を歩いて通り抜け、人の労働で作成された像を見てはならない」と定めた。当時流行して
いたミトラ教の集会場として使用されていたカタコンベを破壊、その上に教会を建てようと
していたアレクサンドリア司教テオフィロスの要求に応じた。
- 392年、キリスト教を東ローマ帝国の国教に定め、死後二人の息子にローマを分与したため、
帝国は東西に分裂した。
テオドシウスとグラティアヌス、ウァレンティアヌス2世の3人の東西ローマ皇帝は、
「使徒ペトロがローマ人にもたらし、ローマ教皇ダマスス1世とアレクサンドリア総主教
ペトロス2世が支持する三位一体性を信仰すべきであり、三位一体性を信仰しない者は、
異端と認定し罰する。」という 「テッサロニキ勅令」を発した。」
https://bushoojapan.com/world/roma/2014/01/16/12791
「キリスト教を信じない奴はブッコロされて当然だからな!」という制度になってしまった」
- キリスト教の教派間の暴力抗争を解決するため、ローマ皇帝コンスタンティヌスは
ニカイア公会議(325年)を開いた( https://ja.wikipedia.org/wiki/キリスト教の歴史 )。
# 概して、一般的な歴史記述では、こうした「初期キリスト教の負の側面」が語られない。
# また、よく見かける「歴史上の評価」は「キリスト教にとっての都合の良さ」でしかない。
# 近現代の感覚で評価し直すと、結果は大違いになる。例えば、「背教者」として知られる
# ローマ皇帝ユリアヌスは、伝統的宗教との間およびキリスト教宗派間の寛容を命じただけ。
# それを聞かなかった上、「背教者」と呼び習わしてきたのがキリスト教の伝統。
https://www.y-history.net/appendix/wh0103-154.html
「宗教への不寛容を戒める」「ユリアヌスの意図とは反対に、各地でキリスト教徒による
神殿破壊や、それに対する報復として教会焼き討ちなど」
「何ものかの放火で神殿が焼き落ちる事件がおこった。キリスト教徒の仕業に違いないとして
将軍たちはこの際、キリスト教を禁止すべきだとユリアヌスに迫った。しかしユリアヌスは、
ローマの正しい伝統は宗教の寛容にあるとして、キリスト教禁止には踏み込まなかった。」
更新履歴^
2022-05-21 00:34 : 改行位置変更、字句修正、リンク追加
2022-05-26 14:10 : タグ #ローマ帝国 を付与。
2022-07-19 23:25 : 他記事からの参照可能位置にid付与、リンク修正。
2022-09-21 07:23 : リンク動作をタブ/ウインドウを開くようにする修正のもれ訂正
2023-03-18 01:05 : 要約を兼ねた節へのリンクを追加
2023-12-08 08:43 : マイケル・ハドソン著「古代の崩壊」からの知見を追加