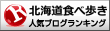辻標「宮町・宝蔵院」
辻標「宮町・宝蔵院」
東照大権現たる徳川家康公を祀る神社「東照宮」。
一時は全国に500社を越える東照宮があったと言われます。
しかし、明治維新後、廃仏毀釈で廃社や合祀が相次ぎ、今や現存するのは130社だそうです。
そう言えば、前に住んでいた横浜市金沢区(神奈川県)の東照宮も瀬戸神社に合祀されていました。
徳川家への忠誠心を示すためでもあったであろう東照宮を見学することは
大名がどのように造営に携わったか、色々な思惑を見ることでもあるのではないでしょうか。
(考えすぎ?)
という訳で重要文化財になっている仙台(宮城県)の東照宮を訪ねてみることにしました。
 ウォーキング・スタート
ウォーキング・スタート
1.辻標「宮町・宝蔵院」


辻標は東照宮へ続く宮町通にあります。
「宮町」は承応3年(1654)に東照宮が落成した時に広野を開拓して誕生した、
市内でも有数の由緒を誇る門前町なのだそうです。
「宝蔵院 」は東照宮の別当寺である仙岳院の塔頭(たっちゅう)の1つでありましたが、残念ながら廃絶となりました。
建物の名前などにその名残を見ることができます。
※別当寺…専ら神仏習合が行われていた江戸時代以前に、神社を管理するために置かれた寺のこと
※塔頭…禅宗寺院で、祖師や門徒高僧の死後その弟子が師の徳を慕い、
大寺・名刹に寄り添って建てた塔(多くは祖師や高僧の墓塔)や庵などの小院
この辻標から東照宮に向かって宮町通を進むと、仙岳院が左手に見えてきます。


梅田川に架かる東照宮前橋を渡ります。

JR仙山線の踏切を行くとすぐ、仙岳院があります。
2.仙岳院


藩の公式行事である拝謁や御礼の先頭を務めたという仙岳院。

境内にはたくさんの神仏が祀られています。
(置き場所がないくらい、たくさんあるように思いました。)
3.仙台東照宮
仙岳院を出ると、いよいよ仙台東照宮です。


幕府への忠誠心を示すために建立したと言われる東照宮。二代目藩主・伊達忠宗公が建立しました。
石鳥居は国の重要文化財となっています。

威風堂々たる立派な狛犬の台座には「葵の御紋」。


石灯籠の並ぶ石段へと進みます。
こちらの石段はリズムよく上がれるよう工夫されています。


やはり重要文化財である随身門(右)まで上がって振り返ると宮町通。
昔はどんな風景が広がっていたのでしょう。

拝殿(左)で参拝後、奥に進むと本殿の唐門と透塀が柵の向こうに見えます。
ちょっと遠かったですが、唐門の装飾は芸術性に富んでおり、素晴らしかったです。
こちらも重要文化財。
諸国に良材を求め、伊達文化の粋を結集、仙台藩の総力を挙げて建立された仙台東照宮。
次に行く時はさらに細部を細かく拝見してみたいです。
(どこもかしこも凝りに凝っている…)
 参考資料
参考資料
- ウィキペディア
- 『仙台城下の町名由来と町割』(古田義弘・著 本の森)
- 仙台東照宮のリーフレット
- 仙臺楽歩 北山・宮町エリア