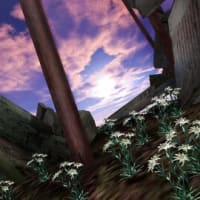北海道新聞 2023年10月24日付記事
<「鉄路の行方」を考える>4 親と子 今も「国鉄」 所有者の責任
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/930001/
2014年1月、
レール幅の検査データ改ざん問題で、JR北海道は監督官庁の国土交通省からJR会社法に基づく行政処分「監督命令」と、
鉄道事業法に基づく「事業改善命令」を受けた。
国交省の鉄道局長に、当時の野島誠社長が深々と頭を下げている。
両者の資本関係に着目すれば、別の見方ができる。
JR北海道は国交省所管の鉄道建設・運輸施設整備支援機構が100%出資する特殊会社だ。
つまり国はJR北海道の実質的な「親会社」であり、
鉄道局長はいわばその大幹部。
不祥事を起こした子会社の社長とともに、利用者に向けて頭を下げる立場でもあったはずだ。
1987年の国鉄改革を一般的に「分割民営化」と呼ぶためか、
JR北海道を民間企業だと誤解している人は多い。
実際は組織形態が株式会社になっただけで、
今も国が所有する鉄道会社、
すなわち「国鉄」だ。
しかもJR会社法に縛られ、代表取締役の選任や毎年策定する事業計画は、
国交相の認可を受けなければならない。
国は、経営安定基金の運用益減少で経営不振に陥り、安全投資を後回しにしているJR北海道の経営実態の全容を把握し、
具体的に助言、指導し、
必要なら社長を交代させることさえできる唯一無二の存在だった。
ところが国は、同社の経営不振の要因について
「地域の人口減少、他の交通手段の発達、高規格幹線道路の供用区間の延長等に伴い、
路線によっては輸送人数が大きく減少し、鉄道の特性を発揮しづらい路線が増加している厳しい状況に置かれている」
(国交省ホームページより)との主張を繰り返してきた。
まるで乗らない沿線住民のせいだと言わんばかりだ。
人口が減少しているのは事実だが、
乗客離れの要因は、JR北海道が年々不便になっているからでもある。
列車本数が少ない、
バスとの連絡が悪い、
すぐに運休する…。
赤字路線の沿線住民なら、思い当たる節はあるだろう。
国交省の有識者検討会が昨年7月にまとめた「ローカル鉄道のあり方に関する提言」は、こう指摘している。
「列車の減便や減車、(特急など)優等列車の削減・廃止、
駅の無人化等の経費削減策や、投資の抑制、先送り等の対応をしてきたが、
その結果、公共交通としての利便性が大きく低下し、
さらなる利用者の逸走(いなくなることの意)を招く負のスパイラルを起こしている…」
実際、経営安定基金の運用益が潤沢だったころのJR北海道は、
「鉄道運輸収入」を発足初年度である1987年度の623億円から、1996年度には800億円まで急増させた。
函館線の「銭函~札幌間」や札沼線の「桑園~あいの里公園間」に新駅を次々と開設し、
札幌圏の通勤・通学需要を掘り起こすことに成功したことが大きかった。
利便性向上や増収、安全確保につながる積極投資を続けていれば、
JR北海道は別の姿になっていたはずだ。
しかし、そうした投資機会は、運用益の急減を放置した国の不作為によって奪われた。
JR北海道が沿線自治体などに ”維持負担” を求めている
現在の赤字8区間(通称・黄色線区)の問題にも触れておこう。
国は2018年にJR会社法に基づく2度目の監督命令を出し、
事業の抜本的な改善方策を示すよう指示。
命令書の中で「地域の関係者との十分な協議を前提に、
事業範囲の見直しや業務運営の一層の効率化」を図るよう要求した。
これは赤字路線の廃止や、沿線自治体に負担を求めることを、
国が促したことを意味する。
JR北海道が主体的に進めているかのように装ってきた路線廃止が、
実は「国の意思」でもあったことを正式に認めたわけだ。
JR北海道の所有者は今も国であり、
同社が保有する道内の路線網は、道路に例えるなら「国道」だ。
その維持負担を、JRに対する権限も財源も持たない道庁や沿線自治体にいきなり要求し、
「負担できないなら廃止する」と迫っているのが、この問題の本質ではないだろうか。
沿線住民が「まるで脅しだ」(沿線自治体首長)と警戒するのは、当然のことだろう。
(文章執筆:特別編集委員 鈴木徹 氏)
<「鉄路の行方」を考える>4 親と子 今も「国鉄」 所有者の責任
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/930001/
2014年1月、
レール幅の検査データ改ざん問題で、JR北海道は監督官庁の国土交通省からJR会社法に基づく行政処分「監督命令」と、
鉄道事業法に基づく「事業改善命令」を受けた。
国交省の鉄道局長に、当時の野島誠社長が深々と頭を下げている。
両者の資本関係に着目すれば、別の見方ができる。
JR北海道は国交省所管の鉄道建設・運輸施設整備支援機構が100%出資する特殊会社だ。
つまり国はJR北海道の実質的な「親会社」であり、
鉄道局長はいわばその大幹部。
不祥事を起こした子会社の社長とともに、利用者に向けて頭を下げる立場でもあったはずだ。
1987年の国鉄改革を一般的に「分割民営化」と呼ぶためか、
JR北海道を民間企業だと誤解している人は多い。
実際は組織形態が株式会社になっただけで、
今も国が所有する鉄道会社、
すなわち「国鉄」だ。
しかもJR会社法に縛られ、代表取締役の選任や毎年策定する事業計画は、
国交相の認可を受けなければならない。
国は、経営安定基金の運用益減少で経営不振に陥り、安全投資を後回しにしているJR北海道の経営実態の全容を把握し、
具体的に助言、指導し、
必要なら社長を交代させることさえできる唯一無二の存在だった。
ところが国は、同社の経営不振の要因について
「地域の人口減少、他の交通手段の発達、高規格幹線道路の供用区間の延長等に伴い、
路線によっては輸送人数が大きく減少し、鉄道の特性を発揮しづらい路線が増加している厳しい状況に置かれている」
(国交省ホームページより)との主張を繰り返してきた。
まるで乗らない沿線住民のせいだと言わんばかりだ。
人口が減少しているのは事実だが、
乗客離れの要因は、JR北海道が年々不便になっているからでもある。
列車本数が少ない、
バスとの連絡が悪い、
すぐに運休する…。
赤字路線の沿線住民なら、思い当たる節はあるだろう。
国交省の有識者検討会が昨年7月にまとめた「ローカル鉄道のあり方に関する提言」は、こう指摘している。
「列車の減便や減車、(特急など)優等列車の削減・廃止、
駅の無人化等の経費削減策や、投資の抑制、先送り等の対応をしてきたが、
その結果、公共交通としての利便性が大きく低下し、
さらなる利用者の逸走(いなくなることの意)を招く負のスパイラルを起こしている…」
実際、経営安定基金の運用益が潤沢だったころのJR北海道は、
「鉄道運輸収入」を発足初年度である1987年度の623億円から、1996年度には800億円まで急増させた。
函館線の「銭函~札幌間」や札沼線の「桑園~あいの里公園間」に新駅を次々と開設し、
札幌圏の通勤・通学需要を掘り起こすことに成功したことが大きかった。
利便性向上や増収、安全確保につながる積極投資を続けていれば、
JR北海道は別の姿になっていたはずだ。
しかし、そうした投資機会は、運用益の急減を放置した国の不作為によって奪われた。
JR北海道が沿線自治体などに ”維持負担” を求めている
現在の赤字8区間(通称・黄色線区)の問題にも触れておこう。
国は2018年にJR会社法に基づく2度目の監督命令を出し、
事業の抜本的な改善方策を示すよう指示。
命令書の中で「地域の関係者との十分な協議を前提に、
事業範囲の見直しや業務運営の一層の効率化」を図るよう要求した。
これは赤字路線の廃止や、沿線自治体に負担を求めることを、
国が促したことを意味する。
JR北海道が主体的に進めているかのように装ってきた路線廃止が、
実は「国の意思」でもあったことを正式に認めたわけだ。
JR北海道の所有者は今も国であり、
同社が保有する道内の路線網は、道路に例えるなら「国道」だ。
その維持負担を、JRに対する権限も財源も持たない道庁や沿線自治体にいきなり要求し、
「負担できないなら廃止する」と迫っているのが、この問題の本質ではないだろうか。
沿線住民が「まるで脅しだ」(沿線自治体首長)と警戒するのは、当然のことだろう。
(文章執筆:特別編集委員 鈴木徹 氏)