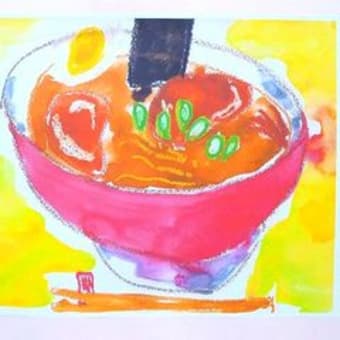「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
今朝の教室ブログ、もうお読みになりましたか?「前後左右上下」の学習をしている生徒さんのお話です。
「上」ひとつとっても、いろいろな意味合いがあるのですね。日常で何気なく使っていると、さほど意識しませんが、言葉を習いたての生徒さんにとっては、言葉と意味は1対1対応していますから、その場の使い方で意味合いを捉えて理解するというのは、至難のわざです。
「画用紙の上」(on the paper) と「画用紙の上」(top of the paper)・・・なるほど。
画用紙自体を中心とすれば、紙面上であればどこの場所をとっても「上」ですが、画用紙の中央の1点を中心とすれば、紙面上にも新たに上下左右の位置が生じてきます。位置は相対的なものだからです。どこに、基準を定めるかによって上下左右の意味するところは異なってきます。
まずは、自分にとっての上下から学習をはじめてみましょう。歌って、体を動かして、「うえ」「した」という言葉に慣れ親しませていくことです。それから、物の上下。それから物の中での上下。
日常の中でも「上」「下」の言葉を使って、言葉の意味を感覚的に体得させていきましょう。
「机の上」「机の下」。指示はゆっくりと、物と位置を指し示しながら発しましょう。物は手のひらで触れて示し、位置は人差し指で指し示しましょう。このとき、「上」と「下」をセットで教えてあげましょう。「下」があるからその対比で「上」がわかるということがあります。「本を机の上においてね」「本を机の下においてね」。
だんだんと、物の中の上下についての指示も発していきましょう。「タンスの上の引き出し」「タンスの下の引き出し」というように。
画用紙の上での上下はさらに難しい解釈です。自分の在る(いる)空間とは、異なる空間を紙面に作り出しているのですから。絵本も写真もそうです。テレビもそうです。
でも、私達の空間処理能力は、異なる区間の処理も同時に行えるほどに、高機能なんです。たとえば、マウス操作でモニタに図や絵を描くことができます。マウスを動かしている空間とモニターとは異なる空間ですが、慣れればたやすく操作できます。お絵かきや絵本に親しむことも、そんな機能を育てることに通じます。
ここではまず、お子さんにとっての「上下」の理解の難しさを改めて認識しましょう。たとえ「上下」の理解がまだ充分でなくとも、小学校に上がれば程なくお子さんは「上から何番目」や「下から何番目」「前から・・・」「後ろから・・・」の学習に立ち向かうのですから。
でも、親御さんもあわてることはありません。先ほど述べた手順で、ゆっくり教えていってあげましょう。お子さんにとっての難しさを踏まえた「上」で(「上」のこんな用法もありますね・・・)、楽しく学習に取り組ませてあげましょう。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp