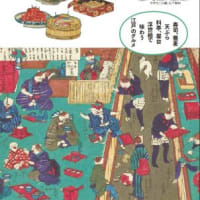『平安の秘仏』展に行ってきました。
東京国立博物館での特別展なんですが、
平成館ではなく、本館特別5室での開催。
6月にあった『ほほえみの御仏』展と同じですね。
それだけでは無く、西院、特別5室での特別展が、
結構有るような気がします。
この部屋、狭いんですけどね。
午前中、色々と出来事が有ったので、
東京国立博物館への到着は午後。
特別5室だと、展示品の数が少ないので、
音声ガイドをレンタルしようか迷ったんですが、
スペシャルナビゲーターが、
イラストレーターのみうらじゅんさんと
作家・クリエーターのいとうせいこうさんだったので、
借りることにしました。
でもこのお二人、仏像関係だと、出てきますねぇ(笑)
肩書を、仏像スペシャリストとか、仏像ナビゲーターとかに
変えたほうが良いのでは無いでしょうか?
展示会場ですが、事前に
「客は多いけど、展示物が見られない程の混雑ではない」
と言う情報を得ていたんですが、実際にその通りでした。
見どころは、《十一面観音菩薩坐像》ですよねぇ。
会場に入って、ど真ん中で一番目立つ所に展示されていました。
って言うか、十一面観音菩薩の坐像では日本最大なので、
目立って当たり前ですね。
3.12mの像高ですが、頭と体は1本の木から彫り出されていると言う事。
と言うことは、これだけの木が嘗ては日本に有ったということですよね。
いまも、探せば有るのかもしれませんが、この坐像が作られたのは、
10世紀の平安時代。
10世紀には、そんな大木がゴロゴロしていたのかなぁと想像したりしました。
あとは《毘沙門天立像》
坂上田村麻呂が鈴鹿山の山賊の追討を櫟野寺で祈願し、
それが叶うと毘沙門天像を造って安置したとも伝えられ、
“田村毘沙門天”とも言われるそうです。
襟を立てた《地蔵菩薩立像》が居て、中々おしゃれ(?)
ちょっとめずらしい気がしました。
鉈彫りのノミ跡が残った《観音菩薩立像》も居ました。
中々素朴な仏様です。
あとは《地蔵菩薩坐像》ですかねぇ。
目立つお腹の帯があって、“腹帯地蔵”とも言われるそうです。
全部で20点と、少数精鋭でしたが、
平安時代の、比較的素朴な仏様たちに癒やされました。
| 名称 | 平安の秘仏-滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち http://hibutsu2016.com/ |
|---|---|
| 会期 | 2016年9月13日(火) ~ 2016年12月11日(日) |
| 会場 | 東京国立博物館 本館 特別5室 |
| 当日観覧料 | 一般1000円、大学生700円、高校生400円、中学生以下無料 |
| 開館時間 | 9:30~17:00 (ただし、金曜日および、10月22日(土)、11月3日(木・祝)、11月5日(土)は20:00まで、9月の土・日・祝日は18:00まで、10月14日(金)、10月15日(土)は22:00まで開館) ※何れも入館は閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜日 (ただし、9月19日(月・祝)、10月10日(月・祝)は開館、9月20日(火)、10月11日(火)は休館) |
癒やされついでに(笑)
ショップに行くと、こんな可愛らしいタヌキたちに遭遇。


櫟野寺が、滋賀県甲賀市にあるのと、甲賀市では信楽焼が名産、
そして、甲賀と言えば忍者と言う連想ゲーム(笑)