日本の政治も、産業構造も、自社もここに記載されている SONY 自身も"成功のトラウマ"に陥っている。それに自らが気づいていても既得権者からの圧力に屈していることが多い。1票の重みの是正、社会保障制度の見直し、医療制度改革、都州制度、農協改革、農地法改革など行うべきことは山積みなれど先延ばしにされていく。
あれだけ明治維新の英雄達が他のアジアの国に先んじて、開国、富国強兵に果敢に挑戦したにも関わらず、太平洋戦争時の戦前、戦中の為政者達は現在と同じように理由無き楽観主義で問題点の解決を後回しにし、結果として国を滅ぼしたことをもっと教訓とすべきだとこの記事を読んで思う。
Apple ( iPod ) よりも、SoftBank ( Pepper ) よりも先んじていたはずの企業でさえ、成す術を知らない。
---------------------------------------------------------------------------------------------
「勝ち組」日立・東芝と「負け組」ソニーを分析
進む家電の2極化、負け組みに明日はあるか http://toyokeizai.net/articles/-/54910
2014年12月3日 小宮 一慶:経営コンサルタント 東洋経済新報社 http://toyokeizai.net/

日立製作所は今期も最高益更新(中西会長(右)と東原社長、撮影:今井康一)
電機メーカーの二極化が進んでいます。2014年9月の中間決算を見渡しますと、日立製作所や東芝、パンソニックなどは増益となった一方で、ソニーは大幅減益となり、まさに独り負けになっているのです。
勝敗を分けたのは、何でしょうか。リーマンショックが起こった2009年3月以降、電機メーカーの業績は、世界同時不況と円高の波に飲まれて急速に悪化。しかしその後、収益環境が平常に戻った今、それ以前からも含めた構造改革が収益の明暗を大きく分けています。そこで、今回はこの中から日立製作所と東芝、ソニーの3社を分析をしながら、二極化の理由を探ります。
「選択と集中」によって復活した日立製作所
日立製作所(以下、日立) の2014年9月期中間決算(4~9月)から見ていきましょう。
損益計算書から業績を調べますと、売上高は、前年同期からほぼ横ばいの4兆4967億円。売上原価を少し抑えたことで、営業利益は23.4%増の2140億円となりました。まずまずの状況です。
貸借対照表から安全性を調べますと、自己資本比率(純資産÷資産)は35.4%ありますから、財務的にも安定していることが分かります。
注目したいのは、事業別の業績です。収益を伸ばしているのは、総じて B to B 向けの事業なのです。
セグメント情報を見ますと、売上高の大きなものは、金融や公共サービスのシステム構築などが含まれる「情報・金融システム」9349億円と、鉄道やエレベーター、昇降機といったインフラ事業の「社会・産業システム」6597億円。それから、電線ケーブル、半導体やディスプレイ用材料等が含まれる「高機能材料」6886億円です。いずれも前年同期より伸びており、好調です。
高機能材料で稼ぐ日立、家電などの貢献はわずか
これらのうち、特に営業利益を稼いでいるのは「高機能材料」の529億年で、全体の25%を支えています。「情報・通信システム」も368億円の利益を上げており、全体の17%を占める主力事業です。
一方、家電が含まれる「生活・エコシステム」は、売上高は3883億円(構成比8%)、営業利益は143億円(構成比7%)と、全体に占める割合としては小さくなっています。かつては15%弱あったことを考えると、家電事業は縮小されていることが分かります。
「生活・エコシステム」のこの期の営業利益は、前の期より145.4%も伸びていますが、これは海外向けの空調設備が好調だったためです。
もう一つ、地域別の業績をまとめたセグメント情報を見てみましょう。全体の売上高のうち、国内が占める割合は53%。続いて大きなものは、アジア22%、北米10%、欧州10%となっています。
アジアの新興国は成長が著しく、インフラの整備が進んでいることから、需要が増えているのです。特に、発電設備などの重電が強いと思われます。
家電はコモディティ化が進み、海外でも安くて高品質の商品が作られるようになりましたから、競争力が低下してしまいました。一方、重電はカスタムメイドするものですから、他社との差別化がしやすく、価格も崩れにくいものです。
そこで日立は、 B to C を縮小して、 B to B の割合を高めました。同社は、かつてはテレビや白物家電、パソコンなどの事業にも注力していましたが、業績が悪化し始めてから、いち早く「選択と集中」の構造改革を行ったのです。
2007年には価格競争が激しくなったパソコン事業から撤退し、2009年3月期に7873億円の最終赤字を計上した時には、一気に構造改革を進めました。不採算事業から次々と撤退し、 B to C から B to B へとシフトしていったのです。この戦略が功を奏しているというのが、現在の状況です。
インフラ系や半導体んど B to B で勝ち残った東芝
続いて、東芝の2014年9月中間決算を見てみましょう。東芝も、日立と同様に、B to B 事業で稼いでいる様子がわかります。
損益計算書(10ページ)を見ると、売上高は前の期より 3.5 % 増の3兆1083億円。売上原価、販売費ともに微増しましたが、営業利益は 7.7 % 増の1151億円となりました。こちらも好調だと言えます。また、自己資本比率は 26.8% ありますので、安全性にも問題ありません。
次に、事業別の業績をまとめたセグメント情報(14ページ)を見ますと、やはり B to B 事業が伸びています。
特に収益を上げているのが、発電システムなどの「電力・社会インフラ」で、売上高は前の期より16.9% 増の9158億円。営業利益もほぼ倍増の300億円を計上しています。
それから、昇降機や流通・事務用機器、空調事業などを含む「コミュニティ・ソリューション」も好調で、大幅な増収増益となりました。売上高は7.7% 増の6456億円、営業利益は70.8% 増の158億円となっています。新興国でのビルの空調や昇降機が伸びたのです。
最も利益を稼ぎ出しているのは、半導体やハードディスクなどが含まれる「電子デバイス」で、1066億円の営業利益を計上しています。中国をはじめとする新興国向けの安価なメモリが好調で、収益を伸ばしているのです。また、9月に発売された米アップル社の「iPhone 6」の製造に伴って需要が増えたという要因も重なったと思われます。
半導体などの装置産業は、製造するための工場や機械などに膨大が固定費がかかりますが、損益分岐点を超えると大きな利益を生むことができます。ですから、たくさん作るほど、利益がうなぎ登りに上がっていくのです。
一方、苦戦しているのは、テレビやパソコン、白物家電などが含まれる「ライフスタイル」です。前の期は351億円の営業赤字となり、この期も293億円の赤字を計上しました。やはり、差別化の難しい B to C ではなかなか利益が確保できないでいるのです。
B to C に主力を注ぐソニーは大苦戦
次に、独り負けしているソニーの業績を見ていきましょう。損益計算書(18ページ)を見ると、同社の2014年9月中間決算は、4年連続の最終赤字となりました。
売上高は、前の期より 7.2 % 増の1兆9015億円。ところが、売上原価と販管費が膨らんだため、営業利益は、前の期は139億円の黒字を出していたのが、この期は855億円の赤字を計上しました。最終損益である四半期純損失も、前の期の62億円の赤字から、この期は1200億円の赤字となり、マイナス幅が拡大しました。
なぜ、ここまで悪化を続けているのでしょうか。セグメント情報(22ページ)からもう少し詳しく見てみますと、大きく営業利益を落としているのは、スマートフォンなどが含まれる「モバイル・コミュニケーション」です。前の期は 213億円の黒字を確保していましたが、この期は 1747億円の赤字を計上しています。
これは、収益が悪化したことで 1760億円の減損が発生したためです。スマホ事業が苦戦している様子がうかがえます。
稼ぎ頭は、ソニー銀行やソニー損害保険などが含まれる「金融」で、914億円の営業黒字となっています。主力の家電製品やモバイル製品よりも利益を上げていますね。
B to C に重点を置いているソニーは、なかなか収益を伸ばせないでいるのです。その分、収益力の高い金融事業に助けられているという構図になっています。
日立と東芝の勝因は、早い段階で選択と集中を行い、B to C から B to B へシフトしたことだと言えます。
2社はかつて、白物家電やパソコンなど、手広く事業を行っていましたが、リーマンショックが起こる前から、価格競争の激化によって業績が陰り始めていました。特に日立は悪化のスピードが速く、お茶の水にあった本社ビルを売却したことが話題になりました。
自動車強化するパナソニック、ソニーの巻き返しも注目
しかし、そこでいち早く社会インフラや重電などの B to B へ方向転換できたからこそ、いわばV字回復することができたのです。自分たちの強みを活かし、将来的にも差別化できる事業に資源を集中したのです。
逆に言えば、家電など B to C でなんとか延命できていたソニーやパナソニック、シャープなどは、かえって大きな痛手となってしまったと感じます。
ただ、パナソニックに関しては、自動車部品の製造など、この先、B to B に注力していくとのことですから、それらが軌道に乗れば今後は業績が上向く可能性があります。
ソニーもオリンパスと提携して、医療機器事業を拡大しようとしています。オリンパスは、内視鏡など医療機器について、世界シェアの約70%を握っていますから、ソニーは映像技術を提供することで、これに乗っかろうとしているのです。こちらもうまく業績を伸ばせるかに注目したいところです。
----------------------------------------------------------------------------------------------
厳しい時代に伸び続けている企業は何が違うのか? 苦境から奇跡的な復活を遂げた企業は何をしたのか? 成功しているビジネスパーソンは何を実践しているのか? その秘密は「離れる戦略」にあります。過去の常識から離れ、商習慣から離れ、古い組織構造から巧みに離れることで、勝者の座に就くのです。この連載では、勝ち続ける者だけが知っている「離れる戦略」を、古今東西、最新の戦略理論もからめて易しく読み解いていきます。
----------------------------------------------------------------------------------------------
勝ち続けるソフトバンクの"離れる戦略" http://toyokeizai.net/articles/-/53985
卸、ケータイ、ロボット・・・コア事業を変える
鈴木 博毅 : MPS Consulting 代表 http://www.mps-consult.com/
2014年11月27日 東洋経済新報社 http://toyokeizai.net/

2014年11月4日、ソフトバンクの決算発表会見での孫正義氏 (写真:梅谷秀司)
■一代で売り上げ高6兆円の企業を創った孫正義氏
携帯電話・インターネット通信企業のソフトバンクは今年、中国最大のネット通信会社アリババのニューヨーク証券取引所上場でも話題となりました。ソフトバンクは2000年、創業期のアリババに出資しており、3割を超える筆頭株主です。アリババ上場による保有株時価総額は約10兆7000億円(11月24日時点のニューヨーク証券取引所でのアリババの株価:114ドル、為替:1ドル=118円で算出)です。
携帯電話や検索サイト Yahoo ! で私たちの生活に浸透している同社は、孫正義氏の創業から33年、極めて短期間で巨大企業への飛躍に成功している希有な存在です。そして着目すべきもうひとつの特徴は、コア事業が何度も変化していることです。
○1981年の創業時:ソフト流通業
○1980年代後半:LCR(最も安い通信事業者を自動選択するシステム)
○1990年代半ば:検索エンジンのヤフー
○2006年:ボーダーフォン買収による携帯事業参入
成長の過程で多数のM&Aを行い、米国第3位の携帯電話会社スプリント・ネクステルなども傘下に収めており、現在はテレビCMにも登場している対話型パーソナルロボットの事業にも注力を始めています。
このように驚くべき成長を成し遂げている同社は、時価総額で現在9兆円を超え、2014年の11月下旬時点で、日本国内ではトヨタ自動車、三菱UFJファイナンシャル・グループに次いで3位です。売り上げ高は2013年度、6兆円を超えます。同社はなぜ、これほど成功できたのでしょうか。
■離れる戦略とぬるま湯の恋愛関係とは?
前回の記事で、企業と消費者の関係を「あなたに過去の姿でいてほしいと願う恋人」に例えました。新たな恋の発見には古い恋を手離すことが必要ですが、通常、これまで恋人と別れることイコール、新しい恋の始まりとはなりません。失恋すれば空白期間が必ず生まれ、寂しくつらい思いをしなければならないのです。
寂しさや苦しみを乗り越えて、古い恋を手離す2つの場合があります。ひとつは現状の関係がすでに破綻して、修復不可能となったとき。もうひとづは、現状の恋では自分の理想とする人生がかなわない、自分の成長もできないと悟ったときです。
逆に、古い恋を手離せないときは、ふたりの関係が不満ながら破綻するほどでもなく、自分自身にも具体的な理想や目標がないときです。これは売り上げや利益がまったく伸びず、しかし日々、なんとか食べてけるビジネスに似ています。生活していける、という状態以上の目標や理想がなければ、人も企業もこの状態にとどまることが多いのです。
したがって現状から離れるためには、極端な危機か、現状に安穏とさせない大きな目標や理想が必要なのです。
■離れるために、牽引してくれる目標が不可欠
ビジネスでも人生でも、本格的な危機を迎える前に離れる戦略を実行できるほうが当然、有利です。孫正義氏は、離れる戦略の実行に不可欠な大胆な目標設定において、ずば抜けた能力を持っている人物です。
【孫社長が掲げてきた大胆な目標】
○社員2人の創業期に「やがて売り上げを1兆円2兆円とするような企業を創る目標」
○2010年の「新30年ビジョン」で、30年後までの時価総額200兆円、世界トップ10
上記のような強烈な目標を掲げ、達成するたびにより遠大な目標に切り替えていますが、自社にぬるま湯の状態から離れさせ、新たな進歩を促進するためだと推測できます。売り上げ目標が兆の単位であれば、ソフト流通業の成功だけで満足するわけにはいきません。
世界的なベストセラーとなった書籍『ビジョナリー・カンパニー』(ジェームズ・C・コリンズ、ジェリー・I・ポラス著)は、時代を超え際立った存在であり続ける企業の特徴が分析されています。その特徴のひとつに、永続する企業は「大胆な目標を定期的に掲げる」というものがあります。書籍内では Big Hairy Audaciou Goal ( BHAG = ビハーグ )と呼ばれていますが、驚くほど大胆な目標を掲げて、進歩を促す強力な仕組みとして活用しているのです。
ソニーはわずか十数人の創業期、社員が食べていくために炊飯器や電気毛布を開発して販売していました。そのような時期に、創業者のひとりである井深 大氏は「会社の創立趣意書」を創り上げています。
【ソニーの会社創立の目的】※書籍『ビジョナリー・カンパニー』から筆者が現代語訳
○技術者たちが技術することに喜びを感じ、思いきり働ける職場をつくる
○日本再建、文化向上に対する技術面、生産面からの活発な活動
○(戦時中に)高度に進歩した技術の国民生活への即時応用
このような大胆な目標があったからこそ、十数人の小企業ソニーはそのときの現状に甘んじることなく世界に挑み、やがて世界のソニーになったのです。また大胆な目標が組織にとって有益なのは「それが達成されていない間だけ」だと本書は強調しています。ぬるま湯から引き離す力を持つ理想、進歩の必要性を突き付ける新たな目標こそが必要なのです。
残念ながら現在、ソニーは凋落が指摘されています。世界のソニーと呼ばれた輝かしい時代が過ぎ、多くの夢を達成したあと、ソニーは将来の成功に自らを牽引する新たな目標や夢を掲げられず、結果、過去から離れることができなかったと考えられるのです。
※『ビジョナリー・カンパニー』 http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/916400.html
※『 Built to Last 』 http://books.google.co.jp/books/about/Built_to_Last.html?id=rFLvnNfgk-oC&redir_esc=y
■「未来の繁栄」を見つめること
孫正義氏の著書『孫正義 リーダーとしての意志決定の極意』には、家業の造船業が斜陽化したときに、必死で立て直した企業家について厳しい言及をした箇所があります。
「なぜ沈みゆく産業に自分の人生を懸けるんだ。もうその時点で経営者として、事業家として失格だ(中略)。もし僕がその立場にいたら、造船業で培った製造する力、マネージする力、営業力、そういう基礎力を使って造船以外をやる。あるいは日本でやらずに、そのノウハウを持っていって中国やロシア、インドの賃金でやる」
「親から受け継いだ仕事をやらざるをえなかった。それは理解できるけれど、僕が同じように受け継いでいたらいち早く業態転換する。先祖代々の家業を意地でも守っていく、そんなことは絶対にしない。少なくとも僕の後継者になる人は、それでは失格です」
離れることは痛みが伴います。心理的な抵抗感も強烈にあるでしょう。それでも離れなければ「1兆円2兆円の企業」を実現できない。大胆な目標を掲げ、その目標から俯瞰をすることで、現状にとどまり成長が停止した状態に甘んじる無意味さを実感できるのです。
逆に目標が現状維持の場合、孫氏のように業態転換をする必要はありません。その意味で「未来の繁栄」を思い描き、どのような未来を見つめるかが重要になります。時間軸を変えることで、現状から私たちの発想を引き剥がすのです。創業者の孫正義氏が掲げ、更新し続けている大胆な目標こそが、ソフトバンクという企業に「離れる戦略を実行し続ける力」を与えて、今後、伸びていく事業領域への進出を可能にしているのです。
人工知能の発達は、やがて対話型ロボットが人のコミュニケーション介在者として大きな役割を得る可能性を秘めています。そのとき、私たちはほとんど消費行動をロボットとの対話を通じて行うかもしれません。ここでも「未来の繁栄」を自ら設定して現状から離れ、新たな一歩を踏み出す"離れる力"が発揮されているのです。
-------------------------------------------------------------------------------------------
「獺祭」「黒霧島」ヒットの陰に"離れる戦略" http://toyokeizai.net/articles/-/52887
逆境から躍進した旭酒造、霧島酒造の秘密
鈴木 博毅:MPS Consulting 代表 http://www.mps-consult.com/
2014年11月12日 東洋経済新報社 http://toyokeizai.net/
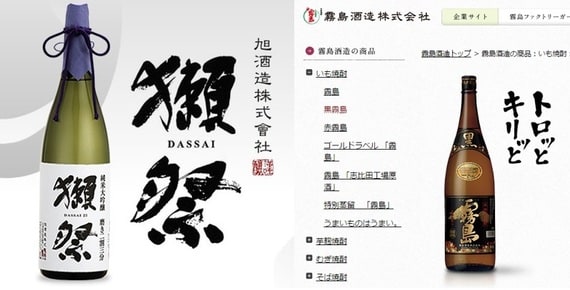
「獺祭」(左)と霧島酒造「黒霧島」(右)。大人気の背景に「離れる戦略」があった!
当初、霧島酒造について「1996年前後に倒産直前だった」と記しましたが、この表現は実際とは異なっており、当時も売り上げ成長を続けていました。表記を訂正し、お詫びいたします。
■苦境から大ヒット
トンネルの先に復活の光が見え隠れする日本経済。2013年からのアベノミクスの恩恵などで売り上げを伸ばす企業がある一方、変わらず閉塞感の中で苦しむ企業もいまだに少なくありません。特に歴史が長い業界では、かなかな企業も消費者も変わらないのが現実ではないでしょうか。
ところが、いわゆる伝統産業と呼ばれる業界の中でも、さらに歴史のある業界である日本酒、焼酎の世界で過去十数年間、躍進に次ぐ躍進をしている2社があります。
純米大吟醸の「獺祭」で有名な旭酒造と、クセのない上品な香りを実現した芋焼酎「黒霧島」の霧島酒造です。現在ではおいしさで有名かつ人気の製品として、不動の地位を誇る2社の製品が、両社とも現在の社長に交替した頃は、新たな打開策が不可欠の状態でした。
旭酒造の桜井博志社長が家業を継いだ1984年当時は、生産量がピークの3分の1の700石(1石=180リットル)まで低下、さらに地ビール事業での失敗によって多額の借金を抱えてしまいます。
霧島酒造の現社長、江夏順行さんが就任した1996年は、業界が増税などで打撃を受け、ライバル企業が地元にも進出し、新たな飛躍を模索する状態でした。
そのような2社ですが、現在では旭酒造は日本酒の生産量が5万石、霧島酒造は焼酎メーカーの売り上げランキング(帝国データバンク)で2004年の業界6位から、2012年に売上高500億円を達成し、三和酒類を超えてトップに躍り出ています。
極めて厳しい経営環境から、2社はどのようにして飛躍のきっかけをつかんだのでしょうか。そこには通常とは真逆の「離れる戦略」の存在を垣間見ることができるのです。
■古い顧客は、あなたの過去の姿でいてほしいと願う恋人
読者の皆さんに考えていただきたい点があります。
販売量が数十倍に増えること、売上高が10倍以上に増えることが、消費としてどんな状態を意味するかです。販売量が過去10年で20倍に増えた製品があるとして、週1回、お酒を楽しむこれまでのお客様を、1週間で20回、お酒を楽しむ消費者に変身させることができるでしょうか。
イメージすればすぐにわかりますが、これは「物理的に不可能」です。毎週金曜日の夜の晩酌を楽しみにしていた人が、20倍を飲むためには週7日、朝昼晩の3食すべてでお酒を飲まなければ、20倍の消費を達成できません。
このたとえで何をお伝えしたいかと言えば、売り上げを劇的に伸ばすためには、既存の古い顧客の枠組みを超える必要があることです。既存のお客様に20倍の消費をしてもらうのが不可能なら、これまで目の前にいなかった消費者を「外から20倍、吸引しなければならない」のです。見たことも出会ったこともない人たちが、あなたの顧客になるイメージです。
ところが、ここで深刻な葛藤が生じます。これまで長い間、愛用してくれた顧客は、その会社の今の製品が好きであり、自らの嗜好に合うから買い続けていたのですから、既存顧客のことだけを考えると「この製品を変える、ビジネスのやり方を変える」ことに強い抵抗感を感じるのです。
打開策を求めていた旭酒造にも霧島酒造にも、最も苦しかった時期でさえ、過去から愛飲してくれた貴重な顧客はいたはずです。
しかし、古いお客様に既存の製品を提供する過去のコミュニケーションでは、売れる数量や利益は増やすことができないジレンマがあります。古い顧客は、あなたに変わってほしくない(成長してほしくない)と願う恋人のようなものなのです。
逆説的に言えば、多くの歴史ある企業は古い(愛用してくれる)顧客によって小さな自己像、限られた売り上げに閉じ込められている状態であるとも言えます。
■古い目標・コミュニケーション方法を手離す
新たな躍進には、多くの場合「古い顧客を手離す」という思い切った決断があります。旭酒造の桜井社長は著書『逆境経営』で、量を売ることを目指すのではなく、徹底的においしい酒を造ろう、酔うのではなく味わう日本酒を目指して舵を切った、と書かれています。
同じように、霧島酒造も「全国の人に飲みやすい、女性でも飲める芋焼酎」を製品開発のコンセプトにしています。既存顧客から離れ、古い自社像や古い製品コンセプトからも離れた英断が、新たな消費者を同社の製品に引き付け、驚くべき飛躍のきっかけとなったのです。
企業側は製品開発や新技術によって、より顧客単価の高い販売を成功させたいと願うものですが、古い顧客はたいていの場合、製品単価が上がることを好みません。古い価格帯だからこそ引き寄せられた顧客なのですから、ニーズが根本的に違うのです。
そのため単価を上げたいと思ったら、新単価を快く受け入れてくれる別の顧客に売る必要があります。古い顧客によって規程された自己像(自社像)から離れ、新しい顧客と関係と作り上げる自社をイメージできるかどうかが、飛躍か停滞かの分かれ道となるのです。
これは日本国内のスポーツ市場と、海外リーグの選手年俸が大きく異なる場合と似ています。1本のヒット、1本のシュートの報酬が10倍以上になる市場に彼らは移動したのです。
製品コンセプトの刷新は、古い顧客像から離れることで生み出されていますが、注目すべきもうひとつの改革は、社員との古いコミュニケーション方法も手離していることです。
桜井社長の著書『逆境経営』には、
○「がんばらないけど、あきらめない」
○「失敗を恐れるな(次に必ずやり方を変えればよい)」
○「絶対に、社長を信頼するな」
などのユニークなスローガンが描かれていますが、これらの言葉は「試行錯誤」への挑戦を続けるため、ひとつの方法に固執して精神的に息切れしないために、また新しいことへの挑戦を続ける社長に「黙ってついてくれればいい!」ではなく、社員一人ひとりが頭を使って主体的に動かないと、会社は危険なんだぞと健全な危機感を持たせるためと推測できます。
霧島酒造のホームページにも「考動指針」として「夢がなくては始まらない」「会社の主役は『私』です」「やり過ぎぐらいがちょうどいい」など、独自のメッセージを社員に投げかけて、旧来のコミュニケーションから離れて、自主性とチェレンジ精神を鼓舞しています。
変化を鼓舞し、社員が自主性を発揮する主役になることを求めており、よくある「頭を使わず、ついてくるだけでいい」という古い管理思想から離れていることがわかります。
※霧島酒造株式会社 企業理念 https://www.kirishima.co.jp/company/philosophy.html
■新しい目標・製品・スローガンで「上手に離れる」べし
苦境からの飛躍を実現させた2社にかぎらず、過去、危機からのV字回復を成し遂げた企業を見ていると、危機から生まれる空白こそが、イノベーションのサイクルを始める起点となっていることがわかります。同じことをやり続けても、行き場がもうないという八方ふさがりの状態が、最後に過去を手離すことをリーダーに思いつかせることになるからです。
【離れる戦略の5原則】
○強みを生かしながら古い戦略から離れる
○古い目標を手離し、新しい目標を掲げる
○消費者と新しいコミュニケーションを始める
○社員と新しいコミュニケーションを始める
○古い自己像から離れ、新しい自己像を高く評価する顧客と出会う
2社は共に「最高においしい製品を磨き作り上げる」という1点だけはぶれていません。その本質的な目標を固く維持しながら、ほかの古いすべてのものから正しく離れています。
現代日本のビジネスシーンは、もはや頑固一徹な執着ではなく、健全な形で「離れる戦略」を実践できる企業と個人が飛躍を始めているのです。
大切な人ではありながら古い愛を手離すことで、人が新たな成長を実現できるときがありますが、企業が社会と新しい関係を育むためには、古い姿に閉じ込められることを避け、より多くの消費者に出会い愛される新たな自社像を打ち立てなければならない時代を迎えているのです。









