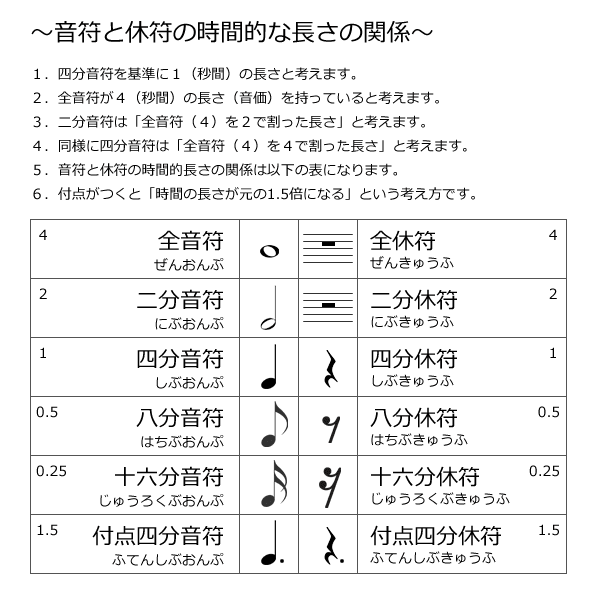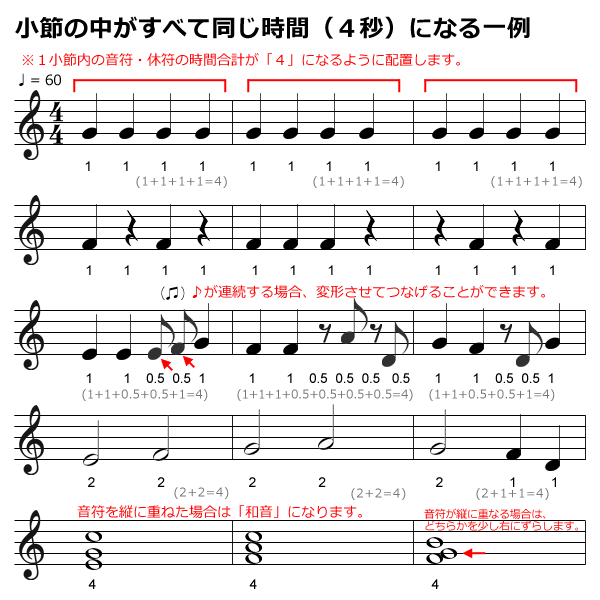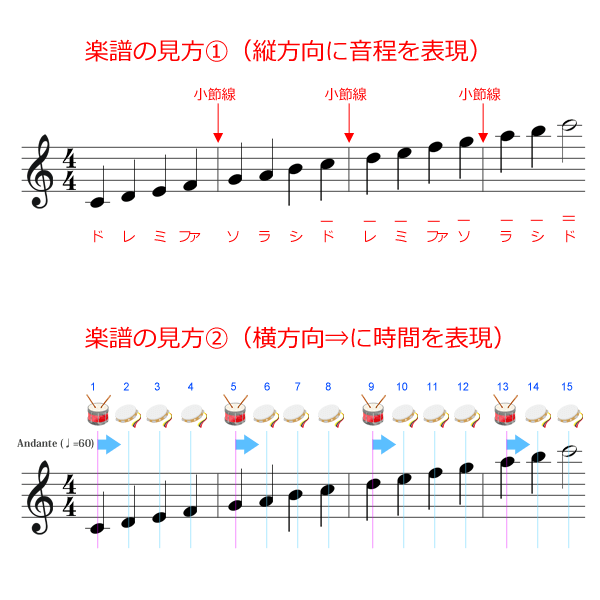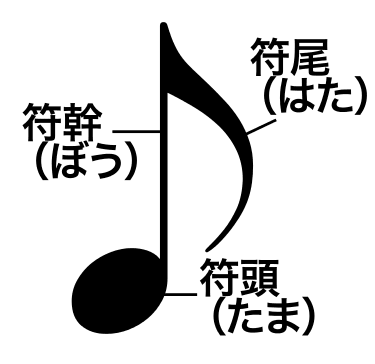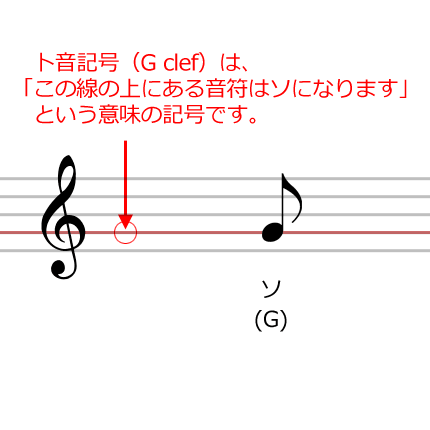アコースティックピアノ(通称、生ピアノ)と電子ピアノについて、個人的感想も少し交えながら、語ってみようと思います。

(フリー素材)提供元→ [フリーイラスト] ピアノを演奏する小人 - パブリックドメインQ:著作権フリー画像素材集 (publicdomainq.net)
例えば、子育てが終わって自由な時間が持てるようになった、定年退職して趣味に使える時間が増えた、という方々が「楽器を本格的に習ってみたい」と思ったとき、最初に生ピアノと電子ピアノどちらを購入するべきなのでしょうか。
もし子どもが「ピアノを習いたい」といってピアノを購入しよう、と考えた場合はどうでしょうか。ピアノの先生が仰るとおり、やはり生ピアノを購入しないとダメなんでしょうか・・・
そういった場合、おそらく正解は存在しないと思うのですが、ひとつの考え方として「こんな考え方どうでしょう?」程度の雑談で聞いていただけたら、と思います。
まず、前提条件として生ピアノを買う場合、以下の要件を充分に満たしているかどうか確認しておく必要があります。
1)床の耐荷重は充分に確保されるか?入居契約に、ピアノ可と書かれているか?
2)ご近所の騒音問題に配慮されているか?
3)購入後、定期的にかかる調律代は考慮に入っているか?(1回の調律は約1万円)
4)地震で倒れる場合のことを、想定に入れているか?
今や近所の騒音問題は世界中で深刻です。ピアノに限らず、大きな音が出る楽器をおうちで練習するのにはリスクが伴います。
また、生ピアノは調律に定期的な出費が発生します。調律しないで放置してしまうと、弦がどんどん伸びて音程が狂ってしまうからです。
弦が切れたり、音の出ない鍵盤が出てきたら、調律とは別に修理代もかかってきます。
田んぼのど真ん中の一軒家に住んでいるか、もしくは地下室のある一軒家か、防音室を整備したアパート、マンションでなければ、おうちで生楽器をのびのび演奏するのはほぼ不可能に近いでしょう。
せっかく音楽を楽しもうと思っても、結果的にリスクを増大させてしまっては何の意味もありません。
電子ピアノの場合ならどうでしょう?
電子ピアノなら耐荷重問題も、騒音問題も考慮する必要はありませんし、家に防音室がなくても、家のどこにでも好きな場所にピアノを置いて、のびのび演奏できますよね。(入居時の規約で楽器不可の記載がある場合は、電子ピアノでもNGの場合があります)
ヘッドフォンをつければ、夜中だって大音量で弾けちゃいます。家族に迷惑をかけることもありません。
「それなら選択の余地もないじゃないですか・・・電子ピアノ一択ですよね?」
と言われてしまいそうなので、ここで別の視点(ピアノ講師側)からも考えてみます。
確かに利便性や、環境問題のことだけを考えたら、電子ピアノ一択になってしまいます。
団地、アパートやマンション暮らしの方にとってはなおさらです。
でも、ピアノの先生は必ず生ピアノの購入を勧めてきます。なぜでしょう?
なぜ電子ピアノではいけないのでしょうか。

ピアノの先生から言わせると、
1)電子ピアノは微妙なニュアンスを表現できない。表現の幅が狭まってしまう。
2)生ピアノの感覚に慣れて欲しい。電子ピアノの鍵盤に慣れてしまうと、生ピアノの鍵盤を重く感じて弾けなくなる。
3)生ピアノの良さをわかった上で、電子ピアノを購入して欲しい。
となるのです。
ドラムの先生でも、家に電子ドラムを買うかどうか相談すれば、「買うより前にまずスタジオに通って、なるべく本物のドラムを叩きなさい」と言うでしょう。
1)はもっとも多い理由のひとつです。弦の振動を体で感じて欲しい、楽器の奥深さをわかって欲しいと思う、専門家としての願いです。
2)の理由は、実際にピアノを教える先生方の多くが、感じていらっしゃるご意見のようです。
3)の理由については私も同意見なのですが、もっとも初心者の方が生ピアノの良さがわかるようになる頃には、そうとうピアノが弾けてる状態でなければなりません。
「そもそも電子ピアノなど、楽器とは呼べない」と言い切る人すら、いらっしゃいます。
生楽器の良さを知れば知るほど、電子楽器が生楽器に届いていない、様々な差異がとても気になるものなのかもしれません。
生楽器の良さを充分わかってらっしゃる先生方からすれば、電子ピアノが本物のピアノに勝るはずがない、とお考えでしょう。
でも、電子ピアノをそんな「悪者」みたいに言わなければならない理由が、少なくとも私にはありません。
これから学ぼうとする生徒さんは、音楽を楽しみたい、楽器が弾けるようになりたい、というたった一つの希望を叶えたいだけなんです。
とっかかりが生楽器だろうが電子楽器だろうが、構わないんじゃないかと私は思うのです。
ただし、電子ピアノをこれから購入される方、ピアノの先生をこれからお捜しになる方は、ひとつだけ気をつけてくださいね。
「電子ピアノでもちゃんと丁寧に教えてくれる心の広い良い先生」を探すことです。
電子楽器には電子楽器の良さがあり、生楽器には生の良さがあります。良さのベクトルをどう捉えるかによって、見方、考え方は変わってくるものなのではないか、と私は考えています。