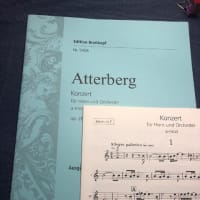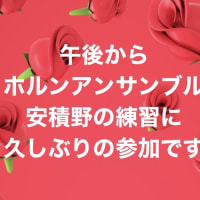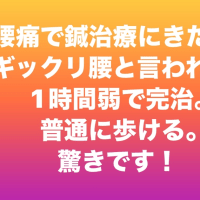今日のブログ…おそらくホルン吹きでなければ…
はっきり言って、つまらないかもしれません…。いや、間違いなく退屈でしょうね。
それでも伝えたい事があって(だいぶ後回しになりますけど…)
俗に言うクラシック音楽、古典とか…ベートーヴェンのころ…
この頃のホルンはただ一つの管(くだ)を巻いたような
シンプルなつくりのホルンでした。
いわゆるナチュラルホルンです。
右手で音程を調整しなければ、、ド、ミ、ソ…っといった自然倍音しか出ません。
そのため、演奏する曲の調に応じて管の長さの違う楽器を使っていたわけです。
たとえばハ長調の曲(in C)ならC管のホルンっという具合です。
極端な話、フルートとピッコロを比較するまでもなく、管の長さが長いほど音は低くなります。
大きな(ナチュラルホルン)ほどより低い音の調を受け持つわけです。
これをすべて一本のホルンで吹けるようになった…それはだいぶ後の時代になってからです
…ピストンバルブに管をつけたホルン…、つまりピストンを押すと、
付け加えた管にも息が通るので(継ぎ足した管を余計に通る、まぁ~吹いた息を遠回りさせてるわけで)、
(倍音と倍音との)間の倍音もでるようになります。
3つのピストンバルブを、それぞれ、半(0.5)音、1音、1.5音低くなるような長さの管を接続させておけば、
倍音を補充しあって、平均律でいう十二音階が出せるようになります。
こうなると音程を自由自在に操れます。
確か…私のつたない記憶では、このバルブホルンはシューマンの頃に登場した…と。
今日ではこの流れを継ぐウインナーホルン
(近年マイスターも増えてきていると聞きます。喜ばしいことです。)
それと、今日主流の「ロータリーバルブ」のモダンホルン、いわゆるフレンチホルンってやつですね。(続きは次回)
最新の画像もっと見る
最近の「ホルンあれこれ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2012年
人気記事