例えば、ビレンキンの「宇宙は無から誕生した」にしても、ですけどw
まず、私は、その言葉を聴いたときに普段の自分の発想を盗まれたと思ったことを忘れもしませんのや、そうでっせ。ほかに生物学者グールドが「我われは偶然ここまで来た」と言った時もそう感じたのですけど、ま、欲張りと言わば言え、ですのや。中学校で理科の授業をしていたらそうなった、というのが、自分が理学部卒だという所以ですがな。で、宇宙を無から誕生させるためには手品のタネが必要でっしゃろ、そやないか。
ビレンキンは己自身では正しい解答を示せていない、そうですがな・・。
あーゆー形で科学者が登場することに私は強い違和感を持っていたし、そりゃ多少なりとも不愉快だった、そうですがな。でー、かくいう私も、二十歳の時に人間原理とほとんど同じ内容のことを思いついてとうとうと述べたことがありますのや、だから強くは申しません、そうでっせ。我われという観測主体の無い物質だけの宇宙なんかシンジラレナイ、と言いましたし、神のよーな絶対的な優越者が存在するかド~か疑問である、ソ~言いましたっけ。
まー、生意気な青年だったものです!
コホン、本題に戻しましょーか、ビレンキンに必要だった手品のタネと言うのは、私の理論ではアトムのクーパー対にあたります。クーパー対というのは真空物質ですから「無」という言葉にもっとも近い存在ですのや。それを最初に仮定するというのがユニバーサルフロンティア理論の手品のタネなのですがな、そうですのや、そうでっせ。もうひとつはメリハリをつけた断定にあるといえますかな、コホン。南部=ゴールドストンボソンをゲージ場が吸収すればゲージボソンになるのではないか、というワインバーグの発想に続きまして、それがフェルミオンに吸着すれば次から次へと変わる色変換の元になるのではないかと思ったのですがな。
ゲージベクトル場はスピン1でフェルミオンはスピン1/2ということから類推したのですわなw
ユニバーサルフロンティア理論の根幹たる、と言っても根幹はたくさんあるのですけど、韓=南部模型の証明部分はそのヨーにして完成したのですわ、そうでっせ。スピン1の場には吸収されっぱなしだけれど、スピン1/2だと次から次へと変わる、と、ソ~考えるのが都合が良かったワケですのや。ま、その証明となると非常に難しい所でしょーけど、トホーフトのように下働きのよーな所を狙ってノーベル賞を取るみたいな離れ業は他の方に任せることにしたのですがな、そうでっせ。そこを上下逆転とばかりに考えたがるヨーダから数学の危機だとか、ツマランことを言い出さざるを得なくなる。
数学者、そらちと虫が良過ぎる、と言うもんでっせw
頭落ちるよーな難しいことをやらなければ値打ちが出ないのは最初から分かりきってることでっしゃろ、ソ~じゃなければ数学なんかするな、そう言いたいですがな。難しいことをやりたがるのがプロの数学者の使命ではないですかな、そんなん社会的に決まっとりますやろ、甘えていたらあきまヘンがな、そうですやろ、そやないか。そして私には権利がございます、標準模型の強い力はそこのところを証明抜きにやっておられます、私が当理論で証明を省略しよーと自由ですがな、違いますやろか。
そこんとこ、ヨロシク!
(あー、今年はイイ年になりソーダw)
まず、私は、その言葉を聴いたときに普段の自分の発想を盗まれたと思ったことを忘れもしませんのや、そうでっせ。ほかに生物学者グールドが「我われは偶然ここまで来た」と言った時もそう感じたのですけど、ま、欲張りと言わば言え、ですのや。中学校で理科の授業をしていたらそうなった、というのが、自分が理学部卒だという所以ですがな。で、宇宙を無から誕生させるためには手品のタネが必要でっしゃろ、そやないか。
ビレンキンは己自身では正しい解答を示せていない、そうですがな・・。
あーゆー形で科学者が登場することに私は強い違和感を持っていたし、そりゃ多少なりとも不愉快だった、そうですがな。でー、かくいう私も、二十歳の時に人間原理とほとんど同じ内容のことを思いついてとうとうと述べたことがありますのや、だから強くは申しません、そうでっせ。我われという観測主体の無い物質だけの宇宙なんかシンジラレナイ、と言いましたし、神のよーな絶対的な優越者が存在するかド~か疑問である、ソ~言いましたっけ。
まー、生意気な青年だったものです!
コホン、本題に戻しましょーか、ビレンキンに必要だった手品のタネと言うのは、私の理論ではアトムのクーパー対にあたります。クーパー対というのは真空物質ですから「無」という言葉にもっとも近い存在ですのや。それを最初に仮定するというのがユニバーサルフロンティア理論の手品のタネなのですがな、そうですのや、そうでっせ。もうひとつはメリハリをつけた断定にあるといえますかな、コホン。南部=ゴールドストンボソンをゲージ場が吸収すればゲージボソンになるのではないか、というワインバーグの発想に続きまして、それがフェルミオンに吸着すれば次から次へと変わる色変換の元になるのではないかと思ったのですがな。
ゲージベクトル場はスピン1でフェルミオンはスピン1/2ということから類推したのですわなw
ユニバーサルフロンティア理論の根幹たる、と言っても根幹はたくさんあるのですけど、韓=南部模型の証明部分はそのヨーにして完成したのですわ、そうでっせ。スピン1の場には吸収されっぱなしだけれど、スピン1/2だと次から次へと変わる、と、ソ~考えるのが都合が良かったワケですのや。ま、その証明となると非常に難しい所でしょーけど、トホーフトのように下働きのよーな所を狙ってノーベル賞を取るみたいな離れ業は他の方に任せることにしたのですがな、そうでっせ。そこを上下逆転とばかりに考えたがるヨーダから数学の危機だとか、ツマランことを言い出さざるを得なくなる。
数学者、そらちと虫が良過ぎる、と言うもんでっせw
頭落ちるよーな難しいことをやらなければ値打ちが出ないのは最初から分かりきってることでっしゃろ、ソ~じゃなければ数学なんかするな、そう言いたいですがな。難しいことをやりたがるのがプロの数学者の使命ではないですかな、そんなん社会的に決まっとりますやろ、甘えていたらあきまヘンがな、そうですやろ、そやないか。そして私には権利がございます、標準模型の強い力はそこのところを証明抜きにやっておられます、私が当理論で証明を省略しよーと自由ですがな、違いますやろか。
そこんとこ、ヨロシク!
(あー、今年はイイ年になりソーダw)










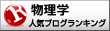








確か、ソ~でしたよ・・、ええw
「認識主体の無い物質だけの宇宙なんて無いと同じだ」と言ったと思いますよ。確か、本当にニールスボーアのセリフと同じでしたよ・・。
中学校で理科の授業ができていたのはすごいですね。
私も障害さえなければ、理工学部に行って、最低限、中学か高校の理科教師になれたはずなのに・・・
一応、私もノーベル賞に関連しそうな場所に所属していたことは一応あるんですけどね・・