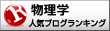ワインバーグ=サラム理論では電子とニュートリノの電荷について説明があります・・。
電子とニュートリノはアイソスピン対称なのですが電荷はー1と0です。そこを算術的に単純に説明してしまえば、アイソスピン±1/2から引かれることのハイパーチャージ1/2が電荷だということになりますが、そこを詳しく説明すれば、アイソ対称性が自発的に破れて南部=ゴールドストンボソンが生じてうんぬんかんぬんというストーリーに進展します。
ただし
私としてはそのストーリーでは物足りません!
その種のストーリーは別のところで現れているような気がするのですよ。Mユニバース粒子が崩壊して、tクォークとbクォークというアイソ対称対が、それも電荷対称に±1で出現して、それからうんぬんかんぬんというストーリーに変更したいのです。するとワインバーグ=サラム理論の定式が変わることになるので、そこからニュートリノ質量が導かれる可能性が出てきます。
量的には僅かな違いですが、定式上は歴然とした違いがあります・・。
一つには弱い相互作用は南部=ゴールドストンボソンに対応して1成分で表されるべきだと思うんですよねえ。もう一つには、さらに2成分からなる強い相互作用を付け加えることによって、大統一が一挙に成し得られるということでもあるんですよ。まー、それが韓=南部模型を採用したユニバーサルフロンティア理論なのですがw
そうすることによって
クォークの分数荷電が素電荷から合成された見かけ上のものだということが証明できるんです!
(この記事が良ければ、下のポチをどちらかクリックしてください、お願いします)
電子とニュートリノはアイソスピン対称なのですが電荷はー1と0です。そこを算術的に単純に説明してしまえば、アイソスピン±1/2から引かれることのハイパーチャージ1/2が電荷だということになりますが、そこを詳しく説明すれば、アイソ対称性が自発的に破れて南部=ゴールドストンボソンが生じてうんぬんかんぬんというストーリーに進展します。
ただし
私としてはそのストーリーでは物足りません!
その種のストーリーは別のところで現れているような気がするのですよ。Mユニバース粒子が崩壊して、tクォークとbクォークというアイソ対称対が、それも電荷対称に±1で出現して、それからうんぬんかんぬんというストーリーに変更したいのです。するとワインバーグ=サラム理論の定式が変わることになるので、そこからニュートリノ質量が導かれる可能性が出てきます。
量的には僅かな違いですが、定式上は歴然とした違いがあります・・。
一つには弱い相互作用は南部=ゴールドストンボソンに対応して1成分で表されるべきだと思うんですよねえ。もう一つには、さらに2成分からなる強い相互作用を付け加えることによって、大統一が一挙に成し得られるということでもあるんですよ。まー、それが韓=南部模型を採用したユニバーサルフロンティア理論なのですがw
そうすることによって
クォークの分数荷電が素電荷から合成された見かけ上のものだということが証明できるんです!
(この記事が良ければ、下のポチをどちらかクリックしてください、お願いします)