前回に引き続き、井上ひさしさんの本から、ボローニャ市の商工会議所がとった戦略を紹介します(本書では3つとありましたが、4つに分けました)。
この商工会議所が解決したい問題は、中心市街地の空洞化でした。郊外に大型スーパーができたことが原因にあるようです。日本だけの問題ではないのですね。
こちらの戦略は非常に具体的で、日本でも大いに参考になるものです。
商工会議所が取組んだ戦略
(1)商店街を専門店の有機的な集合体にするために改装費用を助ける。
(2)商工会議所に店員専門学校を設立してプロの店員を育てる。
(3)商店街の内部を改造して、学生や老夫婦の住居にする。
(4)中心市街地に映画館や劇場を増やすことによって、賑わいを創出し、街中の消費を促す。
上記を眺めると、(1)は日本でもこれまで取り組んできたものです。できれば村上市の取組みのように、費用の使い方は選択と集中が効果的です。
(3)や(4)も一部の地域では取り組まれていると思いますが、多様な世代が街なかで暮らすことが大事だと思います。どちらかの世代に偏ると効果は半減します。国内では、神戸市兵庫区入江地区(稲荷市場)を拠点に活動する「住みコミュニケーションプロジェクト」の活動が非常に面白いです(ハウジングアンドコミュニティ財団の会合で代表の三宗さんのお話をお聞きしました。アートやデザインの活用の仕方が卓越しており、非常に面白い活動をしています)。
日本で一番取組みが必要と感じるのが(2)です。このような活動を行っている地域はあまり聞きません。最近耳にしたところでは、駒ヶ根市の「テクノネット駒ヶ根」の活動です。こちらは官民連携で、非常に中身の濃い取組みを12年間継続しています。
中心市街地に賑わいを取り戻すには、小さなお店や個人が取り組むには限界があります。小さな力を束ね、如何に結果に結び付けるような戦略と行動に取り組むことができるか、これが街の明暗を分けることになると思います。
この商工会議所が解決したい問題は、中心市街地の空洞化でした。郊外に大型スーパーができたことが原因にあるようです。日本だけの問題ではないのですね。
こちらの戦略は非常に具体的で、日本でも大いに参考になるものです。
商工会議所が取組んだ戦略
(1)商店街を専門店の有機的な集合体にするために改装費用を助ける。
(2)商工会議所に店員専門学校を設立してプロの店員を育てる。
(3)商店街の内部を改造して、学生や老夫婦の住居にする。
(4)中心市街地に映画館や劇場を増やすことによって、賑わいを創出し、街中の消費を促す。
上記を眺めると、(1)は日本でもこれまで取り組んできたものです。できれば村上市の取組みのように、費用の使い方は選択と集中が効果的です。
(3)や(4)も一部の地域では取り組まれていると思いますが、多様な世代が街なかで暮らすことが大事だと思います。どちらかの世代に偏ると効果は半減します。国内では、神戸市兵庫区入江地区(稲荷市場)を拠点に活動する「住みコミュニケーションプロジェクト」の活動が非常に面白いです(ハウジングアンドコミュニティ財団の会合で代表の三宗さんのお話をお聞きしました。アートやデザインの活用の仕方が卓越しており、非常に面白い活動をしています)。
日本で一番取組みが必要と感じるのが(2)です。このような活動を行っている地域はあまり聞きません。最近耳にしたところでは、駒ヶ根市の「テクノネット駒ヶ根」の活動です。こちらは官民連携で、非常に中身の濃い取組みを12年間継続しています。
中心市街地に賑わいを取り戻すには、小さなお店や個人が取り組むには限界があります。小さな力を束ね、如何に結果に結び付けるような戦略と行動に取り組むことができるか、これが街の明暗を分けることになると思います。
 | ボローニャ紀行井上 ひさし文藝春秋このアイテムの詳細を見る |














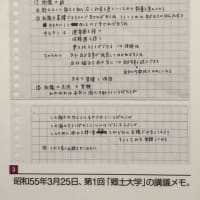

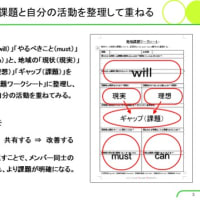
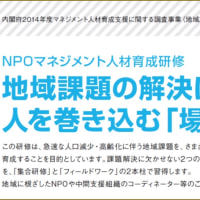
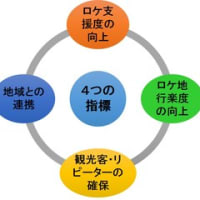








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます