
ボランタリーなツーリズムは、決して真新しいものではない。これまでも農山漁村の体験と交流を通じたグリーンツーリズム、植林やゴミ拾い等を含むエコツーリズムは、ボランタリーな精神を含んでおり広く認知されるようになった。私は更にこの発想を拡大し、日本社会を豊かにするツーリズムとして『ボランタリー・ツーリズム』を提唱したい。
去る2月14日、東京にて開催(協力:国土交通省)された民間主導の「兵庫・新潟観光カリスマ会議」に携わる機会を頂戴した。これは、風評被害など二次災害で甚大な打撃を受けている被災地を、当事者同士の互いの知恵を出し合い、観光を突破口に災害復興をめざすものである。折しも東南アジアのリゾート地が、復興後も観光客が戻らず苦難しているように、残酷にもこの現象は、災害が起こる度に繰り返される。これは観光産業だけでなく、人が途絶えることで地域経済までも冷え込ませてしまう。神戸では10年経過した今なお、被災前の水準には戻っていないという。
これを何とかできないか。私は以下のように考える。
それは観光する人の「後ろめたさ」を取り除くには無理があるということ。仮に被災地でなくても、被災地の近隣で豪遊するのは、意義のあることでも観光産業に無関係な人の理解は得にくいし、やはり躊躇してしまう。事態を整理するために、その他の災害周辺の特徴を列挙してみよう。
・余震や二次災害が怖い、復旧状況がわからない
・ボランティアは時間はあるが、お金がない
・義援金の出資者はお金はあるが、時間がない
・ボランティア志向の高まりと、CSRブームにより、義援金は比較的潤沢(ただし、メディアの依存度が高く、露出度に応じて偏りが大きい)
・支給物資の配分やミスマッチが多く、資金の効果的活用がよく見えない
・都心で観光PRをしても、ターゲットが散漫になり、結果を出すのは困難
以上を踏まえ、次のような具体案を提案したい。
(1)被災地およびその周辺の観光産業は観光に固執せず、ボランティア意欲の高い人を積極誘致する。ボランティア意欲の高い人は、人の役に立つことに喜びを感じるため、お手伝いをしてくれるだけでなく、現地情報発信メディアとして風評被害を抑制する。ボランティア活動は、現地の人と濃厚な人間関係を構築し、長期的なリピーターを生む。
(2)復旧が落ち着いたら、関東・東南海地域の住民向けに災害復興研修ツアーを実施する。今後想定される災害に対し、どのような対策が有効か、どのような困難があったのか、現地にて経験者の生の声を聞くのは説得力がある。
(3)経験豊富なボランティアには、国際・国内のボランティア経験回数に応じた優待運賃を設定し、被災地へ向かう費用負担の軽減措置を講ずる。
(4)できるなら、お金と人材を切り離し、義援金をボランティアの渡航費用に回す新たなビジネスモデルを構築し、時間のある人がボランティア活動を起こしやすい環境を整える。これは義援金の使途を可視化することで、さらに義援金を呼び込む効果がある。災害時に影響の大きい日本旅行業協会や金融機関、NPOなどが連携して枠組みを構築することが望ましい。
兵庫・新潟の連携は、災害大国日本にとって、市民活動の気運を盛り上げる良いチャンスだ。しかも、社会貢献意欲に満ちた団塊の世代(1947年から1949年生まれで約700万人、50年生まれまで含めれば約900万人)が、定年退職を心待ちにしている。
NHKクローズアップ現代<団塊の世代特集>
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-2.html
Volunteer Tourism by Stephen Wearing
http://www.uts.edu.au/new/releases/2002/January/22.html
http://www.niagara.edu/library/voltour.html
去る2月14日、東京にて開催(協力:国土交通省)された民間主導の「兵庫・新潟観光カリスマ会議」に携わる機会を頂戴した。これは、風評被害など二次災害で甚大な打撃を受けている被災地を、当事者同士の互いの知恵を出し合い、観光を突破口に災害復興をめざすものである。折しも東南アジアのリゾート地が、復興後も観光客が戻らず苦難しているように、残酷にもこの現象は、災害が起こる度に繰り返される。これは観光産業だけでなく、人が途絶えることで地域経済までも冷え込ませてしまう。神戸では10年経過した今なお、被災前の水準には戻っていないという。
これを何とかできないか。私は以下のように考える。
それは観光する人の「後ろめたさ」を取り除くには無理があるということ。仮に被災地でなくても、被災地の近隣で豪遊するのは、意義のあることでも観光産業に無関係な人の理解は得にくいし、やはり躊躇してしまう。事態を整理するために、その他の災害周辺の特徴を列挙してみよう。
・余震や二次災害が怖い、復旧状況がわからない
・ボランティアは時間はあるが、お金がない
・義援金の出資者はお金はあるが、時間がない
・ボランティア志向の高まりと、CSRブームにより、義援金は比較的潤沢(ただし、メディアの依存度が高く、露出度に応じて偏りが大きい)
・支給物資の配分やミスマッチが多く、資金の効果的活用がよく見えない
・都心で観光PRをしても、ターゲットが散漫になり、結果を出すのは困難
以上を踏まえ、次のような具体案を提案したい。
(1)被災地およびその周辺の観光産業は観光に固執せず、ボランティア意欲の高い人を積極誘致する。ボランティア意欲の高い人は、人の役に立つことに喜びを感じるため、お手伝いをしてくれるだけでなく、現地情報発信メディアとして風評被害を抑制する。ボランティア活動は、現地の人と濃厚な人間関係を構築し、長期的なリピーターを生む。
(2)復旧が落ち着いたら、関東・東南海地域の住民向けに災害復興研修ツアーを実施する。今後想定される災害に対し、どのような対策が有効か、どのような困難があったのか、現地にて経験者の生の声を聞くのは説得力がある。
(3)経験豊富なボランティアには、国際・国内のボランティア経験回数に応じた優待運賃を設定し、被災地へ向かう費用負担の軽減措置を講ずる。
(4)できるなら、お金と人材を切り離し、義援金をボランティアの渡航費用に回す新たなビジネスモデルを構築し、時間のある人がボランティア活動を起こしやすい環境を整える。これは義援金の使途を可視化することで、さらに義援金を呼び込む効果がある。災害時に影響の大きい日本旅行業協会や金融機関、NPOなどが連携して枠組みを構築することが望ましい。
兵庫・新潟の連携は、災害大国日本にとって、市民活動の気運を盛り上げる良いチャンスだ。しかも、社会貢献意欲に満ちた団塊の世代(1947年から1949年生まれで約700万人、50年生まれまで含めれば約900万人)が、定年退職を心待ちにしている。
NHKクローズアップ現代<団塊の世代特集>
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-2.html
Volunteer Tourism by Stephen Wearing
http://www.uts.edu.au/new/releases/2002/January/22.html
http://www.niagara.edu/library/voltour.html














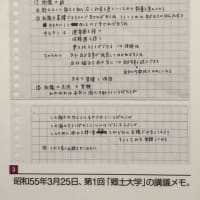

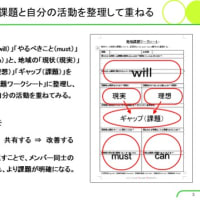
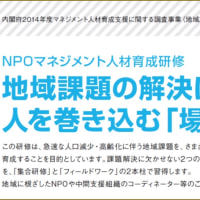
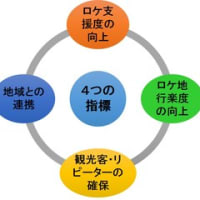








↓『ニューズウィーク日本版』
http://www.nwj.ne.jp/