
(画像は http://www.ike-dyn.ritsumei.ac.jp/~hyoo/em0.pdf からお借りしました)
磁束ΦとインダクタンスL の関係は、一般的に次式で表わされます。
Φ= LI
これは磁気の解説書などに必ず登場するポピュラーなものですが、いささか注意が必要です。それは φ=LI ではなく、Φ=LI ということです。よく見てくださいね、記号φとΦが違うのです。つまり異なる2種類の磁束があるということですが、これは一体どういうことなのでしょう。
「磁気の話①」では、コイルにおける磁束φを次のように定義しました。
φ=μ(S/d)NI [μ:透磁率 S:コイルの断面積 d:コイルの長さ N:巻数]
一方、コイルのインダクタンスL は、実際のコイルの設計資料などでは、しばしば次式のように示されています。
L=Kμ(S/d)N^2 [K:長岡係数(コイルの形状等による)]
K=1 として、磁束φ=μ(S/d)NI に代入すると
Nφ=LI となります。
これが磁束φとインダクタンスL の関係式ですが、実はφはコイル1巻きを貫通(鎖交)する磁束であり、実際にはN 数に鎖交するのでコイルの全磁束はNφとなり、それを記号Φで表わすのです。これはWeb上の説明も借りてみましょう。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/30/30671/30671_1syo.pdf
「巻き線が生む磁束は、すべてがコイルを貫くわけではありませんが、コアが十分長く、かつ透磁率が高ければ、生じた磁束φはすべての巻き線と鎖交し、巻数をN とすれば鎖交磁束数Φは、Φ=Nφに近似することができます」
さすがは専門書。こちらの方がフィットしているかも知れませんね。φを「磁束」、Φを「鎖交磁束数」といいます。
誘導起電力を示す式は、e =-N dφ/dt と e =-dΦ/dt のどちらがしっくり来ますか?
私は e =-N dφ/dt がいいですね。N があるからφの変動が巻き線に鎖交して誘導起電力e を発生させる様子が見えるようではないですか。
関連記事:
磁気の話① 磁界Hと磁束φ、電流Iと巻数N 2012-09-27
電荷と電気③ 電気力線と電束 2011-02-06
コイルとはなにか (電流と磁気) 2012-10-15
磁束ΦとインダクタンスL の関係は、一般的に次式で表わされます。
Φ= LI
これは磁気の解説書などに必ず登場するポピュラーなものですが、いささか注意が必要です。それは φ=LI ではなく、Φ=LI ということです。よく見てくださいね、記号φとΦが違うのです。つまり異なる2種類の磁束があるということですが、これは一体どういうことなのでしょう。
「磁気の話①」では、コイルにおける磁束φを次のように定義しました。
φ=μ(S/d)NI [μ:透磁率 S:コイルの断面積 d:コイルの長さ N:巻数]
一方、コイルのインダクタンスL は、実際のコイルの設計資料などでは、しばしば次式のように示されています。
L=Kμ(S/d)N^2 [K:長岡係数(コイルの形状等による)]
K=1 として、磁束φ=μ(S/d)NI に代入すると
Nφ=LI となります。
これが磁束φとインダクタンスL の関係式ですが、実はφはコイル1巻きを貫通(鎖交)する磁束であり、実際にはN 数に鎖交するのでコイルの全磁束はNφとなり、それを記号Φで表わすのです。これはWeb上の説明も借りてみましょう。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/30/30671/30671_1syo.pdf
「巻き線が生む磁束は、すべてがコイルを貫くわけではありませんが、コアが十分長く、かつ透磁率が高ければ、生じた磁束φはすべての巻き線と鎖交し、巻数をN とすれば鎖交磁束数Φは、Φ=Nφに近似することができます」
さすがは専門書。こちらの方がフィットしているかも知れませんね。φを「磁束」、Φを「鎖交磁束数」といいます。
誘導起電力を示す式は、e =-N dφ/dt と e =-dΦ/dt のどちらがしっくり来ますか?
私は e =-N dφ/dt がいいですね。N があるからφの変動が巻き線に鎖交して誘導起電力e を発生させる様子が見えるようではないですか。
関連記事:
磁気の話① 磁界Hと磁束φ、電流Iと巻数N 2012-09-27
電荷と電気③ 電気力線と電束 2011-02-06
コイルとはなにか (電流と磁気) 2012-10-15
















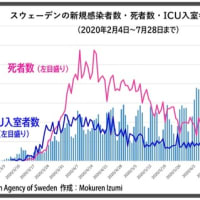









「ファイ」を小文字で書く場合は「磁束密度」を指す使い方がその世界では普通です。
そういう「暗黙のルール」はいっぱいあります。
筆記体で小文字のiだと交流電流とか・・・。
そういう世界で染まると全然違和感がなくなるものです。
抵抗のカラーコードなんかもそうかもしれないですね!
慣れるとゴロあわせなんていらなくて、3本目の色をみてオーダーの判定をして・・・というクセがついてしまうと何の不便もないものです。
コイルの誘導作用を応用したものは現実にたくさん使われていて、一番身近なものですと「スマホ」とか「携帯電話」は意外だと思われるんじゃないでしょうか?
電源部のインバータはみんなそれの応用ですから・・・。
まぁ、マグネッチックイヤホンとかエレキギターのピックアップもそうですけど・・・。
抵抗のカラーコード。「黒い礼服、茶を一杯」などと覚えましたよ。でも慣れというのはすごいもので、毎日見てると瞬時に抵抗値が分かるようになりますよね。最近ではしばらく遠ざかっていたもので、何度もコードを数えていますが。
私は実は高周波の経験がないのです。ですからコイルとの縁はあまりなく、苦手な素子のひとつです。これらの記事は自分の勉強用ですね。
kaoaruさんはミュージシャンでもあるんですね。素敵ですね。私はもっぱら聴くのが専門です。何でも聴きますがクラシックが一番多いかな。
中学生の頃からフォークギターをジャカジャカやりはじめたのがキッカケなだけです。
私も「高周波屋さん」ではなかったのですが、もともとは「ラジオ少年」だったのです。それにフォークギターが加わった・・・というのがホントのところ。
中学生の頃は「クラッシック」のダイジェスト盤がウチにあったのでよく聴いてました。自分で修理した真空管式電蓄で・・・。小六~中学生くらいの頃だったと思います。
自分で修理して、それで聴く・・・っていうのしかなかったなぁ~!
カセットテープレコーダも壊れたおさがりをその後にもらって、メカ部を修理して使っていました。
LL(なつかしいですね!)だったので、多重録音もどきをやってみたりしました。おぉ~、自分でもできるんだなぁ~!って思いましたよ。
昔、自分で作ったラジオが手を近づけたり離したりして動作が不安定だったのもテルミンみたいなモンか?!
バイポーラトランジスタ1発でも充分実用になるAMラジオは作れるものです。
もちろん、コイルも手巻き・・・バーアンテナは適当なジャンクから取ったヤツで・・・。大体、適当なジャンクから取ったコイル類で使いまわしできないことが多いです。結局は手巻き・・・手間ですけど、時間がかかるだけでお金はかかりません。
エナメル線は前のヤツをほぐして使いますから・・・。
こういうことをやってると、結構身に付くものです。
でも、傍目から見た姿は異様でしょうね!
「おじさんが糸巻きに熱中している」様にしか見えませんから・・・。
実際、昔から磁気を応用したセンサが一番多かったのです。パルスを印加した状態でねじるような力を物理的に加えるとパルスの変化が出ます。
こういう現象を応用した「はかり」があったようです。
他にも、特定のガス用センサにも磁気センサがあったらしいのですが、詳細な情報は得られていません。
電子系エンジニアの中にもコイルを嫌う人は多々いるようですが、こんなにもコストがかからない素晴らしいものはない!と思っているワケです。手間はかかるけどねぇ~!
材料はフェライトバーとエナメル線、たったそれだけ!
あとはヤル気。
一時このブログによく来てくださっていたC言語使いの元エンジニアの女性は、「だって自作できる唯一の電子部品じゃないですか」と言って、自分で巻いたコイルの写真を自身のサイトにアップされたりしてましたね。まったく同感です。彼女はスイッチング電源を作るためのチョークコイルを自作するというなかなかの猛者でした。
「こんなにもコストがかからない素晴らしいものはない!と思っているワケです。手間はかかるけどねぇ~!」
kaoaruさんに諸手を上げて賛成~!(^^)
テルミンは空間の静電容量を検出するんですよお。近頃CDC(静電容量-ディジタルコンバータ)が内蔵されているPICもあるようで、あれなんかを使えば簡単にできてしまうかも知れませんねえ。
リアルタイムに高速演算を繰り返す必要があるアプリなら必須です。
ただ、PICのもともともアーキテクチャはクロックの4分の1が基本サイクルなので、もともと速くはないのです。
コンパクトで処理速度を優先するなら、AVRがいいですよ!
AVRは初期の頃仕事で使いました。インストラクションはPICよりもZ80をやったことがある人のほうがとっつきやすいです。
ただ、一言申し上げておくと、特定の特定機能に着眼すると思わぬ落とし穴があるということです。仕事ではイヤというほどそういう目に遭っていましたので・・・。
だから、単純に「静電容量」だけに着眼しないことも肝要です。プログラミングする上で有利になるような構成も検討する、ということなんです。
これは、組み込み系が長かった私の経験から言えることですが・・・必ずしも他の方すべてにあてはまるということではありません。強要はしませんが、そのあたりは柔軟に考えられるとよろしいかと・・・。
あと、マイコンに種々のコンバータが載って便利に思えるというのは、もしかすると経験が浅いせい?と思うのは私だけかな?
案外プリチャージタイムや変換時間などがかかりすぎて暗礁に乗り上げることも多々あります。
あんまり期待せずに「冷静にドキュメントを読む」必要があります。
「クールすぎる!」と思われるかもしれませんが、組み込み系長いと、こうなるモンなんです。
プログラミングは熱くなったらつとまりませんって!
「マイコンに種々のコンバータが載って便利に思えるというのは、もしかすると経験が浅いせい?」
たぶんその通りなんだと思います。前の仕事でH8/SXを選んだのもI2Cのインターフェイスが内蔵されているというのが動機でした(トラ技の付録で出回っていたこともあるのですが)。客先から指定されたADCがI2Cだったんですよね。でもこれは随分と助かりましたね。I2Cのアーキテクチャを自作するなど、とうてい私には無理でしたので。
「冷静にドキュメントを読む」はほんと大事ですよね。
「プログラミングは熱くなったらつとまりませんって!」
はい。重々承知しております。(^^)
そうですか・・・そういうモノにたよらないとできませんか・・・。
「SPI」って、私は「パタパタ制御」って命名してます。
CS、クロック、データの3本だけでとっても簡単な制御インターフェースです。
CSを落として、データラインを確定させておいてからクロックを1パルス送る・・・という操作を必要ビット分完了したらCSを戻す。たったそれだけなんですけど・・・。
そういうのは、Cでもさんざん書きましたし、アセンブラのほうが楽ですけどね、そういうのは。
外付けEEPROMとか、ディスプレイコントローラとか、チューナーのプリスケーラとか、いろいろありましたねぇ~!
PCのパラレルポートを使ってそういうのを書く練習をするといいんですが・・・今どきパラレルポートついているの、ウチのPCくらいだろうなぁ~?
私はI2Cだったら、どんなマイコンでもプログラミングでやっちゃいます。シリアルポートだって、なければソフトでやりますんで・・・。
でも、そういう制御系部分に振り回されていると先が長くなることでしょう!スキルが早く本題に近づくといいですねぇ~!
双方向だとディレクションの切り替えが必要になり、メンドくさくはなりますが、基本は同じです。
それと、SCIに反転が必要な場合、ムリにゲートを使わないでビットシリアルの処理もソフトでやったほうがいい場合もあります。転送レートと受信を割り込みでやるかどうかで違ってきますけど・・・。
H8SXシリーズですと、過去に使ったことがあるH8・2000シリーズの系統ですね!
場合によっては「コンペアマッチ」も使えるといいのですけど・・・ね!
とても多機能なマイコンです。それでも、ARMほどではないので、スキルアップにはちょうどいいかもしれませんね。
SPIで邪魔くさい・・・ってのはどうも・・・一番楽なんですけどね、そいつが・・・。
DACはほとんどSPIですよ。漁船のエンジンコントロールではよく使います。4-20mAのモードで。
SCIはたしか2本あったかと思いますが、1本はデバッグモニタ用に使います。ターミナルモードのPCにつないで、動作モードを変えたり、キャリブレーションをとるモードを操作したり・・・と。
特殊なやりかたでは、プログラム実行中に内蔵フラッシュROMを一部書き換える処理があったり・・・そういうのもあるものなのです。
SCI、SPI・・・いずれもビットシリアル処理なんで、そんなに邪魔くさいとは感じない私です^^;むしろ、それがフツー^^;ただし、組み込みマイコンの場合ね!OSがらみだとやりにくい場合が多いのは確かです。実行スレッドの優先順位を気にしなければいけなくなるので・・・。