
左上の回路が前回検討した回路です。14300ものゲインを持つじゃじゃ馬で、IN1に+0.1Vを入力すれば出力は電源電圧の+15Vに張り付き、-0.1Vを入力すれば出力は電源電圧の-15Vに張り付くというものでした。
それでは右の回路のように、1本の抵抗RF(9kΩ)を追加してOUTとIN2を接続するとどうなるでしょう(IN2はグランドから切離す)。端子を点線にしている1kΩはまだつなぎません。Q2のベース電流を無視量、つまり入力インピーダンス=∞Ωとすると、OUTの電圧がaVだけ上昇すれば、IN2もまったく同じaV上昇します。つまり、OUTの電圧=IN2の電圧になります。ここが重要なところですよ。OKですか?
そしてaVが、IN1=0.1Vを超えると、IN1よりもIN2の電圧が高くなり、出力OUTは-15Vに向きを変えて瞬時に変化します。IN2の値は出力OUTと同じですから、次にOUTの電圧がIN1=0.1Vを下回れば、OUTは再び+15Vに向きを変えて瞬時に変化します。このようにOUTはIN1の電圧を境に、オーバーシュート、アンダーシュートを繰り返しますが、振動し続けるわけではありません。IN2の電圧がIN1の電圧を横切れば、出力OUTが必ず引き戻すように動作するので、“しばらく”するとIN2の電圧=IN1の電圧=0.1Vとなる地点でOUTは静止します。“しばらく”の期間は遅くてもμsecオーダーですから無視量として、瞬時にOUTは静止すると考えて問題ありません。つまり出力OUTを抵抗(今の場合は9kΩ)でIN2に接続すれば、IN1=IN2=OUT(=0.1V)となるのです。OUTとIN2を抵抗(0Ωも可)で接続することをフィードバックするといいます。
つまりIN2の電圧=IN1の電圧となる値にOUTは静止するということです。であるなら、いよいよ次が大詰めです。端子を点線にしている1kΩを接続するとどうなるでしょう。見てきたように、出力OUTはIN1=IN2になる電圧で静止するのですから、OUTは9kΩと1kΩで分圧した値が0.1Vになるような値に決まります。つまり
0.1=OUT×1k / 9k+1k 1k=OUT×1k OUT=1
このように、OUT=1Vになります。入力はIN1=0.1Vですから、ゲインは10ということですね。1kΩを3kΩに取り替えると、OUTは0.4Vとなり、ゲインは3になります。これは実際に計算してみてくださいね。先に結論をお話しますと、右の回路図で、あとに接続した1kΩをR1、フィードバック抵抗の9kΩをR2とすると、この増幅回路のゲインは
Gain=1+R2/ R1
となります。最後に下の図をみてください。もうお気づきですね。これがオペアンプなのです。
関連記事:
差動増幅回路の妙③ 2段目とエミッタフォロワ 2011-04-27
差動増幅回路の妙① エミッタ接地増幅回路 2011-04-13
それでは右の回路のように、1本の抵抗RF(9kΩ)を追加してOUTとIN2を接続するとどうなるでしょう(IN2はグランドから切離す)。端子を点線にしている1kΩはまだつなぎません。Q2のベース電流を無視量、つまり入力インピーダンス=∞Ωとすると、OUTの電圧がaVだけ上昇すれば、IN2もまったく同じaV上昇します。つまり、OUTの電圧=IN2の電圧になります。ここが重要なところですよ。OKですか?
そしてaVが、IN1=0.1Vを超えると、IN1よりもIN2の電圧が高くなり、出力OUTは-15Vに向きを変えて瞬時に変化します。IN2の値は出力OUTと同じですから、次にOUTの電圧がIN1=0.1Vを下回れば、OUTは再び+15Vに向きを変えて瞬時に変化します。このようにOUTはIN1の電圧を境に、オーバーシュート、アンダーシュートを繰り返しますが、振動し続けるわけではありません。IN2の電圧がIN1の電圧を横切れば、出力OUTが必ず引き戻すように動作するので、“しばらく”するとIN2の電圧=IN1の電圧=0.1Vとなる地点でOUTは静止します。“しばらく”の期間は遅くてもμsecオーダーですから無視量として、瞬時にOUTは静止すると考えて問題ありません。つまり出力OUTを抵抗(今の場合は9kΩ)でIN2に接続すれば、IN1=IN2=OUT(=0.1V)となるのです。OUTとIN2を抵抗(0Ωも可)で接続することをフィードバックするといいます。
つまりIN2の電圧=IN1の電圧となる値にOUTは静止するということです。であるなら、いよいよ次が大詰めです。端子を点線にしている1kΩを接続するとどうなるでしょう。見てきたように、出力OUTはIN1=IN2になる電圧で静止するのですから、OUTは9kΩと1kΩで分圧した値が0.1Vになるような値に決まります。つまり
0.1=OUT×1k / 9k+1k 1k=OUT×1k OUT=1
このように、OUT=1Vになります。入力はIN1=0.1Vですから、ゲインは10ということですね。1kΩを3kΩに取り替えると、OUTは0.4Vとなり、ゲインは3になります。これは実際に計算してみてくださいね。先に結論をお話しますと、右の回路図で、あとに接続した1kΩをR1、フィードバック抵抗の9kΩをR2とすると、この増幅回路のゲインは
Gain=1+R2/ R1
となります。最後に下の図をみてください。もうお気づきですね。これがオペアンプなのです。
関連記事:
差動増幅回路の妙③ 2段目とエミッタフォロワ 2011-04-27
差動増幅回路の妙① エミッタ接地増幅回路 2011-04-13
















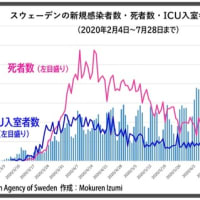









6BQ5でプッシュプルアンプを考えたとき、設計段階から変なことを考えていました。
普通、負饋還は出力トランスの1次側からとるものなのですが、2次側からとる方法をとりました。
書籍に載っていたのですが、この方式の名称は忘れましたが、正饋還になる場合もあるということで、それは覚悟していました。
案の定、正饋還となってしまい、結線を入れ替えてOKになったのですが、私は大きな「ポカ」を犯してしまいました。
スピーカをつながないで通電したために出力管を飛ばしてしまったのです。
プレートが見事にマッカッカになっちゃいました・・・。
片CHだけは難を逃れたので、その管を差し替えて両方の確認はとれたわけですが・・・当時1本800円もしたんです・・・6BQ5。キツかったぁ~!
今考えるとスゴイことやってたな・・・高校生の頃。
普通、負帰還は出力トランスの1次側からとるんですね。これも初めて知りました。私的には、どのアンプも出力端を負帰還するものと思っていましたので、2次側からとるのが通常のようにも思えますが。しかし実際には2次側からは一般的ではないと。音質的にはどうでしたか?球をひとつ飛ばしたのはともかくとして。(^^;
この頃はコーラルのユニットに換装していたのですが、少々低域が抑えられてしまった?っと感じましたが、それはコーラルのユニットの特性だったようです。
全体的な印象は・・・半導体アンプのような音の硬さはまったくなかった・・・苦労して作った甲斐があった・・・という満足感が一番でしたか・・・。
最後まで気にしていたのは「残留ノイズ」だったのですが、さすがにプッシュプルです。スピーカに耳を当てても聞こえないレベルでした。シングルアンプだと電源ハムに悩まされるのですけど・・・。
ちなみに6BQ5という管は安物クラスのものです。
しかし、タマアンプの場合は出力トランスを奢ってあげないといい結果がだせないモノです。
最終的にトータルの部品代は10万近くかかっていたかと記憶しています。電気代もかさむアンプでしたが^^;
またそれとほぼ同じ時代にパイオニアからM22というA級のトランジスタパワーアンプが発表された折に、当時著名だったオーディオ評論家が「真空管アンプの存在意味がこれでなくなったと思った」と解説していたのを覚えています。
6BQ5アンプは部品代が10万円ほどかかったんですか。私がいまトライしているトランジスタアンプもだいたい同じくらいです。
2~3年前にテクニクスのM33のころのデザインのプリメインをヤフオクで入手して毎日ヘッドホンで聴いていました。
好きな音だったのですが、電気料金がいっきにプラス1000円になっちゃって、あきらめました。そういうゼイタクができる状況ではないので・・・。
ピュアオーディオがなんといっても最高!でも・・・金かかるねぇ~!
そういうワケで「セコいオーディオ(なんのこっちゃ?!)」でいくしかない私です。
「ピュアオーディオ」をWikipediaで引いたら、ものすごいことが書いてありました。
「ピュアオーディオ、とは家庭用の音響機器による音楽再生に究極の音質を求めるカルト宗教またはエクストリームスポーツである。まず確認しておかねばならないのは、ピュアオーディオとは、決して道楽や趣味ではないということである。 それは人生であり、哲学であり、全宇宙を超越し、現代科学を超克し、全人類の歴史を塗り替える偉業を打ち立てる、恐るべき営為なのである。ピュアオーディオ人たるもの厳しい自己鍛錬が求められる」
まあ確かにそうなんですが、これには思わず笑ってしまいました。
なんやかや言っても、音楽を楽しむ道具なんですよね。ナイトクルージングをしながらカーステで音楽を聴くのもいいもんです。あんなにS/Nの悪い環境であるにもかかわらず。