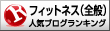観音崎のそばにある横須賀美術館に寄った。
少し前に載せた海の写真も、そのまた数日前の夕景の写真も、そこでとった。
これほど海に接近した美術館は少ないかもしれない。
海を見て、美術を見て、また海を見て、という時を過ごすことができる。
だけど、ひとつの絵を見つめていると、海のことなど忘れてしまうときもある。
海よりも広い何かを、ときに美術はこの世につくる。
藤島武二の「夢想」という絵も、僕にとってはそのようなひとつで、この館が所蔵している。
あまりにも有名な絵だけれど、実物をみるのははじめてだった。
ここに来た目当ては企画展だったのに、この一点で、何かが変わってしまった。
企画展は素晴らしく、現代美術の軌跡をあらためて堪能できた。
何よりもイヴ・クラインの作品に再会することができたし、ダリにもあらためて舌を巻いた。
風倉匠がピアノを叩き壊すパフォーマンス映像も見ることができた。
この続々と展示される巨大な作品の次々にはなつエネルギーがつよくつよくて、
それらから押し寄せる過剰な体験が心をかき乱していた。
めまいと言うか、ある種のカタルシスのようなものもあった。
そして、マーク・ロスコを見つめた。
誰かにさらわれてしまうような感覚とも言えるだろうか。
地鳴りよりも低い、もはや音にならぬほど低い音が、ロスコの絵の中にはあると思う。
なにかが皮膚を震わせてくるような感覚をおぼえたりもする。
絵の前にいて、ふと、この世ではない遠いところに落下しそうな気分になる。
くらくらとしながら、しかし見惚れて棒立ちしていた。
そのとき、見つめているのに見つめられている、という奇妙な、しかし満たされてゆくような感慨を覚えた。
ロスコの絵が見られるときくたび、見に行っていたが、そのたびに体験がちがっている。
ひとつの絵は不動なのだから、わたくし、というものが変化してゆくのを、この人の絵は反射してくるのだろうか。
見つめているのに見つめられている、、、。
そのような、はたらき、というのだろうか、のなかにあって、呼吸や心音までもが意識されてゆくようでもあった。
ひとつの作品の前にいるその時間が、もしかしたら二度とないのでは、と、大切に思えた。
しばらくぼんやりと休んで、所蔵展のエリアに足をはこんだとき、
こんどは藤島武二の絵に、思いがけない強烈さで、眼を奪われた。
突然そこだけが静寂な一点があって、なんだこれは、と思った。
それは、画集や美術本では馴染みに馴染んだ絵なのに、実物はまるで別のものだったのだ。
絵はやはり物質として自立しているものなのだろう。
初めてこの絵を感じ得たと言ったほうが正確かもしれない。
女性の顔を描いているのだけれど、異様な吸引力を感じるのはなぜか。
女性の顔というモチーフを描きながら、その像をつらぬき破ってしまうような、それの背後を、あるいは、何かまだ形にならぬ未出現の存在を、画家は描いてしまったのだろうか。
もしかすると、空も海も無い広大な場所が、にんげんの中には広がってあるのではないか、
と僕は思っているのだけれど、この絵はそのような妄想にもさわるのだった。
 写真は同館配布の印刷物より。
観たもの、聴いたもの
ダンス公演情報
写真は同館配布の印刷物より。
観たもの、聴いたもの
ダンス公演情報